Let your colors
shine.
“RITSUMEI: establish one's destiny
through cultivating one's mind”
- Continue learning to understand who you are



About
立命館学園コンピテンシー・フレームワークとは?
立命館学園では、「イノベーション・創発性人材」の輩出を目指し、本学園で学ぶ児童・生徒・学生が「自分の価値」を見いだせるよう、コンピテンシー・フレームワークを策定しました。
このサイトでは、8つのコンピテンシーとともに、友人、家族および自身との関わりを通した多様な成長の場面を紹介しています。
あなたにとって、これまでの経験を振り返り、それらを通じて育まれたコンピテンシーを考えることで、より豊かな人生を築くきっかけになることを期待しています。
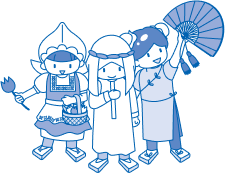
【立命館創始155年・学園創立125周年を記念した限定公開】
記念式典・記念イベント(10月18日)では、NTT西日本様と共同開発している教育向け生成AIを活用したアプリ(デモ版)を公開します。イベント当日にご紹介する内容を動画でご紹介させていただきます。
マップ上をドラッグまたはスワイプしてご覧ください。
をクリックすると詳細を知ることができます。



Episode
立命館学園で育まれるコンピテンシーを、エピソードとともにご紹介します。