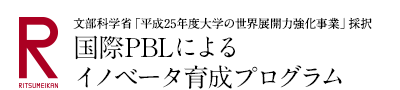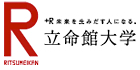参加学生によるプログラム・レポート
2018年10月のレポート一覧
2018.10.30
アクティビティレポート①(2018年派遣:チュラロンコン大学)
国際関係学部 西村 真理奈さん(2回生)
<生活・課外活動編>
こんにちは!現在、チュラロンコン大学コミュニケーションアーツ学部に所属している、2回生の西村真理奈です。
タイに来てから約2ヶ月が経ちました。最初の2週間は、食べ物は辛いし、交通渋滞はひどいし、タイ語が喋れないから英語でコミュニケーションを取ろうとしたら通じないしで、急な環境の変化に戸惑い、日本に帰りたくて仕方がありませんでした。しかし徐々に生活にも慣れ、友達も増え、今では毎日楽しく過ごしています。今回は、普段どのような日常を送っているか、放課後の過ごし方また、住んでいる地域や街の様子など、タイでの生活全般についてお伝えしたいと思います。
私は、朝が大の苦手で、生まれてから今までの人生で1度も早起きの習慣が身についたことはありませんでした。しかし、タイに来て初めてのルームシェアをするようになってから、なぜかアラームを設定しなくても5時か6時にはパッと目が覚めるようになりました。本当に自分でも何が起こったのか、、ただただびっくりしています。朝は基本的にそのくらいに起きて、リラックスして、朝ごはんを味わって食べて、身支度をして、宿題などやることをやったりと、ゆっくり時間をかけて家を出ます。金曜日以外、毎日朝から学校があるので、徒歩で最寄りの地下鉄の駅まで行き、電車を使って学部にいちばん近い駅で降りて、そこからまた徒歩で学部の建物まで向かいます。
授業は、基本的に4時には終わるので、その後は、友達とご飯を食べに行ったり、ヨガクラスに行ったり、道端でやっているズンバに参加したり、ショッピングしたり、遊んだりと様々な時間の使い方をしています。
学校終わり、サイアムにあるレーザーゲームをしに行った
放課後、中秋節をBBQを食べて祝った
私が住んでいるアパートの大半はチュラ大の学生で、主にドイツ、フランスなどヨーロッパから来ている留学生が多いです。ヨーロッパ以外にも、アメリカ、カナダ、メキシコ、シンガポール、台湾など様々な国出身の人々が集まっています。毎日、誰かしらの部屋でパーティーがあったり、プールやジムの共用スペースがあったりと、人との関わりを多く持つ事ができる、とてもソーシャルな場所です。毎日のように新しい人との出会いがあり、いろんな人と友達になることができます。ただ、最寄りの駅からアパートまでが、非常に歩きにくく遠いので、立地は最悪です。
ある日誰かの部屋であったパスタパーティーにて
One day tripで、Hua Hinというビーチに行った
私は、辛い食べ物が一切食べられないので、食選びにはなかなか苦労しています。誰とも予定がないときは、スーパーで買って帰ったり、食堂のご飯をテイクアウトしたりして、家に持ち帰って食べています。タイは物価が安いので、自炊するより買ったほうが時間もかからないし、簡単です。特に食堂のご飯は、バラエティが豊富で、安全だし、美味しいし、安いし、最高です。タイでは、水道水は飲めません。また、こっちの水は硬水なので、髪の毛がとてもパサついて困っています。日本からシャンプー、トリートメントを持ってくることを強くおすすめします。
2018.10.30
アクティビティレポート②(2018年派遣:タマサート大学)
国際関係学部 岸本 啓汰さん(3回生)
こんにちは。タマサート大学で社会福祉を主に学んでいる、国際関係学部3回生の岸本啓汰です。今回は自分が暮らしているマンションについてお伝えしたいと思います。
私は大学から徒歩30分くらいのところにあるアマリンマンション(Amarin Mansion)で生活をしています。8階建ての大きなマンションで、部屋はワンルームでトイレとシャワー(シャワーのみ)が付いています。家賃が1番安いタイプの部屋に住んでいますが、もっと高い部屋になるとキッチンなども付いています。
家賃は学生によって様々ですが、だいたい1ヶ月7000~9000バーツほどです。冷蔵庫、テレビ、Wifiなどの料金は家賃に組み込まれていないので、入居する時に自分で何が必要か選択しなければなりません。私の場合は月10000バーツを支払っています。
警備員が24時間常駐しており、さらにロビーにカードキー/指紋認証のロックが付いているので、セキュリティ面は万全と言っていいでしょう。1階にはコインランドリーと食堂があり、食堂は40~50バーツ程度でしっかりしたご飯が食べられます。また、部屋から食堂に電話をかければご飯を届けてもらえます。タマサート大学の留学生がとても多く住んでおり、屋上で毎夜パーティーを開いたりしているのでマンション内はとてもにぎやかです。
デメリットは大学まで少し遠いことと、マンションの周辺が充実していないということです。大学までは徒歩で30分、タクシーでは10~15分ほどかかります。バンコクの道路はとても混雑するため、下手をすると車でも20~30分かかってしまうこともあります。
マンション周辺には、徒歩圏内で24時間営業のセブンイレブンやカフェ、軽食屋が数件ありますが、スーパーやショッピングモールまで行くとなると少し距離があります。私は基本的にタクシーまたはバイクタクシーで大学やスーパーなどに行っています。
もうすぐ中間テストの時期に入ります。短い留学期間を最大限に楽しみ、活かせるように今後も頑張りたいと思います。
部屋の様子
1階の食堂のご飯 (ミンスドチキン)
2018.10.30
アクティビティレポート①(2018年派遣:ガジャマダ大学)
国際関係学部 岩永 めぐみさん(3回生)
インドネシアに来てから約2カ月が経過し、こちらの生活にも慣れてきました。私が留学しているガジャマダ大学は、ジョグジャカルタというところにあります。ジャカルタなどに比べて物価も安く、治安も良いのでとても暮らしやすい街だと思います。
私の住んでいるコス(シェア型アパート)は、大学から10分くらいの場所にあり、エアコンやWi-Fi、温水シャワーが完備されていて、優しいスタッフの方々が24時間フロントにいるので安心です。また、週に1回ルームクリーニングサービスもあり、快適な生活を送ることが出来ています。
大学の学生数は立命館よりもはるかに多く、学部も多様です。その中でも私は、FISIPOL(政治社会学部)という学部に所属し、インドネシアの歴史やトランスナショナリズムなど国際関係学科の授業を受講しています。FISIPOLにはIUPという英語のコースがあり、留学生も多く在籍しています。IUPに所属している学生は留学が必須で、インドネシア語で行われる通常のコースより、学費が5倍もするそうです。授業についてですが、1時限は2時間行われます。また、1限が7:30から始まり、とても朝が早いので慣れるまでは大変でした。グループワークが多く、授業時間外にもみんなで集まってミーティングをすることもよくあります。
授業がない日には、現地で日本語を勉強している学生との日本語会話会や文化交流会に参加したり、インドネシア人の友人にいろいろな場所に連れて行ってもらったりして、とても充実した生活を送ることが出来ています。特に、険しい山道を1時間ほど登った先にあるCandi Ijoからの景色は絶景で、忘れられない経験となりました。
また、知り合いのインドネシアの方の案内で、完全には観光地化されていない穴場のカリムンジャワという島へ訪れましたが、今までに見たことのないほど透き通った海と夕日を見ることができ、とても感動しました。しかし、シャワーが水だけであったり、トイレも自分で水で流す簡易的なものであったりと(ガジャマダ大学のトイレも同様)、改めて日本は発展しているなと感じました。
8月には一年に一度の犠牲祭というイスラムのお祭りに参加しました。目の前で、生きた牛や羊が殺されるのはとてもショッキングな光景でしたが、食べ物のありがたさを実感するのはもちろんのこと、改めて宗教や文化の違いについて考えさせられる貴重な経験でした。
大学近くの大きな通りには、飲食店がたくさんあります。
犠牲祭で殺した羊や牛の肉をサテという料理にして、村のみんなで食べました。
隠れた穴場スポット、カリムンジャワの海です。
2018.10.30
アクティビティレポート②(2018年派遣:バンドン工科大学)
経営学部 堀内 友貴さん(3回生)
インドネシア、バンドンでの滞在も二か月目が終わろうとしている。最初の一か月目には軽いカルチャーショックもあったが二か月目になると、日本とは異なる水回り事情や、激辛料理、ストリートフードにも慣れ、日々の生活で精いっぱいだった一か月目には感じることができなかった新たな発見もあった。
同じドミトリーに住んでいる、ベルリンの大学から来た、サラという女の子と仲良くなった。サラはベルリン生まれベルリン育ちだが母親が日本人なので、日本語を話すことができる。英語ではなく自分にとって第一言語である日本語で文化の違いについて外国で生まれ育った人と話すことでより深く文化の違いを体感することができた。
日本から離れて客観的に日本や日本の文化について考えることで、僕の中での日本の良い部分悪い部分というのが少しずつ分かってきた気がする。例えば、サラのつながりで、すでに働いている30~50歳くらいのインドネシア人たちとも仲良くなることができた。日本では自分の周りいる人達は大体が自分と同じ年の人、学生ばかりなので、自分よりも大人な人、しかもインドネシア人と遊びに行ったり、旅行に行ったことは非常に興味深かった。インドネシアの人たちは20歳近く年下な僕に対しても、年齢関係なく一人の友達として接してくれた。日本人は年齢というものを気にしすぎているのではないかと思う。年上を敬うのが日本の文化なのかもしれないが僕は年齢関係なくフランクな関係になれる方がいいと思う。
2018.10.30
アクティビティレポート①(2018年派遣:タマサート大学)
経営学部 畑島 亮太さん(4回生)
経営学部経営学科4回生の畑島亮太です。教養学部の東南アジア研究(SEAS)に所属しています。今回はバンコクの街、タマサート大学、所属学部について紹介します。
街について
バンコクの中心街はとても発達しています。高層ビルが立ち並ぶエリアや高級店が入居しているモールがあります。その一方で、偽物のブランド品を売っているマーケットや露店、庶民向けの屋台が多くあります。屋台では100円から200円で済ませることができます。やよい軒や丸亀製麺、CoCo壱番屋など日本の飲食チェーンもたくさん進出しており、日本食には困りません。
インフラと交通に関してもバンコクは発達していると言えます。電車は距離にもよりますが、30〜50バーツ。バスは基本的に空調設備が付いていないものは6.5バーツ、クーラー付きは13バーツです。タクシーの初乗りは35バーツ、メーターをつけてくれるかどうかは運転手との交渉で決まります。そのほかにも、トゥクトゥクやバイクタクシーなど様々な交通手段があります。夕方や雨が降った時は驚くほど渋滞するので用途に分けて利用します。
大学について
タマサート大学は歴史ある由緒正しい大学です。経済界や政界に多数卒業生を輩出しており、学歴を重視するタイではネームバリューのある大学と言えます。よくタイの京都大学と形容されます。私が通っているメインキャンパスであるタプラチャンキャンパスは市街地から離れた王宮エリアに位置します。大学から徒歩圏内にバンコク3大寺院や、バックパッカーの聖地と言われるカオサン通りがあります。タイの大学には制服がありますが、タマサート大学ではテスト期間以外での着用の義務はありません。大学内のブックセンターで購入することができます。スラックス、ベルト、ネクタイ、シャツ二枚、紋章を購入しても約3000円程度です。
所属学部について
私は教養学部の東南アジア研究に所属しています。ジェンダーやCSR、マーケティングの授業を受講しています。どの講座も東南アジアの文化、歴史的背景を前提に海外諸国と比較して考察されるため非常に面白いです。1つの授業が3時間ですし。英語で15枚のペーパーを中間と期末に書かなければいけない点で、日本の大学より大変です。クラスは30人程度で、8割がタイ人です。留学生はアメリカ、ヨーロッパ、マレーシア、日本人が多いです。
ナイトマーケット
渋滞の様子と街並み
サークルはあまり活発ではないが、学部間のサッカー集まりみたいなものがある
2018.10.30
アクティビティレポート①(2018年派遣:インドネシア大学)
経営学部 川西 歩さん(3回生)
はじめまして!インドネシア大学に留学中の経営学部国際経営学科3回の川西歩です。
インドネシアにきて約2週間が経過しました。
このレポートは毎月様々なテーマで留学中の4人が感じたことについて皆さんに共有していくものになっています。そんな最初のテーマはインドネシアにきて感じたカルチャーショックについて書いていきたいと思います。カルチャーショックと書くとマイナスなイメージでとらえられがちなので、マイナスなことだけでなく日本とは異なる文化に触れたことについて述べていきたいと思います。
まず、大前提として、英語があまり通じません。屋台の人は勿論、現地の人は基本的に英語が通じません。そのため、ご飯を頼むのにも一苦労といった感じです。でも、何とかなります!!
交通手段はGrab やGO-JEKだけでなくアンコック乗り合いタクシーがあります。いつでも乗れていつでも降りられます。値段は1kmで30円ぐらいです。あまりの安さに最初は本当に大丈夫なのか心配になりました。また、乗ろうと思えば何人でも乗っても問題ないのが特徴的です。私たちは最大で14人で乗車しました(笑)助手席に2人に乗っていようがお構いありません。インドネシアに交通ルールはないように感じました。
これは現地の人々にも同じことが言えます。1家族でバイクに全員乗るのは当たり前のようで3人乗りならまだかわいいものです。私は先日、5人乗りを見ました。おそらくバイクで乗れるマックスを見た気がします。朝と夕方は車、バイク、タクシーで大渋滞です。
また、朝と夕方の通勤電車は日本の通勤電車より酷い混雑具合です。電車は元々日本で走っていた電車を利用しています。そんな混雑がひどい電車も、ジャカルタでは現在、地下鉄が建設中とのことです。来年には完成するらしいです。
これでも空いている夕方の道路
夕方の帰宅ラッシュ時間のジャカルタの電車
まだ2週間しかたっていませんが、新興国の現状と発展との狭間で、毎日を過ごしています。もうすぐ学校も始まるので楽しみです!
2018.10.30
アクティビティレポート①(2018年派遣:バンドン工科大学)
政策科学部 塚口 勇真さん(3回生)
バンドンの街・大学・授業
バンドンは他の地域に比べ標高が高いため、昼間でも過ごしやすい気温でとても快適に生活しています。ですが、朝晩は少し冷え込むため私は常に長袖と長ズボンを着て寝ています。現在は乾季なので雨もほとんど降らず、気候の面では日本よりも過ごしやすいように感じています。11月頃から雨季が始まり、1日1回強い雨が降り、感染症などが増えてくるそうなので、注意が必要になります。
街の様子は、私が思い描いていたインドネシア像そのままで、車やバイクが行きかい、時間に関係なく道路は渋滞しており、道路の脇には食べ物などを売っている屋台が並んでいます。また、インドネシアの人口の大半はイスラム教徒のため、豚を使った料理を目にすることはなく、レストランに行ってもお酒を飲むことはできません。さらに1日5回、お祈りの時間に音楽が流れ、不思議な雰囲気に包まれます。このような日本では味わうことのできない宗教、文化はとても刺激的で毎日新しい発見があり、非常に有意義な生活をしています。
大学のキャンパスは非常に広く、様々な施設があり、図書館、ジム、プール、食堂など学生にとって便利なものが多くあります。また建物は、伝統的なものと近代的なものが混在しており、歴史を感じられます。私の学部の建物は比較的新しく建てられたもので、清潔感があり私たちにとって使いやすく、いい環境で学習できています。
授業に関しては、私が専攻しているアントレプレナーシップの授業では多くの授業が実際にビジネスを始めている学生のグループに参加しそれをベースに授業を行います。このビジネスに関わることができるという形が私にとって非常にプラスになるように考えています。グループのメンバーと話をする機会も必然的に増え、本気でビジネスをしている学生から学ぶことも多く、インターンシップとは少し違った経験ができているように思います。その他の授業でも、全体的に少人数での議論の時間が多く、1授業内で学ぶことが非常に多いように感じています。また日本と大きく違うのは1コマの時間で、長いものでは約4時間の授業があり、集中力が自分に欠けていることを実感しました。
まだ授業が始まって2週間ほどなので、これから多くを学び、吸収できるように頑張りたいと思います。
街の様子
屋台の様子
2018.10.29
アクティビティレポート⑦(2017年派遣:タマサート大学)
松下 加奈さん(経営学部3回生)
「きっと、うまくいく」
この映画、ご存知ですか?
これは2009年にインド映画歴代興行収入1位を記録し、大ヒットした映画です。
このタイトルは、劇中のキーワードである”Aal Izz Well”の日本語に訳されたものです。
タイ語で無理矢理噛み砕くと”Mai pen rai”になるでしょう。
東南アジア圏の留学経験者は、この「きっと、うまくいく精神」が、
留学生活中、浮き沈みが激しかった情緒の支えになったことでしょう。
私も紛れもなくその一人です。
私はタマサート大学のBJM(Bachelor of Arts Program in Journalism and Mass
Communication)に留学をしました。
日本人留学生がおらず、右も左も前も後ろも皆無な環境。
住んでいるアパートが今にも潰れそう問題に対する不満。
「成績大丈夫!?」と授業毎に募る不安。
ショートヘアの見た目からレディーボーイに見られ、良くない噂を立てられたこと。
色んな方向から問題が突き刺さってきて、最初はこの現実が受け入れられず、目が腫れるまで泣き
ました。
でも、留学を終えて思うことは、なんだかんだうまくいくんです。
それも、私なりの「きっとうまくいく論」を見つけ出したからこそだと信じているので、きっと
うまくいくための私なりの持論を留学を通じて学んだこととして紹介したいと思います。
① 1人で抱え込まない
辛くなるだけです。無理せず先生や友達を頼って下さい。みんなどうにか助けようと、一緒に色々
考えてくれます。自分でどうにかしようと思わずに、甘えてみましょう。新しい道が開けるかもし
れません。
② 息抜きをする
頭も気分もリセットして、メリハリをつけてみてください。
留学中、生活リズムが崩れると良いチャンスも逃してしまうんじゃないかな、って個人的に感じま
した。
③ でもちゃんと最後まで頑張る
②と矛盾してしまいますが、息抜きに休んでもいいけど、止まることはダメだと思うんです。
なので、うまくいかせるには自分自身の頑張りも必要だと思います。
でも、頑張るにしても①の1人で抱え込まず、困ったら周りを頼ってみてください。そして、②の
息抜きをしてください。このサイクルが私の留学生活の支えでした。
もう気付いていると思いますが、どれも当たり前のことです。
でも、なぜかこの当たり前は留学に行くと、当たり前じゃなくなって、友達と一緒にいる時のい
つも通りの自分になれなくなってしまいます。
だからこそ「きっと、うまくいく」と、楽観的に構えずに、その時の留学を精一杯楽しんでくださ
い。
もしよかったら「きっと、うまくいく」の映画も観てみてください。
そして、このレポートで少なからず留学に対して気が楽になった方がいたら幸いです。
なんとかうまくいった一番苦しんだ授業
この子達のお陰でどんなことも乗り越えることができました。
2018.10.30
アクティビティレポート⑤(2017年派遣:インドネシア大学)
国際関係学部 千葉大地さん(2回生)
八月から始まったインドネシア大学での授業の中で、一番実感したことは生徒たちの授業に対する意欲です。先生が生徒たちに意見を求めたときのみではなく先生が説明しているときに、情報を補足したり、説明に対して意見を出したり、生徒たちの能動的に授業に参加する姿勢はまさに、先生・生徒の双方で授業を「作っている」という感覚を受けました。
続いて、インドネシア大学で勉強する生徒たちの英語の能力には日々感心しました。授業が始まる前に教室に集まった友達同士、インドネシア語で談話をしていたのにもかかわらず、授業が始まったとたん流ちょうな英会話にシフトする様子には「言語の多様性」が非常に高いレベルで実現されていることを感じました。インドネシアの学生の英語力を高くしている要因として、英語を使う機会が日常的にちりばめられていることにあると思います。
例として、インドネシアの映画館で海外の映画が上映される場合インドネシア語への吹き替えはされないということがあげられると思います。日本では、海外の映画でも日本語に吹き替えがされ私たちは難なく視聴することができますが、上記の通りインドネシアの映画では、英語で物語を理解することが求められるため英語のリスニング能力、理解力は自然に上がるでしょう。スーパーなどで売っている食料品も日本と比べて海外産が多いため、消費者がおのおの商品の情報を把握するためには英語で解釈することが求められます。この二つの例でみられるように、インドネシアの学生は日常的に英語力が求められます。そしてこの習慣が高い英語力に起因しているのではないかと思います。
インドネシアの生活において達成した最も印象的なことは、国を超えた人間関係を築けたことです。インドネシア人はもちろん、インドネシア大学に留学生としてほかの国から来た人たちとも友達になりました。休みの日には観光をし、授業後にはクラブに行って新たな人間関係の構築を実現しました。母国語は違うとしても理解しあうことは可能なんだなと感じました。
2018.10.29
アクティビティレポート②(2017年派遣:ガジャマダ大学)
経営学部 澤邊 駿さん(3回生)
留学を通して学んだこと・達成したこと
新しいことに挑戦することが留学中の目標でした。その一つとして、私は餅を販売するスタートアップ企業を設立し、リーダーとしてインドネシア人2人とドイツ人1人を牽引しました。
計画当初は実店舗を持ち、餅を販売する計画でした。しかし、学校との協力で屋台と使用して販売を試みた結果、売り上げが伸びませんでした。私は味の追加や様々な工夫をしましたが、それとは裏腹に売り上げを伸ばすことができませんでした。餅が売れない理由を突き止める為に、私は販売市場で聞き込み調査を行い、問題は販売価格である事に気付きました。そこで私は、ターゲット層を変更し、実店舗を持つのではなく、食堂やコーヒーショップに販売を委託しました。
その他にもチーム内部のマネジメントにも工夫をしました。私は、個人の生産性がチーム全体の業績を大きく左右すると考えております。そこで、共同作業の改革を行い、チームメンバーに影響を与えました。具体的には、共同作業を苦手とするインドネシア人の為に、私は共同作業の時間を短縮し、会合では常に要点を絞り、指示を出すことを心がけました。私が司令塔としてチームメンバーに対し個人がすべき課題の明示、分業を行う事で個人の生産性の向上を図りました。結果5ヶ月間で売上を開始当初の月の3倍以上に伸ばす事に成功しました。
この経験を経て、私はリーダーの役割を再確認し、個人の能力を最大限に引き出す事の重要性を学びました。リーダーとして、チームを牽引するだけでなく、個人が能力を最大限に発揮できる環境づくりをした事で今回の成功に至ったと感じております。