 |
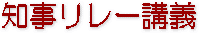  |
|
| 2010年 4月 20日 鳥取県 平井伸治知事 |
||
「 地域主権改革と鳥取県 」 今回は、平井伸治鳥取県知事より、鳥取県の特徴をはじめ、地方分権をめぐる動き、地方財政問題などについて、講演があった。
今日、講義が始まる前に、近くに座っていた学生に出身地を尋ねると、兵庫県の淡路島や山口県など、様々な土地の名が上がった。この立命館大学には、全国各地から学生が来ており、それぞれのふるさとがある。いろいろなところにふるさとを持つ人が集まって来て、社会を形成している。その中で大切なことは、この国は一つの国だということであり、それぞれの地域が輝かないといけない。そのためにどうしたらよいのかを考えることが、私たち地方の現場で働いている者に 「春眠暁を覚えず」という言葉があるが、私たち日本人は少しその気分が長すぎたのではないかと思う。政治がこれからどうなるだろうか。 民主党、自民党という大きな政党が二つある。民主党は国民新党や社民党と一緒に連立政権を作っているが、支持率が低下してきている。これは、政治のリーダーシップや日本のシステムに対して疑問が生じているということである。そこで、「たちあがれ日本」や「日本創新党」など様々な新しい政党が出てきている。イギリスは保守党と労働党の二大政党制だが、今総選挙をしており、この二大政党制が崩れようとしている。第三党として自由民主党があり、今この政党の支持率が上がっている。二大政党制から、2.5大政党制に変わるのではないかと思う。日本もそれに近い状況が起きようとしている。民主党が自民党を参議院選挙で破り、昨年夏の総選挙で過半数を取った。その後、改革を起こそうとして鳩山総理がいろいろ仕掛けているが、普天間問題だとかで厳しい状況に追い込まれている。今、政治システムが変わろうとしている。民主党がどうなるか、参議院選挙がどうなるか分からないが、国民が審判を下すだろう。自民党、民主党以外の党に注目が集まり始めているのも事実である。おそらく、自民党、民主党以外の党がそれなりに票を得て議席を獲得していくだろう。そのようなときに政治的な混乱があるが、われわれがしっかりとした社会のポリシーを打ち立て、それを実行していく力をもっていかなくてはならない。 この時代の変わり目をどうやって乗り切っていくのかを、今日は地域主権の観点から見ていきたい。
・水木しげる氏の出身地 今、水木しげる夫妻の生活をモチーフとした「ゲゲゲの女房」というNHKの連続テレビ小説が放送されている。水木しげる氏は、鳥取県米子市のご出身である。 ・山陰海岸ジオパーク 東西約110キロにわたる海岸である山陰海岸ジオパークの世界認定を受けようとして、今頑張っている。山陰海岸ジオパークは、日本海の歴史を知ることができる。今から2500万年前くらいから少しずつ日本海が出来ていった。日本はもともとアジア大陸の一部であったが、切り離されて現在のような形になった。 ・牛骨ラーメン 各地に様々なラーメンがあるが、鳥取では牛骨を使う伝統がある。もともとは満州のもので、戦争からの引き上げの人が持ち込んだものである。また、鳥取県では牛をたくさん飼育している。先般、日本テレビ系列のB級グルメのコンテストで、富士宮の焼きそばに次いで牛骨ラーメンが第二位となった。 ・鳥取自動車道 佐用ジャンクションから北側にまっすぐ鳥取自動車道が開通し、京都や大阪までずいぶんと近くなった。この自動車道の特徴は無料であること。これは、小泉構造改革で道路公団が問題になり、道路公団をなくせという議論が出たときに作られた新しい制度を利用したためである。以前は、高速道路は道路公団が造っていたが、それに代わって、自治体がお金を出すのであれば無料の高速道路を造るという新直轄事業のシステムである。西日本では第1号の開通となった。 ・温泉 鳥取には10を超える温泉地がある。その中でも有名なのが、皆生温泉である。皆生温泉は海から沸いており、ミネラル分が豊富に含まれている。また、三朝温泉も有名である。三朝温泉は、1160年代に発見された古い温泉の一つ。世界で一番ラドンの含有量が高い温泉と言われており、周辺住民のデータをとると、その他の地域よりガンにかかる人の率が半分であった。 ・食のみやこ鳥取県 食のみやこ鳥取県として、様々な食材を供給している。マツバガニの一番とれる漁場が鳥取県から兵庫県にかけてのところにあり、値段もリーズナブルである。また、境港はマグロの漁獲高が日本一である。大間などとはシーズンが異なり、鳥取では6月〜8月がシーズンである。その他ハタハタなどもとれる。江戸時代に高級品であった魚のかわりに豆腐でちくわを作った豆腐ちくわという料理もある。 ・まんが王国 最近はまんが王国ということで盛り上がっている。境港には、水木しげる記念館がある。平成に入ったバブル頃に、竹下内閣がふるさと創生1億円事業を行ったが、境港ではそのお金を使って妖怪のブロンズ像を商店街の真ん中に設置した。当時商店街の人は、「そんな辛気くさいものを置いてどうするのだ。」、「人が寄ってこないではないか。」と市役所にずいぶん文句を言った。しかし、話題となり、人が集まってくるようになった。今では139体の妖怪が置かれ、年間200万人を目指そうという観光地になっている。大阪府の橋下知事も視察に訪れたが、「ここのまちづくりは一つの地域づくりの見本になる」と評価していた。また、「名探偵コナン」の作者の青山剛晶氏や、漫画家の谷口ジロー氏も鳥取県のご出身である。平成24年の国際マンガサミットを鳥取で開こうと誘致をしている。
地方分権とは、中央集権の対義語で、権力、権限を地方に分けることである。ヨーロッパなどでもDecentralizationといわれている。日本の場合、敗戦後アメリカがやってきて、進駐軍の下で日本国憲法が制定され、新しい民主主義の道を歩むことになった。そのときにアメリカは、この国には地方自治がないという危惧を持った。当時の都道府県は国の出先機関であり、市町村はあったが、財源がなく脆弱なものであった。 その後、地方自治法が制定され、税財政の観点では、地方税法や地方交付税法が順次整備された。財源の観点では、アメリカの学者のシャウプが日本の税財政制度にアイデアを出した「シャウプ勧告」というものがあり、そこで一つのモデルが作られ、今に引き継がれている。例えば、固定資産税は市町村に、個人住民税は市町村と都道府県に、事業税は都道府県に配分するといったものである。事業税については、シャウプが考えたのは付加価値税であったが、実際は所得で課税することになった。この辺りに考え方の差があったが、今でも十分に修正されていない。一部は付加価値税に変わったが、それはごく一部である。 財政の焦点となる総額も十分ではないという状況は今でも続いている。これを是正しようというのが地方分権の考え方である。平成5年に地方分権一括法が決議され、平成12年に施行された。この過程で地方分権ということが考えられた。地方分権を本格的に提唱したのは、細川護熙元熊本県知事である。細川元熊本県知事の問題意識は、バス停の設置許可が国の権限であり、なかなか設置することができなかったということから来ている。当時国は臨調と呼ばれる行財政改革をしていた。行革をすると、政府がダウンサイジングされ今まで提供されていたサービスがなくなると思うかも知れないが、必ずしもそうではない。細川元熊本県知事は、「暮らしをよくする部会」というものを引き受け、行政改革をし、政府を小さくするが、暮らしをよくしようとした。ここで生活を豊かにしようとして出たものが、地方分権である。 国、県、市町村という三層制の行政構造だと、無駄が存在する。若干改善されたが、国の関与が多くある。例えば、幼稚園の園児一人あたりの面積の基準や、理髪店の店内の構造についての基準などがある。無駄を排除し、自分たちで必要なものに順番をつけて選択し、そこに集中投資していけば、地域では欲しいものが上から順番に手にはいる。つまり、政府全体の大きさは小さくなったとしても、お金が有効に使えるため効用は増す。このような考え方を、ナショナル・ミニマムに対してローカル・オプティマムという。ローカル・オプティマムの形で行政を進めるということは、国の権限あるいは税源や人を地方におろしていき、都道府県や市町村が元気になることで、住民の幸せを最大にしようということである。 平成12年の4月に機関委任事務が廃止され、自治事務と法定受託事務に整理された。これは素晴らしいことだと学説上も言われ、大改革に思えたが、現場の感覚ではあまり変わっていない。財源のあり方から、古い因習まで含めて全て変えてもらわないといけない。平成16年から18年に小泉改革があった。三位一体の改革と呼ばれる。三位一体の改革とは、国庫補助金の整理、国から地方への税源移譲、地方交付税の改革をあわせて行うというものである。ところが実際に国庫補助金が減らされたのは4.7兆円であったが、それに対して税源は3兆円しか移譲されなかった。さらに地方交付税が5.1兆円削減されていた。結局約7兆円のお金が地方から消えてしまい、これ以来地方は非常に財政が厳しくなった。 平成18年に地方分権改革推進法が施行され、地方分権改革推進委員会が累次の勧告を行ってきた。例えば、出先機関を整理するということなどをいっている。そのような勧告を受けて動き始めたときに、民主党政権になった。民主党政権では今、原口プランというものがある。地方分権が地域主権改革と言葉を変えた。今年の夏頃までに地域主権戦略会議で、これからの地域主権改革の道筋の大綱をまとめるということにしている。 国直轄事業負担金というのがあるが、例えば幹線道路を造るのは国の事務になっている。その国がやる事業に対して、3分の1程度地方が負担をするというのが通常のルールとなっている。他にも、辞める人の退職金や、国の役所を建てる場合の建設費も地方も一緒になって面倒を見るということになっている。それはおかしいということで、大分強く政府の方に申し上げた。昨年の8月の総選挙のときもマニフェストで民主党だとか自民党だとかに呼びかけた。それに基づいて、この国直轄事業負担金は、維持管理については既に廃止ということになった。さらに、建設事業のほうもこれから改めていこうとしている。 国庫補助負担金が今約21兆円ある。これまでは、使い道など様々な制約がついたひも付き補助金であったが、もっと良い仕事ができるように、自由にして欲しいというのが都道府県や市町村の要求であった。民主党が政権をとり、一括交付金化するということを打ち出しているが、注意しないといけないのは、総額が減らされるのではないかということ。三位一体の改革のときも、補助金が4.7兆円削減されたにもかかわらず、移譲された税源は3兆円であった。同じことが繰り返されてはならない。
時間も迫ってきたので、地域主権改革の中の本質の一つである財源の問題を取り上げる。平成19年の統計で、国地方あわせた税収は約90兆円あるうち、国税が約50兆円、地方税が約40兆円の割合で、国対地方が約3:2となっていた。実際に仕事をしている比率は逆であり、この逆転というものを考え直さないといけないのではないか。地方の税収をしっかり確保するために、国税と地方税あわせた税制度の改革が必要ではないかというのが一つのメインテーマである。忘れてはならないのが、全国には1000を超える自治体があり、それぞれの財政力が違うが、同じように住民を抱えて、同じように行政サービスを提供する。どこの自治体でも標準的なサービスが提供できないといけない。そのためには、税収のあがる自治体もあればあがらない自治体もあるので、これを是正して財源を保障する意味で、地方交付税ないし地方共有税という制度が是非とも必要である。 国税の内訳を見ると、所得税33.2%、法人税22.5%、消費時21.6%、その他22.7%となっている。市町村民税では、個人市町村民税が35.5%、固定資産税が42.5%となっていて、この二つで約4分の3を占めている。個人住民税や固定資産税は非常に安定した税収があがるため、毎年同じような行政サービスを提供する現場の市町村にとっては非常に良い性格の税である。都道府県税は、個人都道府県民税で32.4%、法人二税で28.3%、地方消費税が15.7%となっている。国税と比べると、法人関係税の割合が多く、消費税の割合が少ない。これは問題があって、消費税と法人二税では税の意味が全く違う。各都道府県によって事情は異なるが、鳥取県では個人住民税だいたい140億円くらい、法人二税で140億円くらい。自動車関係の税も130〜140億円ある。だいたい同じくらいのウェイトを持っている。地方税の税収の動きを見ると、固定資産税は時代とともに伸びてきて、バブルが崩壊して低成長に入ると、だいたい税収が横ばいで推移していく。これは非常に安定的な税収であるし、経済の大きさに基づいて大きくなっていく。これに対して、法人二税は景気の波によって5兆円規模が10兆円規模になったりを繰り返す。5兆円と10兆円では2倍の差があるが、日々のわれわれ現場の行政サービスは、景気が良い年は倍ほどサービスするということにはならない。この税目は本当は都道府県税には向いていない。法人に対する課税を付加価値でやろうというのがシャウプ勧告の趣旨だったが、当時、赤字法人からも取るのか、という反発があったため、所得を標準として課税するようになった。ただし、所得では、法人が儲かった年は税収ぐんと伸びるが、儲からなかった年は落ち込んでしまう。法人二税が都道府県の基幹税となっているため、税収構造が非常に悪くなっている。本来であれば、地方消費税が一番地方税の税収構造としては望ましい。 地方借入金残高は大体200兆円くらいとなっており、借金の比率が増えてきている。社会保障負担も、平成23年度には地方負担が18兆円になる見込みである。今後、高齢化が進むと、ますます厳しい状況になる。バブル崩壊以降、国の政策で地方も経済対策を打ったが、これによって地方が財政的に疲弊しているというのも現状である。それを建て直すための税収が必要である。今、地方財政は大変な財源不足になっており、昨年度の知事会の試算では、平成24年まで何の対策もとらなければ、基金がなくなると見込まれている。他方で、政府の現在の方針は、税負担、国民負担には手をつっこまないとなっている。国民負担率や租税負担率は、だんだんと上がってきており、社会保障負担率が租税負担に近づくくらい増えている。これは、介護保険が導入されたり、高齢化が進み、社会変革に対応するための動きが出ていることなどの影響である。 これからの税収を考える上での指標になると思うが、地方法人二税ではとても公平に行政サービスを提供できない。比較的公平なのは地方消費税である。税収が一番多い東京都は一番少ない沖縄の1.8倍でとどまっている。また、人口一人当たりの税収額の指数も、ほぼ90%台となっている。これからの基幹税収を考えたときに、偏在が無く、景気が変動してもだいたい同じ税収になる地方消費税が一つの焦点になるだろう。直間比率を見ると、日本は国税6:4、地方税85:15になっている。地方税が直接税に傾きすぎている傾向がある。ドイツだとかカナダだとかそうした先進国の例に倣えば、国と地方は同じような消費税割合でも良いのではないか、という議論もある。 新しい税目として、地方環境税が注目を集めている。おそらく今年度いっぱいでだいぶ議論になってくると思うが、自動車では自動車税、軽油取引税、自動車重量税という三つの税金が課税されているが、暫定税率を見直すという議論が出ている。当面は今の税制を維持した形になるが、来年度に向けてしっかりと議論しないといけない。京都議定書のことや、鳩山総理がCO2の25%削減を言ったことから考えると、それに対応して、新しい税制を作らないといけない。環境税がそれに有効ではないかと思う。地方公共団体の温暖化対策は、全国的には1兆8000億円にものぼり、これだけの規模になると、やはり一定の税収を考えないといけない。民主党マニフェストの中でも、自動車重量税を自動車税に一本化するということが書いてあったが、環境に配慮した自動車課税のあり方もこれから焦点になってくるのではないかと思う。
地域主権を確立するために、行政庁のいろんな権限の問題も解決しないとならない。例えば、地方出先機関はすべて地方で引き受けられると思っている。そうして無駄をなくしていくという努力もできるし、税や財政にも切り込んでいって、トータルでこの国のあり方を変える改革をしていかないといけないという時が来ていると思う。鳥取県では地域主権研究会を作り、地域主権型社会への提案をほぼまとめた。イメージで言うと、今までは菱餅(国、都道府県、市町村の三層それぞれに重なっていて同じようなことをやっている、という意)のような行政だったが、これでは効率が悪い。もし、三層になっているにしても、これがロケットだったらより遠くまで行くことができる。このような形にして、国と県と市町村の重なっている部分を排除して、新しい行政サービスをつくれないかということを考えている。 このような時代になると、自治体間のパートナーシップも重要になってくる。県と市町村が一緒になって仕事をする場面とか、あるいは県と県が一緒になって一つの役割を果たすということもある。例えば、この春から鳥取県は兵庫県、京都府と一緒になってドクターヘリを運航している。兵庫県の豊岡というところに基地をもって、そこから飛んでいくようになっている。ドクターヘリを維持しようと思うと、年間8000万円くらいかかるため、一つのものを自治体間で割り勘で持つのも必要ではないだろうか。そういうハイブリッドサービスを今後順次提供していきたい。広域連合や、一部事務組合という特別地方公共団体があるが、使いづらい。地域主権の時代にふさわしい自治のあり方が必要ではないか。
鳥取県は、ボランティアの参加率が全国一位で、34.5%の人が一年間のうち何らかのボランティアに参加している。このようなことを活かして、住民の皆様と、あるいは企業と、顔が見えるネットワークを作ろうとしている。行政だけで全ては絶対できないし、住民の皆様も支えを必要とする場面がある。お互いにパートナーとしてやっていく関係を作っていくことが大事である。それを仮に鳥取力と呼んで、鳥取力創造運動というのを始めた。様々なところにでかけて話し合いをしたり、フォーラムをやったりといった取り組みをしている。鳥取砂丘除草ボランティアや、大山頂上トイレキャリーダウンボランティア、さまざまなボランティア活動に多くの人が参加している。 また、祭りにあうまちづくりを推進する「NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会」や、廃校になった小学校・幼稚園を活用した劇場である「鳥の劇場」など、様々な文化的取り組みをしている。産業としては、次世代電気自動車の製造拠点の誘致や小水力発電装置の活用、とっとりバイオフロンティアなどの取り組みをしている。北東アジアゲートウェイ構想を打ち出し、西日本における北東アジア地域への窓口となることを目指している。
人生はたった一度だけしかない。みなさんにとってかけがえのない人生だと思う。いろんな選 ゲーテの言葉に「めいめい自分の家の前を掃け、そうすれば街は清潔だ。めいめい自分の課題を果たせ、そうすれば市会は無事だ。」というのがある。めいめい自分の課題を果たすよう奮闘されますことを期待します。
答 自民党は肯定的、民主党は冷ややかに見ているが、私はどのような形の道州制にするかによって決めるべきだと思う。国にとって都合の良い道州制もある。例えば、地方を各ブロックに分けても、国が事務所を置き支配下におくことも考えられる。そのような形では意味がない。様々な権限を国から切り分けた形の道州制が望ましいが、国はコントロールを残そうとするので、なかなか難しい。議論していくことが重要である。 問 境港の商店街に妖怪のブロンズ像を設置するときに住民の反発が
あったそうだが、どのように理解を得たのか。また、住民への接し方のコツがあれば教えてほしい。 答 どのように輪を広げるのかが大切である。人間はおもしろくないとやる気にならない。商店街の人も新しい商品をつくったりして盛り上がった。私の経験でも、行政が何かを決めて突っ走っても誰もついてこない。まず地元の人達がなにをしたいかを考えて、それをまわりがサポートする形が望ましい。内発的な力を引き出すことが大切である。日本は民主主義が成熟した国なので、このようなことはもっとできると思う。
|
|||||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |