 |
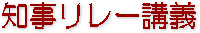  |
|
| �@ �@2010�N�@4���@27���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�̎R���@�m��g�L�m�� |
||
�@�u�@�a�̎R�I�����[��������@�v�@
����́A3��ڂł��B2006�N12���ɒm���ɂȂ��Ă���A3�N�����炢�ɂȂ�܂��B �P��ڂ́A�m���ɂȂ��Ă����ɁA�u�����܂����B���̂Ƃ��́A�a�̎R���͑O�m�����߂܂�A�u�������B���ǂ�����ĉ��v�����̂��v�Ƃ������b�����܂����B �Q��ڂ́A����̃��C���i�b�v���ł��������Ă�������A�ǂ��������������Ă����̂��Ƃ����b�����܂����B 3��ڂ́A�������Ƃ������Ă��������낭�Ȃ��̂ŁA�ς�������Ƃ�b�����Ǝv���܂��B �a�̎R���̃I�����[��������B���̂�����ƕς����������A�b�����Ǝv���܂��B
�����ł́A�펯�̂���������ɂ������B �@�@�����J �����J�͐�ɐ��������Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B�ǂ�Ȃɂ��炵��������ᔻ�������Ȃ��甽�Ȃ��A���������Ƃ�����C�����Ă����Ȃ��Ƃ��������Ă����܂��B�����nj����̓X�e���I�^�C�v�I�B���߂�ꂽ�����J�̉��l�ړx�ɂ���āA�V���Ȃ��������Ƃɂ݂�Ȃ��u�������������v�Ƃ������ɂȂ��Ă��Ȃ����Ǝv���B �R�̏����J���A�|�[�Y���Ƃ��Ă�邱�ƂŐl�C����肽���Ƃ͎v���܂���B �����őO�m��������Ă����u���۔�v�̌��J����߂܂����B�Ȃ���߂��̂��Ƃ����ƁA���������������Ƃ�����Ă��邩��B�����A�Ƃ����킯�ł͂���܂���B�u���۔�v�Ƃ͉����Ƃ������Ƃ��A�l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B �u���۔�v�ƕ����Ė��Ԃł���悤�Ȍ��۔���v�������ׂ��邩������܂���B�Ⴆ�����ӂ���Ƃ���������Őڑ҂���ƈ�ʂ̐l�͍��o�����ł��傤�B�����ŏ��͂������o���Ă��܂����B �O�̒m��������S���������Ƃ����Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�m���ɂȂ�Ƃ��ɑO�̒m����HP�Ȃ��āu����Ȃ��Ƃ�����Ă������������̂��v�Ɗm�F����̂ł��B�����Ɍ��۔�����J����Ă��āu�Ȃ��Ȃ���邶��Ȃ����v�Ǝv�����̂ł����A���g���̂����Ă݂�Ɓu�قƂ�nj��ۂ��Ă��Ȃ�����Ȃ����v�Ǝv�����̂ł��ˁB�Ȃ��Ȃ獡�̂悤�Șb���قƂ�Ǐo�ĂȂ���������ł��B �����̌��۔�ɂ́A�Ⴆ�Όc���Ƃ��Ă̂������̎��ɂ��Ԃ��o���A����͌��۔�ł��B�������A���X�ڑ҂͍����ɂ�������Ă���̂ł����A�����̐l�������Ƃ��ɐڑ҂Ƃ��ĐH��������̂͐H����ł��B��ʓI�Ɍ����Ă�����۔�Ƃ͂��̐H����̂��Ƃł��B�@ �܂�A�u���۔�v�Ƃ������t�ɒ��ڂ��āA���۔�����J���Ă���u���͏����J�����Ă��܂��v�Ƃ���̂́A�R�̏����J���Ǝv���܂��B ���������������Ƃ�b���ƁA��ʓI�ɂ́u�m�₳��͏����J�ɑ��ĐϋɓI�łȂ��ێ�I�Ȑl�v�Ƃ������ɑ�������̂ł��ˁB�������������ɔ��������āA�Ӓn���Ă₹�䖝���Ă������Ǝv���Ă����̂ł����A�悭�悭�l���ď����J������̂͐������̂�����A�u�R�łȂ������J�v�����悤�ƍl����悤�ɂȂ����̂ł��ˁB �@����A�x�ꐻ�쏊�̖x�������Ƃ�����v�ږ�̕��ɁA�e���r�a�̎R�Ƃ����Ƃ���ŗ��h�ȑΒk�����肢���܂����B�����Ă��̌�x�ꂳ�u���y�����܂��傤�v�Ƃ��������ꂽ�̂ŁA�x�ꂳ��̂�����ŏ����オ���Ă��܂����B�����������Ƃ�S�����J���Ă��܂��B�x�ꂳ��ɂ��y�����Ă�������̂͗Ⴆ�u���y�����Ă����������v�ƁA���ɂ�����A����x�o�Ƃ�����Ə����Ă��܂��B����ʼn������傪�������ɏ����J���āu���A�ǂ��Łv�Ƃ����̂����J���܂��B �����A���̒��ɂ͏����J������Ƃ����̂����܂��B�����J�̂Ƃ��Ɉӌ����ɗ��āA�����J�����Ă���Ȃ��Ƒ����A�����Ă�����Ɓu��ڂ��ʂ������v�Ƃ���l�ł��B�����Ĕނ�́u���ɂ��킩��悤�ɏ������Č��J���Ă��������v�ƌ����܂��B�����Ă��������l�̓}�X�R�~�ɋC�ɓ����Ă��邽�߁A�s�����}�����܂��B�܂�A���̂Ƃ���ɏ����H�����Ă�����Ƃ������Ƃł��B�����ǁA����ɂ���ĂƂĂ��Ȃ��R�X�g��������B�����R�X�g���P�O�O���l�̌����ɐs�����̂��A�ꕔ�̂��̗l�Ȑl�ɐs�����̂��B���݂̍s�����͉��̔ᔻ���Ȃ����̂悤�Ȑl��������҂ɂȂ��Ă��܂��B ���ꂩ��I���u�Y�}���Ƃ������̂����܂��B�V���Ȃǂ̃��f�B�A�������J�̋L���������ۂɂ́A�I���u�Y�}���̘b�����ƂȂ�܂��B�Ȃ��Ȃ�ȒP������B�I���u�Y�}���ɑ��Ėl�l�͕]�����Ă��邯�ǁA�ނ�͕ʂɑI���őI�o���ꂽ�킯�ł��A��w�����̂悤�ɂ݂Ȃ���Ɏ�����Ă���l�ł��Ȃ��B�����u�����J�ɂ��Ă̓I���u�Y�}���ɕ������v�Ƃ����X�e���I�^�C�v�I���z�ɂ���āA�ނ�ɕ��������Ƃ������[�g���ł��������Ă��܂��B�����čs���͔ނ�Ɍ}�����邯��ǁA���ꂪ�{���ɐ��`�Ȃ̂��B�F����A���l������������Ǝv���܂��B �܂�A�u�����Ƃ͉����B���`�Ƃ͉����B�v�Ƃ������Ƃ������l���čs��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B �A�@�������B���x���v �a�̎R���ł́A���̑O�̒m�����A�܂��{�茧�╟�����ł��m�����߂܂��Ă��܂��B����͂��ׂĊ����k���̂��߂ł��B���R�A�Ƌ֖@��ƂɂȂ邵�A�������B�̎d�g�݂�W�Q���A�����d�ƂȂ邽�ߍ߂͏d���̂ł��B�����Ă����ގ�����̂��u�������B���x���v�v�Ƃ������ɐ��̒����Ȃ��Ă��܂����B��������ގ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂����A�ގ������㉽���c��̂��A�s���Ƃ��čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł��B �܂�u���[��������Ȃ�v���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɒP�Ɍ}����������ł́A��ŕ��Q���ł�B�Ⴆ�Ί����k������߂悤�Ƃ��A����������������ړI�Ƃ������x�����Ƃǂ��Ȃ�ł��傤���B�������������B�ɑς����˂���Ƃ��A�蔲���H�������邱�ƂɌq����A������H�ŋ����ɕ����Ă������ƂŒn��̊�Ƃ��Ȃ��Ȃ邱�ƂɌq����A�Ⴆ�ЊQ�̂Ƃ��ɏ����Ă�����Ƃ��Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�͂����Ă���ł����̂��B�����������Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����{�̖�ڂł��B ��ʓI�ɂ́A��ʋ������D���ǂꂭ�炢�����̂�����l���Ă��܂��B�����āA�S���m����Ƃ����Ƃ���Ń��R�����f�C�V�����Ƃ������̂����߂܂����B���͂���ɑ��Ĕn���n�������Ǝv���܂��B�����ǃ}�X�R�~�͑S���m����̃��R�����f�C�V�����͐�ƂȂ�A�u����ɂ����ɑ����L���b�`�A�b�v���邩�v�Ƃ������Ƃ��]�����̂����ɂȂ�܂��B �͈̂�ʋ������D�ɂ���Ēk��������Ƃ��͓̂�����O�̂悤�������B�������Q�O�N�قǑO����Ƌ֖@�ᔽ�Ƃ��ĕ߂܂�悤�ɂȂ�܂����B�܂�A�k�������ƌ��Ȃ��͖̂@���ł��B�Ƌ֖@�͌��������߂����Ƃł͂���܂��A�X���[�Y�ɓƋ֖@���{�s�����Ȃ���Ȃ�܂���B�����ǁA��قnj��������Ƃ���������l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ��X�͂P�N�����Ă������萧�x���l���܂����B���s��w�̐搶�A�����Č����c�̕��A���Ƀo�����X�̎�ꂽ�ǂ���������ɑ���c�_������Ă����̂ŁA���̂悤�Ȑl���W�߂Đ��x�Ɋւ���c�_�����܂����B�����Ă��̋c�_�𐧓x�������Ƃ��ɁA�u���[��������Ȃ�A�����Ȃ�����ǂ��Ȃ邩�v�Ƃ����������Q���o�ȂȂ����A�ƍl���܂����B �����Ĉ�ʋ������D�͌��݂Ɋւ���S�Ăɓ�������B���̎��݂͑S���Řa�̎R�����ł��B�Ⴆ�n�[�h���A���̌��ݕ��̑|���ȂǂƂ��\�t�g���A�ǂ���Ƃ��ł��B�w���̓[���ł��B�Ƃ��낪�w�����[���ɂ���Ƃǂ��Ȃ�̂��A�u���[��������Ȃ�v�̎v�l�ł��ˁA�w���Ƃ����̂͐a�m�N���u�ł���A�o����Ǝv���l���w������킯�ł��B�Ƃ��낪��ʋ������D�ɂ���ƁA���N�U�����\�͂��Ȃ��l�������Ă����邱�Ƃ�����܂��B���̂悤�ȕ��Q��h�����߂ɁA���w������݂��܂����B���̂悤�Ȑ��x���l����̂�1�N�قǂ����A�������C�����s���Ă��܂��B ���̌��ʂǂ��Ȃ����̂��Ƃ����ƁA�ڂ����͌���HP����������������킩��̂ł����A�����̗\����܂��܂��B�������Ƃ��������ł��B �����āA���D���ɂ��Ęb���āA�펯�̉R�ɂ��Ęb���Ă݂����Ǝv���܂��B���D���Ƃ����̂́A�\�艿�i�Ύ��ۂ̒��B���i�ł��B���ۂ̒��B���i���A�̂�78���������̂��A87���ɏオ��A���D�����オ�����B�������A�����炷���������100���ۏႳ��Ă���Ƃ������Ƃł��B����ė��D�����������Ƃ����ł͂Ȃ��B �������A�I���u�Y�}���͗��D���������Ɓu�����������Ƃ����Ă���̂ł͂Ȃ����v�ƍl����̂ł����A������ƒ��g�̂ӂ����ċc�_�����Ăق����B���͓K���ɋ������s���Ă���̂ł���A100���ł����ƍl���Ă��܂��B �Ȃ��Ȃ痎�D��100���ɂȂ�Ƃ����̂́A�܂����݂ɕK�v�ȍޗ����ώZ���ă}�[�W����������ƍڂ��܂��B��������Čv�Z����Ƃ��傤��100�ɂȂ��ł��B�܂�100�łƂ��ĂȂ��s�v�c�͂Ȃ��B�����ă}�[�W�����}�C�i�X�ɂȂ�ƁA����̓_���s���O�ƌ����܂��B�܂�܂Ƃ��Ȏ��Ƃ���点�悤�Ǝv������A���D����������悤�Ȑ���͊Ԉ���Ă���̂ł��ˁB�܂肱�ꂪ�����̌��݂ł��B �B�@�������S���Ǝs�������S�� ��X�͒������S�������Ƃɔ����Ă��܂��B���̒������S���Ƃ������O�����A�䂪���̒n�������̕n����������킵�Ă���ƌ����܂��B���̌����H��������Ƃ��ɁA�������Ƃƌ����̂ł����A�Ȃ���������Ă���̂ɒ����Ƃ����̂ł��傤���B����́A�u�����x�z���Ă���v�Ƃ����l���̕\��ł͂Ȃ��ł��傤���B ���̒����H���ł����A�n�������̂��������S���Ƃ��ĕ��S���Ă��܂��B�������A���������獑��100�����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B�����Ă��̂����͍H����������ސE���ɉ����Ă��܂��̂ŁA����Ȃ��ƂɌ��͕��������Ȃ��B���������ĕ��S���͏�������܂������A�c���Ă��镔��������܂��B �������A�������Ƃ���X�͎s�����ɑ��Ă���Ă��܂��B���̍H���ɑ��Ďs�������畉�S�������������Ƃ������x����X�͍s���Ă��Ă��܂��B����ō��ɑ��Ē������S���x���������݁A����Ŏs�����ɑ��Ĉ��㊯�̂悤�Ȋ�����ĕ��S�������炤�A����͑S���ԈႢ�A���`�ɔ����Ă���Ǝv���܂��B�Ƃ������ƂŁA�a�̎R���ł́A�s�������畉�S���������Ȃ����Ƃɂ��܂����B ����͍����I�ɔ��Ɍ��������Ƃł����A���`�ɔ����邱�Ƃł���Ƃ��A���̐�����s���Ă��܂��B �C�@�������H�����ƒn�f�W���� �u���������ł��������Ǝ����Ŏn��������v�Ƃ������Ƃɂ��ďq�ׂ܂��B �n�f�W���̂ɑ��Ă͊Ԉ���Ă͂��Ȃ��Ǝv���܂��B���������̐�������ۂɂ͓d�g���o���Ă���l�ɁA�n�f�W���o�����Ȃ���Ȃ�܂���B�����ǒn�f�W�ƃA�i���O�ǂ���Ƃ��o���ۂɂ́A�����̐ݔ������E�Ǘ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A���N����u�n��A�i���O�d�g�͏o���Ȃ��Ă����v�Ƃ����̂ł��B �����ƊE�Ƃ����̂͋K���Y�Ƃł�����A���̑����Ȃ̐ӔC�͔��ɏd���B�u���[��������Ȃ�v�ƍl����ƁA���̂悤�Ȗ�肪�o�Ă��܂��B���s�ł��R�Ɉ͂܂�Ă���Ƃ���͂���Ǝv���܂����A�R�̒��͓d�g���͂��ɂ����A�A�i���O���͂��Ȃ��Ƃ���̓f�W�^��������܂���B�A�i���O����ɎR�ɏZ�ޏZ���͋����A���e�i�����Ă܂����B�������A�����ȂƑ�e���r�ǂŁu�A�i���O���o���Ȃ��v�ƍ��ӂ���ƁA�ނ�̓e���r�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�n�f�W������̂͌��\�ł����A�u�n�f�W�����邱�ƂŎR�ԏZ�����e���r�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�v�Ɨ\�����A���̂��Ƃɑ���ۏ��K�v�ł��B ��������Ă��Ȃ������Ȃ͖��ӔC�ł͂Ȃ����B�N���[���������ɂ�����������Ă����̂ł����A�܂�100���ł͂���܂���B�����100�����̐ӔC�̂͂�������A�������S���ׂ����ƍl���Ă��܂��B�����N���[���������Ă��邾���ł��d���Ȃ��̂ŁA�n�������̂ƁA�R�ԏZ���Ƃŋ��͂��ăA���e�i�����ĂĂ���Ƃ���ł��B ���ɁA���������������鐭��ɂ��Ăł����A���̂悤�Ȗ��_���u���[��������Ȃ�v�ŏo�Ă��܂��B 1�ڂɍ����ɑ���s���B2�ڂɎ��������邱�ƂŎ��̌��݂��ł��Ȃ��Ƃ������ƁB3�ڂɋ������������ʋ@�ւɑ���e���͑��v���B�����ɑ��A���͐ӔC���铚����p�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A�p�ӂ��Ă���Ƃ͌����Ȃ����ߊe�n�Ŗ�肪�N�����Ă��܂��B ���݂̐��������Ɍ����鎖�ł͂Ȃ��A�O�̐����ł��������Ƃ������܂��B�a�̎R�Ɠ��������ԁu��C�t�F���[�v�Ƃ����̂́A����O�̍������H�������x�[�X�ɂ��ĉ^�c���Ă������ǁA�O��������ň�C�ɏ�q������܂����B�����͂����������������Ȃ�ς��A���҂��闘�v��D�����Ƃ͔F�߂���̂ł��傤���B���̂��Ƃɂ��č��ɑ��ăN���[���������Ɍ������̂ł����A���łƂ��Ƃ��Ȃ��̂ŁA�������Ƙa�̎R���ŏ���������āA�����������悤�ɂ����B ����͗ǂ��e���������炷�����ł͂Ȃ��A�u���[��������Ȃ�v�ƑS�������ʂ�����Ő�����{�s���Ȃ���Ȃ�܂���B �@�@
�@�@�n���������ƍ��یo�ω� ���́A�n���������ł��B�n�������ɂ���ĐӔC����X�ɗ��邱�Ƃ́A�n�������Ƃ͐ӔC�ƍl���Ă��邽�߁A�Ƃ��Ă��f���炵���ƍl���Ă��܂��B�n�������Ƃ͐ӔC�ƍl���Ă���̂́A��������������̂ɕʂ̂Ƃ���Ɍ��茠��������̂͂����������߂ł��B �n���ōs���Ă��邱�Ƃ̉��炩�̎��ɂ��Ă͍��̃R���g���[�����A���邢�͔�̉��ōs���A���ӔC�ɕ��u����邱�Ƃ�����܂��B���̂��ߒn�������͑���Ǝv���܂��B �������A���ł��n���������Ă����̂ł��傤���B�Ⴆ�A�o�ϐ��x�A��F�A���Q����Ȃǂł��B���s�{���ł͋��s�{�̃��[�����~����A����ɏ]���Ƃ����̂͒n�������𐄐i����l�͎^������ł��傤�B�������A���̒n��̐��ق��̗̈�ɋy�ԍۂɂǂ��������Ƃ��N����̂��A�Ƃ������Ƃ��l���Ȃ��Ƃ����܂���B �����P�̗̈悩��l���܂��ƁAEU�������邱�Ƃ��ł��܂��B�d�t�͂Ȃ��������Ă���̂ł��傤���B���x�����������߂ł��B5000���l�̃t�����X�A�C�M���X��C�^���A�A8000���l�̃h�C�c�A�����̍��X��1980�N��ɂ͓��{�ɕ����Ă����̂ł��B�Ƃ����̂́A1��2�疜�l���x�[�X�ɂ���̂�5000���l���x�[�X�ɂ��Ďs��W�J����̂ł́A�O�҂̂ق������|�I�ɗL��������ł��B ���x�ꂵ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ǝ������n�܂����̂��d�t�ŁA����3��6�疜�l�̎s��o�ό����ł��Ă��܂��B���{�͖��炩�ɂ��̐����ɒx��܂����B�A�����J�͖k�Č���NAFTA�A�����R�X�[������Č��ŁA����A�W�A�ł�ASEAN�Ɠ����悤�Ȑ��x������A�������R�f�Ջ�������邱�ƂŐ��x�������Ɠ����悤�ȃV�X�e���Ƃ��ċy�ڂ��Ă��܂��B ���{�ł́A�o�ϘA�g����d�o�`�Ƃ����̂��ꐶ��������Ă��܂��B�Ȃ��ꐶ��������Ă���̂��Ƃ����ƁA���x�����Ă����Ȃ��Ɗ�Ƃ��}�U�[�J���g���[�ɂ����Ċ����ł���͈͂������Ă��邩��ł��B�Ⴆ�Ό����J�����ɂƂ�܂��ƁA�����ȋ��s�ł����K���ł��Ȃ��悤�Ȍ����J��������̂��A���{�œK���ł��錤���J��������̂��A���E���ǂ��ł��ʗp���鐧�x�Ō����J������̂��A��҂̂ق�����������̃R�X�g���������܂��B�܂�R�X�g�p�t�H�[�}���X���悭�Ȃ�̂ł��B���̂���EU���ł��A���R�f�Ջ��肪�ł��A�o�ϘA�g���肪�ł��Ă����̂ł��B�����Ă����������Ƃ��l���Ă���̂����یo�ω��B �����A�n�������I���̍ہA�l�C���Ƃ肽������Ƃ����ĒP���ɒn���������i���f����Ɛ��x���e�n��ł��ɂȂ�A��̂悤�ȕs���v���N����܂��B����ō��یo�ω��͒n���������̂��邱�Ƃɑ��Ă͋���������܂���B�܂�c����v�l�̕��Q�ł��B�����Ă�������z���Ȃ��ƁA�N��������������Ƃ��̓��{�͖������Ȃ��Ǝv���܂��B �A�@����ψ���̐l�����ɂ��� �u�n���ɂł��邱�Ƃ͒n���Łv�Ƃ����̂͒n�������̃t�B���\�t�B�[�ł��B���̂��߁A�u���₷��������낤���v�Ƃ������ƂŁA����ψ���̐l�����̈ړ����������܂��B����݂͂Ȃ����m�ł͂Ȃ���������܂��A�{���̋��t�͕{���̋���ψ�����������ɍ̗p���Ă��܂��i���s�s�͐��ߎw��s�s������Ⴄ�Ǝv���܂����j�B �a�̎R�S�̂ŋ������̗p���āA��]���Ȃ���l���ٓ����s���܂��B����𒆊j�s�s�A�Ⴆ�Θa�̎R�s(40���l)�̐l���z�u�Ƙa�̎R���Ƃŕ����Ă��܂����Ƃ����̂��A�n���������v���i�ψ���̒��ԕA���̂��ߍŏI�I�ɂǂ��Ȃ��Ă��邩�͒m��܂��A�Ɉӌ��Ƃ��Ă���܂����B����͒n�����������炷��Ɣ��ɂ����ƌ����܂����A�u�a�̎R�s�ȊO�œ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����l���ǂꂾ���a�̎R���ɕ�E���Ă���邾�낤���v�Ƃ�����肪����܂��B ���͘a�̎R�s�̎q�����A�k�R���̎q�����A�����悤�ɗD�G�Ȑ搶�ɂ���ċ����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B��������Ƃł��邾���A�a�̎R�œ����Ă����l���W�߁A���̐l�̏i�ƒ�������Ă��邩��A�Ⴂ����A�s�s�̐����ɔ�ꂽ����ȂǂȂǁj�ɍ��킹�āA���낢��l������悤�ɂ������B�����a�̎R�s�Ƙa�̎R���Ƃŕ�����ƁA����܂ł̂悤�ȗ��h�Ȑl���a�̎R���ɕ�E���Ă���邩�ǂ����A�݂Ȃ���͂ǂ��v���܂����B �@���́A���ꂪ�X�e���I�^�C�v���炵���甽�t���闬��ł͂���܂����A���������Ă����Ȃ���Γc�ɂ̎q������邽�߂ɕK�v���ƍl���Ă��܂��B ���Ԃ��Z���Ȃ��Ă����̂ŐV�����o�ϐ���ɂ��ďq�ׂ܂��B
�@�@
�@�@�u�a�̎R�œ����܂��v�v���W�F�N�g ����22�N�̃��[�}���V���b�N�ɂ���Či�C���₦���݁A��ςȏA�E��Ɋׂ��Ă��܂��B�s���K�ٗp�̐l����C�ɐ��̒��ɕ���o����܂����B�����Ă��̐l�X�������悤���Ƃ������ƂŁA����J�����̃e���g��������܂����B�����A�{���ɋQ�������Ȑl�ł���s�����炢������Ȃ����Ǝv���̂ł����A���{�ł͂�������Ȃ��āA�K�ٗp�̐l�����H�ׂ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��Đ�������ɐE���Ȃ��Ȃ�A�~�����Ȃ��Ȃ邱�ƂŖ{���ɓ�ɂȂ�A���������l�ɑ��āA�����Ȃ�O�ɂǂ�����Ď��̐E�������Ă�����̂��A�����������Ƃ��l���Ă����邱�Ƃ́A�א��҂̂��ׂ����Ƃ��Ǝv���܂��B �a�̎R�͂��܂藬�s���Ă��Ȃ��̂ŁA������Ƃ��Ȃ��̂ł͂Ǝv���Ă���̂ł����A���\����܂��B�����ǃC���[�W�ő����Ă���B����܂ł͑��Ƃɂ����l��D���Čق��Ȃ������B�����炱���A�������`�����X�Ƒ����Ă��܂��B�a�̎R��HP�ł͋��l��W�����Ă����Ƃ��Љ�āA�S�����瓭���l���W���Ă��܂��B��������Ɩʐڂ��Ăł����ǂˁB���ꂪ�u�a�̎R�ōP�v�A�E�����Ă݂܂��v�Ƃ����v���W�F�N�g�ł��B ���̎o���҂��A�u�a�̎R�Ŕ_�Ƃ����܂��v��A�u�a�̎R�ŕ�����Ƃɏ]�����܂��v�u�a�̎R�ŏ��ɂȂ�܂��v�Ƃ������L���ŏo���āA�݂Ȃ���̎d�����P�v�I�ɐ��ݏo���Ă��܂��B �s���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�u�����ɍ����Ă���̂��H�v�Ƃ������Ƃ��l���A�����Ă���l���P�v�I�ɋ~�����Ƃ�����Ǝv���܂��B�l�C���̂��߂ł͂���܂���B�����Ă��́u�a�̎R�œ����܂��v�v���W�F�N�g�����ŁA300�l�قǂ̌ٗp���n�o����A�܂����킶��Ƒ����Ă��܂��B�܂���W���Ă���Ƃ��������܂��̂ŁA����������͌�����HP����������������Ǝv���܂��B �A�@�^�[�Q�e�B���O�C���_�X�g���[�|���V�[ �F����́u���������̉āv�Ƃ��������k�s���o������Ă����h���}�������m���Ǝv���܂��B���͐́A�ʎY�Ȃ̊��������Ă����̂ł��̗��ꂩ��]�ꂷ��ƁA��R�O�Y����̌���ɑ��āu������ƃZ�R�C���߂����Ă���ȁv�Ǝv���܂����B��R����̌���ł͂��������������Ȃ��A�������۔h�ł������Y�Ɣh�ł������Ƃ������Η��������āA���̒j�̐킢�̘b���A����������܂�Y�Ɣh�̕��z�M��Ƃ����l����ʂ��ĕ`���Ă��܂��B ���ǁA�ʎY�Ȃ͍��یo�ς̒��Ő����Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��A������Y�Ƃ�ی삵�Ă����یo�ς̂Ȃ��ł͎���ł��܂��܂��B�����獑�یo�ςɓK������悤�ȎY�Ɛ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����v���Z�X�ɓ������̂ł��ˁB1970�N��㔼����80�N��ɂ����āA21���I������܂ł�������������܂��A��{�I�Ȑ���́u�����Ƃ����L���Ă����v�Ƃ������Ƃł��B���R�����Ă���Ƃ��낪�o�Ă���̂ŁA����ɂ��Ă͕ی�����Ȃ��ŁA�Y�ƒ��������āA�ア��Ƃ��狭���Ƃ���ֈړ��ł���A�|�W�e�B�u�A�W���X�����g�|���V�[������Ă��܂����B���ꂪ��{�I�ȒʎY�Ȃ̐������Ǝv���܂��B�������������������A80�N��̓��{�̎Y�Ƃ͂���Ǝ����オ��܂����B �������f�Ֆ��C���N�����Ă��܂��A���̂Ƃ��̃A�����J����̒��S�I�Ȃ��̂̌��������u���{��targeting industry policy������unfair trade
practice�ł���v�Ƃ������Ƃł��B�m���ɁA�ϋɓI�ɎY�Ə��������ďo��Ƃ���͐L���Ƃ����̂́A�\�Ō����Ȃ��Ƃ������Ƃ���������ł��ˁB �Ƃ���ŁA�a�̎R�ł͐��ʂ��炱���錾���Ă���Ă��܂��B�a�̎R�Ɏ���������A�L�т�悤�ȉ肪����A����������Ƃ��A�Z�p�J���Ŏx�����āA�v���W�F�N�g������āA���̐��ʂ���Ƃɗ��p���Ă��炤���ƂŁA��Ɛ�����}��Ƃ������Ƃ��l���Ă��܂��B ����ł炢�̂͂������Ȃ����Ƃł��ˁB�Ȃ̂ŁA���̋��n�I�J��������Ȃǂ𗘗p���āA�a�̎R��10����1�����S����悤�ɂ��Ă��܂��B ���Ԃ��Q��܂����̂ŁA�b�͂���܂łɂ��܂��B�㔼�́A�����ɋ^��Ɏv�������́A���͂܂����܂��̂ŁA�b�ɗ��Ă��炦��Ǝv���܂��B �Ō�ɁA�Ȃ�������̂��ɂ��Ă��b�������Ǝv���܂��B����́A�^�����������͂�g�ɂ��邽�߂ł��B�������͐^����Nj�����͂ł��B�l�̌��t�ɗx�炳���̂ł͂Ȃ��A�����Ō������B���̂��߂ɂ͂�������̌o���ƁA�����K�v�ł��B ���ꂩ��������̒m�������ĐF��Șb��������Ă����Ǝv���̂ł����A�݂Ȃ���́u�����^�����v�ƌ������Ă��������B
��@�F�@���w�����{�j�I�l�A�����j�ɂ��ĕ����Ă���̂ŁA�D�ꂽ�����Ƃ̎����ɂ��ċ���������܂��B�m�������l���ɂȂ�D�ꂽ�����Ƃ̎����Ƃ͉��ł��傤���B ���@�F�@�@�D�ꂽ�����Ƃ͂悭������Ȃ��̂ł����A�D�ꂽ�����s���Ƃ����̂������ɐ����s���Ƃ��APR���ɏq�ׂĂ��邱�Ƃ�����܂��B �P�ڂ��A����Ȃ���Ȃ�Ȃ��u�a�̎R�ɑ��鈤��v���������ׂĂƂ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �Q�ڂɁA�s�������炵�����̂ɂ��悤�Ƃ����M�ӁB �R�ڂ́A�����\���B�撣�낤�Ƃ����ӎv���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͈���E��M�̊���������܂��A�����������ɐ��ʂ��\���킯�ł͂Ȃ����A���낢��ᔻ����Č��ɂȂ邩������Ȃ����A���]�Ȑ܂���̂ł͂Ȃ��Ď������Ċ撣���͂��K�v�ɂȂ�܂��B �S�ڂ́A���@�͂ƍ\�z�́B �����Ƃ͏�Q�A����1�ڂ�����Ώ\���ɐl�C�����܂��B ���������������l���Ă�����A�����Ă���Z���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂�u���ō����Ă���̂��B�ǂ�����Ď�菜�����Ƃ��o����̂��B�v�Ƃ������Ƃ��A�l�����铴�@�͂��K�v�ł��B�����āA�\�z�͂ł��ˁB�Ⴆ�Βi���ł����ɐ�ɘb�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��A�@���������K�v���A�a�̎R�������ʼn����ł���̂��A�Ƃ��������ɂł��B��������čl���Ȃ���A���܂ł����Ă����͉������܂���B ����͐����Ƃ����łȂ��A�S�Ă̍s�����ɂƂ��Ă��K�v�ŁA���Ƀg�b�v�ɂƂ��ĕK�v���Ƃ������Ƃł��B ��@�F�@�m���̂��b�̒��ŁA�ŏ��̂ق��ŏ����J�����邱�ƂŁA�ǂ�Ȃɂ�������ł��ᔻ�ɂ��炳��Ȃ��ƕ����Ă��܂��Ƃ������b�ƁA�l�C���ł͂Ȃ��P�v�I�Ȑ�������Ȃ���ΐl�͋~���Ȃ��Ƃ���������܂����B�����Q�����킹�āA�����Ɍ������Ăǂ�ȓW�J�����Ă������Ƃ���Ă���̂ł��傤���B ���@�F�@���Ԃ�Ȃ��Ƃł�����Ȃ����ȂƂ������Ƃœ��������Ă��������܂��B�^������������͂��K�v���ƊF����ɂ��b�����܂������A�܂��́u����������v�Ƃ������Ƃł��B�{��ǂނ��Ƃ��厖�����ǁA���̏ꍇ�͌���������B�������Ƃ��ċN�����Ă���̂��m�邽�߂ɂ́A���ڂ��̏�ɍs�����Ƃ��厖�ł��B�Ⴆ�Θa�̎R�̓�̕��ɍs���Ɣ��̎��肪���Ԃň͂܂�Ă��邱�Ƃ��悭����A�����Ǝv�����璖�E���E���ɂ���Ĕ����r�炳��邱�Ƃ����ɂȂ��Ă����ł��ˁB�����������Ƃ��A�c�ɂ��U�Ă���Ƃ킩��B���͍l���邱�Ƃł��ˁB����ɑ��鐭��������炱���Ȃ�A�u���[�����炱���Ȃ�v�ōl����̂ł��B�����Ď��s���Ă����B�R�̂悤�ɂ������D�揇�ʂ����āA�n���ɂ���Ă��������Ȃ���Ȃ��ł��傤���B ��@�F�@�����J���ɑ���1�l�ɑ��đ���ȃR�X�g�������邱�ƂɂȂ�Ɣᔻ�̑ԓx������Ă�������Ⴂ�܂����B�����A�{���ɏ���K�v�Ƃ��Ă���l�ƁA�����łȂ��l�A������ǂ�����Č�������̂ł��傤���B ���@�F�@���邳�������Ă���l�������J���ƌ������킯�ł͂Ȃ��A���̏��ł����Ă���l�̂��Ƃł��B���Ȃ����������A�K�v�Ƃ��Ă���l���Ă��Ȃ��l�́A�������ƍl���Ă��܂��B�S���ɏ����������炢���Ǝv���Ă��܂��B�������A���̐l��������悤�ɏ������H���邱�ƂŃR�X�g�������邽�߁A���H���Ă��Ȃ����̂���Ă��܂��B��������������܂��B���������̐l�ɛZ�тāA���H����������邱�Ƃɑ��Ĕᔻ�����Ă���Ƃ��������ł��B
�@ |
||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. ���̃y�[�W�Ɋւ��邨�₢���킹�́A�����ّ�w�@���ʋ��琄�i�@�\�i�����ǁF���ʋ���ہj�@�܂� TEL(075)465-8472 |