 |
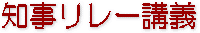  |
|
| 2010年 5月 18日 福井県 西川一誠 知事 |
||
「ふるさと」の発想で新しい自治を創る
『ふるさとの発想』という著書に、今回述べる「ふるさとに対する考え方」が書かれていますので、ぜひ読んでいただければと思います。 私も京都で勉強をしていました。今ではお寺や神社とかお祭りとかに遊びに行くべきだったなぁと後悔しています。今月は葵祭りもあるし、これからも京都の色んな行事があります。今年は大河ドラマで龍馬伝をやっていて、今後京都が舞台として出てきます。京都のいろんな史跡とかにも行って欲しいと思います。後で役立つと思います。 私の名前は西川一誠と書き、イッセイと読みますが本当はカズミと言います。立命館大学の白川静先生から音読みのほうが良いだろう、というアドバイスを受けてイッセイを通称としています。
白川静先生の話をしましたが、先生は福井県出身です。そのため福井県では白川先生の漢字学をもとに色んな事業をやっています。 まず、色んな漢字について話をしてみたいと思います。 「告」という字は、これは牛が口を開けてあることをしゃべるというふうに中国の字引には書かれていました。だけど白川先生は、甲骨文字、青銅器に書いている文字を調べて漢字ができた流れを調べられた。その結果、神の言葉を入れる器がサイ、そしてその中を突き刺して、抜き出す、つまりお告げを抜き出すという意味があるのです。 「遊」は、楽しく遊ぶという意味ではありません。旗があり、翻って、そこに神様が宿っているという意味。つまり昔は神様しか遊ぶことができなく、それを人が少しだけ参加させてもらう。 「文」の本当の意味は入れ墨のこと。昔、こどもが生まれると、元気に育つようにと×の形に入れ墨をしていた、その名残です。 このような知識は一生の宝であると思います。一冊でもいいので、白川先生の本を読んでみてください。就職活動や、社会人になってからも何らかの話題になると思います。 勉強は、楽しくやるということが大事なため、教材や教え方にも工夫を入れている。 漢字は小学校でいくつ習ったと思いますか。1006文字です。これは文部省の学習指導要領で定められています。福井県では、小学校で教える漢字数は1006文字、また学年ごとに何を教えるのかという配当が決まっていることに対し、それをオーバーしてもいいかなどを文科省に確認し、「自由にやってもよい」ということでした。そこで、福井県では、学習指導要領を超えて、漢字を教えています。白川先生の文字学を中心に教育を進めている。 また、学力では、秋田と並んで日本1です。体力テストも日本1です。 アンケートを見ていただいてもわかると思いますが、いろんな著名の方がいらっしゃいます。福井県出身で有名な学者といえばノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎先生や、沖縄返還交渉をされた、若泉敬先生などたくさんの学者がいらっしゃる。アンケートを見ていただいても、色んな著名な方がいらっしゃるということです。
地方自治の話をします。 皆さんの中にも自治体公務員の勉強をされている方がいらっしゃるかもしれません。立命館出身の福井に勤めている人は52人います。今年度の採用は86人、立命館大学と同志社大学を2人ずつ採用しました。 日本には300万人の学生・短大生がいます。京都には17万人、東京は75万人。対して福井県の全人口は83万人。東京には、福井県と同じだけの学生がいるということです。さらに大学生の4分の1が東京にいるという、人口の一極集中以上に大学生が大都市に集中しています。 それと、年間約3,000人の学生が大学へ行きますが、帰ってくるのは約1,000人、2,000人は帰ってきません。学生が18歳になるまでに1,700万円程度かかりますので、地方は、それだけ経費をかけているわけですが、3分の2の人は、大都市へ行ってしまいます。 『ふるさとの発想』には、こういった問題について述べているので、ぜひ読んでみてください。 「ふるさと」とは古い言葉だが、それを新しい言葉として使おうとしている。「ふるさと」とは何か、講義ではこのことについて述べます。 「ふるさと」というのは、大昔(戦後まもなく)は帰りたい場所だった。昔は無理して集団就職をし、上野駅に着いたところで「早く母に会いたい」と思える、帰りたいという場所でした。「ああ上野駅」や、「いい日旅立ち」という歌は「ふるさと」はどこにでもあるということを歌っています。五木ひろしも同じようなことを歌っている。 現代の「ふるさと」は、我々の仕事もそうだが、自分たちで自分たちの地域を盛り上げていこうという発想の「ふるさと」。大学や就職した人も、「ふるさと」はいろいろあるが、自分の住んでいるところを応援したいと思っている。 「ふるさと納税」というのがありますが、あの制度は私が中心となって制度化しました。 民主党政権になり、世の中はものすごく変わってきています。現場ではそれをはっきりと体感しています。1993年、細川政権という非自民政権ができましたが、非常に短命でした。そして2009年に民主党政権になり、55年体制は終わりました。 歴史や地方自治、政治を少し長い目で見ると、大きな変革は1回では変わらないということがわかる。 これは追試や、男女関係にも言えます。つまり、2回おきると偶然ではないということです。なぜかというと、1回目は偶然だと思う。今回の政治的な変革も、おそらく本当に起こったのだろう。オイルショックもそうだった。2回目が起こって、本当にエネルギーの状況が変わった。ヘーゲルという学者も言っているが、2回起こると初めて本当になる。ヘーゲルに関しては、今は簡単な本が出ているので、ぜひ読んでみてください。 地方と都市の関係をこれから申し上げます。 日本には上場企業が4000社ほどあり、半分が東京に本社がある。これを3大都市に広げると85%の上場企業があることになります。京都にも70社あります。明治維新で京都から東京へ政治の中心が移ったのですが、当時政府が京都に投資をし、地元企業が頑張ったから今企業が残っている。そして全体の投資額のうち4分の3が太平洋ベルトに投資されてきた一方、日本海側は非常に少なく4分の1でした。これは作られた格差といえるかもしれません。京都は京都として今頑張っていますが、大都市の格差は広がったと考えています。一極集中は当たり前と思われている方も多いと思いますが、東京一極集中は世界的に見て珍しい。アメリカには世界トップクラスの企業が多くありますが、企業の発祥の地に本社を置いています。こういった日本にしたいと考えているのですが、なかなか実行できないのが現状です。 こういうなかで、大都市中心のこういう構造を打破し、ふるさとを大事にし、地域を守っていくことが重要です。 この教室の電気はどこから来ているか。若狭原発から来ています。みなさんの生活、そして会社のライフラインである電力エネルギーは地方のふるさと福井県で支えられていると思わなくてはならない。水も同じく、地方のふるさと滋賀県から来ている。関西の人口約2000万人のうち、1400万人は琵琶湖からの水を飲んでいます。都市は地方が支えていることを忘れてはいけません。電気や水や米がどこから来ているか、大都市と地方の関係を考えていくことが重要です。 中国の話をしますが、中国で国会にあたるのは全国人民代表大会です。どういう選び方をするかというと、農村部から選ぶには都市の8倍の人口が必要でした。今は4倍になりましたが、大都市の4倍の人口になって、はじめて都市と同じ1人をたてられる。アメリカでは、どの州も上院議員2人選ばれます。地方の格差という議論をするときに、もう少し地方の意見が反映されるような選挙制度へと、工夫する必要があります。 最近、地方の自治体の動きとしては、まちづくりというのが大変さかんになっています。 福井県でもそういう動きがある。一例をあげると、小浜という町があるが、オバマ大統領を応援しようという取り組みは名前が同じというだけで応援しています。このような活動から新しい関係が生まれるかもしれません。 私たちは個人主義の考えを非常に受けてきたと思います。自分で考え自立しろという考えです。私はこういったバラバラになった社会を個化社会と呼んでいます。だけど、個人だけでは自分を支えることはできません。そこで、地域つまり地域内の繋がりが個人を支える必要があると思っています。私はそういう方向に行ってほしいと考えています。 今年1月、ふるさと知事ネットワークを設立しました。 これは、自立と分散で新しい日本をつくる知事ネットワークというものです。青森、山形、福井、山梨、長野、奈良、島根、鳥取、高知、熊本、が集まって、田舎同士で頑張ろうという組織を作りました。最近は石川県も入れて、11県でいろんな問題の議論、提言をしようとしている。 田舎同士の連携の例として、ファーマーズマーケットで、例えば福井で売れるものがないときに、山形からさくらんぼを持ってきてもらう、その代わりに福井から梅を持っていく。このような取り組みを地方同士で、東京を経由せずやろうということです。また学力をあげる研究を地方同士でやろうということもできる。 このネットワークの発想には、ストラスブールへ昨年8月に全国知事会を代表して行ってきたことにあります。そこで、ヨーロッパにある自治体の会議で、日本のふるさとや地方自治の話をしてきました。そこで影響を受け、「世の中を良くするために、大きいものをつくるのは大変だが、自治体同時でのネットワークをつくるのがいいのではないか」ということです。 英語でLocalという言葉には、「田舎」という意味は含まれず、「ある一定の場所」という意味があります。ここから、ローカル&ローカルということを考えています。私は道州制に関して批判的です。今ある既存体制で力を合わせることができるのではないかと思っているためです。 ふるさと知事ネットワークの会議の際、「東京ではなく11県のうちのどこかで集まろう」という話がありますが、どこかの県庁に足を運ぼうと思うと時間がかかります。平均すると、奈良県に集まるのが一番早いが、それでも4時間26分かかる。一番長くなるのは熊本県に集まること。逆に東京に集まると3時間10分で集まれる。日本の交通体系がこういう形にしているのだと思っています。さらに面白いことには、各県の県庁に集まるより、ソウルの仁川空港に集まるのが早く、平均4時間ですむ。地域が大変ゆがんでいるためです。この歪みを直そうと、いろんな提案をしていきます。 また単身赴任者が日本には今30万人いますが、これは教育にも健康にも悪い。民法の条文に「夫婦は同居し・・・」という条文があります。これを実行するため、研究もしようとしています。それから家族も助け合わないといけないという条文もある。みんなで助け合う地方にしないといけない、ということです。
最後に、希望という話をします。 今、福井県は子供の学力・体力日本トップクラス、また長寿県、各世帯の年収800万円以上の割合は、日本一高くて4割を超える。この世帯年収の高さは同居が多い、共働き日本一だから、ということもあるかもしれません。 これから、これらをさらに良くしようと思うと、「希望」という話になります。 東京大学と連携し、希望学というプロジェクトを進めています。つまり、地域社会も入れた全体の問題を、福井県をフィールドとして研究する。福井県のこどもたちは希望を持っているのか、立命館の学生は希望を持っている人がどれだけいるか。全国学力調査には、希望をもっているかという調査も含まれますが、その中で福井県は40番以降と低い方です。それはなぜなのか気になるところです。希望は、学力の高さとあまり関係はない、宮崎、和歌山、高知が、希望を持っていると答えるこどもの割合が高いという結果もでています。多少地域差があるかもしれないし、研究すべき分野だとも思います。あらゆる実態調査をして、今後調査をしていきたいと思います。 知事ネットワークで、ふるさと希望指数というもの発明しようと考えています。それがLocal Hope Index(LHI)。気持ちを行政に反映させよう、という取り組みです。子育て、住環境など指標にできるものはいろいろあります。鳩山 希望学での希望の定義は、”Hope
is a wish for something to come true by action.” 希望というのは、具体的な何かを行動によって実現しようという願望。ここからはaction(行動)が大事、ということが読み取れます。 さっき冒頭に南部陽一郎先生の話をしましたが、「こどもたちに励ましの言葉」をお願いしたら、”Boys and girls, be ambitious.”という言葉をいただきました。「少年少女よ、大志を抱け」という意味かと思ったのですが、違うのではないかと、内村鑑三が明治27年に書いた『後生への最大遺物』という本を読んで思いました。この本には「希望」に対する訳語として、Hopeと書かずAmbitionと書いています。AmbitionとはHope by action、つまり「希望を持って行動する」ことです。 みなさんの若い世代は、特定の趣味などにこだわらず、ぜひ「ambition」を持って色んなことに取り組んでください。 |
|||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |