 |
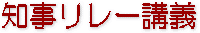  |
|
| 2010年 5月 25日 総務省 自治大学校 門山泰明 校長 |
||
「 求む、自治の担い手 - これからの地方政府 - 」
地域主権改革が頻繁に叫ばれています。そうなると、地域を担う人材がますます大事になってくる。地域を担う人材というのは、知事や市町村長だけでなく地方議員、自治体職員、町内会役員やNPOの人、企業も様々な形で地域にかかわろうとしています。つまり地域にかかわる実践家、自治の担い手、ということが重要になっているのです。 最近は、公民連携、新しい公共というものを考えようという動きもあります。要するに、自分の住んでいる地域を良くしたい、地域の問題に自分も参加したいと思う人がどれだけいるかで、そこの地域の将来が決まるという面は強いということです。若い皆さんにはぜひ自治の担い手になってほしい。そして、できるだけ多くの人に自治体職員の試験を受けてほしい。というのは、地域主権改革が進むとことで地方政府の職場はおもしろくなるためです。 最初に、地域主権改革についてお話します。民主党政権では、地域主権改革は一丁目一番地であるという言い方をしていますが、「地域主権改革」とは何か。主権とは国の問題であり、地域ではおかしいのではないか、というような意見が学者からも言われました。「地域主権改革」についてきちんと定義をする必要があります。 地域主権戦略会議では、地域主権改革を「日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸問題に取り組むことができるようにするための改革」と定義しています。前政権までは「地方分権改革」という言葉が使われていましたが、内容はほぼ同じです。 地域主権改革が頻繁に叫ばれています。そうなると、地域を担う人材がますます大事になってくる。地域を担う人材というのは、知事や市町村長だけでなく地方議員、自治体職員、町内会役員やNPOの人、企業も様々な形で地域にかかわろうとしています。つまり地域にかかわる実践家、自治の担い手、ということが重要になっているのです。 最近は、公民連携、新しい公共というものを考えようという動きもあります。要するに、自分の住んでいる地域を良くしたい、地域の問題に自分も参加したいと思う人がどれだけいるかで、そこの地域の将来が決まるという面は強いということです。若い皆さんにはぜひ自治の担い手になってほしい。そして、できるだけ多くの人に自治体職員の試験を受けてほしい。というのは、地域主権改革が進むとことで地方政府の職場はおもしろくなるためです。 最初に、地域主権改革についてお話します。民主党政権では、地域主権改革は一丁目一番地であるという言い方をしていますが、「地域主権改革」とは何か。主権とは国の問題であり、地域ではおかしいのではないか、というような意見が学者からも言われました。「地域主権改革」についてきちんと定義をする必要があります。 地域主権戦略会議では、地域主権改革を「日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸問題に取り組むことができるようにするための改革」と定義しています。前政権までは「地方分権改革」という言葉が使われていましたが、内容はほぼ同じです。 地方分権改革の説明を簡単にします。行政改革と政治改革という流れが1980年代から始まり、その流れの中で地方分権というものが出てきました。そして、2000年に地方分権一括法ができ、この時を第一次分権改革といいます。第二次は2004年くらいから2006年にかけて行われた三位一体改革、第三次が同じく2006年にできた地方分権改革推進法によるものという流れがあります。そのような流れのなかで、新しい地方分権に取り組もうというのが鳩山内閣の政策です。 地方分権改革について勉強したい人は、西尾勝先生の『地方分権改革』という本を推薦します。 今日は地域主権改革と名前が変わって、新しい改革で何を変えようとしているのか、それをすると何が変わるのかをお話します。 (1)何を変えようとしている改革なのか 何を変えようとしているのかというと、法令等による義務付け・枠付け、国庫補助金、基礎自治体の権限、中央政府の地方出先機関、地方自治法の5つを挙げることができます。最初の項目から4項目までは、今年の夏までに地域主権戦略会議で改革の柱となる大綱を作ろうとしています。そして原口プランで示されたのもこの4つです。中央政府の地方出先機関については、今の内閣の方針は原則廃止と、大変分かりやすい。そこで、前2つの事項にしぼって話をします。 ○ 法令等による義務付け・枠付け これを廃止しようというのが改革の方向性です。保育所の話を例に紹介いたします。今、子どもを保育所に預けたいという保護者が増えて、待機児童が増えていきているため、去年の10月頃からかなりメディアで保育所の話がとりあげられてきています。マスコミでは保育所を地方分権と絡めてとりあげている。小学校入学前の子どもをもつ母親という立場で考えると、働きに出るときに子どもを預かってくれる施設が必要です。また駅や職場の近くに立地する、夜遅くまで預かってもらいたいという住民のニーズが出てきます。 保育所は一つの行政サービスの提供です。保育所の設立には、児童福祉法の下に要件や基準が細かく定められています。例えば、2歳未満の乳児については、1.65平方メートルの乳児室、2歳以上の幼児には1.98平方メートルの幼児室また3.3平方メートル以上の遊技場などといった基準があります。他にも保育士の人数や、保育の時間は原則8時間なども定められています。基準を全てクリアしないと、保育所として運営できない。 保育所設置者は市町村である場合と民間である場合がありますが、制度が非常に厳しいため、その結果、国が画一のサービスを全国一律に提供しているのと変わらないのが現状です。ですが保育所に求められるニーズは様々なのに、このような基準によって保育所が作れない、そして待機児童が増える。これは何かおかしいのではないでしょうか。隣に広い公園があるのに運動場を作る必要があるのか、また小学校の廃校舎を使おうとしても、面積基準をクリアしていないから活用できない。 なぜこうなるかというと、国の役所がサービスの水準を一律に決め、例外を認めない形になっているからです。このように、要件・基準をがっちり決めることを、義務付けといいます。そして、地方政府が何か仕事をするときはこのようなやり方でやってください、と枠をはめていることを、枠付けと言います。 義務付け、枠付けを廃止したら何が変わるのでしょうか。保育所の例では、それぞれの街で、議会などを通じて、どういうものを作ろうということができるようになる。そうすると、働きに出たい母親のニーズに答えることができるはずです。 このような方向性に対し、中央政府ではなく自治体に任せると安全が心配だという声が今も聞かれます。しかし、地域で自分たちの街の子どもが入る施設を作る時に、危うい施設を作るでしょうか。 市町村が決められるようにすれば、住民のニーズに応えた様々な政策パターンがでます。今では服も個性がないとみなさんは受け入れない。行政サービスも同じです。ニーズ、質、量、タイミングに応じていることが重要です。 保育所については少し進み、東京などの待機児童が非常に多いところに限って、待機児童が減るまで面積の条件を少しだけ改善しようとなりました。 保育所問題は、地方分権問題としてマスコミに大きく取り上げられました。そのマスコミの議論で気になるのは、子どもの安全を守るためには面積基準を緩めることに対する批判がずいぶん言われていたことです。地方分権改革は、「基準を引き下げなさい」と言っているわけではない。「基準を決めるのは誰が良いか」と言っているのです。 市役所や県庁も政府。霞ヶ関、永田町が中央政府だとすれば、京都府庁、京都市役所は議会を持った地方政府。政府である以上は、国は関与すべきではないという思いもこめられています。地方にはもっと責任を持った仕事をやってもらい、中央政府はよけいなことをしない。逆に、地方政府職員は今までは「国の基準」を言い訳にし、逃げることもできたが、これからはギリギリの知恵をしぼらないと住民からは納得してもらえないということです。 地方政府とは何か、と考える際にヒントを与えてくれる本が、19世紀の政治学者トクヴィルの『アメリカのデモクラシー』です。地方自治とは何かと考えると、一つの大きなポイントは自由だとわかります。自由というものが地域の自治あるいは地方自治という問題の基本だとすれば、成功する自由もあれば失敗する自由もある。自由はありがたいものかもしれないが、苦労の始まりでもあるのです。 ○ 国庫補助金 改革の方向性は一括交付金化と言っています。この改革は最終的には自主財源を増やそうという方向になっていくと思われます。ある人は、「地方分権をするには自由に使える金さえ渡してもらえばいい」とまで主張している。それほど地域主権改革には財政の問題が深くかかわっているということです。 今、地域主権改革で焦点があたっているのは、国庫補助金について、一つは補助金という制度があると、ある仕事をしないといけないと思っていても、補助金がくるまで待ってしまうということがある。二つ目に、補助金を受け取る条件が細かいということ。三つ目は、補助金が入ると費用対効果の分析が甘くなる。本当は必要がなくても、補助金があるからやってしまうということです。 国庫補助金は非常に不思議な面があると思う。中央政府も非常に財政が厳しい状態です。一方、地方公共団体側が三位一体改革で「いらない補助金リスト」を作成し、補助金の一部をいらないと中央政府に主張しました。だけど中央政府はその意見を受け入れなかった。受け取る方はいらない、出す方は国債を発行してまでも必要だと主張している。これは何か変ではないでしょうか。補助金はお金を中央政府からもらうから得だ、という感覚があるのですが、それとは全く逆に「地方にお金を出させる手法だ」という見方もあります。例えば3000万円の事業のうち3分の1は国庫補助金で賄い、残り2000万 (2)何が変わるのか ○住民サービス そもそも地方政府は何のために存在するのでしょうか。その疑問の答えのヒントがアメリカの西部開拓時代にあります。西部の町で最初に誕生した公務員は保安官と収税員です。街をつくるとなると、治安を守る仕事を保安官として24時間誰かやらないといけない。そしてその人は自分で畑を耕せないが、食べていくために給料が必要となる。そのために収税員が町の住民から税を集めて払う。日本では、政府はお上という意識が強いが、サービスを提供してもらうための道具と思っても良いと思う。 義務付け、枠付けをなくすことは、障害物をなくすことにはなるが、直接それでよくなるということではありません。 地方政府の職員の努力も必要です。地方政府の仕事は増えて、責任も重くなり、厳しさも増えますが、やりがいも増える。既に決まった手法でやるのと、問題解決を自分のやり方でやるのとでは明らかに後者のほうがおもしろいからです。
最近の大きな変化は市町村合併です。そして、都道府県をどうするかということで道州制の問題がある。第一次分権改革の流れで市町村合併が進められました。それには市町村に多くの権限・仕事が委譲されるので、市町村の基礎体力を上げることを目的にしていました。そして平成11年から市町村の大合併が急速に進みました。 結果的に、平成11年に3200程あった市町村が平成22年には1700程になりました。ここまで自治体数が減った一番の背景に、財政の問題があります。このままではやっていけないということで合併を選んだのです。 大合併に対して世の中の評価は結構厳しいのです。というのは、地域を良くするために行われた大合併のはずなのに、合併地域の中心地だけがよくなり、周辺部はよりすたれたという現状もあるためです。このような見解はありますが、この大合併によって基礎自治体の体力は強くすることができるようになったということは間違っていないと思います。 市町村がめまぐるしく変化しているのに対し、都道府県はどうか。都道府県と道州制の議論についてお話します。 明治の初めに日本には約7万の市町村がありましたが、今では1727。約40分の1まで減ったということです。県庁の仕事は市町村とのおつきあいが多いため、数がこれだけ変わると仕事の内容も変わってきます。一方都道府県はどう変わっているか。香川県が愛媛県から分かれた120年前から変わっていないのです。市町村は変わっているのに、都道府県は変わらなくて良いのかというのが道州制の議論の出発点。「道州制のあり方に関する答申」というものがありますが、これは「こういう道州制がいい」というものではなく、色んな議論をするための叩き台として作られています。 関西で今、関西広域連合を形成して共同でいろんなことをしていこうという取り組みがされていますし、九州でも広域連合の案が出ています。道州制は今後も議論がされていくテーマだと思いますが、このテーマの一番のポイントは、国と市町村の間にある組織が何をしなければならないのか、ということです。そして中央政府がどれだけ仕事を選択と集中ができるのか、ということにも通じています。
国家公務員制度の改革が、今熱いのです。制度がどうなるか、天下りや人事の縦割りと 自治の担い手という部分で考えると、自治体職員は自治の担い手の中心です。もちろん議員、知事や住民組織や民間企業もそうです。ですが、自治体職員、公務員でないとできない仕事は何なのか、ということが民間委託などを考える上でも重要です。 自治の担い手も変化しつつあります。主婦やサラリーマンなども議員として参加することで、地方議会も変わってくるのではないでしょうか。特に興味深い提案に、地方政府の職員が議員も兼務しても良いのではないかという議論があります。 今後、自治を担う役割として自治体職員の役割は大きくなっていきます。もちろん皆さん全員が公務員になられるわけではないのですが、地域の自治に関心を持っていただき、地域の活動に参加していく人がこれから重要になるという意味をこめ、「求む、自治の担い手」というメッセージをお送りします。
質: 道州制に関して。道州制を進めることでどういう国家像があるのか。またその場合、中央政府の役割は夜警国家のような必要最低限だけを担うものか、また別の形があるのか、お伺いしたく思います。 答: 地方に任せられることは地方に任せ、国は経済政策、国防、また口蹄疫のような危機管理など国でしかできないことを担うべきだと思います。ですが、現状は国がすべきことが他のことで手一杯になり十分に行えていない、そのため道州制が中央政府のスリムアップのために必要だとも言われています。つまり中央政府の仕事を「選択と集中」をすることが、道州制を進める上での一番の理由だということです。 道州制が持つ国家像ですが、よく日本全体を社会経済的、地理的、歴史的、文化的条件を勘定して画定した図として描かれます。国家像ではないのですが、画定されたブロックが、中央政府がこれまでしてきたことをほぼ担えるようになり、国際社会の中で競争することができるようにしよう、そうすることで国全体の活力をあげることができる、という主張があります。ただし、色んな主張があるため「これだ」とお答えすることはできません。 質: 都道府県や市町村は、地域主権改革によって拡大してくるであろう仕事を担うだけの体制は整っているのでしょうか。 答: 整っていますが、まだまだパワーアップする必要がある。実力的には問題がありませんが、人とカネは足りません。そのため人とカネも一緒に委譲してもらいたい。つまり、能力的には足りているが、物量的に不足しているということです。 質: 基礎自治体が強くなることで、都道府県や道州制は必要なくなるのではないでしょうか。 答: 基礎自治体ができることは基礎自治体がやる。だけど防衛や外交は中央政府が必要ですし、同じようにして都道府県の役割も議論されなければなりません。何よりもまず、広域自治体でしかできないことは何か、を議論することだと思います。道州制についてもその必要性を問うことが先。 質: 道州制や地方への権限委譲が行われることによって、地方政府が柔軟に動けることになる、また地方政府への関心が高まることは賛成ですが、地域間格差に繋がることはないでしょうか。財源が少なく弱い地域同士が集まることは、逆に衰退するのではないでしょうか。また国が借金まみれの状態で財源委譲をすることで、借金も一緒に移譲されるのではないかと考えられますが、どう思われますか。 答: 市町村合併が進んだ理由として、地域間格差をなくすために進められました。道州制も同じで、道州制推進派の人の主張の1つでもあります。しかし、道州制で複数の県が集まっても、中心部だけが栄え他の地域が衰退する、というのも懸念されている1つです。ですが経済的にも競争力を上げる必要があり、競争には格差がつきまとうものであるため仕方ない部分はあるかと思います。ただ1つ言えるのが、道州制を推進する人の主張には格差を少なくするために推進するということです。 借金委譲を主張されている人は、すでに出てきています。これについては道州制推進派の人は反対しているようですが、慎重な議論が必要です。 政令指定都市でしたら、相模原市と神奈川県が公共事業の財源委譲をする際、公債をどうするかという議論がされていました。
|
|||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |