 |
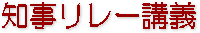  |
|
| 2010年 6月 8日 立命館大学 公務研究科 教授 今仲 康之先生 |
||
今回は、日本銀行京都支店長の講演の予定だったが、急な公務により、担当教員による講義となった。
人口は、国で制度や計画を作るとき、地方公共団体で総合計画や基本構想を作るときの最も基本的な指標である。なぜなら、比較的、中期の場合には、人口予測は確実であるためだ。例えば、10年という中期的な計画作りのときは、人口は予測に沿ってほぼ動いていく。 人口が増えるのか減るのかということで、制度や計画は大きく変わってくる。また、高齢化が進むのかどうかでも制度や計画は大きく変わる。すなわち、人口がどのように動くのかを踏まえて、制度を作り、計画というものも考えていかないといけない。 国では、将来的な人口を想定して、制度を考えてきたが、その通りには動いていないところがある。大きなポイントは、財源について、考えたようには確保できなかったためである。このため、現在、財源の問題が大きな課題である。 人口推移と高齢化 医療や介護、年金を考えるときに、人口がどのように動くのかは、非常に大きな問題である。高齢化の動きがどの時点でどう動いてくるか、また、高齢者を支える世代がどのように変化してくるかということである。 端的に言えば、労働力人口が高齢者を支えるが、今後高齢化はさらに進んでいく。皆さんは生産年齢人口に入り、負担者になる。高齢者が増えるため、当然負担は大きなものになる。 人口は、地方公共団体の施策にも非常に大きくかかわってくる。例えば、小学校・中学校・高校といった学校の整備では、学校を増設しないといけないのか、減少させないといけないのかということである。 今日までは、人口が増えていた。したがって施設を増設するという時期が続いていた。 しかし、人口が減少すると、特に年少人口が減少してくると、そういう施設は過剰になると見ておかないといけない。都市施設の整備では、上下水道の整備や体育施設などでも同じことが言える。地方公共団体は体育関係施設を相当整備した。特に地方では随分整備した。その時は野球がスポーツの中心だったため、野球場を整備した。しかしながら、現在十分使われているかというと必ずしもそうでもない。随分整備したものもあるので、そうした施設の整備はかなり進んでいて、もっとうまく活用していかないといけない。 高齢化率(65歳以上人口の割合)が50%以上の集落が、限界集落である。今日、かなり増えてきている。限界集落が今後どうなっていくのかというときには、人口がどのように動くのかと直接関係してくる。これからはかなりのスピードで人口が減少していくので、限界集落がどうなるかについてはかなり厳しい時代に入っている。 このため、限界集落について、それぞれの地域でどう対応を進めていくのかが課題となる。宇佐市長からも、限界集落を限界集落だけで見ていたのでは大変だから、周辺の集落を含めて考えているという話があった。そのように、どのようにしてうまく課題に取り組んでいくのかが、人口を考えて、どういう政策をとるかということと結びついてくる。 大正9(1920)年は人口が約5600万人、その内65歳以上人口は5.3%であった。昭和20年、25年あたりを見ると、人口は増えていき、7千万人、8千万人に入る。しかし、65歳以上人口は5%程度という状況であった。昭和40(1965)年、昭和45(1970)年あたりに人口が1億人に達するが、それでも高齢化率は6~7%程度であった。 昭和60(1985)年あたりで人口が1億2千万人くらいになり、高齢化率が10%を超えた。 平成17(2005)年が1億2700万人くらいで人口がこのあたりでピークとなり、そこから総人口が減少していくというのが日本の現実である。同時に、この時期に高齢化率が20%を超えている。 昭和60年頃~平成17年頃で高齢化率が倍になった。このことで、ずいぶん財源の状況がかわってきた。国でも社会保障費がどんどん伸び、地方財政でも、民生費がどんどん増加していった。公債残高(国)は平成22年度末で637兆円、地方の借入金残高は平成21年度で197兆円。国と地方あわせて800兆円くらいになる。公債残高(国)の累増を見ると、建設公債は245兆円である。建設公債は、施設を整備するときに、一旦公債で資金を調達し、償還は利用者にも負担を求めて、ある程度長期の負担で整備をしていくものである。特例公債残高は392兆円ある。特例公債は赤字公債である。特例公債がこれだけ累増した裏には、人口の中で高齢化率がどんどん増えて、社会保障費や民生費がどんどん増え、これを国では国債でまかなってきたという現実がある。社会保障費だけではないが、この間の伸びが著しいのは社会保障費であるのは事実である。人口の動きを考えると、高齢化率10%から20%へ伸びるというだけでもかなりの財政負担になったのである。 平成37(2025)年に人口が1億1900万人となり、1億2千万人を切ると予測されている。また、その時には高齢化率は30%を超える。 2045年から2055年あたりで、1億人を切ると予測されている。また、その時の高齢化率は40%に達すると見積もられている。 限界集落は、65歳以上人口が集落の50%以上で、集落の維持が困難になっていると話したが、高齢化率が40%になった国の在りようは、かなり大変だと予測していただけるのではないか。 その後、人口の減少はより激しくなっていくが、高齢化率は40%程度で推移していくというのが、現在の人口に関する試算である。 また、高齢化率の変化について、2000年あたりを注意すると、ここで高齢人口と年少人口がクロスする。2000年以降、65歳以上人口は伸び続けるが、年少人口は減っている。生産年齢人口(15~64歳)も徐々に減っていく。 経済を考えるときに、労働力は非常に大きなファクターである。経済の成長を考えると、労働力の推移、それから資本装備率、技術の水準といったものによって、経済の水準は決まってくる。労働力は徐々に減っていくため、生産性の向上を図っていかないと経済を維持していけない。 日本では、高齢化率が低い時期が続いたが、最近どんどん上がって、将来もしばらくは上がり続けると見込まれる。これは他人事ではない。皆さんは負担する側に入っていくが、負担する側としてかなり大変だということが言える。その時に、どういう社会を創っていくのかということが経済との関係でも重要になってくる。皆さんも人口の変化をよく見ておいてほしい。 合計特殊出生率 合計特殊出生率が2を少し上回らないと、人口を維持できないが、平成19年では1.34となっており、かなり低い水準で推移している。昭和55年では1.75だが、それと比べてもかなり低いと言える。どう対処していくかを考えると、一つは保育所を整備しないといけない。また、子ども手当など、子どもへの対応を社会的に考えていくことが大切になっていると言える。 こうなった理由を調べると、前回の国勢調査の資料で、20歳代後半から30代にかけての未婚率が上がっている。25~29歳で、平成17年で男性では71.4%が未婚、女性では59%が未婚であり、晩婚化の傾向がはっきりと出てきている。 それだけではなく、35~39歳のところを見ると、男性で30%が未婚である。女性でも18.4%が未婚である。こういう状態になってくると、一つは非婚化というケースがかなり出てくる。 こういったことも今後のあり方としてよく考えていかないといけない。ヨーロッパなどを見ると、いわゆる婚外子という形で合計特殊出生率が上がっているというのもあるが、安定的な社会を創るには、婚姻という形でもって合計特殊出生率が上がるように考えていく必要がある。 世界の人口推移 世界の人口推移では、2010年の世界人口は約69億人である。2050年には92億人くらいになると国連の人口予測で予測されている。どのくらい増えるかは一概には言えないが、一つは、アジアが41億人から52億人へ増えていくと見込まれている。 BRICsという言葉もあるが、中国やインドや東南アジアが経済成長をしている。それにあわせて人口も増加している。日本企業が今後この地域にどのようなスタンスで臨んでいくのかも考えないといけないということが分かってくると思う。 二つ目は、アフリカも約10億人から約20億人に増えると予測されている。 一方、ヨーロッパは約7億3千万人から、約6億6400万へ減ると見込まれている。
国内総生産 名目の経済活動別国内総生産の表を見て欲しい。昭和45年から平成17年までは5年きざみで、それに平成18年から20年まで1年きざみのものが加わった、表である。 国内総生産はどんどん増えている。昭和45年は73兆円くらいであったものが、平成17年には500兆円くらいになっている。昭和45年から平成17年までの大きな動きを見ると、増え続けていると言えるが、増え方は産業によって異なっている。 農林水産業は、4兆円くらいから大きくなり、平成2年に11兆円くらい、そこから減ってきて平成17年には7兆5千億円くらいになっている。1次産業の全体の産業に対する割合は、昭和45年には5.92%あったものが、平成17年には1.44%になっており、全体に占める割合が低下してきている。 鉱業は、もともと比較的小さい額だが、現在はかなり減った数字で、平成20年では4千億円くらいになっている。 製造業は、昭和45年が26兆円くらいで、平成2年には約121兆円だが、その後減ってきて平成17年では105兆円、平成20年には約100兆円になっている。製造業もピークを過ぎて減ってきているのである。 建設業は、もっとドラスティックで、昭和45年に5兆円くらいだったものが、平成7年に50兆円くらいになり、平成20年には31兆円くらいで、ピークの6割くらいとなっている。建設業は公共事業の拡大、削減との関係もあって、こういう動きをしている。 電気・ガス・水道業でも、昭和45年では1兆5千億円くらい、平成7年に約13兆円で一番大きな数字となり、そこから減ってきて、平成20年では約9兆円になっている。 卸売・小売というのも、昭和45年で10兆5千億円くらいで、平成12年に70兆円くらいまで増加して、その後は横ばいか、少し低下しているという状況である。 金融・保険業も増えていて、昭和45年で3兆円くらい、平成17年に約35兆円となっている。アメリカやスイスでは、金融や保険のウェイトが日本に比べ高い。金融・保険は、生産性の低い産業ではなく、生産性を上げ得る産業である。生産性を上げるためには、知力とある程度の組織、世界的なネットワークが大切となる。 不動産業は、昭和45年で5兆9千億円くらい、平成7年に62兆円くらいになり、そこからは大体横ばいというところである。 運輸・通信業は、昭和45年で5兆円くらい、平成12年で34兆円くらいになり、そこから横ばいになっている。 最後に、サービス業は、一貫して上昇している。昭和45年では7兆円くらいで、平成17年で107兆円、平成20年では114兆円程度となっている。 また、サービスと名の付いている政府や民間非営利の額を合算してみると、昭和45年で12兆5千億円くらい、平成17年で165兆円、平成20年では173兆円程度である。 これらのことからすると、一次産業から二次産業へ、二次産業から三次産業へと、付加価値が変化してきている。 産業別の状況 各産業別の状況で見ると、昭和45年では、一次産業が5.92%、二次産業が43.13%、三次産業が50.95%。それが、平成20年では、一次産業が1.43%、二次産業が25.51%、三次産業が73.06%となっている。 これからの産業の発展や経済成長を考えていくときに、二次産業が大切な産業であることに変わりはないが、三次産業もよく捉えておかないといけない産業であるということも意識しておいてもらいたい。労働契約や雇用関係のあり方を三次産業でもよく考えていかないといけない状況になっている。 就業者数の状況 国勢調査の就業者数の数字を見ると、昭和45年と平成17年では、就業者総数が5094万人から6356万人へ増えている。 5年きざみで見た時に、数として最も多いのは平成7年で、6457万人である。その後は減少してきている。 一次産業は、昭和45年では17.4%、平成17年で4.4%である。 二次産業は、昭和45年に35.2%で、平成17年には27.0%に落ちてきている。 三次産業は、昭和45年47.3%、平成17年では67.4%と増加している。 その中の分類を見ると、情報通信・運輸のところは、昭和45年324万人、平成17年で493万人となっている。 卸売・小売、飲食、宿泊は、昭和45年で1012万人、平成17年で1465万人であるが、宿泊業は、これからの観光とも相まってどうなるかということである。 金融・保険、不動産業のところでは、昭和45年で132万人、平成7年262万人、平成17年では232万人で、平成7年頃がピークで、そこから減少してきている。 サービス業の就業者数を見れば分かるが、昭和45年で751万人、平成17年では1831万人と、一貫して増えている。高齢化が進むと、医療、福祉が増えてこざるを得ないため、近年では特に医療、福祉の分野で増えている。ここで大切なのは、医療や介護といったことを考えたときに、そこで就労する人たちにとって、就労したいと思えるような条件になっているのかどうかである。このあたりは制度をどうするかと同時に、負担をどうするかという問題である。そこで、就労者の雇用をどう安定化させるかということになる。随分昔の話だが、教育に関して先生を確保するために先生の給料に関する特例法を作って給与を上げたこともあった。 産業別就業者数の各国比較 産業別就業者の各国比較については、農業関係では、日本は3.8%。韓国は7.1%。アメリカが1.5%。イギリスが1.4%。ドイツが2.2%、スイスが4.0%、ノルウェーが2.2%、ロシアが8.4%となっている。 韓国やロシアはまだ農業への就労者人口が多く、二次産業がより発展していくと考えられる。今から10数年まえ、ベトナムの内務省で、農業就業率は70%程度だと聞いた。当然、二次産業を早く発展させたいと思っていた。話をしていると日本からも産業立地を進めるように願いたいと言われた。 製造業では、日本は18.4%、アメリカは10.9%、イギリスは12.0%、ドイツが22.0%。アメリカやイギリスと比較すると、日本の製造業は就労率が高いというのが分かると思う。 金融仲介業では日本は2.6%、アメリカは5.0%、イギリスは4.3%、スイスは5.8%となっている。金融を上手く使うことが、その国の所得を生み出す一つの原動力になるということも分かるのではないか。 教育、保険衛生・社会事業では、日本はそれぞれ4.5%、9.4%となっている。それに対して、韓国は7.2%、3.2%となっている。アメリカは9.1%、12.5%となっている。イギリスが9.1%、12.4%、ドイツが5.9%、11.7%、ノルウェーは8.7%、19.9%となっている。これからすると、日本では、教育、保険衛生・社会事業の部分が大事になってくる。保険衛生・社会事業では、日本の場合特に人口の高齢化あるいは少子化との関係があり、こういうところに重点を置くことが大切である。 労働生産性 もう一つ大切なことが労働生産性である。OECD諸国について、労働生産性がどうなっているかということについて指標が出ているが、日本の労働生産性はOECDの平均を下回っており、2008年で20位である。1位はルクセンブルグ。2位はノルウェー、3位はアメリカ合衆国である。日本はまだ労働生産性は低い。格差社会という話があるが、これからの日本は生産性の向上に努めていかないといけないということが分かると思う。製造業も含めて、生産性の高い分野へ投資し、また生産性を高めていく必要がある。 貿易依存度 貿易依存度については、日本はそれほど高くない。2008年で輸出依存度が16.1%、輸入依存度が15.6%である。日本は輸出入に依存するのではなく、国内で付加価値が大きく付いているという経済となっている。輸出入が重要であることに変わりはないが、国内需要、国内の生産力をどうしていくかということが大切である。 韓国は、輸出依存度、輸入依存度が随分高く、2008年の輸出依存度は45.4%、輸出依存度は46.8%となっている。 アメリカは、2008年で輸出依存度が9.1%、輸入依存度が15.2%となっている。依存度という面では、アメリカは輸出入にそれほど依存していない。 中国は2008年で輸出依存度が33.0%、輸入依存度が26.2%であり、意外と中国も輸出依存度、輸入依存度が高くなっている。 ドイツは2008年で輸出依存度は39.9%、輸入依存度は32.7%であり、かなり輸出入で大きなウェイトがある。 商品分類別輸出入額 商品分類別輸出入額を見ると、日本の輸出総額は78兆円程度、輸入総額は76兆円程度である。ドイツは輸出総額が約146兆円、輸入総額が約120兆円となっている。中国は、輸出総額が約143兆円、輸入総額が約113兆円となっている。アメリカは、輸出総額約130兆円、輸入総額が約216兆円となっている。 ポイントは、日本は、鉱物性燃料(中心は石油や天然ガスなど)が輸入では26兆円強となっていて大きいことである。輸出では、機械類、輸送用機器が48兆円程度で、日本は機械類、輸送用機器に非常に重点が置かれた結果になっている。 ドイツを見ると、機械類や輸送用機器も大きいが、化学製品や工業製品にも輸出部分の数字がそれなりに出てきている。スイスも化学製品のあたりに相当の数字が出てくる。 OECDの中での日本の生産性は高くないと話したが、クスリなど生産性の高い部分に投資をすることが重要になっているということは各国比較を見ても言える。 中国は、工業製品や雑製品の輸出が多く、生産性としてはまだあまり高くない。 各国比較をしてこれからどうするか考えると、地方公共団体でも、国でも、手を打たないといけないということが分かる。最近、太陽光発電や自然エネルギーの活用といったことが大切になってきているが、このようなところに重点的に早く取り組んでいかないといけない。 グリーンニューディールという言葉が出ているが、日本は各企業が競い合って、太陽光発電では随分進んでいた。ところが、日本はいわば分散投資であったが、ドイツが太陽光発電から電力を買い取るシステムを作り、重点投資をしたところ、日本は遅れをとったという結果になっている。その他、かつて反省しなければいけない点があった。半導体のDRAMの分野では、日本はそれぞれの企業で取り組んでいたが、韓国のサムスンが重点投資をして取り組んだ。そうすると、すぐにサムスンに追い抜かれたという例がある。 そういうことも踏まえてこれからの日本の産業のあり方、経済のあり方を考えていかないといけない。 国際収支状況 国際収支状況を見ると皆さんの感覚が大きく変わると思う。 平成20年の日本の経常収支を見ると、約16兆円の黒字になっている。 貿易・サービス収支は約2兆円の黒字になっているが、貿易収支は約4兆円の黒字で、サービス収支は約2兆円のマイナスになっている。 それに対して、所得収支は約16兆円の黒字。 現在の日本は、所得収支のほうが、貿易・サービス収支に比べてかなり大きいという経常収支の構造になっている。 その裏腹として、資本収支がマイナス18兆円という数字になっている。これがマイナスなのは、海外にそれだけ投資しているということを意味する。つまり、投資がそれなりにうまくいってそのリターンが入ってきているということである。 日本は、これから産業への投資をどのようにするのかということが課題になってきていて、それを国が制度としてどう仕組んでいくのかが重要で、また生産性の高い分野への投資を上手くしていかないといけないということが分かっていただけると思う。
全国総合開発計画は、第1次から第5次まで5回作られた。 ここには重要な分岐点が二つあり、一つ目の分岐点は、第2次から第3次へ変わる時である。この時にオイルショックが起きた。オイルショックまでの計画は、重化学工業中心で、重化学工業を全国的にどのように立地させていくのかが主眼だった。それを効率的に行うために、道路の整備や港湾の整備や工業用地の確保、電力の確保を効率的にやるというのがここまでの計画であった。全総計画(第1次)は比較的うまくいったが、新全総(第2次)はあまりうまくいかなかったというのが率直なところである。 そこで、オイルショックが入ったことにもよるが、3全総は「人間居住の総合的環境の整備」とあり、今までとは視点が違っているのである。総合的環境とは、一つは生産環境、二つ目は生活環境、三つ目は自然環境のことである。生産環境、生活環境、自然環境の総合的環境の整備をするということと、それによる定住構想ということが含まれている。 もう一つの大きな分岐点は、第4次から第5次に変わるところである。第4次と第5次の間で、1991年にソ連が崩壊し、東西冷戦構造が終焉した。第5次のところで、「地球時代」や「大競争」という言葉が出てくる。この頃から中国の動きが激しくなってきて、今日のような中国の経済発展につながっている。 第4次の計画は、「多極分散型国土の構築」ということで、東京一極集中から多極に分散して、地域ごとにもっと頑張ってもらおうという構想である。第5次になると、「多軸型国土構造形成の基礎づくり」とあり、「地域の選択と責任に基づく地域づくりの重視」ということが掲げられている。 ある面では、こうならざるを得ない時期になったと言える。昭和50年代後半に、日本は先進国へのキャッチアップをほぼ達成し、先進国となった。先進国になると、ここからが大変で、それまでは先進国がどうなっているかを調べて計画づくりをして、それに対する予算を積算して財政担当へ持っていくと、確実に説明ができた。現実にこうなっているということを、先進国の事例で説明し切れた。キャッチアップが達成されると、自分たちで考えてやっていかないといけなくなるため、そこには以前と違ってリスク負担が出てくる。その時に、国ではなかなか予算が通らないというのが実情だった。国の予算編成では、リスクをゼロにするという方向で議論するため、なかなか難しいのである。 それぞれの地域で自立して創意工夫をしてもらう。それぞれの地域が知恵の時代に入っていると思ってもらえれば良い。大切なのは、知識の時代ではなく、知恵の時代であるということである。知識はある面では過去のものだが、それに対して知恵は将来に向かってどうしていくかをいくつもの視点から予測して確実性の高いものを着手していくものである。 そのような変化の中で、現在では全総計画は終わり、国土形成計画をつくるという方向に変わっている。 国土形成計画は、全国計画と、広域地方計画の二つに分かれている。 全国計画は大きな指針を示し、広域地方計画はそれぞれの圏域で特色を持って取り組み方を決めるというものである。 各ブロックの広域地方計画の主なポイントを見ると、それぞれの圏域で重点がかなり違うというのが分かってもらえると思う。 創意工夫や知恵が大事だというのは分かるが、しかしながら足りない面もあるのではないかということがある。今までの全総計画のときもそうだが、「国土の均衡ある発展」、「地域の発展」ということでやってきたため、結果として、ハブ空港やハブ港湾という機能を考えたときに、世界的にみて機能が低い状態になってしまっている。 日本の各地方空港にハブ空港はどこかと聞くと、韓国の仁川空港がハブ空港のようになってしまっている。港湾でも、プサンの港湾が日本のハブ港湾になっているようで、空港や港湾では日本のハブの影が薄くなっている。今、国土交通省でもここに重点を置くことを考えている。 また、各知事や市長の話を聞いても分かるが、高速道路や新幹線ができているところとできていないところで大きく違ってくる。例えば、東北地方は高速道路の整備や新幹線の整備で大きく変わっている。以前、九州の話があったが、大分や宮崎が高速道路で取り残された形になっている。 なぜ取り組めなかったのかは、財源がなくなってきたためである。重点投資をするとしても、なかなか動けない枠組みになっているのが現状である。
地方自治の原則として、地方自治法第1条の2第2項では、国は、①「国際社会における国家としての存立にかかわる事務」、②「全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動もしくは地方自治に関する基本的な充足にかかわる事務」、③「全国的な規模でもしくは全国的な視点にたって行わなければならない施策及び事業」の3つことを行うものとし、住民に身近な行政はできるかぎり地方公共団体にゆだねることを基本としている。 これが、国と地方を考えるときの基本的な原則である。①の例としては外国や防衛がある。②の例としては生活保護の基準や、労働基準などがある。③の例としては、幹線道路の整備などがある。 地方自治法第2条第3項では、市町村が基礎的な地方公共団体であるとされている。 また、5項にあるように、都道府県は広域の地方公共団体として市町村を補完するという立場で考えられている。 8項9項のところに、自治事務と法定受託事務について書かれている。地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務に分かれている。 しかし、自治事務の中に、自治体独自の事務と国の受託事務がある。国からの受託事務は法定受託事務だけではなく、自治事務の中にもある。そのような受託事務について、国の負担金が入ってくる。独自事務に対しても、国の補助金が入ってくる。 そして、地方税や地方交付税などで地方公共団体の財源を確保するという仕組みになっている。 そこで、自治事務について、国が義務付けや枠付けをするのではなく、地方公共団体のそれぞれの事情に合わせて、地方公共団体独自で基準を考えていくべきではないかということが言われている。 義務付けや枠付けについて、地方公共団体で条例を作って基準を調整し、それぞれの地域でやっていくほうが、実状に即して、良いのではないかということである。 このため、地方分権改革の中で、そのようなことが謳われたのである。
|
|||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |