 |
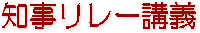  |
|
| 2010年 6月 22日 三重県 野呂昭彦 知事 |
||
「 将来に希望を持って生きられる社会を目指して 〜全国知事会「この国のあり方に関する研究会」を通して〜 」
今回は、野呂三重県知事より、県政運営の方針と、全国知事会の取りまとめた「この国のあり方に関する研究会」報告書の内容について、講演があった。
立命館大学の全国知事リレー講義には、これまで4回ほどお邪魔しており、今回で5回目になる。三重県庁では、立命館大学出身の職員が一番多いと思う。立命館大学と三重県は非常に関係が深い。立命館アジア太平洋大学が大分にあり、この大学はドイツの環境関係の大学と連携しており、そこの環境関係の学生が、四日市の環境技術支援センターに来たり、高校生と交流したりしている。 今日は、将来に希望を持って生きられる社会をめざしてという表題で話をする。
県政は、県民の人生の舞台づくりだと考えている。そのように捉えたときに、どういう県政が大事か。私は平成15年に知事になったが、そのときの県政運営の3つの柱は、「県民が主役の県政」、「県民との協働」、「感性を磨く」であった。 「県民が主役の県政」は、舞台の上で人生の舞を舞うのは県民であるという考え方である。「県民との協働」は、県民と一緒になって創造していく舞台づくりということである。「感性を磨く」は、行政は何のためにやっているのかということを考えたときに、行政にある立場として、感性を常に磨いて受け止めていくということが大事であるという考え方である。 その中で、特記されるようなものとして、1つ目に経営品質向上活動がある。北川前三重県知事が提唱して平成12年から始まったが、そのとき私はまだ松阪市長をしていた。北川前知事と一緒になって、松阪市も経営品質向上活動に取り組んだ。これは、私が知事になってからも県政のマネジメントのベースに置いているものである。平易に言えば、誰のための、何のための県政かを常に考えていくということである。つまり、公共サービスの受け手の立場に立って、最良の仕事の進め方をしていくということである。レーガン時代に、アメリカが日本の経営を勉強しに来た。日本では品質管理がしっかり浸透しており、それをアメリカは学んで帰り、製品の品質管理ではなく、マネジメントの品質管理のツールとして新たに開発した。それを逆輸入したのが日本の経営品質向上活動である。要するに、職員の意識を未来永劫磨いていこうというものである。 2つ目は「新しい時代の公」である。私が知事になり、総合計画を作るときに、考え方の柱の一つに置いたものである。行政サービスはどうしても画一になりがちだが、NPOなど多様な主体の人たちと平等・対等なパートナーとして連携してやっていくことによって、行政サービスそのものももっと広がりきめ細やかな大きな効果が出せるのではないか、と思い、平成16年以降大きな柱にしている。民主党政権になって、「新しい公共」ということがよく言われるが、三重県では平成16年からすでにこのような取り組みをしていた。 3つ目は「文化力」という考え方である。文化とは生活の質を高めるための人々の様々な活動とその成果のことを指している。分かりやすく言うと、私たちの生き方・生き様・くらしぶりなど広い意味の文化ということである。その文化は、とても人を魅了し、惹きつけ、お互いに高めていくような多様な力を持っている。人間力、地域力、創造力などがあるが、素晴らしい生き方をする人は、必ずまわりの人を感化させる。目を輝かせて、生き生きと生きているような人がいる地域は、よそから尋ねてきた人も魅了する力を持っている。それが地域力である。人間の持っている魅力や地域力に、さらに新しい知恵をつけ磨いていくことができるのが創造力である。三重県では、地域力、創造力などをあらゆる政策を策定する際の物差しとしている。 平成18年に文化力指針というツールをつくり、平成19年以降文化力を政策の中に活かそうと取り組んでいる。平成19年からは、「質の行政改革」としてトータルで取り組んでいる。文化力で政策の質を高め、新しい時代の公にふさわしい仕事の進め方をしているかということを考えながら、その根底には職員の意識を常にみがきながら取り組んでいる。こういった取り組みは、地方分権が叫ばれるなかでとても大事である。地方分権を進めていく中では、特に地方にとっては行政能力と質をどう高めていくのかが極めて大事である。 いろいろな取り組みをしているが、なかなか成果がしっかり出てきていないのが現状である。 国では改革ということが言われ、地方分権と言うと権限移譲や財源の配分や道州制などの改革議論が行われるが、この国の形そのものの議論の前に、今さまざまな問題が起こっており、少子高齢化、人口減少が非常に進んでいる。小泉内閣によって小さな政府論が強調され進められてきたが、結果として福祉を縮小させ、雇用システムを崩壊に追いやり、貧困や格差が拡大し、三位一体の改革は地方を本当に疲弊させる原因になった。 世界的な経済危機になり、新自由主義的な構造改革がこの国の社会経済を崩壊させることになった。改革やいろいろな取り組みをするときに、この国がどういう国民の暮らしぶりを実現しようと目指しているのかという将来像がイメージされていないということがあった。
昨年夏に全国知事会 この報告書は5章から編成されている。 まず各県の知事に、今この社会の中で不安感、閉塞感をもたらしている要因を経済面、社会面、環境面、政治面などいろいろな角度から抽出してもらった。 経済面から見ると、工業社会から知識社会へ変わっていくと言われているが、そのイメージが見えていない、行き過ぎた規制緩和が行われている、正規労働者と非正規労働者が二極化しているなどの意見があった。 社会面では、貧困・格差の拡大、地域医療の崩壊、セーフティーネットの崩壊、年金制度の崩壊、絆がなくなっているなどの意見があった。 環境面では、農地の放置、森林の荒廃、食品の安全性などの意見があった。 政治面では、不祥事、政治とカネの問題、地方の疲弊、膨大な借金などの意見があった。 こういういろいろな我が国の不安感、閉塞感から、この国は峠のときにあり、今求められているのは、制度論や改革議論も大事だが、このような制度や枠組みを俯瞰した、国民生活そのものから、この国のあり方についての議論がまず必要ではないかということを第1章で結論づけた。 第2章では、福祉政策と雇用政策ということで、国際比較から見た我が国の特徴を描いた。国際比較から見ると、政府の大きさと経済成長は結びついている。大きな政府だと経済成長が阻害されると言うが、国際比較で見るとそうでもない。 格差や貧困をなくすためには、現物給付の充実も必要である。それは住民に近い地方の政府が行うのがふさわしい。アメリカも日本も社会的支出が少なく小さな政府だが、ヨーロッパ諸国ではドイツやスウェーデンは社会的支出が非常に高い。 経済成長率を見ると、一番成長率が高いのは、一番大きな政府のスウェーデンである。アメリカは新自由主義に徹しているため成長率は高いが、日本は経済成長率も低い。 政府の財政状況を見ると、スウェーデンは黒字だが、他の国は赤字となっており、大変財政が厳しい状況である。相対的貧困率もスウェーデンが一番低く、格差もスウェーデンが一番小さい。 大きな政府のほうが財政的には黒字で、格差や貧困は小さな政府ではむしろ大きくなっているということが分かる。 社会的支出を生活保障と雇用保障として区分してみると、スウェーデンの現物給付は最も高い。現金給付も相当なレベルにあるが、現物給付が高いということが格差・貧困を小さくしているということが分かる。雇用の点では、雇用の弾力性(解雇することの容易性)は、ドイツは非常に高い。スウェーデンは積極的労働市場政策をとることで、再教育・再訓練という政策を強化している。こういうところのほうが貧困や格差は小さくなっている。 日本の特色は、社会的支出が非常に低いということである。かつては長期雇用で守られてきた働き手が、その家族も支えて、失業率を低くし、格差や貧困を抑えられてきた。雇用レジームが崩壊してきたことで、福祉の体制、制度も機能しなくなってきたというのが現状である。これまではこの国独自の歩みをしてきたが、それが今は崩壊してきている。新しい日本型のモデルが構築されなくてはならないということを第2章で導いた。 第3章では、私たちはこれからの目指すべき社会の方向性は、将来の希望を持って生きられる社会を構築していくことだと指摘した。具体的には、すべての人々が能力を高め、発揮をする中で、多様性と創造性に満ちた活動が保障され、何らかの事情で活動できなくなった場合も一定の生活が保障され、繰り返し活動できることが不可欠であり、家族や地域といったさまざまな絆が育まれあらゆる場面で助け合い、支え合い、そして分かち合いが出来るような社会だと描いた。 その社会を3つの側面からとらえた。第一に、生き生きと働ける社会である。働くと言うことは、生活の糧を得る手段にとどまらず、人として生きる誇りあるいは喜びである。この誇りや喜びを享受することで、社会に活力と安心がもたらされる。そういう意味では、産業を元気にしていく必要があるし、多様な選択ができ、再挑戦ができる社会が大事だということを指摘した。 第二に、生涯を通じて不安のない社会である。いろいろな不安要素を解消して、安心して生活できるという実感を得ることで生き生きと働くこともできるし、明るい家庭を築いていくことも出来るし、さまざまな地域での活動もできる。 第三に、さまざまな絆がはぐくまれている社会である。家族や友人と喜びを分かち合い、お互いに貢献をすることが喜びである、といった価値基準で形成されるもので、競争による効率性の追求や、需要と供給で決定されるような経済原理に基づくものではない。絆は公共サービスをより質の高いものにするための基本的な考え方である。 第4章では、「この国」を実現する政策の方向を、どう実現していくのかについて提案をしている。将来に希望を持って生きられる社会を作るためには、人という宝を大切にする必要があるという指摘をしている。人という宝を未来に向けて磨き、高めていくためには、さまざまな絆が育まれている必要がある。 張り合いと潤いを得るなかで、子どもが健やかに成長し、適切な教育の下で、若者となって、そして社会に出て、その上で生き生きと活動をし、安心して生活を営み、そして次の世代を育成していくという連鎖が途切れないような政策をパッケージとして作り上げていくことが大切である。 そこで、4つの柱を打ち出した。柱1は、次世代の育成は、新たな社会基盤として位置づけられるものだとした。コストではなく、未来への投資と捉えて、子どもを社会全体で支えていくということが大事で、子育てと就労の調和を支援する政策も必要である。適切な現金給付と合わせて保育サービス、就学前教育サービス、放課後児童クラブ、小児医療サービスなどもの現物給付の充実も非常に大事である。子どもには個人の能力に応じたきめ細やかな教育サービスの提供が必要で、少人数教育や、多様なカリキュラムを整備していく必要がある。キャリア教育や職業教育など社会人にも広く教育を受ける権利を保障することが大事である。 次に、柱2として「活動保障」としての生き生きと働ける場づくりを政策の方向として大きく掲げた。産業政策にもまず4つの視点を置いた。例えば、知識集約型産業の視点がある。先端的な研究開発、技術開発や地域資源の活用、あるいは優れた感性の活用などの視点から、これからの産業を考えていかないといけない。教育や健康では、強い社会保障なども言われているが、福祉や教育関連の産業は、これからもっと雇用を吸収していく産業になる。そういったところを強調していかないといけないということを指摘している。環境としては、省エネやエコ住宅、自然エネルギーの活用などを指摘している。農林水産業でも、高付加価値化、公益的機能を増進するといった視点から産業を捉えることもできる。国境を越えた視点では、国際競争力の強化の観点として、例えば新幹線を海外に輸出していくといったように、国際貢献にもつながるものもある。国際交流から言えば、国際観光も産業として捉えられる。 次に、生き生きと働ける条件づくりということがある。スウェーデン等の例のように、積極的な労働市場政策として、仮に病気や事故で働けなくなっても、いろいろな教育や訓練をいつでも受けられて、いつでも社会のなかに戻ることの出来るようにしていくことが必要である。保育や育児休暇を取りやすくしたり、女性も含め労働市場に参加していく機会を保障したりすることや、採用時期や退職時期を弾力化することも含めて指摘をしている。公共事業については、地域の競争条件の向上にもつながるものであるから、真に必要なもの、国際戦略上不可欠なもの、未来への投資などは大事だが、新たな視点も大事である。すなわち、ストックを重視した視点、自然の営みを再生改善するという視点である。 3つ目の柱として、「生活保障」として安心して生活できる環境づくりということがある。安心は、防犯や食の安全など、いろいろな観点から捉えられるが、ここでは、自立、健康、老後、環境といった視点から整理をした。自立ということでは、一定の生活保障をする制度が用意されていて労働市場に参加できない場合に、生活を保障ができるような政策をとっていることが大事である。例えば雇用主に対しても各種の奨励金の充実をすることで、障害者や高齢者の雇用の促進にもつながる。健康・医療の側面では、安定的で持続可能な医療制度を作っていくことが大事である。質の高い地域医療が提供できる政策をしていかないといけない。老後は安定的で持続可能な公的年金制度を再構築していかないといけない。お年寄りの介護もあるが、医療と介護が連携した制度、体制を作っていく必要がある。環境の観点では、自然との共生、持続可能な循環型社会を構築して、次世代につないでいかないといけない。 柱4は、張り合いや潤いをもたらす絆づくりである。絆は、活動保障や生活保障の基礎的な支えとなるもので、経済原理だけでは捉えられない、張り合いや潤いをもたらすものである。家族や地域の絆の再生、多様な主体の参画と連携、多様な交流による新たな価値の創造といったことを提案している。こういうことが相互の理解を高め、新たな価値も生み出していくだろうし、ネットワークも広げていくことになる。最近はソーシャルキャピタルというのが言われているが、絆づくりはまさにソーシャルキャピタルの考えに共通するものである。 第5章では、これまで示した政策の方向性を実現していくために、どのように取り組んでいくのかということを提案している。質の高い公共サービスが必要になってくるが、ここでは公共サービス、財政、信頼性という3つの側面から捉えた。 公共サービスという観点では、地方政府による現物給付と中央政府による現金給付、年金など社会保険による現金給付というものがセットになって高い水準の公共サービスが必要になってくる。そういうサービスを提供する手法や水準、給付の対象を考え、その上で産業政策の展開やインフラ整備にも触れている。現金給付と現物給付では、公共サービスにおいては、教育、職業訓練、福祉・医療あるいは養老サービスなど現物給付が非常に重要になってくる。現物給付はそれぞれの地域で個別のニーズに応じたきめ細やかなサービスを提供する必要があることから、地方政府の役割と言えるが、地方政府がこの役割を果たす上では、地方政府への権限移譲や財源移譲が不可欠である。したがって、地方分権をさらに推進していく必要があるし、そういった中で地域主権の社会が実現されていくことになるのである。 給付水準とナショナル・ミニマムという観点では、ナショナル・ミニマムとは国民の生存にかかわる最低限の生活の水準という意味だが、最近はいろいろな広い解釈がされており、今一意義を明確にしておかないといけない。その上で、それは中央政府によって国民に等しく保障する必要があるということを指摘している。地方政府には財政力に格差があるため、財政調整制度を通じて、地方政府が担う現物給付のミニマム保障をしていく必要がある。不偏主義と選別主義ということでは、ユニバーサリズムの考え方を強調している。貧困や格差を少なくするという観点から、現物給付は所得の高低にかかわらず、一定の条件に合致した場合には同様のサービスが供給されることが求められる。子ども手当が今年から始まったが、これは所得制限等を設けておらず、普遍主義に基づいている。政策によって選別主義とするのか、不偏主義にするのかは異なってくる。例えば、生活保護は所得制限が設けられるべきもので、選別主義に成らざるを得ない。高い行政サービスを提供するためには不偏主義をしっかり捉えておかないといけない。また、産業政策は地域政策でもあるという視点を忘れてはいけない。三重県は、中小企業も含めて世界に通じるレベルの高い技術を持っている。競争力のある産業という視点からは、地域に根ざした技術を活用しながら取り組んでいかないといけない。産業政策は国が中心になってやるべきではないかという議論もあったが、地方発の国際競争力のある戦略的な産業政策も必要だということになった。中央政府は将来成長が期待される分野の研究開発の促進や、投資環境の整備をし、マクロ的な観点から金融や経済財政政策をしっかり責任をもってやっていかないとならない。 財政から見た政府のあり方としては、高い公共サービスを提供するためには、増税は避けて通れなく、税制の抜本的な見直しが必要であると指摘した。税制の改革は総合的に検討する必要があるため、法人税や消費税についても検討する必要がある。消費税は税金のなかでも最も安定した税目で、地方にとっても非常に良いと考えている。低所得者層への配慮も大事で、税の抜本改革に向けての議論を参議院選挙後本格化すると菅内閣も言っている。消費税では、低所得者層へ配慮をするのであれば、品目毎に税率を変えることや、給付付き税額控除制度がある。これらを実現するためには、政府に対する高い信頼がないといけない。さらに、中央政府と地方政府の役割分担に応じた税源配分を見直していかないといけない。現物給付ではこれから地方の責任が大きくなってくる。そのためには、景気に左右されない安定的な税源が確保されないとならないが、これは消費税ということを意味している。同時に地方の課税自主権の拡大も大事である。財政調整制度、財源保障制度では、現行の地方交付税制度は政策的に誘導されるものではないという原点に立ち返る必要があるということを指摘している。知事会は前々から地方共有税制度を提案しており、国の会計を通さず、地方税として独立した制度の実現が大事であると指摘している。財政赤字は大きな課題であり、しっかりとした経済成長戦略をたてながら、安定した税収が確保できるようにし、財政赤字を解消していくことが必要である。当面の回避措置として、国債の借り換えや、償還期限をもっと長期化することなどを指摘している。政府に対する高い信頼がないといけないため、その意味では信頼回復が非常に大事である。説明責任をしっかり果たし、税の改革が自分の活動保障・生活保障へ見返りとして実感出来ることが大事である。 結論としては、この国は次の新たな国を構築していくために、将来に希望を持って生きられるこの国のあり方を実現していかないといけないと指摘をした上で、大きな政府、小さな政府というより、日本型モデルとしてしっかり活動・生活できる国を作っていかないといけないということである。地方政府が果たしていかないといけない役割は、この国のあり方を実現していくためにはとても重要なことであるため、地方分権や地域主権の社会を実現しないといけない。
みなさんも、「形」議論ではなく、なぜ地方分権が必要か、地域主権の社会が必要かということを考えてもらいたい。東京大学の玄田先生が希望学というのをやっている。「希望」を英訳するときに、A wish for something to come true by action.という訳
問 一括交付金が来年度から順次やっていくことが決まった。このような財源移譲についてはどう考えているか。 答 一括交付金は補助金制度をやめて、補助金として地方に行っているお金を、分野毎に一括して地方に渡すという制度にしていこうというものである。現物給付、現金給付は、政府がやろうとしているサービスについて、お金で配るか実際に公共サービス給付としてやるのかということである。国はいろいろ一括交付金化について言っているが、中身ははっきりとわからないのが現状である。 問 地方分権ということを言っているが、地方議会の問題についてはどう思うか。 答 行政能力を高めるためにいろいろなことをやっている。地方は行政と議会があるから、議会も議会能力を高めることが非常に大事である。三重県議会は都道府県としては初めて議会基本条例を作った。三重県では、議会能力を非常に高めていると思うし、今後地方議会がしっかりとチェック・監視し、議員提案もしっかりできるような議会にしていかないといけない。 問 介護サービスは国家が保障するべきで、そこまで地方自治体がするべきなのかと思うが、この点はどうお考えか。 答 現物給付のサービス給付は、介護でもそうだが、個人個人で度合いが違うため、個々のニーズ、地域性もあり、きめ細かく対応するためには、実際のサービスを実施するのは、基礎自治体がやるのが適切だと思う。
|
||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |