 |
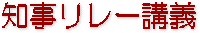  |
|
| �@ �@2010�N�@6���@29���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɍ��@��˕q�O�@�m�� |
||
�@�u�@���C�ň��S���S�ȕ��ɂ��߂����ā@�v�@
(�P)����ɂ��� ���Ɍ��ɂ����邢�����̉ۑ���Љ��B �l���������S���I�ɐi�݁A���Ɍ�����N�x11��1���̐��v�ł�1������560���l�Ɍ����Ă����B��قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����A560���l���s�[�N�ł���ȍ~�����Ă������낤�B��_�W�H��k�Ђł́A�O�N�x����A541���l��540���l�ƌ������B ���݂́A�������23�������A2040�N�ɂ�38���قǂɂȂ�Ƃ��\�z����Ă���B�l����������̓����ɕt�����ċN�����Ă��邱�Ƃ��A�l���̍\��������A���q���̐i�s�ł���B �{���Ԉړ����v���X�̓s���{���́A�������X�������Ȃ��B�����{�Ɍ��肷��Ƃ���ɏ��Ȃ��A����A���ɁA���ꂾ���B����A�N��ʎЉ�������Ă݂�ƁA60�Έȏ�̓]���҂��������Ƃ��ߗו{���Ɣ�r���ē����I�ł���B �]���҂���҂ł͂Ȃ��A����҂������Ȃ邱�Ƃɑ��Ăǂ������邩�B���ی��̑Ώێ҂������邱�Ƃ��ۑ肾�Ƃ����l�����邪�A���͂����͎v��Ȃ��B�Ƃ����̂́A�]�����鍂��҂̑����́A���Ɍ��̗ǂ��𗝉��A�]��������œ]�����Ă��邩��ł���B����]������̂��Ƃ����A���U�w�K�Ȃǂł���B�܂�����҂͒��������������Ă���Ƃ����_�ł��A�傫�ȏ���ґw�ɂȂ邾�낤�Ɗ��҂ł���B ���Y�N��l���ł���15�`65�͂��ꂩ��20�N�Ԃŋ}�����A����ɂ���ĎЉ�̊��͂�������̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜����Ă���B���ɂ�2010�N�ł͐��Y�N��l����63���A����Ґl���͑S�̂�21�`23���قǂ����A����20�N��ɂ͑S�̐l�����R������ƍl�����A���Y�N��l����59���l(6��)����������Ɨ\�z����Ă���B �������A�����������Y�N��l����15�`65�Ƃ����̂́AOECD�̒�`���̗p���Ă��邾���Ȃ̂ŁA���{�̎Љ�ɍ��킹�Ē�`���Ȃ����K�v������B�����ŁA���Y�N��l�����Q�O�`69�Ƃ��Ē�`���Ȃ����Ƃǂ��Ȃ邩�B2010�N���_�Ő��Y�N��l����65���ɑ����A20�N�����`�ύX�O�ɔ��13���l������B�܂�A�Љ�̊��͂́A60�㍂��҂̎Љ�I�Q����Љ�V�X�e���ō��グ�邱�ƂŁA�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B (�Q)���q�����ւ̑� ���ɁA���q�����ɂ��Đ�������B���v����o�����͂����ߔN1.3�������O�サ�Ă��邪�A�l���������ɂ��Ă������߂ɂ́A2.07�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ����ŁA20�`39�Ƃ����o���K��̏����̐����A��70����������4�N�o��8���l���������Ă���B �o�����͍�N48430�l�ƂȂ����B�l���������ɂ��邽�߂ɂ́A���v����o�������Q�ȏ�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���݂�1.33�̂܂܂��ƌ������Ă����B�o���K��̏����͂����Ă����B����Ǝq�ǂ��ޑS�̐�����������B����Ǝq�ǂ������܂��m��������B �����ʼn�X�͏o���ڕW��23�`27�N�܂ł̊Ԃ�24���l�Ƃ����ڕW���f���A�l�X�Ȏq��ăv�������\�z���Ă���B ���̒��ł��������̂��u�o��E�����x�����Ɓv�B�q�ǂ��͕v�w�ł���j������Y�܂��킯������A���q����̂��߂ɂ͕v�w��������K�v�����邪�A�������̂̌����A�܂��Ӎ��������{�̌X���ł���B���{�͉��Ă̎{����Q�l�ɂ��邱�Ƃ��������A���[���b�p�ł͖����̕ꂪ�������A�ޏ������͎Љ�I�ɗe�F����Ă��邱�ƁA�܂��A�����J�͈ږ��̍��̂��ߎЉ�I���傫���Ⴄ���߁A���{�Ǝ��̐�����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�o��T�|�[�g�Z���^�[�B���̃T�|�[�^�[�Ō��������l�͂܂����Ȃ����A�t�������Ă���3�`5�N�����邽�߁A���㑝����̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z�����B ����ɁA�R�E�m�g����Ƃ́A�_�R�����̐l�ɓs�s���̎Ⴂ�������Љ��Ƃ����C�x���g�B����܂�120�g���a�����A����ɂ������̂͗������Ȃ����ƁB �����āA���q����̂��߂ɂ͎q��Ďx�����K�v�ł���A��e�̎d���Ɛ����̃o�����X��ۂĂ�悤�x�����Ă���B�Ƃ����̂͑�2�q�ނ̂́A�ǂ����������������������̂������Ă݂�ƁA�ł��W�܂����ӌ����u�p�[�g�i�[���玙����`���Ă���邩�ǂ����v�������B�����Ŏc�Ƃ����炵�A��Ƃ̌�������������{������Ă���B�Ⴆ�ΐ�i�I�Ȋ�Ƃ̌��C��A�玙�x�ɂ𗦐悵�Ď�点���Ƃւ̏������z�z�Ȃǂ����Ă���B ���q����Љ�ɓW�]�������Ă��Ȃ��l�������A���͂����v���Ă��Ȃ��B����҂̂������ی��T�[�r�X���A�Q�������ԂɂȂ��Ă���l�͍���ґS�̂̂T���قǂł���B�܂����T�[�r�X���Ă��邾���̐l�͂P�T���قǂŁA���������������ł���l���唼�ł���B�ނ�͌��C�ł���A�~��������A�Љ�Q����ł���d�v�ȑ��݂ł���B���̂��ߎЉ�Q������邽�ߎd�g�݂�A��Ð��x�𐮂��邱�Ƃ��d�v�ł���B �܂��A�Љ�̊��͂��������ŏd�v�ȑ��݂������ɂ��Љ�Q��ł���B�Љ�Q��x�A�܂�d���������Ă��鏗���̔䗦�͓��{�S�����ς�45.5���ł���̂ɑ��A�k��������90���A�t�����X�ȂǑ��̃��[���b�p������86���Ɣ��ɍ������ł���B���{�ł͏����͂���2�{�قǎЉ�Q�����ł���͂��ł���A���̂��߂ɂ͏����̓����₷�����Â��肪�K�v�ł���B�����ŁA��قǏq�ׂ��悤�ȕۈ�T�[�r�X�̏[���A�q��Ďx�����K�v�ɂȂ��Ă���̂ł���B (�R)�n��l���̕� �l�������ƂƂ��ɋN���錻�ۂ��A�n��l���݂̕ł���A�n��l���݂͒̕n��ɂ���Ċ��͂̊i���ݏo�����ƂɂȂ�B�_�R�����ȂǑ����R�n��ł͐l�����������A�ƁA�����k��n���o������Ȃǂ̖�肪�������Ă���B �����ŁA�n��Đ�����Ƃ���������s���Ă���B��̓I�ɂ́A�n��̊��͂��ቺ�����鑽���R�n��𒆐S�ɁA�u�܂��Ȃ��U�����f�����Ɓv�u���K�͏W�����C���v�u�ӂ邳�Ǝ����v�搄�i���f�����Ɓv�u���R�ԁg�_�̍Đ��h���i��v�u�����R���Z�̐��i�v�u�n��Đ��������Ɓv�ȂǑ��l�ȃ��j���[�ʼn������Ă���B �܂��Ȃ��U�����f�����Ƃ̈��Ƃ��āA�����ɂ���Ė���@�\���ړ]���Ă��܂����ꏊ���A�n��̓��킢�Â���̏�Ƃ��Ċ��p���Ă���B�Ⴆ��NPO����Ɏ������Ƃ��ė��p���Ă��炤�A���X��U�v����Ȃǂł���B�܂��A�ӂ邳�Ǝ����v�搄�i���f�����ƂƂ������w�Z��P�ʂŋ��ꂽ�n��Ԃ̃l�b�g���[�N����邱�ƂŌ݂��ɘA�g�E�x�����������Ƃ�����B����ɒn��Đ��������ƂƂ́A�ߑa�n�ɂ�����n�抈��������`�������Ƃ����c�̂Ƃ̋����ɂ��A�擱�I�v���W�F�N�g�𐄐i���Ă���B (�S)�܂��Ȃ��̊������ɂ��� ���X�X�A�܂�܂��Ȃ��̉ߑa�n�т̊��������傫�ȉۑ�_�ł���B�����Ŏ��̂悤�ȏ��X�X�E���̊��͍Đ����Ƃ��s���Ă���B �P�ڂɁA���X�X�E�܂��̍Đ��̂��߂̃v��������������B�Ⴆ�R���T���^���g��h������A�����̋X�܂��W�߂����X�`����{�݉���A���ԏꐮ�����ւ̏���������B 2�ڂɁA�X�܂̊��p�̂��ߐV�K�o�X�̉����⏤�X�p���x���A�܂蒇��Ƃ��s���Ă���B�X�܂̊��p�ɂ��ẮA�������X�X���ɋ�������X�܂��J�Ƃ���Ɗ����X�܂����邽�߁A�𗬃Z���^�[�Ȃnj����{�݂��J�݂���ȂǍH�v���Ă���B 3�ڂ́A���X�X�̃R���p�N�g���B���X�X�̊e���X�̐l���������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�X�����ł���Ƃ�������������ōs���͍̂���ł��邱�Ƃ��������߁A�V���A�[�P�[�h�P���x�������s���Ă���B 4�ڂɁA���X�X�̖��̓A�b�v���s���Ă���B���X�X�͂��ꂩ��ĕ]������Ă���Ǝv���B�x�O�^�̑�^���X�͔̔������ł��̌�̃t�H���[�A�b�v�܂ōl�����Ă��Ȃ��ꍇ�������B����ɑ��܂��Ȃ��̏��X�͔̔���̃T�[�r�X���ォ����Ă��A�܂��Ȃ��ɏZ��ʎ�҂ł��鍂��҂ɂƂ��Ă͂܂��Ȃ��ɂ��̂悤�ȃT�[�r�X��ł��鏤�X�̕������p���₷���B�܂��b�����肪�ł���A�C���]���ɏo�čs���ꏊ���ł��邱�Ƃ��ł���̂͗ǂ����Ƃł���B�܂��Ȃ����X�ɑ���]���͂��ꂩ�獂�܂��Ă������낤�B
�M���V���̍����j�]���A���ɖ��ɂȂ��Ă���B���{�������j�]�ɑ��Ĕ��Ɋ뜜����Ă��邪�A���ۗL�҂Ƃ����ϓ_����M���V���Ɠ��{�͑S���\�����Ⴄ���߂�������ɐS�z����K�v�͂Ȃ��B�܂�A�M���V���͍������������w�����Ȃ����ߊO���ɗ��邵���Ȃ��A�j�]����\���������B������{�̍��ۂ̑唼�͎������������Ă��邽�߁A���������Ŗ����������B�܂�A�o�ύ\�����S���Ⴄ�̂Ɋ�@�������K�v�͂Ȃ��̂ł���B ���[�}���V���b�N�ȗ��A���ɂ̗L�����l�{��0.92����ň�0.4�ւƔ����������A���X�ɖ߂����B�����ĕ��Ɍ��͕���19�N�x�̌��������Y��7�ʁA�S���̐����i�o�z�̂T�����߂Ă�����̂Â��茧�ł���B���̎Y�Ƃ̓����Ƃ��āA�����Ƃ̊������S���Ɣ�r����1.15�ł���A���ɓd�C�E�@�B��A���p�@�B�Ȃǂ̉��H�g�ݗ��Č^�H�Ƃ𒆐S�Ƃ��Ă���B ���̕��Ɍ��̋��݂ł�����̂Â���Y�Ƃ̊������ɂ��ďq�ׂ�B �P�ڂɁA�H�ƋZ�p�Z���^�[�̐����ɂ���Ă��̂Â����Ƃ̋Z�p�͋�����i�߂Ă���B 2�ڂɁA���̂Â����w�Z�̐������\�肵�Ă���B��̓I�ɂ́A�����Y�Ƃ��x����l�ނ̈琬��ݐE�ҌP���A����ɏ��w���⒆�w���ɂ��̂Â���̂悳��m���Ă��炤���߂́A�{�i�I�Ȃ��̂Â���̌��̒��s���Ă���B�܂��A�Z�\�m�̗����ǂ̂悤�ɂ��č��̂��A�ǂ̂悤�ɂ��ė{������̂����ۑ�ł���B 3�ڂɁA������Ƃœ����ݐE�ҌP��������܂ł͎Г��Ō��C���ł��Ă����̂��A�s�i�C�Ō��C���ł��Ȃ���Ƃ��o�Ă������߁A���̏��^���鎖�Ƃ��s���Ă���B 4�ڂɁA�_�ƂƏ��Ƃ��A�g���x�����A�_�ѐ��Y���������p���������Ƃ̊��������s���Ă���B ���̂Â�����x����̂́A�Ȋw�Z�p�ł���B ��N�A���Ǝd�����Ŕ��ɒ��ڂ��ꂽ�Ȋw�Z�p���������A�u�Ȃ����E��̌����{�݂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v�Ǝ��₳��邱�Ƃ�����B�������A�t�Ɏ��́u�Ȃ���Ԉȉ��ł����Ǝv���̂ł����v�ƕ����Ԃ������B�Ȃ��Ȃ��ԁE�O�Ԏ�ł����Ǝv�����Ƃ���ɋ����ɕ����Ă��܂����߂ł���B���̂��߁A������X�[�p�[�R���s���[�^�[�{�݁A������w��[�v�Z�Ȋw�������A�_�ˑ�w�V�X�e�����w�����ȂȂǂւ̎x�����s���Ă���B����ɐ��d���ɐ��E�ő勉�̑�^���ˌ��{�݂����A�d���Ȋw�����s�s�ɍŐ�[�Ȋw�����������v������s���Ă���B �헪�I�Ȋ�ƗU�v��k�Е����ɍ��킹�čs���Ă����B���̌��ʁA��Ɨ��n�����͑S��1�ʂ��ێ��������Ă���B�����P�S�N�ɎY�ƏW�Ϗ����{�s���Ă��畽���Q�O�N�܂ł̂V�N�̊ԁA���n����562���A�������z1��3000���~�A�]�ƈ��Ґ�3���l�Ƃ����Ɛт��o���Ă���B��ȑ�K�͗��n����Ƃ��āA�v���Y�}�f�B�X�v���C�p�l���H��A�t���p�l���H��A�����ԗp�d�r�H��Ȃǂ���������B �@�@
��_�W�H��k�Ђ���15�N�����A���̂悤�Ȗ��_�������オ���Ă����B1�ڂɁA���킢���߂�Ȃ��n����������Ƃł���B�܂��̓��킢���̂��߂ɁA�Ⴆ�ΓS�l28�����܂��̃V���{���Ƃ��ėp�������������� �k�Ђ���̑����I���������A�k�Ђ̌o���Ƌ��P�̔��M�̂��߁u�l�Ɩh�Ж����Z���^�[�v��ݒu�����B���̃Z���^�[�͌o���Ƌ��P�̓W���A�h�Ђɑ��錤���̖����������Ă���B�{�Z���^�[�́A�����ݒu���ׂ����ƍl���A���ɐݒu�̗v�������A�����Ɨ��s���@�l�Ƃ��ׂ����Ǝv���̂����A���̍������Ȃ��Ƃ������ƂŁA���Őݒu����ɉ^�c����d�����ƂɂȂ����B ����ɁA�䕗���̕����Q�̋��P���������Ă���B����16�N�̑䕗��Q�͎R���K���ɊǗ�����Ă��Ȃ����߂ɂ��̔�Q���g�債���B���̋��P�Ƃ��Č����ΐł����Ă���B�����ΐłƂ́A�������ʂ̍��Y�ł���u�v�̕ۑS�E�Đ����Љ�S�̂Ŏx���A�������Q���Ŏ��g�ގd�g�݂Ƃ��ĕ����P�W�N�x�ɓ������Ă���B125���~��ςݗ��Ă�����x�[�X�ɁA�ً}�h�Зѐ����A���R�h�Зѐ����A�j�t���тƍL�t���т̍���ѐ����A�쐶�����琬�ѐ���������Ă���B ����21�N�䕗��9���ł́A���ő�̂Q�S���ԉJ�ʂR�Q�V�o���L�^���A�R�O�O�N�ɂP��Ƃ�����吅�Q�����B���̑�^�䕗�Ƃ��̍ЊQ�ɂ́A�z�������^���ɂ��쐅�A�R���̕����k������̓y���E���̗��o�A���ŋ��������ǂ��邱�Ƃŏ㉺����݂��j������Ȃǂ̓��F������ꂽ�B �����̏����āA���̂R�̑���s�����Ƃɂ����B�܂��R�̊Ǘ���O�ꂵ�ЊQ�ɋ����X�����s���B�����ĒJ�Ɏ��R�E���h�{�݂̎{�݂��s���B�������Ƃ̃o�����X�̎�ꂽ���㗬�̉͐���C������B�������đ䕗�̋��P���������Ă���B �܂��A�Z��Č����x�ɂ��Ă��A�V���ɉƍ���ΏۂƂ������x��lj����邱�ƂŊg�[���Ă���B���ꂪ�ƍ����ϋ��t���ł���B����͍^�������㑝���邱�Ƃ����z���Ă̐���ł���A�^���ʼnƂ��Z������ƁA�Ƃ����łȂ��ƍ����ꏏ�ɂ��߂ɂȂ邽�ߑn�݂��邱�ƂɂȂ����B
�R�A�C�݃W�I�p�[�N�̌v����i�s���ł���B�R�A�C�ݍ��������𒆐S�ɁA���͋��O��s�̌o�������琼�͒���s�̔��e�C�݂܂ł̃G���A�ɁA���{�C���a�����������̒n�`�E�n�����ώ@���邱�Ƃ��ł��邽�߁A�������W�I(�n��)�����ɂ��悤�Ƃ����v��ł���B���݂͐��E�W�I�p�[�N�l�b�g���[�N�ɔF��\�������A���n�R����8���ɓ���\��ł���B �܂��A�R�E�m�g���Ă�n��Â���ɂ��āB�R�E�m�g�����a��Ƃ���_�n�ɔ_�܂���A�G�T�ƂȂ钎�Ȃǂ����Ȃ��Ȃ������߁A���a�S�U�N�ɓ��{���̖쐶�R�E�m�g������ł��Ă��܂����B�����Ń��V�A����c�������������A�������N�ɏ��̐l�H�ɐB�ɐ������܂����B���ꂩ��Q�Q�N���o���A�����I�X�Ɩ쐶���X���珉�߂Đ����a�����A�쐶��DNA���������g�L���a�������B����͔��Ɋ�������Ƃł���B ���n�ł̓g�L�̐l�H�ɐB���s���Ă��邪�A�����s���̂��ߐ������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����������������̂ł͂Ȃ��A������̎��ӊ��Â�����d�v�ł���B�Ⴆ�A���Ӕ_�Ƃ���ɔ_����g��Ȃ��_�Ƃ��ł��Ȃ����˗����A�݂��ɋ��͂��Ă��炢�������ꂽ�R�E�m�g���̊��Â�������Ă���B����̓R�E�m�g���ɂƂ��Ă��������ł͂Ȃ��A�_����g��Ȃ��L�@�ĂƂ��Ďs��ŕ]������A�ȑO��荂�����i�ł��Ă邱�Ƃ��ł��Ă���B
�_���͂R����B �P�́A������n��匠�̒S����Ƃ��̎Y�����グ�邱�ƁB �Q�ڂ́A���ɂ�����L��s����W�J���邱�ƂŁA���S�̂̍L��s����S���ӔC��̂�����Ă������ƁB�܂�A���C��C��k�Ђ͊m���ɋN����Ɨ\������Ă��邪�A�{���őقȂ�͍̂���B �R�ڂɁA���ƒn���̓�d�s�����������邱�ƁB �L��A�����S�������̑Ώۂ́A�h�Ђ�A���ۑS�A��ÁA�Y�ƐU���Ȃǂ̍L�掖���B �܂��A�L��A�����ł�����A������̌����Ϗ����āA�����̈�̓I�ȊǗ��A���R��`����p�����`�̈�̓I�ȉ^�c�Ǘ��ȂǂɃt���Ɏg�������B ���B���ƈႤ�_�́A���B�����{�������̂悤�Ȍ`�ɂȂ�̂ɑ��A�{�����x���������邱�ƂƁA�L��A���͕{��������I�ɐݒu���邱�Ƃ��ł���_�ł���B �{�����Ȃ��Ȃ�Ƃǂ����낤���B���B�����̑����I�o��@�ւɂȂ�\��������A�n�������̗���ɂ͔�����B���ɑ��{�̋��{�m����WPC���āA���B���̖{���ɂӂ��킵���Ƃ����Ă��邪�A�{���E�������Ɍ��̒[�����̏܂Œm�邱�Ƃ��ł���̂��B����͎s���������̖�肩����w�E�ł���B
�����Ɋ֘A���āA���̂Ƃ���A����}�͌��ǂ̂Ƃ��뒆�g���Ȃ��B�Ƃ����̂́A��̓I�ɉ��������� ����ł̖��ɂ��Ă͔����Ēʂ�Ȃ����낤�B�܂��[���ȃf�t������������B���̌o�ϑ�Ƃ́A�����s�ɂ���Č������Ƃ����邱�Ƃɂ��i�C�������Ƃ������̂ŁA���̓��ł���B���̑����@�́A�K���ɘa�����Ď��R�ȋ�����i�߂邱�ƂŐV�������v�ݏo�����Ƃ����A������H�I�ł���i�����������Ă��܂��B�����č��A�����咣���Ă���o�ϑ�́A���A���̓��Ƃ͈Ⴄ�A��O�̓���ڎw���Ă���B�܂�A�f�t���M���b�v�����܂�Ȃ��̂́A����҂��������g��Ȃ����߂ł���A�ŋ����グ�邱�ƂŐŎ����グ�āA����𐬒��Y�Ƃ֓������邱�ƂŌi�C��ڎw�����Ƃ������̂ł���B���ꂪ��O�̓��ł���B�������K�Ȏx�o���ł��邩�����ł���B
|
|||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. ���̃y�[�W�Ɋւ��邨�₢���킹�́A�����ّ�w�@���ʋ��琄�i�@�\�i�����ǁF���ʋ���ہj�@�܂� TEL(075)465-8472 |