 |
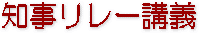  |
|
| 2010年 7月 6日 秋田県 佐竹 敬久 知事 |
||
「 21世紀前半 〜時代認識〜 」
今回は、佐竹秋田県知事より、海外の情勢、地方分権の考え方、秋田県の特徴等について講演をいただいた。佐竹知事は、秋田市長を以前務められ、市政、県政両方の分野の経験を持つ人である。
この講義を引き受けようとした時、よく考えると私は知事になって1年ちょっとで、他の知事がどのような話をしているか分からず、何を話そうか迷った。 東北からすると京都は遠い感じがする。私の生まれは角館で、殿様の末裔の家系である。昔からの源氏の流れで、元々は滋賀の大津あたりにいた。そういうこともあって、京都とは精神的なつながりを持っている。角館は秋田を代表する観光地で、京都の名残が見られる。
今いろいろな政治家がいるが、最初に話したいのは、今さかんに選挙をやっているが、日本人は最近、モノをよく考えなくなり、短絡的になったということである。その中でも一番変なことを叫ぶのが政治家である。 「国民の為の政治」を言うが、当たり前のことで、「国民の為にならない政治」というスローガンを掲げる政治家はいない。また、「国民目線」、「市民のために」、「郷土のために」と言うが、その逆を考えたときには標語にならない。そのような標語を叫ぶということは、非常に思考が劣化しているということである。それを受け入れる国民も劣化しているのだと思う。昨年知事選挙に出るときに、「そのような標語はあるか」ということを言った。そうすると、相手はそのような標語を喋れなくなる。「秋田県民の為にならない政治」という標語はないのである。 最近の選挙を見ていると、消費税等いろいろな問題が出てくるが、どうも中身をきちんと分析していないし、しっかりと計算されたマニフェストではなく、相手を見ながらマニフェストを作るために、破綻してしまう。アメリカの大統領のマニフェストは非常に膨大になる。本来、簡単に説明する政治は嘘がある。中身がないため簡単にしてしまうのである。分かりやすい政治でごまかすのが日本の政治の最近の流れで、しつこいくらい分析したり、様々な論理構成を持ったり、シミュレーションをやったりする癖を日本が持ち直すべきでないかいというのが最近の感覚である。
私は、東アジアを中心に年に6〜7回くらい海外に行っており、日本全国で最も海外に頻繁に行く知事だと思う。秋田は日本海側に位置しており、これからは東アジアとの交流が一番大切になってくる。私はある程度しつこくものを聞くので、細切れだが最新の情報を持っている。 ここ10年ほどずっと海外へ行って日本の状況を見ていると、いくつか感じることがある。 一つは、日本の学生は勉強しなくなっているということである。今日の午前中にトヨタ自動車の系列会社の社長で、ハーバード大学の経営学修士号を持っている方と話をしたが、当時それからしばらくは、アメリカの大学にも結構日本人が勉強していたそうである。しかし、最近はほとんど日本人がいなく、中国人が多くなっている。日本人が行きたがっていないわけではなく、日本人は合格しないと聞いている。 二つ目は、学生だけではなく、大人も勉強しなくなっているということである。感覚的になっていて、目からだけ情報を入れているので、自分で文字を調べない、文字を書かない、自分で計算をしないようになっている。 こういうことからすると、かなり日本人の勉学能力が下がっていると感じる。他律的思考と言うが、自分でものを考えなくなっており、しつこいくらいものを考える習慣がなくなっているように思う。
(過度の行政依存) 過度の行政依存ということがある。成人式のときに、新成人が行政に対して望むことについてのアンケートをすると、ふざけた話だが、成人式のお祝いに100万円欲しいという回答があった。冗談だろうが、行政に対する発想が、行政から与えられるのが国民・県民・市民だという発想になっており、自律性がなくなっているという感が否めない。 (少子高齢社会) 今の日本は少子高齢社会で、これからの活力という面では、少なくとも人間力は減ってくることになる。それをカバーするためには、日本人全体の人口が減っているため、労働力は減るが、一定の生産性を確保しないと日本は食べていけなくなる。 それには一つしかなく、一人一人の能力を高めないといけない。単純な計算で、皆さんは同じ一人でも、我々の時代の1.5倍くらい能力的にアップしないと、日本の活力は維持していけない。しかし、社会のシステムがそうなっているかというと、そうなっていないのが現状ではないかと思う。これからは人的能力を高めるのが日本では一番大切ではないかと思う。 (周辺新興国の台頭) 我々の年代くらいだと、相変わらず日本は社会的、産業技術的、社会システム的にも非常に進んでいるという錯覚に陥っている。 しかし、最近の状況を見ると、日本はかなり遅れてきているのは確かである。人的能力の遅れや劣化、新しいものを社会に取り入れ使いこなすアプローチが非常に弱いことは憂慮すべきことではないかと思う。 先端技術分野で日本がトップを維持しているのはほんのわずかになっているのは確かである。昨日も今朝も名古屋地区の大企業の幹部との意見交換をしたが、大企業の幹部の皆さんも同じように、日本の産業技術に対する将来への不安がかなり高くなっていることは確かである。 一例は、日本が明治以来進んできて、さまざまな社会システムを取り入れてきたため、一定の形が今の日本の社会には整っている。この中に、さらにいろいろなものを入れ込むのは非常に難しいのである。 中国や韓国等、台頭している新興国は、そのような社会システムができあがっていないため、一気に新しいものに突入できる。簡単な例としては、アフリカでは携帯電話しかないということが挙げられる。アフリカでは有線電話の線を通すよりは鉄塔を建てて携帯にしたほうが早く、アラスカやロシアの奥地でも携帯は通じるが、固定電話はないのである。 そのような所では、新しいものを瞬間的に取り入れ、それを社会システムにしてしまう。 かつての社会システムであればまだ良かったが、最近の社会システムはすべて情報インフラとかかわりがある。産業経済でも、民生部門、行政部門にしても、行政サービス、市民サービスにしても、これからは情報インフラが一番大きく左右するが、その一番大切なところで遅れているのが大きな問題ではないかと思う。 かつて、新しい金属を採用するのが少しくらい遅れても、ある部分だけなので、取り返しがついたが、情報インフラは社会の根っこ的なところなので、その産業革命的なところで遅れると、その後取り戻すのはなかなか大変である。 日本の今まで積み重ねてきたさまざまなシステムがそれを排除している。または、入りたくてもさまざまな規制があって入れないということもある。 一昨年上海に行ったが、上海ではエリア単位で制度が違うのである。医療システムを見てきたが、上海は上から指示をするとただちにやることができる国であった。日本にはそっくり当てはまらないが、話していると、「日本の轍を踏まない」と言っており、日本を反面教師にしていた。もし中国で日本と同じようにうまくいかなかった場合、13億の人口がいるため、日本以上に大変なことになる。中国で医療精度が向上してくると、日本と同じやり方では絶対間に合わないと言っていた。医療の中身を維持し医療に専念するために、まわりの事務処理を徹底的に省力化していた。例えばペーパーレス化があるが、今の日本でも処方箋のペーパーレス化はすぐにできるのである。もう一つは、すべてのエリアの病院で共通のICチップ付きカードを導入し、血液型、既往症から過去の検査データまですべてを蓄積させていた。それは他の病院でも読み取ることができる。頻繁に調べなくてはいけない検査データと、一年に一回調べれば良いような検査データがあるが、日本では病院を変われば初めから再検査するが、ここでコストが全然違ってくる。データを蓄積させることでコストが一気に下がるのである。 日本でもこのことは分かっているが、できていない。それには、医療法の問題やしがらみの問題がある。このようなところをシステム化することで、産業の形態が変わる。単純な話をすると、処方箋の紙がいらなくなるため、それを納めている人は大変になる。また、年をとると、いろいろな検査をするが、血圧などは家庭で簡単に計れる。それを医者にデータで送れる。そのデータをかかりつけ医にチェックしてもらえば、無駄に病院に行かなくて済む。年をとって既往症が生じると、良くても悪くても病院に行かなくてはならず、それだけで医療費がかさむことになる。
良いか悪いかは国民的な判断だが、政治の世界で今の行政改革、財政問題を叫んでいるが、本質的なサービスを低下させずに、社会の間接コストを下げて財政の健全化を図るという発想をする政治家がほとんどいないことに驚いている。これが日本の今の硬直した行政・政治システムにあるのは確かである。 私はこのような観点からの地方分権、地域主権ということをいつも言っている。近接性の論理、補完性の原理という難しいことはよく、さまざまな形での技術の進歩、社会の進歩、国際的な交流の拡大を、政治行政システムに日本もそろそろきっちりと取り入れないと大変な遅れを生じることになる。 そのような中で、何を目指すべきだろうか。日本人はやはり変化への挑戦はなかなか苦手である。頭の中で、「政治を変えよう」と言うが、本当に変えて欲しいのかと思う。日本人はやはり変わることへの恐怖感が大きいのではないかと思う。問題は、われわれの世代は変われない。私くらい歳をとると変わるのは無理である。しかし、皆さんの世代は変わることができる。若い世代への希望は、能力を高めること、また、変わること、変えることに恐怖を持たないということである。ほとんど変わらない生活をしているため、意外と皆さんも変わることへの恐怖があると思う。 戦乱に明け暮れるところで、毎日命や食べ物の心配をしてという世界に住んでいる人は、変わることへの恐怖はないが、今皆さんは豊かな生活をしているため、潜在的に恐怖感があるのは確かである。それをどう克服するかが大学生活ではないかと思う。 そのためには、歴史的な経緯や伝統を守るべきものもあるが、最も新しいものに近づく、ふれてみる、接触してみる、経験してみることが大事だと思う。そうすると、新しい社会システムなり社会の変化に対して希望を持つようになる。新しいものに触れて希望を持ち、なんとか活用しようと思うことが大切である。皆さんの世代は、単位をとるための勉強だけでなく、いろんなことにチャレンジしてほしいと思う。 そのような中では、特に海外との関係が大切で、海外に目をむけてほしい。日本人は海外に行くと小さくなってきている。若いみなさんが海外の人と付き合ったり、アルバイト代で海外へ行ったりして、外を覚えることが大切だと思う。これからの日本は、かなり海外志向でないと希望をふくらませることはできないと思っている。
坂本龍馬が今流行っているが、私は秋田で、カネのあるところとヒトのいる場所でしか商売ができなくなってきているということを言っている。ものづくりやものを売るという商売を目指すときに、この場所へのアプローチが一番大切だと言っている。 ふるさとに根っこをおきながらも、カネがあるところにアプローチすることが大事で、私も海外に売り込みに行っている。見回すと、量が出るか出ないかは別にして、新しい市場を開拓することは、次にやる人への希 秋田の人口は一番多かったときに135万人いたが、今は110万人。さまざまな産業政策はあるが、地元の秋田で、秋田のこれからを担う人達に、「銭のあるところとヒトのいるところにまず入れ」と言っている。実際にアプローチをしてみると、新しいことを覚える。そうするとまた挑戦して、どんどん拡大していく。外へ行って現場を見ないと分からないことがたくさんある。 具体的には、小さい話だが、香港のキャセイ航空の関係の旅行会社で、日本への観光客送り込みに非常に熱心な会社があり、その社長と話をした。私たちは秋田の売り込みをした。秋田には二つ空港があるが、それほど飛行機が飛んでいないため、空き時間はいくらでもチャーター機を受けることができる。 社長に「飛行場の近くの道路は混んでいるか、空いているか」と聞かれたので、「ほとんど混んでいない」と応えたら、それは良かったと言われた。田舎の空港でできるだけ周辺に車が走っていないところを探していると言われた。一体何を狙っているのだろうかと思ったが、行ってみて直接やりとりして分かったことがある。香港は右ハンドルで、車の7割くらいがトヨタの車である。香港は東京以上に道路が混雑していて、坂道だらけで、免許を取ってすぐ運転すると確実に事故を招くと言われている。そこで、日本にチャーター便を飛ばし、日本のレンタカーを借りて、田舎のほとんど車のないところで走らせるということを考えた。これが観光だと言う。そのように、ビジネスのチャンスはたくさんある。 この点でいくと、秋田は最高の観光地である。県の北部の大館能代空港は、まわりの道路は良いが、車がほとんど走らない道路がたくさんある。これが商売のネタになるということを日本人は考えたことがなかった。 もう一つあり、秋田ではリンゴがとれるが、量はあまりないため質で勝負している。そうすると、リンゴの木のオーナー制度を考えていると言われた。香港には一軒家に住んでいる人はほとんどいない。土地がないため、普通以上の人は高層住宅で、一軒家に住んでいるのは、島に住んでいる貧乏な人くらいであるため、庭の概念がないのである。そこで、ただ一本の木に憧れるようである。リンゴの木に名札をつけて、次の年から一族郎党で写真を取りに来るようになった。これらはごく最近の私の経験した例である。 日本は海に囲まれているが、中国でビザ緩和が始まったこともあり、そろそろ外貨の稼ぎ方を変える時期でないかと思っている。しかし、それになかなか国がこれについて来られないのが現状。国の硬直した例は、管理監督する人が現場を見ていないことに尽きると思う。例えば、香港に官公庁の出先機関があるが、再開発の立派なビルに入っている。そこには観光コーナーがあり、日本全国の観光地のさまざまな資料が置いてある。日本に旅したい人はそこで資料をもらえば良いわけだが、そのビルは警備が厳しくて一般人は立ち入り禁止となっている。そこに誰が行くだろうか。地元の人が行けないようなところに事務所があるのである。これが都道府県だとすると、大変なことになる。そういうものをつくると、県議会議員が視察に来て、変な場所に作っていると、議会で吊し上げにあってしまう。明らかに海外戦略では国が遅れている。 これからの日本の地方分権の視点はさまざまあるが、日本の外貨の稼ぎ方や観光行政はまさに地方分権でやらないと、とても国で一本化してやろうとしても無理だと思う。時代の必然に対して、どう政治が手を打つかが今求められている。 もう一つは、地域を担っていくときに、必ず波があるということである。いろいろな波があるが、悪いと思っていたことが突然良くなったり、良いと思っていたことが突然悪くなったりする。世の中はうまいもので、非常に波がある。 今、環境の時代と言われるが、まさにその通りで、秋田は以前鉱山県で銅・鉛・亜鉛を1000年以上前から鉱山で産出していた。太平洋戦争のちょっと後までは石油もとれた。他にも、コメ、木材もとれる。戦後、国際化の波の中で鉱物資源が枯渇をしてきたこともあり、コストが高いということで、閉山になってしまった。秋田にはかつて栄えた鉱山の跡がたくさんある。そういうところのまちは、現在ではほとんど衰退した過疎に悩まされている。これからは日本の国はリサイクルでもたないといけない。例えば、携帯電話一台から相当の有用金属がリサイクルできる。これを取り出すのは昔の鉱山の精錬技術で、かつて栄えて衰退して一回消えた鉱山が、日本中の家電製品からさまざまな形で資源回収をする基地に変わりつつある。 また、水は最大の資源である。秋田の水は川の水を飲んでもほぼ大丈夫で、枯渇することもない。水はありとあらゆる源である。 もう一つは、アメリカ一辺倒から東アジアの時代になっているということである。アメリカと東アジアは近いか遠いかの違いである。アメリカと比べると東京の方が近いが、ロシア・中国が栄えてくると、日本海側はそちらの方が行き来しやすいのである。 秋田とウラジオストックは非常に近く、一昼夜で船で行くことができる。秋田の港は戦後駄目になったが、ロシアや中国の台頭に伴って、北米航路の貨物に日本から荷物を積み込むとする時に、秋田で東日本の物資を積むようにもなった。これは世の中の流れで、今までは流れにのっていればよかったが、今は流れに乗りながらその流れを強くするのが政策である。 それは国も地方も同じで、波があるときに、早めに波を持ってきたり、振幅を大きくしたりするという政策展開が必要である。今やっと国でもハブ空港の問題や港湾の重点化の議論がされるようになったが、地域の単なる引っ張り合いではなく、全体として調和されながら、どうやって日本の国内に利益を生じさせるかという政治のリーダーシップが必要である。これも遠くにいては分からず、地元にいて初めて分かるのである。 面白いのは、中国やロシアでは経済は地方分権となっていることである。今の発展途上国は国策で大きな経済政策をしているが、個別事案は非常に地方分権的で、秋田県と中国のある省との間で協定を結ぶということができるようになってきた。国と国との協定では包括的な利益を考えないといけないため、いつになるか分からないし、現場には役にたたないのである。 中国では、州や特例市で経済のかなり細かいところまで決められるが、日本はそれができず、あちらのほうが分権社会になっていて、こっちはそうなっていないというのが現状である。非常にジレンマを感じている。 経済活性化のための分権ということを今一番強く訴えたほうが国民に分かりやすいのではないだろうか。地域主権や地方分権と言っても、役所だけの話で、予算や権限が国・地方のどちらにあっても国民にとっては変わらない。市道だろうが国道だろうが、きちっとしていれば構わない。 最近の地方分権の議論は国民に分かりにくいと思う。私は地方分権の論理はこれからの経済の活性化と非常に密接な関係があると言って理解を求めている。いつも地方分権と経済活性化を一緒に話をすることにしている。
秋田に最近、国際教養大学というユニークな大学ができた。海外展開を睨んだ大学で、全寮制となっており、必ず海外留学を義務付け、すべての言語は英語となっている。 授業も日常会話も校内のインフォメーションも全部英語となっている。卒業率が40%だが、就職率は100%となっている。日本の公立大学としての初めての取り組みだが、常に80カ国くらいの留学生と一緒の生活をさせるため、言葉も自然に身に付く。偏差値もほぼ東大と同じになった。 最初の卒業生がどうなるのか心配したが、今企業が求める人材と非常に合致していると思う。卒業生は、英語はきちっとできて、国際経済を一通り学んでいるため、次の日からアメリカに出張させても大丈夫という状態になっている。
皆さんは学部の単位をきちっととって、それ以外の勉強もしないといけない。学生の本分は勉強で、今まで以上に学力を高めてもらわないといけない。国際化ということについてはありとあらゆる業種・職種がすべて関連してくる。 日本が東アジアでマイナスになっているのは、結局は言語の問題で、絶対的に日本が劣るのは語学である。なんとか日本人が日本語の他に、若干カタコトでも他の言語も学んで欲しい。現場に行っていてそう思う。社会人になって英語教室に通おうとしてもなかなかできないので、今のうちが大切である。いろいろな学問があるが、語学を少し強くしていただくことが、相当これからの日本の社会の役に立つと思う。 東アジアが上がってきた中で、今後競争していかないといけない。競争力を強くすることは、まずは個人の人的能力を高めることである。 あまり政治に期待しないことが必要である。政治は経済の成長をもたらさない。できれば黙っていてほしいと思っている。経済と政治を密接に結びつけるのは間違いで、自由度を高めるほうが良いと思う。自由度を高めることには格差の問題があるが、あまり格差是正ばかりを言うと、成長はあり得ない。 もう一つは、海外をできるだけ経験する、あるいは、何らかの言葉を少しでも覚えて頂くなかで、将来への希望を増進させられるのではないかと思う。 皆さんに期待するのは、インターナショナルなたくましさである。確立した個人としての能力とチャレンジ精神、そして政治行政への依存度をできるだけ下げて、自分の道を切り開いていくという姿勢を持ってもらいたい。
(自殺率) 秋田は自殺率が非常に高い。高齢化率が高くなるとガンが増えるため、高齢化とのつながりもあると思う。 (婚姻率) 秋田は婚姻率が非常に低い。婚姻率は所得とあまり関係ないと言われている。結婚は強制ではないが、結婚しないと、老後誰にも養ってもらえないという時代はやってくる。カネはあっても人がいないから養ってもらえないという時代にまもなくなるのは確かで、生殖能力のあるうちに自分のために結婚するということが一つの考え方ではないかと思う。そういうことで、秋田では県で婚活事業をやっている。 (学力) 秋田は子どもの学力が日本一である。小中学校の全国学力調査の結果が3年間連続トップとなっている。教育には非常に力を入れており、昔からの少人数教育が非常に功を奏したのだと思う。秋田は教育に力を入れている他にも、子どもの体力も日本一である。小学校の運動場の面積が日本一ということもあると思う。
機会があればふらっと秋田に遊びに来てほしい。立命館で学んで、社会人になったときに、日本や社会を一定の希望ある方向に導いていただくことが、皆さん方の責務で、皆さん方しかできないということを認識して、楽しい学生生活を送ってほしい。
問 少子高齢化について、一人一人の能力を高めるべきとのことだったが、高齢者の社会参画を進めていくべきではないのか。 答 元気な高齢者に社会の役割を担ってもらわないといけないのは当然である。しかし、過度に子どもが少なくなるということは、全体として社会の活力は失われることになる。現実問題として、高齢者が50〜60%を超えると、全体としての活力は失われる。 問 小・中学生の学力が高いという話だったが、どのようにして維持しているのか。 答 比較的早い時期から小学校の少人数教育をしていた。教える密度が濃くなっているのは確かである。秋田では地域活動と小中学生の結びつきが強く、地域の人たちが子ども達を健やかに見守っている。また、朝ご飯摂取率が非常に高いということもある。「早寝早起き朝ご飯」とよく言うが、規則正しい生活というのが一つある。生活習慣が非常に規則正しいというのが全体の流れでできている。 |
||||||||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |