 |
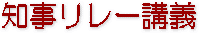  |
|
| 2010年 7月 13日 佐賀県 古川 康 知事 |
||
「 口蹄疫。その瞬間(とき)、何ができるのか。 〜守りぬけ!佐賀牛〜 」
7月11日に参議院選があったが、今回の選挙でおもしろいと感じた点がマニフェストである。マニフェストという言葉は、前回の衆議院選挙で非常に輝きを持って登場したが、初めて使用したのは私の2003年の佐賀県知事選挙の時であり、その後もマニフェストという言葉を広めていく運動をしていた。そして前回の衆議院選では、民主党はマニフェストに子ども手当てや、高校の授業料の無料化など色んな政策を掲げて政権をとったが、現在になってその政策実現が難しいことがわかっ 私は全国知事会で各党のマニフェストを評価する仕事の責任者をしている。そこでは色んな党のマニフェストの読み込みや、政策決定責任者との意見交換をしている。そこで面白かった話が、前回の衆議院選では自民党は「政権公約」という言葉を使っていたが、前回の衆議院選で多くの人が「選挙といえばマニフェストだ」と思うほどに認識が広がり、グーグル検索でマニフェストと検索した時に自分たちの党が上位に表示されないのは困る、ということで今回から政権公約ではなくマニフェストにした、ということである。 一方、今回議席数を急激に伸ばしたみんなの党は、マニフェストという言葉を使っていない。というのは、できもしないことを並べて選挙のために使うもの、というイメージが民主党によって広められたためである。そこでみんなの党では、マニフェストではなくアジェンダという言葉を使うようにしている。 この参議院選や、大相撲界の事件と同時期に起こっていた問題が、口蹄疫問題である。今回はこの口蹄疫対策について話をする。口蹄疫は佐賀県では起こっていないが、宮崎県から180kmほどしか離れていない。ここ、京都に置き換えて考えると、兵庫で悪性の動物伝染病が流行っているようなものだと捉えてもらえればいい。今回は地方自治体の最前線ではこの問題に対しどのようなことを考え、どのようなことを実行し、どんなことに悩まされているのか、についてみなさんにお話したい。
口蹄疫とは、牛・豚・ヤギ等に感染する病気である。よく相談センターに「犬猫は大丈夫か」という質問が入るが、口蹄疫は蹄のある動物にしかかからないため、犬猫に感染はしない。ただし、これまでの口蹄疫との違いは、豚に感染しているかどうかである。豚にかかるということは、猪など豚に良く似た動物にもかかるということ。猪は豚と大変近い動物で、野生の猪のほとんどに豚の遺伝子が入っているともいわれる。何が問題かというと、野生の猪の状態・状況把握ができず、猪が感染した場合は、家畜に感染しないよう対策を打つことが非常に困難だということである。 口蹄疫にかかるとどうなるのか。突如40〜41度の発熱をし、元気がなくなり、よだれがでる。そして蹄や口に水疱ができ、食欲不振、足を引きずるなどの症状が出てくる。乳用牛の場合は乳量が減る。潜伏期間は2〜14日で、伝播様式は小さな動物や車によって運ばれることがあるし、伝播した動物に触れたり、感染した動物が排出したもの(唾液・糞尿)が人やものに付着したり、空気中に飛散することで伝播する。これは鳥インフルエンザや新型インフルエンザとも似ている。 ただウイルス自体は酸・アルカリに弱く、酢だけで死滅することはできるとそれほど強いウイルスではないが、非常に伝播力があることが問題点である。また感染した牛や豚の肉、牛乳が市場に出回ることはない。口蹄疫に感染した家畜を食べても人間には影響がないが、家畜伝染予防法で市場に出してはいけないと規制されている。それは、市場に出す過程で他の動物に感染するからである。 ところで「27>15」という数字の意味がおわかりだろうか。これは、宮崎県で殺処分・埋却してきた家畜数27万頭と、一方佐賀県で飼養している家畜数15万頭ということであり、宮崎県並の感染が佐賀県で起きれば、佐賀県にいる全ての家畜を殺さないといけなくなる、ということである。 なぜ宮崎で口蹄疫が始まり、拡大したのかははっきりとは分からない。 ただ言えることは、最初に発見した、感染した家畜を早急に殺処分しなければならないということ。口蹄疫に感性しているかどうかを早急に判明しなければならないということ。口蹄疫は非常に感染が早く、まわりの人間が口蹄疫を持ち運んでしまう可能性もあるため、その人達を移動してはいけない。そのため、感染しているかどうかを出来るだけ早く判断し、感染している家畜を発見し、発見したらいち早く殺処分する。初動が大事だということが、宮崎での発症件数の急激な増加からもわかる。
口蹄疫対策に関して、畜産農家から次のような声が入ってきた。「防がないといけないことは分かるが、口蹄疫の症状を見たことないから口蹄疫かどうか分からない。また口蹄疫だと分かってもどうしたらいいか分からないため、マニュアルを作ってほしい。」 そこで我々は、異変に気づいたら家畜保健センターに連絡をするよう畜産農家の人に言ったが、彼らは家畜保健センターには電話しないと言った。なぜかというと、畜産農家にとっては、かかりつけの獣医にまず見てもらった上で、口蹄疫かどうかを判断してほしいという気持ちがあること。また家畜保健センターの仕事は規制行政・警察行政 また「マニュアルを作ってほしい」という要望に対し、『行動の手引き』を作成・配布した。この手引きの中には、口蹄疫の症状について、また口蹄疫の疑いがある際にとるべき行動をチェックシートに沿って確実に行ってもらうように工夫している。 厳しく言っていることは、診療した獣医を含め、農場にいる人はその農場から動かないように注意していることである。つまり感染の疑いがある家畜を診療した後で、また別の農場へ診療に行くと、そこで感染が広がるおそれがあるからである。 また、作業中の人にも一斉に・正確に・後に残る形で口蹄疫の情報を伝えるために、佐賀県の防災・安全・安心情報配信システム「防災ネットあんしん」によって携帯電話宛にメールで情報発信をしている。そのため畜産農家の人にはその防災あんしんに登録してもらうようにしている。
初動の必要性については、当事者である宮崎県東国原知事も迅速な初動防疫、蔓延防止対策に全力をあげていると述べているし、また山田農林水産大臣も記者会見の中で迅速な殺処分の必要性や、政府は迅速な拡大防止の必要性について述べていることも分かる。 ただし、初動の必要性は分かっても、現行制度では口蹄疫の疑いがある家畜が発見されてから殺処分までに20.0時間もかかる。 どういうプロセスを経るのかというと、口蹄疫の疑いがあると判断してから動物衛生研究所で検査されるまでに10.5時間、さらにPCR検査で陽性確認ができるまでに16.5時間、そして口蹄疫発生の告示がされるのが19時間後で、最終的に殺処分できるのは20時間後である。 それに対し、佐賀県ではこれにかかる時間は3.5時間でいいと主張している。つまり、県独自で口蹄疫に感染しているかどうかの判断をし、動物衛生研究所でされる検査時間を省くことで時間短縮ができるのである。そして口蹄疫の拡大を防ぐことができる。 ちなみに、現行制度ではどのように規定されているのか。家畜伝染予防法13条には、口蹄疫の疑いを発見した際には、都道府県知事にその旨を届けなければならない、と書かれている。 ここに「遅滞なく」という規定があるが、法律で急がなければならない際の表現に、「直ちに」、「速やかに」、「遅延無く」で、一番急がないといけないのは「直ちに」であり、「遅延無く」は忘れない程度にと緊急性があまりなく、早急な対応が求められている現状に合致していない。 なぜこのような表現がされているのかというと、農水省からは昭和20年代の法律だからという答えだった。さらに同条4項に、都道府県知事はその旨を告示すると共に、死体の所在地を管轄する市町村長および隣接市町村長に報告しなければならないと規定されている。 また、第15条には蔓延を防止するために72時間を超えない範囲内において期間を定め、感染した家畜の所在の場所とそのほかの場所との通行を制限し、遮断することができるとも規定している。そのため学校に行かなければならない子どもは学校に行ってはならない。ただどうしても届けなければならない郵便物や買い物も必要になるため、その際は防護服を着るなど万全の態勢をとっている。 そこで、口蹄疫だと分かるものは、県で処分をスタートさせてほしいと、農水省に申し上げた。現行制度が無理であれば条例を作ってでも対応しなければならない。もちろん話はすんなり通ったわけではなく、2・3日やり取りを続けることになった。結果、化学検査ではなく臨床検査だけで処分の判断ができるようになった。つまり、条例をたてず現状の法律のままでできるようになった。 もちろん「口蹄疫でなかったらどうするのか」という質問をよく聞かれるが、私が恐れているのは「口蹄疫ではない畜産物を殺処分してしまう」ことより、「口蹄疫だと分かっているのに国から許可が出るまで、何もできないまま感染が広がってしまう」ことである。 そして佐賀県での畜産農家に関する問題に責任を持っているのは、農水省ではなく知事である私である。責任を持っている人間が判断することは当たり前である。そして今回の家畜伝染予防法をめぐるやり取りで、その当たり前のことが農水省から認められたわけである。 地方分権という言葉をみなさんはこの講義でよく聞くだろう。私は、地方分権とは権限や財源ではなく、実際に地方で仕事をする我々地方に「責任」を与えることだと考えている。「責任」を持つことが、地方分権のポイントである。 そして、農水省と佐賀県とのやり取りを経て、口蹄疫防疫措置実施マニュアルを農水省が発行した。このマニュアルの特徴は、異常な病変部位をデジカメで鮮明に撮影すること、また病歴等の医学情報を畜産課と動物衛生課へ電子メールで直ちに送付すること、など以前の農水省の対応からは考えられないものが盛り込まれることになった。
他にもいろんな問題が残っている。まず殺処分された家畜が多く、埋却する場所が見つからない。法律では家畜所有者が自分たちで穴を掘って埋めなければならない、とされているが、非常に数も多いためそのための土地を探さなければならない。また川や水脈を汚染する恐れなどへの考慮、近隣住民との調整等などもしなければならないが、それが非常に難しい。 宮崎県では埋却用の土地の確保ができないという問題があり、それを受け佐賀県では畜産農家に今のうちから埋却用の場所を用意しておくように言っている。 また、テレビで埋却処分の様子を写した映像が流れることがあるが、現場はテレビで報道されるようなきれいなものではない。現場の様子をそのまま流すことはあまりにも残虐すぎるため放送されていない。そんな中で、自治体職員や畜産農家の人、さらに死体を運ぶために依頼される建設業者が何とかこの事態を終わらせるために努力され 作業した人や近隣を走る車に対して入念な消毒をしなければならない。消毒も簡単にできると考えられているが、畜産関係車両は肥料やわらや家畜を運ぶものであり、こういう車両は10〜20トンと非常に大きいため、それらの車両は消毒のために道路の脇に寄せる必要があり、そのための消毒ポイントを設置する必要がある。また消毒ポイントを探す際にも、消毒液が近くの田んぼに雨で流れ込み悪影響が出ないかなどの心配をされるため、周辺住民や農家との調整が必要である。 住民間の調整の必要性では、こんな経験もある。県民に社会資本整備の中で何を最も整備してほしいかというアンケートをしたところ、街路灯・防犯灯がもっとも多く、市町村と一緒に設置にとりかかることになった。 だが、そこで問題点が2つ上がった。まず、街路灯・防犯灯設置をどの部・課が担当するのかが分からなかったことである。街路を照らすのだから道路課と思えば、街灯は道路を照らすものだけではなく公園内に設置されるものもあり、それは公園課も担当することになる。つまり、責任体系がはっきりとしていなかった。2つ目に、消毒ポイントの話と同じく、道路に街灯をつけるとそこだけ夜中も明るくなり、農家の人からは近くの田んぼの稲の生育状態が変わることで困ると言われた。これに対しては、点灯時間を短縮する、問題があり言いにきてもらえれば対応する、ということで役所の人が対応している。
質 現行制度では、家畜が口蹄疫にかかったと疑いが出てからセンターに送らなければならないが、検査用のキットが各県にあれば時間短縮なるのではないか。 答 我々も全く同じことを農水省に質問した。そこでの農水省の返事は、「開発されていない」ということと、「県に信用ができない」ということだった。「人がかかる新型インフルエンザではそれができるのに、家畜がかかる口蹄疫はそれができないのはおかしくないのか。」と質問したところ、その場での返事はなかったが、最近になって各県にキットを持つことで、各県で対応できるようにすると表明した。おそらく他の県も我々と同じ事を言ったのだろう。 現在ある制度はじーっとしていても何も変わらないが、おかしいのではないか、こうしたらいいのではないかと思い行動したら、変わることはいっぱいある。 質 「地域主権とは責任を取ることだ」とおっしゃられたが、大きなプロジェクトにかかる責任に対し、知事の政権が変わるときにどんな引継ぎが行われるのか。 答 責任を取るというのは色んな意味があるが、今の佐賀県民だけではなく将来の佐賀県民に対してもとらなければならないが、任期が終わり別の知事さんになると、それは責任の取りようがない。 それは民主主義だから仕方ない。地方自治は任期が4年で、一般的には8年、多い人では12年と任期中の仕事を全うしている。 一方国はどうだろうか、首相がおよそ毎年変わっている。基本的に過去の責任者の仕事は次の責任者に引き継がれるが、過去に行った判断に対して自分はそう思わないということもある。例えば自立支援法について、前政権では一定の負担を障害者の方にもしてもらい、その代わり給付に必要な経費は国が全額補助するとしていた。しかし、この法律を立案した政権は選挙で負け、新しい政権ではこの法律をなくそうとしている。しかし、またしてもこの法案を廃案にしようという政権の議席数が参議院選で減った。政策は長いスパンで考えなければならない。 つまり責任者は、物事の判断を次の選挙に有利かどうかで判断せず、今と将来について責任を取ることができるか、と考えて判断しなければならない。 |
|||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |