 |
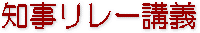  |
|
| 2010年 7月 20日 神奈川県 松沢 成文 知事 |
||
「 神奈川から日本を変える 」
前回の衆議院選から多くの政党からマニフェストが発表され、その中で民主党が選ばれたが、民主党のマニフェストの政策の多くは必ずしも実現されなかった。民主党ではマニフェストが選挙に勝つための道具として扱われ、国民が喜びそうな政策ばかりを羅列し、政策同士の整合性や財政的にそれらの政策が実現可能かどうか検討していな 例えば、注目された政策の一つである子ども手当ては、5.3兆円という巨大な金額が必要となり結局借金をしてまで配ることになったが、それは将来的に子どもたちの負担を大きくすることにもなる。他にも、高速道路無料化という政策を実施すると高速道路の維持管理や未完成の高速道路の建設に係るお金をどこから捻出するのかという問題になる。国民の中にはお金をかけずに遠出できるということで賛成した人もいるかもしれないが、今の財政が厳しいことを考えると、見直さないといけないということに国民も気付き始めた。 私はマニフェストという言葉を使い始めた一人であり、また当時全国で8人の知事がマニフェスト選挙を始めた。当時私が知事に立候補したのは地方からの改革を進めようと思ったから。そしてマニフェストにもスローガンではなく、具体的な政策実行手法を示した。 有権者は立候補している人物を選ぶのに、その候補者や彼らが属する政党が打ち出している政策を見て判断する。だけどマニフェストに明記されている政策が具体的でないと選ぶことができない。マニフェストには政権公約で掲げた各政策の進捗状況を外部に評価してもらい、情報公開している。有権者にはその情報によって政策の進捗状況のチェックと政策の勉強をすることができる。 それに対して、国が出しているマニフェストは選挙に勝つための道具であり本来の役割を果たせていないと言える。本来マニフェストとは、政策中心の政策、政治、行政をつくるための道具である。つまり、選挙の時ではなく選挙が終わった後が大事。 私は二期目からマニフェストを使った改革をしようと考え、11本の新しい条例を作ることをマニフェストに記載した。この11本の新しい条例をローカル・イレブンと呼ぶ。条例とは地域社会の法律であり非常に重要なものである。その11本の新しい条例の中で、全国的にも話題になり、施行するまでに非常に多くの困難があった条例二つについて、今回は紹介させていただく。
知事や市長はアメリカでいう大統領制であり、大統領制を採用する国は多選禁止の定めがあるが、日本にはその定めがなく、市長や知事の権力が長期化する傾向がある。任期4年間は知事に非常に大きな権力が集まる。例えば予算、人事、公共事業の発注、許認可の権限は知事が持つという、つまり権限はものすごく大きい。 しかし絶対的な権力が長期化すると、政治権力は絶対に腐敗をする。最近で分かりやすい例は北朝鮮である。金正日に刃向かうとすぐ政治収容所送りであり、側近にはイエスマンしか置かず、一般国民はそれによって苦しんでいる。社会主義国家のみならず、現代の民主主義の国でも権力が長期化すると腐敗していくことが分かる。 多選自粛条例を作っている地域はあるが、これはルールではない。そこで神奈川県では自粛ではなく、今後の神奈川県知事に就く人はいずれも多選をしてはいけないというルールをつくった。これには権力の腐敗を防止するという目的がある。 これに対し待ったをかけたのが総務省。彼らは憲法や公職選挙法、地方自治法に触れる恐れがあり勝手なことをしてはいけないと主張するが、それは総務省の法解釈であり、神奈川なりの新しい法解釈を出して、今国と闘っている。最終的にどちらの解釈が正しいかを決定するのは総務省ではなく、司法機関である。 民主政治は分権の政治制度である。アメリカの政治制度が徹底的に分権化されたのは、独裁政治、集権政治の犠牲になった人達によって造られたためである。どのように分権化されているかというと、例えば立法と司法と行政を分担、連邦制、地域でできることは地域でやり、国防など地域でできないことだけ国にやってもらうなど。 反対に、総理大臣は単選禁止法といったものを作ったほうがいいのではないか。改革とは時間がかかるもので3、4年先を見据えて制度を作っていかなければならず、1年でリーダーが変わると改革はできない。総理大臣は任期4年しっかりやらせようというルールを作ったほうがいい。
タバコが健康に危害を加えるということはみなさんご存知だろう。吸いたい人は吸えばいいが、問題は受動喫煙である。健康のためにタバコを吸わないのに、周りにいる喫煙者のためにタバコの煙を吸ってしまうことは理不尽である。実は副流煙の方が低温度でフィルターなしで燃やしているために主流煙より多くの毒物を排出している。 そのため公共的な施設という不特定多数が出入りする空間は禁煙とされているのが、欧米では当たり前である。「それは欧米だからできる。アジアではできない」という意見があるが、香港やシンガポールなどでは進められている。世界の都市は受動喫煙防止法を制定しているが日本で制定されていないのはなぜか 日本で喫煙規制が進まないのは縦割り行政の弊害によってである。厚生労働省はWHOで定められた条約に加入しているのに、推進しないのはおかしいと、この規制を進めたいと考えている。それに対し反発をしたのが、財務省である。なぜなら彼はタバコと深いかかわりがあるから。 まずは、タバコ税である。タバコの規制をすることで税収が少なくなることを危惧している。さらにJTの株式を財務大臣は50.1%も持ち、筆頭株主となっている。JTの業績が下がれば財務大臣の評価も落ちる。民営化会社ではなく国策会社のようである。さらに巨大な天下り先となり、人事の面でも財務省支配下である。 財の価格は需要と供給で決まるが、タバコは違う。農産品は農林水産省が担当しているがその中で唯一財務省が管理しているのがタバコであり、財務省はできたタバコを全部買っている。一般の農作物は市場の中でJAと調整する、また自分で流通先を開拓するなど農家は努力しているが、タバコについては別である。JT一社で、生産−製造−流通まで独占して、財務省がやっている。そのため巨大な利権が形成されているのである。 このような利権はタバコ以外にもあり、道路や郵政がその代表である。かつての小泉元首相がこれを壊してきた。最後に残った利権がタバコ利権である。 また、確かにタバコ規制をすることでタバコ税は多少減り、財政が苦しくなるかもしれない。しかし、長期的視野に立てばタバコを皆がやめることで、国民が健康になり、医療費の削減に繋がると考えられるため、財政的にも正当に評価されるべき政策だといえる。
私は国が喫煙規制をしないため、神奈川県の条例として制定することを決めた。この政策は世の中を二分するものである。まずは喫煙者と非喫煙者であり、喫煙者からの反対があった。また商業施設も不特定多数が出入りする空間であり禁煙にしていくため、居酒屋や喫茶店業界の反対は大きかった。 タウンミーティングを色んな商業施設運営者とすることで、色んな意見を聞くことができた。例えばある居酒屋の人は、居酒屋にとっての三種の神器とは、お酒、タバコ、おつまみであり、その場を提供するのが居酒屋だと言った。また、朝に喫茶店へ行く人も新聞、コーヒー、そしてタバコはが必須である。一方、味を大事にするレストランやすし屋はこの条例を歓迎してくれた。一番困ったのは喫煙率が非常に高いパチンコ屋だった。また雀荘は全部を仕切ることは賭けマージャンをやっていないかチェックするために、スペースを作ることができず、風俗営業法との折り合いはどうするんだ、という意見もあった。 こんな反対者に対して何も手を打たずに、強権的に条例を制定、施行すればどのような弊害があるだろうか。郵政改革を小泉さんは非常に強権的に進めた結果、今になって潰されかかっている。私はこれを反面教師にし、反対意見を持つ人と徹底して話し合いする路線で行くことにした。 話し合いによって何とか妥協点を探す、これが政治である。そのためJT、居酒屋、理容店、パチンコ屋などいろんなところへ話し合いに行き徹底的に議論した。大変だったが、7割のサイレントマジョリティーによる支持や、色んな団体、医療関係者が応援してくれたことはとてもうれしかった。 議員は県内の色んな利害関係者とつながりがあり、その利害関係者には反対者もたくさんいる。政治家はその政策を実行して結果を出せないといけない。しかし私もマニフェストで条例を通すことを約束したため、何としても通さないといけない。そこで議員を食事に誘って議論する、また政策に賛成している医師会を呼んで議論をするということもあった。また議員さんの中でもタバコを吸われる方がいらっしゃるので、彼らを説得するのも大変だった。 さらに議案を出したところ、議員から修正案が2つも出てきた。一つは小さな居酒屋や飲食店、宿泊施設は対象にしないということ、二つ目は罰則をかけないということ。 これでどちらの修正案も蹴ってしまったら、議案自体が承認されずこれまでの話し合いが無駄にな そこで、前者の案では、3年内は努力義務ということを加えた。 しかし、後者の方は、妥協しなかった。なぜなら、罰則のない条例では、単に啓発するだけであり、実効性が何もともなわないものになってしまうからだ。 民主政治とは「政治というのは交渉・妥協の芸術である」とも言う。 10か0かで考えず、議論して妥協点を探ることで、現時点より1歩、2歩でも進むことを目指す方がいい。だから妥協したとしてもネガティブには捉えてはいない。 この条例を作る過程を本にした。さらに「それでもタバコを吸いますか」という笹川洋平さんと対談した本もできた。ぜひご一読していただきたい。 この条例は、他の県にも波及し始め、静岡や京都、奈良でも検討が始まっている。このようにして日本全体でタバコ対策が進んだら、県境問題もなくなるし、いずれはタバコ利権がなくなるだろう。
質 京都市でも繁華街の屋外が禁煙となった。このように屋外でも、そして屋内でもすえないとなると、どこで吸ったらいいのかということにならないか。 答 屋外の喫煙を禁止している地域でも、一部禁煙になっていないエリアや喫煙シェルターを設けることで対応しているだろう。また家で吸う事は禁止していないので自宅の自分の部屋で吸ってもいい。ただ私は、奈良や京都は全面禁煙にした方がいいと思う。京都や奈良には木造の歴史的建造物が多く残るため、タバコの火の不始末によってそれらを傷つけるおそれがある。京都や奈良の財産は国民の財産だと思って守るよう心がけてほしい。 質 話し合いによって合意形成ができない場合、どうされるか。 答 人間とは不思議なもので、議論をすることで折衷案がうまれる。それでもまとまらないときには、多数決で決めます。最も悪いのは、みんなの合意が得られなかったからやらないこと。 質 2点質問があります。1点目は、松沢知事が衆議院議員を辞め、知事になろうと思われたきっかけは何か。2点目は、飲食店の人々はお店のジャンルによって意見が異なるというお話があったが、飲食店別に分けることはできないのか。 応 1点目について。私は国会議員になり、10年間野党だった。政治家である以上自分の考えていた政策を実現し、社会をよくしたいと思っていたが、野党の仕事は与党の政策に対して文句を言うだけで、これでは社会を変えられないと感じた。一方、都道府県知事は任期が4年間と定められていることや、多大な権限を持っていることから、ちょうどいい。権限や財源の委譲が叫ばれているが、地方でできる地方らしい政策をどんどんやっていくことで、地方から国を変えることができる。 2点目の質問について。同じコーヒーショップというジャンルでも志向が違うことがある。スタバやタリーズは禁煙志向だがドトールは席だけ分煙であり、方針が違う。そこで分煙のレベルをシールによって分けたらどうかという提案もあったが、禁煙政策のため喫煙を認めることはしたくなかったので、屋内完全禁煙という政策になった。 |
||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |