 |
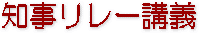  |
|
| 2010年 10月 5日 前 兵庫県知事 貝原俊民 氏 |
||
「 長寿国にっぽんの構築にむけて -阪神・淡路大震災に学ぶ- 」
1995年に阪神淡路大震災が兵庫県南部に大きな災害をもたらした。この地震は単に大きな地震であったというだけでなく、我が国のあり方がどのようなものかということについて国民全体に大きな問いかけをしたものだったと思う。そのような地震を経験した知事は私だけなので、今日はその立場で話をしたい。 皆さんは大震災の頃、5歳か6歳にならないくらいの年齢の人が多いと思うので、新聞やテレビの報道はあまり記憶に残っていないかもしれないが、阪神高速3号線が倒壊し、 阪神淡路大震災は高齢化した成熟都市を直撃した災害としては、人類史上初めてだと言われている。このような大災害が起きた時に、国は被災者に何をするのかということが非常に大きく問われた。6434人という大きな犠牲者が出た。全壊棟数は10万4千棟、世帯数では40万世帯が全壊している。被害額はストックの被害だけで約10兆円にのぼった。このようなときに、災害対策はどのようになっているのか。 災害対策には二つの形があり、一つは集権型である。集権型は災害についての権限と責任を一つのところに集中させて対策にあたるという考え方である。もう一つは分権型と言って、多くの機関に責任と権限を分散させて、みんなで協働して災害対策にあたるという考え方である。 日本は1868年の明治維新で近代国家ができ、明治憲法が国の骨格を決めていたが、このときの日本の災害対策は集権型だった。当時の日本は、アジア各国へ欧米列強が侵略してくる中で、藩幕体制を解体して新しい近代国家を作ってそれらに対抗していくということが国家としての最大の任務であった。そのようなときのやり方としては、資源も資金も人材も十分にないため、出来る限り一極に集中させて、その集団が国を引っ張っていくという集権型のシステムが望ましかった。 明治憲法は立憲君主制をとっているため、文武官任命権はすべて天皇が持っていた。武力集団を率いる統帥大権も天皇の権限であった。このような形で日本では中央集権制がとられていた。 災害対策も、国家警察、国家消防で中央政府が権限を持っていた。明治の終わり頃までは、このような形をとらないと外国に対抗できないということでやむをえなかったのだろうと思う。 しかし、日清戦争、日露戦争、第二次世界大戦に入るということになると、国がさらに権限を持っていき、国家権力の中に国民が巻き込まれていくことになった。大政翼賛会というシステムを導入し、外国に対抗するために、国民一人一人に協力を求め、国が上にあり国民がそれに拘束されるというきわめて封建的なシステムだった。 その結果、第二次世界大戦で、日本は負け、何のために日本は多くの犠牲を払ったのか、このようなシステムで良いのか、という反省があり、戦後新しい憲法が制定された。 新憲法は明治憲法とは逆で、国民に主権があり、国民の生活を平和で幸せなものにするために国家がサポートするというシステムに転換した。国家権力を規制し、国民の基本的人権を憲法で保障し、それを国家が侵してはならないという民主的なシステムとした。 災害対策も分権的な考え方に転換された。今は市町村消防となり、自分達のふるさとは自分たちで、火災から守るという考えとなっている。犯罪対策でも、都道府県単位で警察を持っている。台風や地震などの自然災害の対策も第一義的には市町村が責任を持ち、住民と一緒になって自分達の財産、身体、生命を守るというシステムとなっている。 災害の規模が大きくなり、市町村の範囲を超える場合には、県がそれを調整することになる。さらに広域になる場合は、国家が調整をするというシステムになっている。 外国からの侵略は国家権力同士の争いなので、当然国家が所管する。新憲法では、出来る限り権限は分散させ、国民に身近なところに権限を持たせているという考え方になっている。 1945年に第二次世界大戦が終わり、その後新しい憲法が出来たが、それから50年経った1995年に阪神淡路大震災が起きた。それまでは大きな突発的な危機はなかった。新憲法で新しいシステムを作ったが、それで上手くいくのかということが検証されないまま50年経っていた中で、突然1995年に阪神淡路大震災が起きた。 結果は残念ながら上手くいかなかったと思う。私は当時知事をしていたが、知事としても十分な対応が出来たとは思っていない。国家も危機管理能力が成っていなかった。日本には国民が信頼すべき危機管理体制がなかったのではないかということを、国民に知らしめたのも阪神淡路大震災だったと思う。 集権型と分権型の考え方の差がどこにあるのか。 集権制の明治憲法では、アメリカやロシアという大国と対抗しないといけないため、国が非常に大きな力を持たないといけなかった。そのため、公的な領域が非常に大きく、私的な領域は軽視をするというあり方だった。 現行憲法では、公的な領域はできるだけ小さくし、国民の生活である私的な領域をできるだけ大きくして位置づけるという考え方でできている。これが上手くいったかどうかが阪神淡路大震災で問われた。 地震が起きたとき、まずは犠牲者を助け出さないといけないが、分権的なシステムで上手く救助体制が出来ていただろうか。 現実は、西宮市の消防力基準で同時に何件まで火事を消すことができるかという指数は、3件だったが、大震災の時は実際には11件の火災が同時に起きていた。 被災地では40万世帯が被災しているため、住民数は120万程度と考えられるが、その地域に配置されている警察官は5000人だった。午前5時46分という状況のため、大半の警察官は帰宅していて、当直していた1200人の警察官が直ちに出動したが、どこで警察官が活動しているか分からないという状況だった。 そのようなときのために自衛隊があるのではないかと言われたが、兵庫県を担当する自衛隊は1200人で、他の地域の担当を含めてもすぐに出てくるのはせいぜい6000人程度しかない。公的な機関で被災者を救助するということが目に見える形では展開されなかった。 結局、被災者が自らの命を助けていたのである。阪神淡路大震災で家屋に閉じこめられた人がどのくらいいて、どのような救助がされたかという推計で、約16万4千人が家屋に閉じこめられ、そのうち自力で脱出した人が12万9千人、残りの3万5千人は他から救助されたと推計された。そのうち、公的機関により救助された人は7900人で、全体の4.8%しかない。民間人によって救助された人は2万7100人で全体の16.5%であった。公的な機関による救助に限界があるということが分かるが、自らの命は自らで守るしかないという状況になっている。 警察や消防、自衛隊の数を増やせばもっと救助率は高くなるが、そのために税負担を求めることは合理的だろうか。阪神淡路大震災規模の地震は50年に1度程度しか起きないと言われているが、そのために過大な消防や警察を持つことが国民の欲するだろうか。そのために、大きな災害が起きたときはこのような状況に成らざるを得ない。 「公助」に限界があるのなら、全て自力で良いのかというとそうはいかない。今は高齢化が進んでいて、被災者の中にもお年寄りが多くいて、ハンディキャップを持った人や日本語がよく分からない外国人もいる。そのような人達は自力でと言ってもそう簡単にはいかない。その人達を公で助けようとしても、公助が不足するのならどのような手だてがあるか。 それは、「共助」と言って、近所の人やボランティアの人が助けるといいうことである。当時は大学生を中心とした若い人達がボランティアとして活動した。「公助」、「自助」に限界があるのなら、「共助」という方法もあるのではないかということを大震災の経験から学んだ。
(ハードの復興) ハードの復興では、道路や下水道などの公共財は税金など公的な資金で修復することになるが、問題は私有財である。 住宅や店舗、工場などは個人や企業の持ち物で、これの復興は個人や事業者が行わないとならないというのが私有財産制の仕組みでは当然のことである。しかし、大震災のときは、個人では困難なため、公的な支援をすべきだという意見が出てきた。高齢者は今まで働いたお金で住宅を建て、老後を楽しく暮らそうとして人生設計をしているが、その住宅が壊れるとどうしたらよいのかということが言われた。もう一度建てることは残された時間が短いため、ほぼ不可能である。若い社会であれば復興できるが、高齢化した今の日本では無理である。そのようなときこそ、公的な資金で援助すべきだということが大きく意見として出たが、我が国の私有財産制の下では、私有財産に対して公的資金を投入することはできない。支援の財源は国民の税金となるためである。納税者の中には住宅を持っておらず借家住まいの人もいるため、被災者だとは言え、そのような国民の税金を渡すことに国民的な合意が取れるだろうか。 私有財産には自分で責任を持つべきだというのが、今の日本の制度となっているが、ここで新しく生まれたのが「互助」という考え方である。被災者に対して、全国あるいは外国から1860億円という大きな募金が寄せられた。税金で支援をするわけにはいかないが、義援金という形で自発的な支援で住宅を復興することは構わない。 40万世帯が被災したため、一世帯あたりでは40万円となり、家を建てる資金にはとても足りないが、このような大きな災害は50年に1度程度しか起きないため、それに備えて義援金を積み立てていけば対応ができるのではないかということで、互助の制度を作った。 (ソフトの復興) ソフトの復興では、個人個人の領域、生きていく基盤が非常に脆弱化しているのではないかと思う。 従来は家族の中で色々な機能を持っていたが、今ではお金で介護や教育を買うようになっている。家庭の絆が弱くなり、一人所帯などが増えてきている。人と人との絆が失われた無縁社会に日本は成りつつあると言われているが、そうなると災害が起きたときに、共助が出てこなくなるが、私生活の中に公な権力は入っていくことができないため、新しく出てきたのが「共働」である。 同じような境遇にある人が集合して住宅を建てていく建て方、被災者が共同で生活するグループホーム、高齢者が集団で住んでそこにケアを付けるという住まい方、コーポラティブ・タウン・プランニングと言って、住民が暮らしやすい町づくりを進めるやり方などが出てきたが、ソフトの復興でも公の役割は限定的となる。 しかし、私的領域でも十分ではないというときに、被災者同士がお互い助け合って共働して住宅を建てていくというあり方が出てきた。日本のように、経済が発展し、生活レベルが高い成熟した社会での公・私の働きに限界があるのではないかということを阪神淡路大震災は我々に問いかけた。 公の限界とは、市民の価値観が多様化し、国際化が進むと、日本の政府や地方自治体だけではなかなかコントロールできない問題が出てくることである。一般の市民、国民が経済力も知識も行動力も持っているため、役人だけで日本を引っ張っていくという状況ではなくなっている。役人の能力には限界が出ている。 しかし、市民の力で万全かというとそうではない。アダム・スミスは、個人個人が自由に経済活動をすると、市場も調和していくということを言ったが、だんだん上手くいかなくなり調和しなくなった。結果として、自由主義経済の国では格差の問題、人を殺して何が悪いのかという議論まで出てきて、人権の荒廃が起きてしまう恐れもあるように、全てのことを私的領域に任せておくのも問題がある。そのため、新しい公を構築していく必要があるのではないかという議論が出てきている。 (新しい公) 「新しい公」とはまさに助け合いのことで、住民同士が助け合うという共助、互助、協働のことである。 今までは私的な領域と公共的な領域は完全に分けて考えられていたが、それが成熟した社会ではうまくいかなくなる。完全に分けてしまうと、例えば家の前にゴミが落ちているとき、清掃は公の領域だとして市役所にゴミを取りに来るよう電話することになるが、そんなことをするよりは、家の前のゴミくらいは自分で処理したほうがはるかに効率的である。公的な領域と私的な領域の間に公共的領域があり、この部分を「新しい公」として、皆が責任を持っていくようにしたらどうかということが、阪神淡路大震災後出てきている。 私たちが最初に「新しい公」の考え方に気付かされたのは、1960年にアメリカのJ・F・ケネディ大統領が誕生した時に就任演説で、「祖国があなたのために何が出来るのかを問うのではなく、あなたが祖国のために何ができるかを問うて欲しい。」ということを言ったときである。 オバマ大統領も表現は違うがこのようなことを言った。アメリカは自由主義経済のモデルとなって私的な領域を尊重し、公的な領域を狭くするという考え方の国だが、それではなかなかうまくいかないため、新しい公共に参加して欲しいということを言っているのである。 また、民主党のマニフェストでも「新しい公共」ということを言っている。今年1月に鳩山前首相が「人を支えること、人の役に立つことは、それ自体が喜びとなり、生きがいともなる。こうした人々の力を私たちは「新しい公共」と呼び、この力を支援することによって自立と共生を基本とする人間らしい社会を築き、地域の絆を再生するとともに、肥大化した官をスリムにしていくことにつなげたい。」ということを施政方針演説で言った。 それに続けて、「今、神戸の街にはあの悲しみ、苦しみを乗り越えて活気があふれている。大惨事を克服するための活動は、地震の直後から始められた。警察、消防、自衛隊による救助・救援活動に加え、家族や隣人と励まし合い、困難な避難生活を送りながら、復興に取り組む住民の姿があった。全国から多くのボランティアがリュックサックを背負って駆けつけた。復旧に向けた機材や義援金が寄せられた。慈善のための文化活動が人々を勇気づけた。混乱した状況にあっても掠奪行為はほとんどなかったと聞いている。みんなで力を合わせ、人のため、社会のために努力をした。15年前の不幸な震災が、日本の「新しい公共」の出発点だったのかもしれない。」ということも言っていた。 これは私の認識とまったく一緒である。1995年は我が国ではボランティア元年と呼ばれている。それまでは日本にはボランティアは根付かないのではないかと言われていたが、若い人も高齢者も積極的にボランティアに参加した。参加した人の意見では、単に被災者がかわいそうだから参加したのではなく、被災者同士が励まし合って楽しく生きている輪に自分も入っていきたいという考え方で参加した人が非常に多かった。
今の被災地の現況は、人口も被災前の人数に戻り、インフラも元通りになり、街も綺麗になった。しかし、活気がない。隣の岡山や大阪を見てもやはり同じ状態で活気がない。日本は高齢化したことで何となく活気がなくなったことは確かである。 理由の一つは労働力人口が減少する社会に入ってきているということである。日本の労働力人口(15歳〜64歳人口)は、2000年までは増えているが、それから2010年にかけては少子高齢化、団塊の世代の退職の影響で減少している。労働力人口が減ると労働所得が減るため、トータルとして使うお金が減ることになる。退職者は貯金もしているが、将来のことを考えて大量に消費するということはしない。働いていた時代よりは一人当たりの消費金額は落ちてくる。そのため経済も活力が出ない。 「経済とはその地域で暮らす人々の生活をより良くする仕組みだ。液晶テレビなど高性能の電化製品や、環境対応車の人気は高い。しかし、多くの人達が切実に求めているのは、安心できる親の介護サービスだったり、深夜まで面倒を見てくれる育児施設だったり、安価な医療サービスなのではないか。潜在的なマーケットは大きいのに、供給体制が貧弱な状態が続いている。そうした経済的ニーズを経済システムがくみ取ることができなくなっているという現状をどう考えるのか。」ということを指摘した人がいた。 確かに企業はアジアの低賃金の地域と非常に熾烈な競争を強いられて、派遣社員などで労働賃金を抑えるという経済構造となっているように、国民のための経済になっていないのではないかという問題が指摘されている。このことが就職難につながっているのである。 二つ目の問題は高齢者扶養の負担増である。15〜64歳までの労働力人口と65歳以上の高齢者の割合を見ると、2000年の国勢調査では、労働力人口3.9人で高齢者1人を養うという割合になっているが、2005年には3.3人で1人、2050年には1.3人で1人となる。将来の若い人達は高齢者を養うために今よりも大きな負担がかかることになるなど、日本の将来に対して先行きが不安だという現状がある。 ここに「新しい公共」の考え方を入れていけば解決できると思っている。日本の平均寿命は高く、また、元気な高齢者が非常に多い。65歳以上で要介護高齢者は11%、少し支援が必要だという人が4%で、15%の人が介護保険のお世話になっているが、残りの85%の人は、元気なのである。元気な高齢者をどう考えれば良いのだろうか。 WHOの研究機関が神戸にあり、1998年に高齢社会についてのシンポジウムを開いた。その結論の一部で、「我々は全レベルの政府及び民間組織に対して高齢化という広範な意味を認識することを求めたい。我々は高齢者の技術や社会経験を十分に活用し、社会の一員及び貢献者としてコミュニティに参加してもらうことで、高齢者はケアの受給者だけであるという認識を変える適切な政策とその実践を求める。長寿社会における健康への投資は、さらなる発展のための投資である。」ということを述べた。 我が国の生産年齢人口が15〜64歳だと決めたのは、1960年のことである。その時の日本の平均寿命は男女合わせて68歳だったが、2010年では、男女の平均寿命は83歳となっている。平均寿命が68歳のときに上限が64歳だったのなら、平均寿命が83歳の今、それに相当する年齢は78歳となる。1960年当時と同じではなく、78歳まで引き上げても良いのではないかという議論もできる。 生産年齢人口を引き上げ、65歳以上の半分が扶養する方に回ると考えると、2050年でも3.6人で高齢者1人を支えることになり、今とあまり変わらなくなる。高齢社会になったときには、高齢者がどんどん社会参加していくようなシステムをつくっていくことで、若い人達の負担も軽くなるし、高齢者自身も生きがいを持って社会生活を送ることができる。このようなシステムを作ることで長寿国日本をつくることができるのではないか。 このためには当然前提条件が必要となる。一つは、高齢者が就業するためには健康対策として医療サービスを充実すること、また、介護のシステムをしっかりと整備しないとならないということである。介護の状況を整備するためには、家庭にいる女性にどんどん就労してもらう仕組みを作っていく必要があるが、日本では男女の就労率に20%程の差がある。欧米諸国では10%程度しか差がない。日本では子育て以外にも女性の就労を妨げている条件がある。例えば、保育所不足、親の介護という問題である。保育所の整備や、介護システムの整備をすることで就労人口を増やすことができる。 医療、介護、福祉、教育についてもっとシステムを整備していかなくてはならないが、そのためにはお金が必要になる。日本では消費税を引き上げないといけないという議論にすぐになるが、新しい資金運用としてシステムを作っていったらどうかと思う。 我が国の国民は個人金融資産を1400兆円も持っている。国・地方が借金で大変だと言われているが、これはまだ1000兆円もなく、それ以上に国民が個人金融資産を持っているのである。その資産を信用できる公的な機関に預け、その資金で介護、医療、教育を運用してもらうという仕組みにすると良いのではないか。それが新しい公共的主体の設立ということになる。今の都道府県、市町村だけではなく、国民が安心だと感じられる公共セクターをつくるという考えをしても良いのではないかと思う。 北欧がモデルで、特にスウェーデンは市町村にあたるコミューンは住民たちがつくっている。自分たちが持っている金融資産を共同で運用している。それで教育や福祉をまかなっているので、個人でお金を持たなくても、将来の介護や医療、教育のお金は全てそこでまかなってもらえるため、個人でリスクを負って運用する必要がないという安全で安心な社会となっている。そのような公共セクターを作っていったらどうか。これが長寿国日本構築の前提となる。
日本では、公と私というものがはっきり分業するというシステムでずっとやってきたが、震災のときに起きた現象を見てみると、公と私の間に公共的領域というものがあって、共助、互助、共同生活といった住民同士で助け合っていくシステムが必要となっていることが如実に出てきた。 今の被災地の状況を見ると、長寿国の中で労働力人口が減少し、企業も国民のニーズに対応していないため、新しい共助のシステムを作っていかないといけない。 長寿国日本は元気な高齢者が多く、技術や生活の知恵を持っているという高齢者は資産である。そのような資産を活用するようなシステムを活用することで、長寿国日本を構築することができるのではないかと思っている。 これは国民一人一人がきちんとしたモラルを持って努力をしないとうまくいかない。ロシアのノーベル賞作家が日本の新聞に寄稿していたが、「我々はとうの昔に自制という名の黄金の鍵を海の底に落としてしまったので、己に犠牲を強いたり無欲になるということは難しい。しかし、自己抑制は自由を手にした人間が目指すべきものであり、また、自由を獲得する最も確実な方法だとも言える。自分の欲求をしっかり制御し、自分の利害を道徳的基準に従わせる術を身に付けなければ、人類はバラバラに分裂してしまうであろう。真の進歩というものは一つしかあり得ない。個々人が、人生の過程で己の精神を高め、より完全なものへと近づいていく。その総和が進歩である。」ということを言っている。 公共的領域を作っていくためには、社会の構成員ひとりひとりが、自分のことだけではなくて、社会全体のため、人のために、自分の意思で役に立っていくという考え方で行動しないといけない。 その時に初めて「新しい公共」というものが生まれ、高齢社会でも活力のある地域社会を作っていくことができるのである。
<問> 公共的領域の議論は、公的機関が今までやっていたことを国民が積極的に引き受けることだと思う。国民の負担が増えるように思うが、公共的領域に対する反対意見はなかったのか。 <答> 当然反対の意見もあった。1996年にNPO法人を設立するための法律ができた。NPO法人が盛んにでき活動したが、そのうちに公的な機関の下請けをするようになるものが出てきた。NPO法人は公的な機関がやるべきことを肩代わりさせられるものなのかという異論が出てきた。人間一人一人の欲求レベルが高くなり、それを満たすためには今までやっていなかったことをやらなくてはならない。そのような分野が「新しい公共」的領域である。公の下請けでも私の下請けでもなく、新しい活動領域なのではないか。 具体的には、高齢者が社会参加すべきだということを言ったが、必ずしも高齢者が会社勤めをするとか自営業をするということではない。自分達が今までの長い人生経験で培ってきた技術や知識を自分の意思として社会的に役立つことをしようということになると、シニア・ボランティアという形でアジアで技術指導をするなどでも役立つことができる。 これは今まで公でも私でもやっていなかったこと。新しい領域に出かけて行き活動することで、その人自体が生き生きと人生を送ることができ、社会全体も輝く。そのような長寿国日本を作るべきではないかと思う。そのような領域が新たに誕生していくと考えてもらうほうが良い。 |
||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |