 |
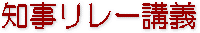  |
|
| 2010年 10月 12日 岡山県 石井正弘 知事 |
||
「 岡山の先人に学ぶ〜未来を拓く夢づくり県政と分権改革 」
1−1.天才的プロデューサー 津田
永忠(つだ ながただ) 津田永忠は江戸時代前中期の岡山藩の藩士で、岡山藩池田家の初代藩主と二代目のときの奉行をしていた。土木屋ではないが、後楽園や庶民の学校である閑谷学校をつくった。一番の大きな業績は新田開発を行ったことだと言われている。 津田永忠自身は技術屋ではなかったが、非常に優秀な技術者2人を抱え、高度な技術を取り入れ、領民の賛同を得ながら巨大な事業を完成させた天才的なプロデューサーと言えるのではないか。 社倉米という制度も津田永忠が作ったものである。社倉米制度は、池田光政の長女が姫路藩主本多忠平に嫁いだ際の持参金(銀1000貫=米約2万石)を元手に運用し、干拓資金や藩営事業に充てるとともに、領民に低利で貸し付け米として貸し出す制度のことである。現在の特別会計や基金に相当するものであったと言える。非常に厳しい藩の中で、将来の発展の基盤を作った手腕に大変驚かされる。 1−2.行財政改革の先達 山田
方谷(やまだ ほうこく) 山田方谷は江戸時代末期から明治時代初期の備中松山藩の藩士で、老中となった板倉勝静を支えていた。厳しい藩財政を建て直すため、行財政改革を行った。 当時の行財政改革の一つは質素倹約で、今で言う歳出の抑制である。さらに、将来を見越して産業を興すという産業政策も行った。この二つを車の両輪として藩政改革を行ったのが山田方谷の大きな業績となっている。 5万石あると思われていた藩の実収入が実際には1.9万石しかないことを公開し、質素倹約をして財政を建て直し、利益をあげていく必要を説いた。また、産業を興す必要があるとして、備中鍬やタバコ・茶・和紙などの特産品を開発した。大阪にある藩の倉庫を藩内に移し、大阪の市場の動向に左右されないようにした。 最も大胆なこととして、価値が下がった藩札を公衆の面前で焼き払い、変わりに兌換を義務付けた藩札を発行したということがある。藩民の信頼を得ながら改革を成し遂げたのである。 債務の返済を実現し、自分自身の俸給も公開し、民衆の協力を求め改革を率先するという強いリーダーシップを持っていた。その後は人材育成にも努めた。 行財政改革の中に、山田方谷の精神を多いに活かしていきたいと思う。 1−3.先人に学ぶ今日の地方行政の視点 この二人の先人から読みとれる教訓は、四つある。 一つはピンチを将来へ向けてのチャンスに変えていくというという精神が大事だということである。 二つ目は明確なヴィジョン、プランを事前に人々に提供するということである。方向付けを示さないと人々の協力が得られない。 三つ目は、協働、自立による地域づくりである。江戸時代は幕府からの援助はなかったが、自立した財政運営を目指し財政を建て直した。それを幅広く領民の賛同を得て実行した。 四つ目は斬新な改革の精神である。 当時は江戸時代で、厳しい幕府の監視下に置かれながらも、財政的援助がなく、自立して厳しい行財政をすべて藩の責任で運営していくという時代であった。そのような中には、今の地方分権改革の重要性に共通するものがあるのではないかと思う。
2−1.新おかやま夢づくりプラン 「新おかやま夢づくりプラン」は、現在岡山県が進めている中長期の行動計画である。 県政の基本目標は「快適生活県おかやま」の実現で、この中に「ピンチをチャンスに変える精神」、「自立と協働」、「創造と改革」などの理念を位置づけている。 2020年の岡山県が目指すべき将来像として、「いきいき岡山」、「きらめき岡山」、「中四国州」の実現を掲げている。 長期構想を実現するため、5カ年の中期計画を位置づけている。その中には「教育と人づくりの岡山」の創造、「安全・安心の岡山」の創造、「産業と交流の岡山」の創造の3つの基本戦略を位置づけている。この3つを結びつけるものとして、「中四国推進プロジェクト」を位置づけている。 おおむね順調に進んでいるが、昨今は雇用や経済の情勢が厳しいため、これらの分野の数値は思ったほど達していないものもある。来年度が行動計画の最終年度にあたるため、今一度すべて見直して、遅れているところは前に向かって進めていかないといけないと思っている。 2−2.持続可能な財政構造の確立 県政の運営にとって最も重要なことは、安定した自立可能な財政ということである。 私が知事に就任した平成8年当時の県の財政状況は非常に厳しいものだった。財政全体に占める借金の比率は全国で最も厳しい数字だった。起債制限比率がまもなく20%を突破する見込みであった。第二位の県が15%程であったため、岡山県は飛び抜けて高い県であった。一方、貯金にあたる基金は40億円程度しかなかった。借金での運営を余儀なくされている状況の中で私は就任した。 そこで、全国に先駆けた行革を徹底してやっていこうとして、様々な改革を行ってきた。 第一に、大きな事業の凍結や見直しを行い、規模を圧縮した。また、公共事業の削減にも思い切って取り組んできた。平成8年度から平成20年度にかけて、公共事業を657億円から320億円削減し、337億円とした。一般行政経費についても、一般財源ベースで772億円から323億円削減して449億円とした。内部管理費も64億円の削減をした。総定員も平成9年度から平成20年度にかけて2499人の削減を行っているが、治安を守る警察官の定員はずっと増加させている。 このようなさなか、いわゆる「交付税ショック」があり、平成16年度予算の時に、三位一体の改革(補助金の見直し、国税から地方税への税源移譲、地方交付税の見直し)が行われた。補助金の見直しにより4.7兆円の削減効果があったが、税源移譲は3兆円であったため、国家の財政が1.7兆円好転したことになる。これに加えて、地方の財政を調整する地方交付税が突然5.1兆円削減された。この削減が地方の財政に大きな打撃を与えた。このことを「交付税ショック」と呼んでいる。これによって岡山県では平成16年度では前年度より248億円交付税が減少し、非常に厳しい財政状況に陥った。 当時の推計では、平成20年度以降収支不足が361億円から始まり、最大450億円規模までの収支不足が毎年続くという厳しい見込みとなった。持続可能な財政構造にしていくために「財政構造改革プラン」を進めている。その内容は、毎年巨大な収支不足が続く中で、約400億円の歳出削減を進めるというものである。一気に改革はできないため、4年間かけて段階的に進めていくこととしている。また、平成24年度までに、120億円の独自の給与カットも併せて行っている。 税収の増加、普通交付税の増加などの影響もあるが、平成22年度の収支見通しはプラス12億円となり、改革の効果が出てきている。あと2年改革を成し遂げたいと思っている。改革ができれば、厳しいながらも明るい岡山県の未来が確保できるのではないかと考えている。私が就任したときの知事部局の定員は約5800人だったが、現在は4100人まで削減している。今後は3600人まで減らしていきたいと思っている。これは、全国的に見ても上位の定数削減を行っていると言える。 就任当時一般会計予算は8000億円規模だったが、今ではそれから1238億円程度削減されている。これに加えて、今後さらにカットを進めていき、20%の削減を目指している。公共事業は就任時から3分の1になった。このように、血が滲むような改革をしていることを理解してほしい。 歳出の削減では、平成10年度から平成20年度までの10年で、地方は都道府県全体で13.3%の歳出を削減してきた。社会保障関係費が増え続ける中で、住民サービスの水準は維持しつつ行革でこれだけの削減を達成してきたのである。国はむしろ0.4%増やしている。国は法律を制定すれば、赤字国債を発行することができるため、借金をするという傾向が強かった。地方は勝手に借金ができず、臨時財政対策債は別として通常の起債は建設事業債に限られている。地方はどこも公共事業を減らしており、起債も減ってきている。そのような中で、社会保障などはしっかりと守っているのである。 職員数の削減では、地方は平成13年度から平成21年度までに16%削減してきているが、国は2% 給与カットも地方は必死でやっているが、国はまだ実施していない。 2−3.地方財政の将来推計 平成23年度には地方全体で0.4兆円の財源不足、平成24年度には2兆円の財源不足となり、平成23年度に都道府県が破綻、平成24年度に市町村が破綻するという推計も出されている。社会保障関係費はどんどん増えていき、毎年7千億円以上増えていっている。介護保険や医療保険の都道府県負担分も高齢化とともに増えていく。このような推移の中で、このまま行くと財政が破綻するという推計である。 地方交付税が財政の中に占める割合は、岡山県は33.8%となっている。今後のことを考えると、地方もしっかり建て直すためにも、我々の固有の財源である地方交付税をしっかり確保してもらいたいと思う。 2−4.地方消費税 地方交付税とあわせて地方消費税も重要な財源であると考えることが必要である。今の国と地方の仕事の割合を見ると、税収は国が3、地方が2である。実際の仕事は、国が2で地方が3で逆転している。その差が交付税や交付金で成り立っているが、もっと安定的になるように仕事をしている割合に応じて、地方の財政を充実強化する必要がある。 地方税のうち、法人二税や個人住民税は変動する。一番安定しているのは固定資産税だが、消費税はそれ以上に安定していると言われる。 消費税5%のうち、1%が地方にまわってきて、半分ずる都道府県と市町村の税収となっている。国税にあたる4%のうちの1.18%分が地方交付税特別会計に繰り入れられる。今現在地方は5%のうち2.18%分配分されているが、国のほうが多い。 今すぐではなくとも、消費税を引き上げる議論をするときには地方消費税をしっかりと充実強化していくことを主張している。抜本的な税制改革は避けて通れないと思っている。 2−5.未来を拓く県政の推進 (1)国民文化祭を契機とした文化振興 文化は心を豊かにし、潤いを与え地域を元気にする。国民文化祭という文化の一大祭典が10月30日から9日間行われる。文化によって元気な地域興しをしていきたいと思っている。そこでは特徴的な文化の発信をしていこうと思っている。 岡山県は教育県として教育に力を入れてきたが、県庁の前にある県立図書館の入館者数、貸出冊数が、5年間連続1位となっていることであることを誇りに思っている。 (2)競争力ある成長産業の育成と観光立県の推進 岡山県では産学官の連携でユニークなこともしている。 岡山県は光化学に注目して、光量子化学研究所を県自ら持っている。自治体が理論研究所を持っているのは世界でも岡山県だけではないかと思っているが、そこでは将来の研究者を育てようとしている。 電池関係の産業育成に力を入れているが、太陽光発電や電気自動車を考えると、電池は非常に重要になってくるためである。これから実用化が進んでいくであろう燃料電池の研究を、産学官の連携で立ち上げている。 木質系のバイオマスにも力を入れている。セルロースをナノテクで超微粉砕したセルロースナノファイバーを作るプロジェクトが今年度から5カ年の計画で発足した。セルロースナノファイバーは、鉄の5倍の強度を持つが、重さは鉄の5分の1である。プラスチックの代替品として実用化を目指していこうとしている。木皮なので、土に埋めると土に還っていくため環境に優しい。 成長産業ということでは観光も非常に大切である。中国人観光客を含め、アジアのインバウンド客を増やそうとして上海の万博会場などでアピールをしている。日本各地に中国人を中心とする観光客が来ているが、岡山県は医療の先進地なので、PET(人間ドック)の健診を受けて同時に観光もしていただくという医療ツーリズム(メディカルツーリズム)の分野に着手をしている。 B級グルメでは、大会で初参加で第2位に入った蒜山焼きそばや、第4位に津山のホルモンうどんなどがある。B級グルメで地域の活性化を目指していこうと思っている。 (3)太陽光発電・EV(電気自動車)の普及促進 岡山県では太陽光発電とEVの普及にも力を入れている。岡山県は「晴れの国」と言っていて、降水量1ミリ未満の日が最も多いため、太陽光発電に適している。住宅や事業用の太陽光発電に補助制度を使って応援している。非常に普及していて、昨年で3000件、今年でも1000件の申し込みが来ている。 EVは、平成27年までに1000台をかかげている。県の公用車にも導入し、カーシェアリングとして実際に希望者に体験してもらったりもしている。水島という工業地帯に、三菱自動車の工場があり、日本で最初の普及型電気自動車が生産されているため、しっかり後押ししていきたい。外国からの注文通り作成するOEM供給の受注もしている。 (4)総合特区制度と「おかやま発展戦略会議」 総合特区制度として、国に3つの提案をした。 一つは、水島港と水島コンビナートの企業を活かした「ハイパーコンビナート水島特区」として提案をした。水島港は鉄鉱石の取扱量が日本一で、穀物の取扱量では第二位である。非常に特徴的な港で、国際戦略としてしっかり位置づけていきたい。 二つ目は、グリーンバイオの特区である。これにより新しい産業の育成を目指していこうとしている。 三つ目は、「革新的医療フロンティア特区」である。臓器移植や遺伝子治療で優れた技術を持っている岡山大学や、人工関節の素晴らしい工場があるため、メディカルイノベーションを目指して医療の特区を申請中である。来年度以降是非実行に移していきたいと思っている。
3−1.地方分権改革の現状と今後の課題 地域主権戦略大綱が決められたが、後は実行あるのみだと思う。気になるのは、地方税財源の強化がしっかりなされるのか、社会保障関係費の増加を念頭に置いた改革が講じられるのかどうか、交付税を地方の固有の財源と認識して改革が進められるのかということである。 残っている問題は大きく二つある。一つは国の出先機関の問題である。国の出先機関は原則廃止し、都道府県や市町村に事務を移譲するという方針が打ち出されている。方針としては歓迎しているが、果たして実行できるのかどうかが疑問である。菅総理大臣が強いリーダーシップを発揮することが必要である。 もう一つの問題は一括交付金である。補助金・負担金を自由度の高いものにするという方針は賛成である。国税から地方税への税源移譲を一番望んでいるが、今の方針は、一括交付金として自由度を高めて、来年度は投資的経費を中心に新しい交付金を作るとしている。これは、税源移譲へ向かう経過的な措置として歓迎しないわけではないが、省庁が非常に抵抗している状況がある。国と地方は対等になったと言われるが、お金の面では中央集権の側面が残っている。これを改めてもらいたい。 3−2.道州制の導入と中四国州の実現 戦後、中央集権体勢の中で日本は大きく発展をしてきた。 今は量的な拡大よりも、地方が質的な拡大を求める時期になっている。文化、医療、教育、人づくりといった点に地域の関心が非常に高まっている。独自の産業政策も地域が特色を持ってやれば良い。 内政は基本的に地方にゆだねることで、お互い切磋琢磨して良い政治が行われ、地域が元気になり、日本全体が良い方向に活性化していく。このように考えると、地方分権改革は是非ともやらないとならない。 究極の姿として、私は道州制を主張している。中国と四国が一つとなった「中四国州」を主張している。平成15年には中四国州には市町村が520団体あったが、平成19年には208団体まで減少している。岡山県でも、78あった市町村が今では27まで減少している。市町村合併が大きく進み、一方で交通網、通信網が大きく発達した影響もある。 道州制では、国が持っている事務を道州に移譲し、都道府県が持っている事務は市町村にゆだねることとし、市町村は住民に身近なことをやり、道州は国の出先機関の事務のしっかりとした受け皿になる。国は外交、防衛、司法、大きな経済政策など、日本のこれからの形に関する仕事に専念する。このようなイメージでいくと、道州制は地方分権改革の総仕上げで避けて通れない大きな議論だと確信している。 中四国が一緒になると、オーストリアやノルウェーに匹敵する経済規模となり、自立した経済力を持つことや、将来の発展可能性がある。また、環境の保全や福祉、文化、瀬戸内海の管理など様々なことが新しく一体的にできるようになる。 道州制の議論をすると、「市町村がなくなるのではないか」という意見が出るが、むしろ市町村が道州制の中心で、市町村に事務が都道府県から移譲され、道州制の主役となって欲しいと思っている。市町村の範囲を超えるような広域的なものは道州が担い、国は外交や防衛に専念してもらいたいというのが道州制の基本的な考えである。 今の政権では、道州制は将来的な検討課題としているが、最近では若干前向きな議論が出ているようにも思う。全ての知事が同じ考えというわけではないが、私は地方からしっかりと発信していきたいと思う。
これからは本当に分権型社会が進んでいく。地方の行政は非常に魅力的でこれからも伸びていく分野だと思う。また、地方分権が進むと、国からの指示や命令がなく思い切った行政が展開できるため、やりがいがある。 皆さんの素晴らしい前向きな行政センスを活かすことができると思うので、地方自治や地方分権に関心を持ち、地方行政の場に活躍の場を見出してもらえればと思う。
<問> 現在、ねじれ国会など二院制が上手く機能していない中で、参議院を知事連合などに変更し、国と地方で予算編成を決めていくというのはどうかと思うが、知事はどう考えるか。 <答> 参議院に知事会代表を参画させて地方分権を目指していくという提案だと理解している。私も関心を持っていて、先般ドイツに行って連邦議会の調査をしたところ、ドイツでは連邦参議院には知事が数名選ばれて参画して議論している。地方に関連する議案は知事たちの同意がないと駄目だとしている。道州制の発展した連邦制の議会でそのようになっていたので、非常に傾聴に値する提案だと思うし、そのような思い切った提案を含めた活発な議論が必要だと思う。 <問> 地方分権では権限と税財源を地方に移譲することが重要とのことだったが、一方で地方交付税をしっかり国が交付する重要性も強調していた。この二つは矛盾するものではないのか。 <答> 地方交付税を含めて地方財政対策が講じられている。地方税だけでは行政需要に足りないときに、足りない分を国が地方交付税特別会計の中から配分している。地方交付税と両方あわせて行政が司っている。6割ほどの県では地方交付税の割合のほうが地方税の割合より高い。そのような税構造になっているため、交付税が一方的に5兆円規模などで削減されると、大変な財政危機に陥る。 思い切った行政をやっていくためにも、必要な財源は確保されないとならない。おねだりをするわけではないが、突然減らしたものは元に戻すことと、地方に税源移譲することを主張して、それを中央の議会で議論していくことが必要である。配分権は国にあるが、地方交付税は地方の固有の財源である。 |
||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |