 |
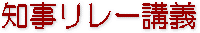  |
|
| 2010年 10月 19日 茨城県 橋本 昌 知事 |
||
激動する世界と「いばらき」
地方分権や地域主権とさかんに言われるが、地方がしっかりしていないと国は成り立たない。また、国がしっかりする元気を出すためには、今までのような中央集権では良いアイデアが出にくい。地方にもっと力を与えていくことで、日本の活性化をもたらすのではないだろうか。国と地方は持ちつ持たれつの関係にあると思う。
(1)グローバル化の急激な進展 これまでの世界の話は、西側諸国の発展などが中心で、本当のグローバル化という感じではなかったが、リーマンショック以降、グローバル化が本格的に進んできた。グローバル化が進む中で、中国、インド、ブラジルといった国々が本格的に発展してきた。また、今やアジアの各国あるいはアフリカなど世界中のほとんどの国がものすごい勢いで変化をして、それぞれの国のつながりも深まっている。 中国の統一された「銀聯」というカードが、ここ5年ほどで決済額が30倍くらいになった。これを使えるようにしておかないと日本で商売している人も売上が伸ばせないということもあり、今では日本でも銀聯を使えるようにする商店はどんどん増えている。中国の人口は日本の10倍以上いるが、この人達が今やものすごい勢いで中間層になっている。インドも人口が12億人で、特に若い人達は目を輝かせていて、何かを吸収して自分がこれから出世していこうという勢いをひしひしと感じる。 世界の動きの中でどんどんグローバル化が進むが、日本はこのままで良いのだろうか。若い人達に切迫感、緊迫感が極めて欠けていると思う。以前グアムへ行ってきたが、中国・韓国の人がすごい勢いで来ていた。そこでは、日本のホテルが、韓国資本に買収されたりしている。グローバル化が進んでいる中で、日本はどうやって生きていくのかが大きな課題となっている。 (2)パワー・ポリティクス ■国際紛争 これまではアメリカの傘の下で全体を調整していたという感じもあるが、今では国の力を背景にしながら、自分の言いたいことは通していくという傾向が大変強くなっている。 尖閣諸島の問題はパワー・ポリティクスである。レアメタルも中国が握っているため、輸出をやめるようになれば日本では工場の操業を止めねばならないなど、いろいろな点で影響力がある。 中国は資源を有しており、これまでは製造面で中心だったが、今は消費市場としてもメインの立場をつかみとろうとしている。リーマンショック以降、中国経済が発展しなければ世界経済が発展しないということを感じているため、日本も自信をつけていきたい。中国はこれからものすごい力をつけていくと思う。 ■新重商主義 UAEとベトナムで原子力発電所を日本の企業が受注すべく一生懸命やってきたが、結果的に両方とも日本の企業がとれず、韓国やロシアがトータルな交渉の中で取っていってしまった。新重商主義ということで、国を挙げて取り組んでいくことが必要となっている。韓国やロシアは原子力発電所などに必死でがんばっている。国策として必死で取り組んでいる。スポーツにしても学問にしても、国土づくりにしても国策をしっかり立てている。 日本はそうではない。韓国ではプサン港や仁川空港を世界でも5本の指に入るほどの位置づけにもっていっている。日本では神戸港にしても東京港、横浜港にしても、地位がどんどん下がっている。成田空港もどんどん地位が下がっている。もっと国策を重用視してやっていかなければならないと思っている。 世界の動きとして、グローバル化が進むなかで力を背景とした動きが強まっているのである。 (3)資源獲得競争と寡占 世界の人口が今は68億人で、2050年には91億人になると言われている。中国にしても生活レベルがすごくあがり、食糧や石油を輸入しなければならず、すごい勢いで需要が増える。需要が増えるということは、価格が上がるということである。同時に寡占が進んでいく。 例えば、鉄鉱石は3社で67%のシェアを持っており、値段を思い通り決められているという状況になっている。レアアースでも、価格をどうするかは中国が自由に決められる状況になっている。このように、資源がかなり偏っている面があり、一部が価格支配力を強めている。 粗鋼では、BRICsが2006年から2009年の間で10%以上シェアを伸ばしている。世界の企業別粗鋼生産ランキングを見ると、2009年では、2位〜4位を中国が、5位を韓国が占めている。前年は2位にいた新日本製鐵は6位まで下がってしまった。シェアが少なくなると鉄鉱石の価格にも交渉力がなくなってくる。日本の力が相当の勢いで落ちていくのではないだろうかと思う。 日本はエネルギー自給率でも18%しかない。ウランの輸入分を差し引くと、4%しかないということになる。食糧自給率も40%にとどまっている。食糧自給率は50%を目標としているが、何度やってもそこまではいかない。エネルギー基本計画でも、エネルギー自給率を倍増させる方向性を打ち出しているが、なかなかうまくいかない。世界の動きが厳しさを増している中で、日本は何をやっていくべきかを考えなければならない。
(1)国際社会における日本の地位 GDPでの日本のシェアは、今でも2番目だが、今年中国が日本を追い抜くのは間違いないだろうと言われている。それにも増して大きなことは、1993年には17%あったGDPのシェアが、今はその半分もなくなっているということである。一人当たりGDPのシェアも1993年には2位だったが、今では19位になってしまっている。国際競争力のラン 1993年での世界の港湾のコンテナ貨物取扱量では、神戸港が6位、横浜港が9位だったものが、2008年には東京港が24位、横浜港が29位まで下がっている。空港の貨物取扱量でも、成田空港は1993年には2位だったが、2008年には8位まで下がってしまっている。韓国は仁川空港をつくり、それが4位まで伸びている。外国企業の上場数を見ても、東京市場は他の都市より桁違いに少ない。日本の立地競争力では、2007年と2009年を比べても、アジア統括拠点、製造拠点、R&D拠点、バックオフィス、物流拠点すべてで中国が地位を伸ばし、日本の地位は下がっている。 外国企業を呼ぶという方針を政府は打ち出しているが、このような状況では呼び込めない。いろいろな事情があるが、日本に立地しようとしてもスピード感が確保できず、時間がかかるという課題がある。法人税率以外にも障壁があり、本格的に外国から企業を呼び込もうと思うと今の体勢では無理な状況である。そのような中で、韓国などの努力は大変なもので、国策としてがんばっている。韓国は4800万の人口しかいないが、空港も港湾も世界で5本の指に入っている。スポーツや国づくりでも方向性を作ってがんばっている。 存在感の低下が著しいのが今の日本の立場なのである。 (2)豊かな国民生活の維持 ■外貨の確保 食糧もエネルギーも価格が上がる中で、内需を拡大するだけではなく、カネがないといけない。食糧やエネルギーは消費してしまうため、どこから買うお金を持ってくるかが重要である。これまでは製造業で稼いだ利益で輸入して消費していたが、これからは内需拡大だけでは日本の景気はうまくいかない。 外国からモノを買わないとならない資源小国としては、モノを買えるだけの外貨を確保していかないと成り立たない。このことはなかなか表に出ていないために、内需拡大をすることだけが言われるが、それでは日本の今後はない。外貨を獲得するためには、これからもものづくりを大事にしていかないとならないと思う。 ■科学技術創造立国 科学技術創造立国ということを国は打ち出しているが、その割には事業仕分けでの「2位じゃだめなんですか。」発言など、消極的な面もある。ものづくりと科学技術創造立国による最先端の科学技術を以てしか日本はこれから生きていけないと思う。 ■新成長戦略 外国の企業を呼び込むにしても、スピード感がないことが最大の課題である。環境エネルギー分野や観光分野など、様々な分野が政府の新成長戦略では挙げられている。しかし、観光にしても、中国から100万人、韓国から160万人の観光客が来ているのが現状で、将来的には3000万人観光客を呼びたいとしているが、呼ぶための体勢がなかなかできていないのも事実である。日本に観光に来ても不便で、自由に動き回れないような状況であったり、空港への航空機の乗り入れができなかったりするなどの問題があった。今動き始めてはいるが、まだまだ十分ではない。 健康分野では医薬品や医療器具が中心だが、医薬品を売り出すにはまず治験をしないとならないが、日本はまだ十分な体制ではなく、時間がかかりすぎている。治験をやって売りだそうとしても日本では許可がでないため、外国で治験をしてくるということは普通に行われている。中国の場合には桁違いの人口を抱えているため、治験にしても数という面ではすぐ出来る。 どうやって成長戦略を現実のものにしていくかということはすごく難しい。本当に実現できるかというと、そう簡単にはいかない。どうやってより具体的にしていくかが大きな課題になってくる。日本国民をどうやって豊かな生活の中に置いていくのかを考えないとならない。 (3)人口減少時代の到来 ■未婚化・晩婚化・晩産化の進展 今1億2700万いる日本の人口が、2050年には1億人を切ってしまうのではないかと予測されている。そうなると、人口のアンバランスが大きな課題になる。生産年齢人口を20〜65歳と考えると、2005年には3人で1人の高齢者を支えていることになるが、2050年には1.2人で1人の高齢者を支えることになる。 どうやってこのような時代になるのを防ぐか、あるいはこのような時代でも社会が成り立つ体制をどのように作るかが大きな問題となってくる。2050年はみなさんにとってはきわめて重要な時期である。1.2人で高齢者1人を支えるのは不可能であると予見されているのに、現実的にどう対応していくかを考えないとならない。 人口を増やすには合計特殊出生率が2.08を超えないといけないとされている。出産適齢期の人口はどんどん減っているため、合計特殊出生率が多少上がっても出生数は増えていないため、日本の社会をどのように維持していくかがこれからの課題である。 未婚化・晩婚化・晩産化を少しでも良い方向に持っていかないといけない。未婚化では、1975年では30〜34歳の男性は86%、女性は92%結婚していたが、今では男性では53%、女性で68%しか結婚していない。生涯独身率が男性では16%、女性では7%となっている。晩婚化ということでは、女性の初婚年齢が24歳から28歳へ変化している。結婚してもすぐ子どもを生まず、ある程度新婚生活を楽しんでから産むようになっている。そのようなことも人口減少に影響を与えていると思う。 ■人口減少・少子高齢化社会の課題 非正規労働力がかなり多くなっており、いろいろな点で社会に悪い影響を及ぼしていると思う。今の社会で就職したくても就職できず、非正規雇用に就いている人が増えており、労働者の3分の1が非正規労働者となっている。これまでのように、意図的にパートやアルバイトといった雇用形態をとっているのではなく、5割以上が不本意ながらそうせざるをえなくなっている。若年層の非正規雇用も激増している。当然給与も低い人が多くなり、年収200万円以下が約1100万人もいる。このようなことになると、なかなか結婚も思うようにいかなくなる。2002年の独身者約1万人を2007年に追跡調査すると、正規雇用では24%が結婚し、非正規雇用では12%しか結婚できていなかった。人口減少に雇用が不安定であるということが影響している。 あわせて、就職しても大卒が31%、高卒で40%が3年以内に退職しており、ものづくりの技術の継承という点では、大問題となっている。 日本の賃金はずっと上がっておらず、1995年から2008年の13年かけて4.3%しか上がっていない。一方で、アメリカでは43.8%、中国では約4倍になり、韓国では1.5倍となっている。日本の場合には賃金が上がらないために、生活レベルを維持できない人が増えている。 雇用形態別の生涯賃金では、正規の大卒男性の生涯賃金は2.7億円となる。しかし、生涯非正規でフルタイムの男性では1億円にしかならない。年金額でも大きな違いがある。 今まさに就職氷河期だが、みなさんもしっかり職業観を養ってどのようなところに就職するか全力でやっていかないといけない。生涯非正規に入ってしまうと大変な状況になってしまう。就職の段階で格差社会が出てきてしまうため、何とか賃金が上がるようにし、生涯希望を持って安定した生活ができる社会にしていかないといけないと思う。 それが人口減少社会を少しでも緩やかにする方法だと思う。 社会保障が成り立たなければ、生産年齢人口1.2人で高齢者1人を支えることは不可能で、労働力の確保もできなくなるし、消費も投資も停滞し、地域社会の維持もできなくなるという状況があらゆるところで発生してくることになる。 (4)地域間競争の激化 日本の中でどこも同じように人口が減るのではなく、一部のところは増えて、一部のところが急激に減るという形で、日本全体では人口が減少するということになる。平成になる前くらいまでは東京の人口をどう分散させるかという議論が中心だった。しかし、東京も減少しているため、東京にもう少し仕事や学校を集中させようという動きが出てきている。それにより、一旦外に出て行った大学が都心へ戻ってきたり、大規模な工場が都心へ戻ってきたりするなどで、東京がどんどん人口を伸ばしていき、他が減少するということになってきた。 東京の伸びは凄まじく、その影響を受けて他は四苦八苦している。われわれ行政を預かる者は、そのような状況の中で、どうやって自分の地域を少しでも勝ち組にするかということを大きな課題として考えている。 地域間競争はあらゆるところで起きている。競争しても勝てないからあきらめているところもあるなど、厳しさを増すばかりである。企業も合理化・集約化を進める中で、条件の良いところに集まってくるため、どうやってそのような状況を作っていくかが地域環境層の一番大きな課題となっている。 (5)地域主権 地域にもっといろいろな権限、財源を与えないとならず、中央官庁の考えだけではもう限界がきている。地方にはたくさんの公務員がいるため、その人たちにもっと独自に考えさせないとならない。成功例を全国に広めたり、地域に合った形で取り入れたりする必要がある。 地方自治に関しては、道州制にすればばら色の未来が開けるといったことを書いている本もある。今の日本の都道府県でも道州制は実施できるとは思うが、大きさが問題ではなく、地形的、地理的に結びついているところは道州制にしても良いが、今のようなただ大きくすれば良いという道州制では実のある形で導入できるとは思わない。道州制を本当に導入するには、本気で取り組めば都道府県の形でもできないことはないが、一律にやっていくことは賛成ではない。 国の行う道路工事などに対して、建設費の3分の1を直轄事業負担金持たせるという仕組みがあった。維持管理費についても45%の負担があったが、これは今年度から無くなった。茨城県には国営ひたち海浜公園があり、維持管理費の45%を県が持っていたが、それでも「国営」と言われてしまうのである。 茨城県では、国から受け取る補助金よりも、県が支出する直轄事業負担金のほうが大きい。責任の所在を明らかにするためにも、直轄事業負担金や補助金を廃止して行政を行っていけないかと思っている。 (6)教育の振興 日本がこれから生きていくためには、教育をどうするかが一番大きな課題だと思う。ノーベル賞を受賞された鈴木先生が、「日本には人間の頭しかない。もう少し若い人が理科系に興味を持って欲しい」ということを言っていた。根岸先生は、「若者よ、海外へ出よ」ということを言っていた。しっかりと理科系の割合が高まるような政策をとり、世界でやっていけるようなたくましい人間をつくっていかないと、日本は豊かな生活を維持していけないと思う。そのためにも教育の振興が重要である。 外国の留学生もなかなか日本に来ない。アメリカでも同じ状況で、アジアへどんどん留学生の活躍の場が広がっている。人の取り合いに負けているようでは、日本はどんどん世界から取り残されてしまう。もう少し貪欲にいろいろなことをやる若者を作っていかないとならない。
■茨城県の紹介 茨城県は、人口では296万人で、広島県、新潟県、京都府などよりは大きな人口を抱えている。可住地面積では、3976平方キロメートルで、日本で4番目に大きい。 製造品出荷額では、全国で8番目となっており、農業産出額は全国で2番目、1人あたり県民所得では12番目である。 茨城港は東京より北では一番の水深を持っており、自動車の輸出も行っている。つくばエクスプレスでは東京の秋葉原まで45分で行くことができるように、東京と一体化し始めている。鹿島港というコンビナート地帯もある。また、茨城空港が3月に開港した。 ■県政の目標 茨城県政の目標は、 1.安心・安全で快適な「住みよいいばらき」づくり 2.充実した教育が行われ、個性や能力が発揮できる「人が輝くいばらき」づくり 3.競争力あふれる産業大県「活力あるいばらき」づくり による、すべての県民が安心、安全、快適に暮らせる『生活大県』の実現 である。 そのために、基盤整備を行ってきて、ある程度進んできたと思っている。県民が住んで良かったと思える県、日本の発展の一部を担える県を目指している。 日本全体が発展していく中で、茨城県として外貨を稼いでいくようにしたいと考えている。ものづくりの工場もあるし、つくばには試験研究機関が300あり、国の研究機関は3分の1がつくばに集まっている。つくば市は人口21万人だが、研究者が2万人おり、1割が研究者ということになる。また、博士号取得者は7千人いる。学術会議の回数も増えている。サイエンスツアーバスで研究機関を訪ね歩くというものを市で運営して見学者も増えている。また、東海村には世界最先端の加速器がある。 こういったものを活用して、ものづくりでは、東海村に最先端のものがあり、つくばには博士がいるという特徴を活かし、東京と近いため連携をしていき、世界でも中心になっていけるような場所を作っていきたい。 工場の立地面積の過去10年間の累計では全国で1位となっている。誘致した企業には税制面での優遇をしている。企業にとってはインフラを整備したことも大きなメリットとなっていると思う。 少子化対策では、いばらき出会いサポートセンターを作り、支援をしている。民間では入会金が高いということや、だまされるということもあるが、われわれは住民票を取り寄せ審査を徹底している。行政がそこまで介入するべきでないという意見もあるが、介入しないとどうしようもないと思い、サポートセンターを運営している。 茨城空港ではLCCを積極的に導入している。今ではLCC(Low-Cost-Carrier)が世界中で普及し有名になってきているが、昔は知名度が低かった。現在、ヨーロッパでは36%、アメリカで28%、アジアで16%がLCCとなっている。LCCは3時間以内の便が主流で、昔風のサービスをなくしている。例えば、弁当も希望者が購入するようにし、今までは欲しくない人も料金に含まれていた点を解消した。飛行機で弁当を食べてゆったりするというのは、飛行機に乗ることがステータスシンボルだった時代の遺物で、今は早く安全に行ければ良いという時代になっている。 日本でもこれからは近距離のLCCが爆発的に増えていくと思う。中国にある唯一の民間航空会社である春秋航空が茨城空港に入ってきて、上海と茨城空港の間を限定で片道4000円で飛んでいる。茨城空港は東京から遠いと言われるが、東京駅八重洲口から茨城空港まで500円で乗れるバスを運行している。サービスを切り捨てた低価格のスタイルが日本にも普及すると思う。 茨城空港の特徴は、ターミナルビルの設計を徹底的に改善したことで、ボーディング・ブリッジを使わないで済むようにし、搭乗後のプッシュ・バックも不要にした。フロア・マネージャーの人数も少なくて済むようにした。いろいろなことに取り組み、徹底的にLCC仕様にしている。これからどうやって活用していくかが重要である。 神戸空港へは茨城空港から最安5800円で来ることができ、神戸便は大変人気となっている。
世界では今までの発想では考え付かないような変化が起きている。これからは日本での職場がどんどん減っていくかもしれない。今これだけの円高が続いており、国内で製造したのでは国外では商売ができないという厳しい時代になっている。そのようなことを見ながら、これからどのような勉強をし、仕事を選んでいけば良いのかを考えていってほしい。 あえて申し上げるとすれば、国際感覚を是非養ってほしい。学生時代にどこでも良いから海外に1〜2回行って欲しい。また、英語がしっかりできて、さらにもうひとつくらいの言語が出来ないと世界ではやっていけないという時代になっているため、プレゼンテーション能力をしっかりと養ってほしい。最近海外で働きたくないという人が増えているが、このような傾向が続いたのでは日本はやっていけない。アジアだけではなくアフリカとの連携も必要だと思う。これからの日本をどうするかということを考えていってもらいたい。
<問> アフリカという話があったが、アジアとの連携を強めるのが大切ではないか。 <答> アジアは当然で、もっと大事にしていかないといけない。しかし、これから猛烈な勢いで動き出そうとしているが、諸外国とのつながりがまだそれほど密接ではないという点でアフリカがあるのではないかと思う。つくば大学はアフリカに事務所を作って、アフリカのいろいろな国を訪問し、日本との関係を良くしようという取り組みをしている。アジアは当たり前で一番大事だが、その先を見ていかないといけない。当たり前のことを考えていたのでは遅れてしまう。 <問> 茨城県として教育に関して取り組んでいること、取り組みたいと思っている政策があれば教えて欲しい。 <答> 理数系に力を入れないといけないと思っている。県立の学校でも理科系のコースを設置している。先生が理科をあまり知らないという状況もあるため、小学校の教員を採用するのに、中学校の理科の免許を持っている人を優遇する制度も始めた。つくばの研究者が子どもたちのところに出向き、子どもたちに理科の面白さが伝えるという取り組みもしている。理科系を伸ばさないと日本は大変になると思っているので、その点の強化をしている。英語と数学は置いていかれると後で追いつけないが、数学では小学校4年生あたりから差が出るため、夏休みに5日ほど登校してもらい、教員志望の大学生の協力を得て能力に合わせた個別指導を行うなどしている。 <問> 政策を進めるには、他の県との協力や、国との協力が必要となってくると思うが、協力している相手があれば教えて欲しい。 <答> 国とは常に協力体制にある。例えば、つくば大学などと協力して研究を行っている。隣県との関係では、観光分野で協力している。外国人が観光に来て、茨城県だけで満足して帰るということはない。中国の人で多いパターンとして、関西空港に降りて、大阪観光をし、その後東京観光をして茨城空港から帰るというものがある。協力して観光メニューを作っていかないと人が来てくれない時代となっている。 |
|||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |