 |
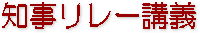  |
|
| 2010年 11月 2日 広島県 湯郫英彦 知事 |
||
「 新たな広域自治体のあり方 〜進化論的モデルによる活力創出〜 」
私は、平成2年に通産省(現 経済産業省)に入省し、その後スタンフォード大学のMBAを取得し、1998年からアメリカのシリコンバレーのベンチャーキャピタルというファンドに通産省から出向していた。 ベンチャーキャピタルとは、創業後間もない会社に投資をし、その会社が大きくなり株式を上場したり、大企業が買収をしたりして、投資した時より高い株価となったときに、株を買ってもらい利益を出すというものである。また、ベンチャーキャピタルは、ベンチャービジネスが大きくなる度にいろいろな手助けもしている。シリコンバレーはベンチャーキャピタルのメッカと言われている。 日本に戻った後は通産省をやめ、アッカ・ネットワークスというADSLを提供する通信業者を立ち上げた。アッカ・ネットワークスはソフトバンクやイーモバイルといった会社と一緒に、日本全国にADSLネットワークを提供していった。2005年に上場したが、2008年に私は退いた。 その後、2009年11月に広島で県知事選があり、当選した。
地域主権について話す前に、今の社会的な情勢の基本認識について話したい。 県政を行うにあたって、最も重視をしているのは、人口の動態である。人口がどう動いていくかということが、いろいろな政策を考える上での非常に大きな視点となる。この問題を考えずして他の問題を考えている場合ではないと思っている。 ピーター・ドラッカーという経営学者が、1950年代にGMのコンサルタントをしていた。GMは当時世界で最大の企業で、最も自動車を多く生産していた。経営の最先端を行っていると言われていた会社であった。1960年くらいにドラッカーは、GMはいずれ潰れるだろうという予想をした。GM自身にもそのようなアドバイスをしたが、あまり変わらず、実際最近潰れた。 ドラッカーは、政治家であれ、企業の社長であれ、社会のリーダーが気にすべきことは第一に人口の動きであると言っている。これはまさにその通りである。 広島県の人口は、平成10年に288万4千人でピークを迎え、ピークから平成20年ころまではほぼ横ばいとなっていた。しかし今、人口が減り始めている。 これが将来どうなるかを推測すると、平成47年には239万3千人になり、ピーク時から50万人人口が減ると予想されている。 少子高齢化とよく言われるが、人口が50万人減っていくのである。広島県には、広島市という110万人の人口を抱える第一の都市、福山市という46万人の人口を抱える第二の都市があるが、50万人というと広島県から福山市が丸々無くなるくらいのインパクトがあると言える。 日本全体では9000万人弱の人口となり、2000万人ほどいなくなる計算となる。このようなことが向こう25年の間に起こる。25年と言っても意外と早いため、この人口の減少を何とかしないといけない。 高齢化という点では、生産年齢人口が、平成12年では割合は66.7%で人口の3分の2だったが、今から25年後の平成47年には55.8%となると見込まれる。 平成12年には老年人口1人を生産年齢人口3.6人で支えていたものが、平成47年には1.6人で1人の高齢者を支えることになる。 1.6人は全生産年齢人口で計算したときの値だが、日本では結婚した女性の半分は働いていない。そのため、女性の労働力率が変わらなければ、働いている人1人で高齢者1人を支えることになる。 そのような状況の下でも、固定的に維持しなければならないものはたくさんある。例えば、教育がそうである。子どもが少なくなり、極端に言うと学校はどんどんいらなくなってきているが、田舎で生徒が少なくなったため学校をなくすと、地域社会が成り立たなくなってしまう。田舎に住んでいれば医者がいないのも当たり前だから病気に罹っても我慢しなさい、というわけにはいかないため、固定的にかかる社会コストはかなりある。これらをきちんとサポートしないと社会は成り立たないが、インフラを維持するためにはもっと稼がないといけない。 人口全体が減るため、1人あたりの所得を25年以内に今より15%増やさないと、今後このようなサービスを維持していけないのである。 菅総理大臣が、「強い経済、強い財政、強い社会保障」ということを内閣交代の時に言ったが、それぞれ順番に意味を持っている。菅総理はもともと社会民主連合にいて、要するに大きな政府で社会保障をどんどんやるという思想にもともといた。しかし今は、現実的となり、「経済」を一番に持ってきた。経済を何とかしないと今後まわらなくなる。今と同じ所得では、高齢者の生活水準が切り下がるか、生産年齢人口の生活水準が下がるかのどちらかとなる。そのために強い経済が必要であると言っている。
広島県では、「人づくり」、「新たな経済成長」、「安心な暮らしづくり」、「豊かな地域づくり」の4つの挑戦に取り組んでいる。無い袖はふれないため、まずは経済成長に取り組んでいかないとならないとして取り組んでいる。人づくりは一朝一夕ではできず10年20年の時間がかかるが、人づくりはすべてのことのベースとなるため重視している。
現在は社会経済環境の変化が地域社会に負の連鎖を起こしている。地域社会、要するに田舎は疲弊していて活力がない。一方で、栄えているのは東京である。京都や広島には東京の六本木ヒルズのようなビルは一棟もないように、関西などは地盤沈下を起こし、一方で東京が発展しているのである。 これからは、地方が自分達の力で発展していかないと、日本全体が立ちゆかなくなるのではないかと思っている。これまでは東京にどんどん人を送り込み、税収や経済力を生み出し、地方に戻していた。集団就職をした人が東京で富を産み、公共投資や地方交付税で地方にお金を回していたのである。しかし、地方は今稼ぐ術を失っている。 小泉改革は地方を崩壊させた地方は小泉改革のせいで崩壊したと言われるが、実際はほとんど関係ない。 地方はどんどん人口が減少しているため疲弊しているのである。なんとかお金を回すことでこれまでは取り繕っていたが、今はもうどうしようもなくなっている。その証拠が国の何百兆円という借金である。赤字が莫大にふくらみ、首がまわらなくなり、成り立たなくなっている。地方への再分配もできなくなっている。 人口は引き続き三大都市圏に集中している。日本の出生率がある程度あった時には地方もそれなりに増えていたが、今は人口減の社会で、地方は人口が減っている。システム自体が破綻してしまっている。しかし、システムは破綻しているが、システム自体はまだ動いている。これがさらに進むと田舎では人口がさらに減っていくことになる。 日本が成り立たなくなっている中、これから必要なのは、国が中央から全てをコントロールして地方に再配分するというやり方から、地方がそれぞれ自分でどうやって活力を生んでいくのかを考えて動いていくこと、それが地方分権である。 中央集権によって富を東京に集中させ、それを再配分する仕組みとしての霞ヶ関があった。勘違いがあるかもしれないが、これをやってきたのは霞ヶ関だけではなく、永田町も一緒なのである。国会議員が霞ヶ関を批判しているが、そのシステムを作ってきたのは永田町も一緒で、永田町の役人と霞ヶ関の国会議員がセットでやってきて、破綻している。 今このシステムを変える必要がある。地域が自立的に発展できるように、霞ヶ関と永田町の権限と財源を、最適化していくことが地域主権の本質だと思う。 しかし、何故地域主権をやらないといけないかということを真剣に議論しているところは少ない。これまでのシステムがうまくいっているのなら変える必要ないが、うまくいっていないため変える必要がある。 中央に全て集めて再配分するというシステムはもう成り立たず、必要とされる新しい仕組みが地域主権である。それによりそれぞれの地域の最適条件の設定による活力創出をする。内容は地域毎に違い、例えば広島や中国地方では自動車産業が多くあり、これを発展するように応援していくことができる。東北で自動車産業を応援するといっても応援する対象がない。このように当然やることが違い、地域毎の強みにあったことをして、経済発展をめざしていくことが一番である。
20年くらい前までは、日本は欧米と比べいろいろな面で遅れていたため、欧米のモデルがある意味正解で、それに対する処方箋を考えていれば良かった。 しかし今は、日本は最先端にいるため、モデルが分からない状態となっている。目指すべきものを作ってそれが失敗したらどうしようもないことになる。もっとたくさん目指すべきものを作って、地域が地域毎にいろいろとやっていくと、失敗するところもあるが、うまくいくところもある。そのうまくいったところを真似すれば良い。うまくいくものが生き残るというのが進化論的発展ということである。 多様性を日本の中に生んでいくことが重要で、それを行う上では地域が総合力を発揮しないといけない。 人づくりを考える上で、広島に人が定着してほしいと思っている。少し前までは広島は若者が集まる県だったが、今の20〜25歳くらいの年齢層を見ると、年間2600人くらい人口が流出している。これを止めようと思うと、もちろん就職してもらわないといけない。しかし、職業ももちろんだが、良い家がもてる、子育てがしやすい、良い教育が受けられるということも必要となる。それは、都市政策や福祉政策などあらゆる政策に関係してくるため、何かをしようと思うと総合的に取り組まないといけない。そのための総合的な権限や財源が必要になる。 現在は変化が激しく、間違ったらすぐに違うことをしないとならないため、政策の弾力化、迅速化が必要である。中央では地方が何をやっているか分からないが、広島にいれば広島のことはすぐ分かる。なるべく身近なところでマネジメントスパンを小さくすることが必要である。 京都の偉大な経営者である京セラの稲盛会長は、「アメーバ経営」ということを言っている。企業が成長して大きくなると、マネジメントすべき範囲を小さくし、いくつもの集団に分けてマネジメントしていくということがこれから求められている。最適化とは、地域に合ったビジネスを展開していくということを意味する。 これまで行政システムには競争というものがなかった。国は一つしかないし、都道府県同士が競争をしているわけでもなかった。基本的に国が決めるため競争のしようがなかったということが大きな失敗のもととなっている。公務員が問題だという話が出てくるが、その問題の根源も競争がないということにある。いかにこの仕組みの中に競争を持ち込むかということが大事だと思う。 日本の中が5〜10くらいに区切られて、それが自分で好きなことをやると、自治体間が競争する。法人税や所得税をどうするかということを考えても、まず企業を自分の自治体に来てもらおうと思うと法人税を下げる。日本は国際的に法人税が高いと言われている。そうすると無茶苦茶なことになるという学者もいるが、私はそうは思わない。 税が0で成り立つわけではないから、どこかから取って落ち着くことになる。各団体が、法人税を下げて勝負するか、研究開発を後押ししてサポートするのかということを真剣に考えるようになる。 今でも霞ヶ関はかなり真剣に考えているが、頭は一つで考えている。これを、地方が5〜10の頭で真剣に考えるようになると、より良いものが生まれる可能性がより高くなる。 これはポートフォリオ理論と呼ばれる。ポートフォリオ理論は、株式投資で発展した理論で、どれがうまくいくかということは予想できないため、一番儲かる確率を高くしようと思うと、全てにまんべんなく投資すると良いというものである。 地方自治体の中にもある程度ポートフォリオ理論は適用されると思う。何かやるとしたら土地、住宅、交通、福祉、環境政策など、すべてやらないと総合的に政策は考えられないため、なるべく自治体に自由度を与えていくことが必要である。 昭和50年の政府の予算規模は15兆円だったが、今では53兆円で、約3.5倍となっている。事業仕分けでがんがんやれるのもそのはずで、公務員の数は減っているにもかかわらず、マネジメントスパンが大きすぎる。今では大変な種類の福祉手当があり、それぞれがどうなっているか管理できない。細かく区切って地方に渡したほうが地方はしっかり見ることができ、正しいか間違っているかの反応もすぐ帰ってくる。 違う仕組みが日本全国に47あると大変で、企業や住民も混乱するため、せいぜい5〜10だと思う。あまり減ると競争の意味がなくなる。逆にあまりにも多いと日本が分裂してしまうかもしれない。5〜10程度にするとある程度のまとまりが出てくる。 中国地方は5県あわせて760万人の人口がおり、人口的にはほぼスイスと同じ。しかし、中国地方のGDPは2610億ドルだが、スイスのGDPは4340億ドルである。 スイスは資源があるわけでもないにもかかわらず、中国地方の倍程度のGDPを持っている。関西だけでもヨーロッパの中規模の国に匹敵するくらいの大きさがある。 日本という中央集権に従属しているため、我々は低いところに甘んじている。一人当たりGDPでは広島県は日本のほぼ平均で、広島県は全都道府県で10番目だが、あとは全て平均以下となってしまっている。ある程度まとまりを持って取り組まないと日本の再発展はないのではないかと思っている。 その実現に向けた取り組みを広島県では今行っている。関西広域連合もそのような取り組みの一つと言えるだろう。 暗くなるような話をしたが、本当に暗くなるかはこれから何をやるかにかかっている。関係ないと他人事にしていたら、自分たちが一番苦しくなる。
<問> 私は、広島の出身で、知事は育児休暇を取ったと聞いているが、育児休暇を進める政策についての話を教えていただきたい。 <答> 人口が最も重要だと話した。少子高齢化で労働力が減るなかで、何が必要かというと、少子という問題を少しでも改善しないとならないということである。生まれた子どもは大事に育てていく。一人も無駄にできない。子どもをきっちり育てて社会の役に立つようにしていかないとならない。できれば少子化にも歯止めをかけてもっと子どもが生まれるようにしていきたい。女性の労働市場への参加も大きな課題である。子どもを増やし、女性が労働市場に参加するためには、子育てを女性がやっていれば良いと考えるのではなく、社会全体で支えていかないとならない。それにより、子どもを増やし、女性は職場に戻っていく。 子育て支援ということは、これから先20年、30年を考えると非常に重要だが、男性が育児に関わることへの意識が低いのが現状である。 論争を見ても、「子育てなんか男がやるものではない」という意識が根っこにある。この意識を変えることは非常に大きな仕事だと思う。 <問> 以前岡山県知事が中四国州についての話をしていて、今日の話に関連していると思った。広島県も道州制に積極的なのか。 <答> 名称は別として、道州のように都道府県を大括りにしていかないといけないとは思っている。 <問> 道州制についてどう考えているかをもう少し詳しく教えていただきたい。 <答> あえて道州制という言葉を使わないのは、道州制とはどういうことかが定まっていないためである。中身はかなり自立した行政ができるような権限と財源を地方に与えること。与える先は従来の都道府県の枠をもう少し大括りにして、日本国内で5〜10にしていくことが必要だと言った。それに道州制という名前をつければ道州制になると思う。大事なのは名前をつけることではなく、中身を作ることなので、あえて中身の話だけをした。 <問> 広域連合についての話を聞きたい。広域連合では複数の都道府県が一緒になって行政を行うことになる。その中で、多少力の強いところが中核となり新たな産業を興していったりするのか、アメーバ経営のようにもっとバラバラで動けるようにするのか、というあたりはどう考えるのか。 <答> 難しい問題だが、良い質問だと思う。日本を5〜10に分けてその中にそれぞれミニ東京を作るのかという話になるが、ある程度集積が地域には必要だとは思うが、東京のような極端な集中はいらないと思う。ある程度集積をしないと生まれないサービスもあるため、ある程度の集積は必要だと思っている。 |
|||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |