 |
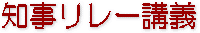  |
|
| 2010年 11月 9日 徳島県 飯泉嘉門 知事 |
||
「 「徳島の挑戦」 ~ピンチをチャンスに~ 」
今は100年に1度の経済危機真っただなかだが、このようなピンチのときにこそイノベーションをはじめいろいろなチャンスが転がっている。ピンチはチャンスというのはなぜか。口で言っているだけでは意味がないので、徳島が行ってきた今日的な挑戦を基に説明していきたい。
1.「糖尿病死亡率」改善への挑戦 皆さんは若いから、糖尿病は関係ないと思うかも知れないが、日本は今や糖尿病大国である。飽食の時代で、一人一台車を持つ社会になっており、運動不足が横行している。徳島県は、平成5年から平成18年まで14年 まずは原因を究明しなければならないが、その一番目はやはり食べ過ぎであった。徳島県は近畿の台所でもあり、おいしいものがたくさんあるという食の宝庫でもあるが、しっかりとカロリー計算をして美味しく食べるようにする必要がある。そのための取り組みとして、栄養士とともに、「ヘルシー阿波レシピ」を用意したり、「ドクターズキッチン」として食育フェアを行ったりしている。 原因のもう一つは、運動不足である。徳島県は、男性も女性も統計上一日の歩数が全国平均より1000歩少なく、これでは当然運動不足になる。しかし、徳島には世界に誇る阿波踊りがある。阿波踊りをもじった阿波踊り体操を広げたり、ウォーキングや走ることが大事という点では、東京マラソンに負けない徳島マラソンを開催したりしている。 2.世界的な「糖尿病研究開発・臨床拠点」の形成 このような取り組みの甲斐があって、平成19年にはワーストワンを脱却してワースト7となったが、少し安心したのか平成20、21年には再び全国ワーストワンになってしまった。根本的な対策が必要だろうということで、徳島県から徳島大学の病院に委託するという形で、糖尿病の対策センターを設置し、本格的に医療面から対策を行っている。 これだけ糖尿病が多いからには、このフィールドを活用しない手はないだろうということで、文部科学省の競争的資金である「地域イノベーション・クラスター事業」に対し、糖尿病をテーマとした「徳島健康医療クラスター構想」を打ち出して採択された。 今では徳島は世界的な糖尿病の研究開発、臨床拠点という位置づけとなっている。県内の医療関係者、大塚製薬など多くの医薬メーカーと共に、研究開発をし、商品化にも取り組んでいる。 3.糖尿病治療をベースとした「医療観光の創造」 糖尿病の研究プロジェクトでは、最先端の治療法の開発も行っている。「世界に向けて」というのがテーマとなっているため、友好提携をしているドイツや中国やアメリカの大学とも一緒に取り組んでおり、徳島の人々の治療をすることはもちろんだが、こうしたパワーを世界に向けて発信をしてはどうだろうかと考えている。まさに「ピンチをチャンスに」である。 今の糖尿病の世界的な状況は、日本だけでも予備軍を含めて2000万人も患者がいるという状況で、世界にいたっては約3億人もいる。また、2030年には4億人をはるかに突破するだろうと見込まれており、その半分以上がアジア型と見込まれている。それならば、アジアの人々に徳島の知見をピーアールしていってはどうだろうかと考えた。糖尿病の治療に徳島を訪れていただくだけではなく、鳴門の渦潮、阿波踊り、阿波人形浄瑠璃など徳島の文化も体感していただくという、「糖尿病をテーマとした医療観光」に現在取り組んでいる。 この取り組みのピーアールが必要だろうということで、今年5月から始まった上海万博では近畿の府県と共に、徳島のブースを出し、この中で医療観光を大いにピーアールした。阿波踊りも連れて行き、5月下旬に「徳島ウィーク」を設定して徳島のピーアールや医療観光の相談会を行った。ここで実感を持って、医療観光が商売としても成り立つと思ってもらわないとならないため、万博に先立ち3月20日~23日までチャーター便を用意し、中国からのモニターツアーを行った。 このモニターツアーでは、研究開発の中心となっている徳島大学に検査メニューを作ってもらった。また、検査だけでなく、歩くのが大事なので、歩いて回るのに適している観光名所として、大塚美術館などを取り入れた観光メニューも作った。このツアーにはマスコミ関係者、旅行会社の関係者、糖尿病患者が参加し、中国に持ち帰り大いにピーアールをしてもらった。 実際のツアーの第一弾として、5月に中国からの旅行者の企画ツアーが訪れた。10月に入ると、徳島大学が作った研究メニューを、県内の民間の医療機関も対応するようになり、この取り組みを民間の医療機関にまで対象を広げることが出来た。 4.中国人「先客万来」プロジェクトの展開 中国のみなさんを医療分野だけでなく、どんどん呼んではどうかと考えている。そのための環境も昨年7月に整った。それまでは中国では個人観光が解禁されていなかったが、それが解禁されるとともに、昨年の7月には富裕層を半年に限って、今年1月からは中国全土の中間層までも対象となり、対象人員が10倍に拡大された。 中国の人々にどんどん徳島に来てもらおうということで、銀聯カードの導入を進めたり、案内板に英語表記、中国語表記、ハングル表記を加えたものを用意していったりした。そうすると、中国の湖南省から是非友好提携を結びたいという話もいただいた。今では友好提携に向けて調整を進めている。 5.「教育旅行」の創造 医療観光をテーマにするだけではなく、もう一つ海外へ向けての目玉商品を用意しており、それは教育旅行である。 徳島県の南部では、美しい海を対象として、アウトドアスポーツや漁業体験ができる。四国の中央にあたる県西部にはラフティングのメッカである吉野川がある。こうした形で特色のある海洋型・内陸型の体験を、国内の修学旅行を対象にどんどん誘致している。利用した学校は、平成18年には1校だったものが、平成21年度には23校となり、1900人を超える修学旅行生を誘致することができた。 これをアジアに広げてはどうだろうかということを、海外からの教育旅行の創造として考えた。 その第1弾として7月には中国の天津から、第2弾として8月には韓国から741名の学生が訪れた。このような取り組みによって、まだ修学旅行が制度化されていない中国、韓国の人々にどんどん徳島に来てもらいたいと思っている。また、徳島から橋を渡ることで、京都や神戸や大阪という観光のゴールデンルートもたどることができるということもあわせてピーアールしようと進めている。 糖尿病死亡率ナンバーワンというピンチを、今では日本の成長戦略である医療観光のモデルケースを担うというチャンスに変えたのである。
1.徳島県のテレビ事情 徳島県は放送法上、四国放送とNHK2波の3波しか見られない県となっているが、実際にはそのようなことはなく、関西の放送も見られる。チャンネル数としては、大阪や東京よりも多い。 2.「地上デジタル放送」導入による影響 2011年7月24日に地上デジタル放送に完全に移行すると、大きな問題が生じる。徳島県はアナログ放送のため関西波が見られていたが、デジタルになると見られなくなり、10波あったものが3波になってしまう。日本全体のテレビが便利になるという機会が、徳島県にとってはピンチとなった。 この問題をクリアするために、徳島県では全市町村にケーブルテレビを張り巡らせ、ケーブルテレビで地デジの対応をしようと平成14年から取り組んでいる。その結果、地デジでも10波が視聴できるようになり、また、ブロードバンド環境、IP電話の環境を手にすることができた。それらのネットワークを使い、修学旅行の情報や、災害の情報なども流すことが可能である。徳島には「葉っぱビジネス」で有名な上勝町があるが、そこでも光ファイバーのインターネットを使って受注をしている。 3.「ひかり王国とくしま」の創造 ケーブルテレビは大都市部を対象に有料でサービスを提供するため、都市部を中心に普及しているが、徳島県では、平成22年度中には全市町村で整備が完了する見込みである。 統計データでは、平成22年3月末で全県の70.3%に普及しており、全国では第5位となっているが、来年になるともっと普及率が上がる。これら全てを光ファイバーでひいているため、地方公共団体の持っている光ファイバーの延長は全国で第3位となっている。県民一人当たりで見ると延長は1位で、まさに光王国と言える。 4.「ICT関連産業」の立地促進 (1)「コールセンター・データセンター」の誘致拡大 徳島県では、ICT関連産業の立地促進にも取り組んでいる。コールセンターなどICT関連産業の誘致を決めた平成15年当時では0社だったが、平成22年10月末には9事業所となり、720の雇用が生まれた。特に、若い女性の働き場所となっており、大勢の女性がコールセンターなどで働いている。また、企業に対しては全国屈指の優遇制度も設けている。 (2)「デジタルコンテンツ産業」の育成 地デジやブロードバンド化が進むと、その中身であるデジタルコンテンツが勝負となってくるが、今は地デジ化をした後に、それに対応するだけのソフトがない。そこで、デジタルコンテンツ産業がこれから大きく伸びゆく産業だと言われている。 徳島では、デジタルコンテンツの中でもアニメに着目して、コンピュータグラフィックの制作会社を誘致していこうと取り組んでいる。さらに、大きなイベントも作ってもらおうということで、県とユーフォーテーブルという会社と協力する形で、秋・冬にアニメを核とした「マチ☆アソビ」という企画を実施している。そこでは普段は素顔が見えないのが魅力でもある声優の方々に頑張っていただいている。 このようなイベントは東京以外では絶対に成功しないだろうと言われていたが、それを覆し、逆に地方での良さを打ち立てた。今では各地でこのようなイベントをやってみようという動きが出てきている。 また、ただ企業を誘致するだけでなく、誘致をした企業に県内の人々が従事すべきでないかということで、県内の学校に対してデジタルクリエイター養成講座を行ってもらったりしている。新しいデジタルコンテンツクリエイターをどんどん育成することを県としても強力に進めている。 地デジ化によってテレビが見られなくなってしまうというピンチをチャンスに変えた。
1.往年の日本の成長産業「林業」の衰退 京都を代表する下鴨神社は鎌倉時代に造られたが、その建築の際に徳島県産の木が寄進されたという記録がある。また室町時代には兵庫県の北関の港に、阿波の船が年に122回も入港しており、積み荷のほとんどが木材であったと記録されている。このように、京都、大阪、神戸などの木材の建物は多くが徳島の木材で造られている。 江戸時代に入ると、藍染めの産地である徳島では、藍染めが50万石もの富を支えていた。藍商が、財力を活用して材木商も営んでいたときに、まずは大阪に進出し、阿波座の開発をした。大阪の地下鉄中央線の大阪港駅の次は阿波座駅である。いくら四国と近畿が近くても、土佐座も伊予座も讃岐座の駅もないが、阿波座はこうして昔から親しまれていた。東京では木場にいち早く進出し、関東の阿波踊りもこの木場から伝わって広がっていった。 昭和期に入ると、阪神市場でスギ薄板の8割を席巻し、昭和30年代にはマイホームブームで木材の需要が逼迫した。国民生活を圧迫するまでになり、ここが隆盛のピークであったと言える。外材がどんどん入ってきたため、ここから一気に下落をしてしまう。薪・炭からガスに転換し、木が見向きされなくなったということもある。 2.森林・林業を取り巻く環境変化 1ドル360円の時代から、変動相場制が昭和48年に入り、円がどんどん高くなっていき、平成6年には100円を割った。こうなると、どんどん外材が入って来ることになり、昭和44年には木材の自給率が50%を割った。そうなると、従事者がどんどん減少し、山の放置が進み、林業の崩壊につながることになる。平成20年には木材の自給率が24%にまで低下した。 徳島は県面積の75%が森林で、民有林が多いという特徴がある。全国平均では民有林は58%だが、徳島県では89%を占める。これまで近畿をはじめとして関東の木材市場を支えた徳島の森林だが、このような状況になると、商売が成り立たなくなってしまう。商売が成り立たなくなると、大変なことが起こり、山の所有者が山を放っておくようになる。それらの木は根が張っていないため、災害が起きると一気に崩壊してしまう。また、川をせき止め二次災害が起こることになり、本当に手がつけられなくなっている。 平成15年以降国際的に大きな動きが出てきた。一つ目は、木材資源の囲い込みが熾烈になってきたということである。ロシアが木材に対する関税を引き上げたり、中国がどんどんロシア材を買い上げたりするようになってきた。そうすると、ロシアの木材が日本に入ってこなくなる。 また、二つ目は、環境面の要求もあり、二酸化炭素削減のために森林を活用しようとしている。京都議定書での6%の削減目標のうち、3.8%を森林で削減すると国は打ち出しており、二酸化炭素の削減分を排出権取引で温暖化への対応を企業が取るという形も導入されている。そうなると、商社も南方で木を切るよりは木を植えた方が得な時代が来る。 これらをあわせると、北からも南からも外材が入って来にくいという状況が日本に起こる。徳島ではそのような状況を先取りしようと、息絶え絶えだった林業をまずは再生することに取り組んだ。 3.「林業再生」へ「徳島発」の挑戦 平成17年から、徳島県では林業再生プロジェクトへの挑戦に取り組んでいる。最初は誰も見向きしなかったが、川上と川下両方の手入れをしようとして取り組んでいた。 川下では消費の拡大を狙っている。良い木材も良くない木材も全て使うことにしている。あまり良い木材でないものは合板で使うために、工場を誘致している。また、山で働き、木を切り出す必要もあるため、高性能林業機械の導入をした。若い人々にも参加してもらっている。 川上と川下と両方で対応することで、林業の再生を図っている。生産力もどんどん増強しており、高性能機械の使用前と使用後で3倍にまで増えた。材料の供給体制が整ったなら、木をどんどん使っていこうということで、「根っこから梢まで」を合い言葉にして、全て使うための取り組みをしている。良いものも悪いものも全て使うようにし、従来は捨てられていたものも、チップ化をして合板に加工している。 4.再生から「飛躍」へ、攻めへの転換 徳島では需要から供給まで一貫して行い、今では新規の就業者が130を超えるとともに、公共事業が目減りするなかで、建設業から林業に入る手助けもしている。さらに、需要を拡大するために、県が発注する工事の中にどんどん県産材を使っている。 また、ガードレールを木製にし、徳島を訪れた人に木のぬくもりを味わってもらおうとしている。さらに、徳島で産出される木の付加価値を高めるため、県独自の認証制度も導入している。 5.「環境の世紀・21世紀」への「徳島モデル」構築 これからは林業だけでなく、山というものを考えていこうとしている。21世紀は環境の世紀ということで、徳島モデルを構築しており、まずは公有林化を進めている。このことは、今、中国などの海外資本が日本の山をどんどん買おうとしているが、これに対しての防衛ともなる。 さらに、地球温暖化に正面から取り組むため、中四国では初めて、地球温暖化対策推進条例を制定した。同時に、カーボンオフセットを強力に推進し、これにより企業とパートナーシップ協定を結んでいる。 国では林業を新成長戦略に位置づけているが、徳島はその最先端を行こうとしている。産業と環境がマッチした徳島発の取り組みをしており、まさにピンチをチャンスにであると言える。
1.「三位一体改革」の激震 三位一体改革とは、平成16年度に小泉元首相の時代に行われた改革である。地方分権を一番縛っているのは霞ヶ関の権限・補助金行政であると有識者に言われたため、国は補助金行政を緩和し、その分だけ国税を減らし地方へ税源を移譲するということを行った。地方が自由に使えるように、補助金は減るが、国税を減らし地方税を増やすという改革を行ったのである。これと併せて地方交付税の改革も行われた。地方交付税とは、国が一旦取った税金の一定割合を、地方の固有の財源として再配分を行うというものである。地方公共団体がやりくりを行う上で一番の稼ぎ頭は地方税だと思うだろうが、実は多くの都道府県ではそうでなく、一番の稼ぎ頭が地方交付税であるという団体は32団体もある。全都道府県をおしなべて見ると、稼ぎ頭の内訳は、地方税は27.3%、交付税は33.7%が平均の割合となる。歳入の中で一番地方交付税に頼っている県は高知県で、歳入の50.9%が地方交付税となっている。 三位一体の改革により、一見地方の権限・財源が増えたように見えたが、財務省にしてやられたという感じである。稼ぎ手である地方交付税は、全国で23.9兆円あったものが、わずか1年で2.9兆円もカットされてしまった。徳島県では、1年で227億円もカットされてしまったという状況であった。これは、対前年で12.3%の減となった。都道府県の貯金にあたる財政調整基金を、平成15年度末と平成21年度末で比べると、487億円も減らす結果となった。地方交付税の227億円の削減は、行政的な歳出(サービス)を落とすことなく、歳入だけが減らされたのである。これが6年間だと1362億円も減ったことになる。財政調整基金で487億円なので、削減分の約3分の1は貯金で何とかしたが、地方交付税の削減により徳島県は大ピンチに陥った。 2.国に先駆けた「財政構造改革」の推進 今は、国でも財政構造改革などの議論がされているが、そんな流ちょうな話はしてはいられない。絶対に地方公共団体として払わなければならない経費を義務経費と呼び、これには人件費、扶助比(医療費、福祉、介護などの経費)、公債費(借金の返済)があてはまる。徳島県では人件費の削減に取り組んだ。 公務員は、地方公務員も国家公務員も、法律で身分が保障されているが、この人件費をなぜ下げることができたのかというと、まず職員数の削減を行った。私が知事に就任する前の平成10年から15年までの間で、114人削減し、削減率は2.9%だったが、就任後の平成15年から平成22年まで7年間で467人、12.3%の人員削減を行った。これは、早期勧奨退職を行ったり、「団塊の世代」の大量退職分の補填を少なくしたりするなど厳しい定員管理を行った結果である。 しかし、これだけでもまだ足りなかったため、平成20年度にいきなり10%ほどの給与カットを行った。国家公務員の給与水準を100としたときにラスパイレス指数は平成15年には全国22位だったが、全国でも最大級のカットを行った結果、平成20年にはラスパイレス指数は92.5となり、全国最下位となった。徳島県庁職員には大変申し訳なく思っている。 高齢化が進む中で、扶助費はうなぎのぼりとなるという状況がある。全体で見れば、義務的経費は右肩上がりになるはずだが、徳島県ではほぼ横ばいとなっている。 3.「既存施設の有効活用」で県民ニーズに即応 徳島県では、根本的に行政の質を変えようとしている。 今では、社会的な資本が成熟している。従来は知事でも市町村長でも、何か自分の代に何かを新しいものを造りたいというモニュメント行政だったが、地方公共団体は何でも新しく造れば良いというものではなく、既に建てられた日本の優秀な技術で造ったものは、耐震化をすると同時にリニュアールすることで、お金がない時代でも少ないコストでより性能を高めることができる。このよう考えて、徳島県では既存施設の有効活用を行っている。 (1)「県立郷土文化会館」の有効活用 県立郷土文化会館では、以前は椅子が小さく窮屈だったが、椅子を大きくして対応した。収容人員は少なくなるが、施設の面積自体を広げてカバーした。また、文化的イベントには女性のほうが多く参加するため、女性用トイレを拡大し、男性用トイレを縮小することもした。同時に耐震化を行っても、施設を一から造るのに比べ、3分の1から4分の1のコストで行うことができる。 (2)「県立青少年センター」の有効活用 県立青少年センターには、地下に大きなプールのある無柱空間があった。プールの耐震性について不安の声があがった時期があり、その時に別の場所に温水プールを造った。青少年センターのプールはなくし、スポーツができる場所や、音を自由に出せる場所が欲しいという要望があったため、このプールを改築して対応した。そこでは、建設だけでなく、全国でも珍しい維持・管理・運営まで含めたPFI方式を導入した。無柱空間の耐震化は大変難しいが、これも最新の技術を使って対応した。さらに建物のネーミングライツ(施設命名権)を活用し、地元の銀行の名前をつけた。 4.「とくしま“トクトク”事業」の推進 根本的に予算のあり方を変えようとするのが、「とくしま“トクトク”事業」である。予算の金額が多ければ多いほど良い事業だと今までは言われてきたが、そうではなく、金額の多寡ではなく、事業の中身で判断してもらおうというのが基本理念である。 3つの取り組みから成り立っている。一つ目は、職員の知恵・工夫で事業を造るという「ゼロ予算事業」というものである。二つ目は、今ではNPO団体やボランティア団体がたくさんあるため、このような人々のノウハウや人脈を活用して、県が直営でやっていたものを、何かは出すが、団体の活動にあった形で協力していただくという「県民との協働推進事業」である。三つ目は、企業から需要のあるイベントは、イベントのノウハウや会場は県が提供し、企業に経費をもってもらうという「県民スポンサー事業」である。 (1)「ゼロ予算事業」の事例 ゼロ予算事業の典型として、大阪府と広報誌の紙面交換を行っている。徳島県では、「県政だよりOUR徳島」という広報誌を約33万部発行しており、大阪府でも「府政だより」という広報誌を約340万部発行している。それぞれの同じ面積同士を交換しあい、お互いのピーアールに活用している。 (2)「県民との協働推進事業」の事例 河川の清掃や改修は、従来は県が直接行っていたが、住民の皆さんには草刈りをしてもらい、建設業者にはトラックを使って運搬をしてもらい、市町村はそれを処分してもらうというような形で協働推進事業を行っている。経費は県が持つが、一回当たりの単価を5分の1におさえ、回数を増やすことができた。 (3)「県民スポンサー事業」の事例 県民スポンサー事業の例として、道路の照明灯に広告を載せ、代わりに年2万円ほどの電気代を負担してもらうという取り組みをしている。このような取り組みは、公共的な維持管理の経費を抑えるのに役立っている。 5.「実証実験・モデル事業」の展開 今は、国も都道府県も新しいことをやることになかなかお金が出せない。しかし、駄目だと言われると、新しい試みをやってみたいという人の挑戦心は燃え上がるものである。今はチャレンジ精神が旺盛な時代であるため、成功する確率が高いと思う。そのような取り組みに、徳島県はどんどん協力しようとしており、実証実験やモデル事業という形で、やりたいという精神を応援している。 (1)実証実験の事例「コンビニとの連携による東京アンテナショップ設置」 今では全国の都道府県が東京にアンテナショップを持っているおり、徳島県も虎ノ門に持っていたが、東京都の都市計画で立ち退きにあうというピンチに直面した。どうしようか迷っているうちに、景気がどんどん悪くなってきて、アンテナショップはどこも苦戦するようになった。一から税金で新しい店舗を建てると税金の無駄遣いだと言われるだろう。 虎ノ門にはローソンの不採算店があった。そこでは、店舗面積が広すぎるというデメリットがあったため、徳島県と手を組んで取り組みを行った。 今までは公務員がアンテナショップを経営していたため、土日祝日は休みだったが、コンビニは24時間営業しているため、コンビニを訪れた人が徳島の商品やイベントのピーアールに触れることができる。このようなローソンとアンテナショップのシナジー効果(相乗効果)で、順調に売り上げがあがっている。 (2)モデル事業の事例「独立ソーラー式電動アシスト自転車普及モデル事業」 SANYOのリチウムイオン電池の世界最大の工場が、徳島空港近くの松茂の工業団地にある。このSANYOと組み、太陽光発電で発電したものをリチウムイオン電池に蓄え、それを用いて電動アシスト自転車を走らせるという取り組みをしている。これは昨年のエコプロダクツ大賞を受賞した。 今ではどんどん地方公共団体に普及している。このように、企業のやる気を引き出すとともに、行政のやってみたいことも実現するという時代に来ているのである。
今は本当に100年に1度のピンチの時代である。しかし、これを逆に考えれば、今までできなかったことが出来るということを意味する。新しい取り組みをすることで、徳島発展の礎を築くチャンスにするための転換期がきているのだと思っている。
<問> 医療観光の取り組みでも、林業の取り組みでも、徳島の外のお金を県内に持ってくるという方針だと思うが、その入ってきたお金をどのように徳島でまわしていこうと考えているのか。また、その仕組みがあれば教えてほしい。 <答> そこは大事なポイントである。日本全体の経済規模はどんどん縮小しているが、その中でも日本人は生活していかないとならない。自動車メーカーなどは生産拠点を海外に移し、円高リスクを避けるといった行動をとっているが、これができない業種もある。 典型的なのは、観光や医療・福祉の世界で、日本全体の経済規模が縮小するなかでも生きていかないとならない。それをしっかりと支えるのが行政の仕事だと思っている。昔は歯科医になり開業すれば銀行が開業資金を貸してくれたが、今では患者が減るだけではなく、患者の支払額も減っており、また、医療改革として診療報酬もどんどん削られている。そのため、歯科医でも年収300万円以下の人が3分の1もいる。これらの人々には銀行は融資してくれないため、県が貸し付けを行っている。 つまり、外からのお金を県民が生業を建てるためのお金に使っていくようにしている。 <問> 徳島県は交通分野が弱いと思う。交通の拡充についてはどう考えているか。 <答> 電車が走っていない県は日本に一つしかなく、それは徳島県である。徳島の場合はJRも電化がされておらず、高速道路も平成6年に出来た。交通基盤が弱いというのは図星だが、後発の利もあると思う。鉄道を電化するときには、今あるトンネルをパンタグラフの高さに合わせるために掘り返さないとならないが、それには莫大なコストがかかる。しかし、これからは機関車もディーゼルではなく電気機関車となり、パンタグラフもつけなくてよくなってくる。この機関車の試作車も出てきており、これからの戦略として、そのようなものの実証実験をどんどん誘致していこうと考えている。 大量のお金をかけられない時に、それをカバーするのは技術の高度化だと思っている。高速道路も、交通量の少ない所は対面通行にするなどしており、これからはコストを考えた公共事業の時代だと思う。後発の利を使い、いろいろな交通機関のモデルになっていきたいと思う。 <問> 禁じ手である職員給与削減をどのように行ったのか。それを行ったことによる職員の反発はなかったのか。 <答> 国家公務員では国家公務員法、地方公務員では地方公務員法の中で、どのような場合に給与を減らされるかが規定されており、これに反するため「禁じ手」であると述べた。 しかし、税収的な状況が許さない場合はやむを得ないため、職員組合との交渉を重ねて最終的に理解していただくという形で交渉を進めてきた。組合は職員の地位向上を図るものであるため、結果的にはやるなら勝手にやれという決着になった。しかし、組合もやはり県の職員であるため、最終的には大変さや県民の生活の厳しさも理解してもらえていると思う。今回は平成21年からの3カ年を対象にしているため、平成23年度からどうするのかが最大の焦点となっている。景気が悪く税収があがらないなど厳しい状況にあるため、どこまで県民の理解を得られる形で給与を少しでも戻せるのかどうかについても大詰めをするのがこれからの課題である。 |
||||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |