 |
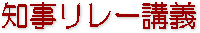  |
|
| �@ �@2010�N�@11���@30���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��s�@�|�R�C�g�@�s�� |
||
�@�@�@�@�����ɔ��u���R�E�����s�s�@��v�@
���́A��N�V���R���ɂR�S�N�ԋΖ��������{����ސE���āA �܂��A�����O���{�m���ƈꏏ�ɕ{���Ŏd�������Ă����B�������ېV���v�̈���Ƃ��āA����� ���̑I���^���ɕt���Ă��Ă��ꂽ�̂́A���̖���A���̕����̂R�l�������B�R�l�����ꂼ��̗F�l�A�m�l�A�e�ʂ֓���������Ƃ������̍��̑I���^���������B����ɂ͑����̐��}�����Ă������A���͂܂������̖��}�h���������߁A������Ǝv���Ă����B �X���[�K���́A�u
�Q�|�P�D ��́A�����n���������s�s�^���n�ŁA�C�O�E�����̎�v�n��ւ̃A�N�Z�X�����ɂ߂č����ꏊ�ł���B �l���͂W�R���X��l�A�ʐς͂P�T�O�����L�����[�g���ŁA ����`����͂Q�U���ŁA�C�O����֗̕������ǂ��B �Q�|�Q�D �Q�|�R�D���E����n��ɂ����� �Q�|�S�D ���ꂪ���Ȃǂ̐����ɂȂ���A���͐n���⎩�]�Ԃ̐����ɂȂ����Ă���B �Q�|�T�D �ՊC���́A��[��Ƃ�D�ꂽ���Z�p��L�����Ƃ��W�ς��Ă���B �s�S���́A�̂���̎s�X�n�ŁA���ƁA�Ɩ��n���`������Ă���B�܂��A�@�B�����H�Ƃ̏W�ς�����B �������́A������Ƃ𒆐S�Ƃ����H�ƏW�ς�����B�܂��A���{����w�⒆����Ƃ̎x���Z���^�[������B �u�˕��͗ΖL���Ȑ�k�j���[�^�E��������B�����ł͔_�Ƃ��傫�ȃE�F�C�g���߂Ă���A���{�̔_���Y�i�̈ꊄ�������Ő��ݏo�����B �@�@
�R�|�P�D�Y�ƐU���i��ƗU�v�{��j ��͊�ƗU�v��i�߂邽�߂ɁA��Ɨ��n���i���𐧒肵�A�Œ莑�Y�ł⎖�Ə��ł��ō��T���̂S���Ƃ��Ă���B�V�K�ɂU�O�O���~�ȏ�̌��������Ă�ꍇ�A���̂Q�O���ȏ�̐l �H�ꗧ�n�@�Ɋ�Â��������߂���ł́A���ŏ��߂ėΒn�K���̊ɘa���s�����B ���ʁA�F���Ƃ͂T�X�ЁA���������z�͖�X�O�O�O���~�A�ٗp�l���͂S�V�O�O�l�ŁA���̂����s�����Z�҂͂P�S�O�O�l�ƂȂ��Ă���B�N�Q�S�O���~�Ŏ����オ�錩���݂ŁA����łR�U�O���~�̌y�����s���Ă���B���̏��͂���ɂR�N�ԉ������A��̘p�݂̐�[����Ɠ������̂��̂Â���̋Z�p���h�b�L���O�������Ǝv���Ă���B �s�S�n��̋Ɩ��n�]�[���Ɏ��Ə��⋳��@�ւ�����ꍇ�A�⏕�����o���Ă���B��͂��̑��̓s�s�Ɠ����悤�ɓs�S�n��̋����n�܂��Ă��邽�߁A�ՊC���͌��C�����A�s�S�̌��C���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�s�S���Ɏ��Ə��������Ă��邽�߂ɁA�⏕�����o���A��������������Ƃ���������Ƃ��Ă���A���̌��ʂ��o�n�߂Ă���B �R�|�Q�D�ό��U���@�i�Ñォ��̗��j������̊ό������j ��͌Ñォ��̗��j�����ό���������������B���l�ȎY�ƁA�Y�i�̔��˂̒n�ŁA�m���V�c�ˌÕ�������ւ�S��A��������o�y���Ă���B���ݐ��E��Y�o�^��i�߂Ă��āA�b��ꗗ�\�ɋL�ڂ��ꂽ�B���E���炱�̌Õ��Q�����ɗ��Ăق����Ǝv���B �����ɂ͎��R�Ǝ����̓s�s�Ƃ��ėL���ŁA�痘�x���䂩�璃�̓�������n��A���{�ɍ��t�������B�M���A�G�g�䂩��̐_�Е��t������B�ߐ��ł́A��̑ł��n����������B���ł̓v�������l�̂W�O������̑ł��n�����g���Ă���ƌ����Ă���B ���j�I�������������A�R���ƂƂ����Z��͍]�ˏ����̏Z��ŁA�������莩�R�Ɋϗ��ł���悤�ɂ����B�ߑ�ł͗^�Ӗ쏻�q����Ő��܂ꂽ�B�܂��A���d�S���P�X�P�P�N�ɊJ�Ƃ����B ����͊����f���s�s�Ɏw�肳��Ă���A�N���[���t�����g���A�R�O�O�O���т̓d�͂��܂��Ȃ��郁�K�\�[���[������B�i�V���i���g���[�j���O�Z���^�[�����N�̂S���Ɋ������A���{��\�`�[�������[���h�J�b�v�֍s���O�ɂ����ŗ��K���Ă������`���痷�����čs�����B�\�z������������A�U�O�`�V�O���l�̗��p������B �R�|�R�D�ό��U���A�i�ό�����������������Ȏ��g�݁j ��̊ό��q�͌��ݔN�ԂU�T�U���l�ŁA�T�N��ɂ͂P�O�O�O���l�ɂ������Ǝv���Ă���A��̊ό��̒��S�ł�����j�����ό����\�t�g�E�n�[�h���ʂ���[�x�������Ǝv���Ă���B���̂��߂ɁA�痘�x�Ɨ^�Ӗ쏻�q���R���Z�v�g�Ƃ��āA�����E�ό����_����낤�Ƃ��Ă���B���E������Y�̔F��܂��������̂��߂ɁA�S�㒹�Õ��Q��m���V�c�˂̎��ӂ����Ă���B �܂��A��̐V�������͂����������j���[�c�[���Y���𑽖ʓI�ɓW�J���悤�Ƃ��āA�Y�Ɗό���X�|�[�c�ό������Ă���B�C���o�E���h�i�O���l���s�҂̗U�v�j�U���̂��߂ɁA�C�O����̐l���ǂ��Ăэ��ނ����l���Ă���A�C���o�E���h��������A�؍��A�����A�V���K�|�[���A�C���h�l�V�A�̃C���o�E���h�W�҂������čs���Ă���B���̌��ʁA��֍s���K�R�����܂����悤�Ɍ���ꂽ�B���̕K�R���Ƃ��Đm���V�c�˂���̎����ɂ������Ǝv���B �R�|�S�D���g����i�u�N�[���V�e�B�E��v�̎����Ɍ����āI�j ��s�ł̓x�C�G���A���u���x�C�G���A������G�l���M�[�E���Đ�����v�Ƃ��Ē�Ă��Ă���B�����ł́A�ŋ��������Ȃ�A���̑����I�Ȍ������ł��A�l�ވ琬���ł���B���̋Z�p���J���{�W�A�Ȃǂ̊O���ɓ`���邽�߁A�E����h�����āA�����P�{����l���Ă��炤�悤�ɂ������B�����������N�[���V�e�B�����肽���Ǝv���B ���̂��߂ɁA�l�ވ琬�v���O������C�O�Z�p�҂̎�����l���Ă���A���{����w�ƈꏏ�Ɍ������Ă���B
�S�|�P�D���ߎw��s�s�ւ̈ڍs�i�����P�W�N�S���j �S�|�Q�D �l���ł́A�����P�V�N�����łP�X�s�s���P�S�ʂƂȂ��Ă���B ����Ԑl���䗦�͂P�T�ʂŁA��͊֓����Ǝ����X��������B ����Ɛ��ł́A�P�V�ЂłP�U�ʂƂȂ��Ă���B��ォ��{�Ђ������ֈڂ�̂�h�����߂ɁA�I�[�����Ƃ��Ď��g�܂Ȃ��ƂȂ�Ȃ��Ǝv���B��ɂ��{�Ђ�������A������Ƃ����ł����肷��悤�Ȑ�����Ƃ��Ă��������B�ǂ̂悤�ȃC���Z���e�B�u�����邱�ƂŁA��ɗ��Ă��炤���Ƃ��ł��邩�A��Ő��܂ꂽ��Ƃ����ł��邩���l���Ă���B�������ɗ���K�R�������Ȃ��ƂȂ�Ȃ��Ǝv�����߁A�ʋ�̓I�Ȍ��������Ă���B �s�E���̐��ł́A�����Q�O�N�S���P���ł͂T�X�T�S���̂P�W�ʂŁA���ɏ��Ȃ��l���Ŏd�������Ă���B �����͎w���́A�O�D�W�P�łP�Q�ʂƂȂ��Ă���B�����͎w���Ƃ́A����������v�̂��ƂŁA��{�I�ȓs�s�Ƃ��Ă̎��v�Ǝ������ׁA����������ΖL���Ȓc�̂ł���ƌ�����B�����͎�ɐł����A�P���L�����̈�̃o�����[�^�ƂȂ�B �o����x�䗦�ł́A�X�S�D�U�łW�ʂƂȂ��Ă���B�o����x�䗦�Ƃ́A�`���I�Ȍo���Ŏ��Ȃǂ̌o��I�Ȉ�ʍ����Ŋ��������̂̂��Ƃł���B�`���I�Ȍo��Ƃ́A�E���̐l��������A�����ی��Ȃǂ̕}���������B�X�S�D�U�Ƃ������Ƃ́A������p�͂T�D�S�������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�A�P�O�O����Ɠ����I�o��O�Ƃ������ƂɂȂ邽�߁A����M���M���̂Ƃ���ł���B�l���s�͂P�ʂ̂W�U�D�P�ŁA�P�S�������I�o��ɂ܂킹��Ƃ������ƂɂȂ�B �����͎w����o����x�䗦������ƁA��͍����I�ɂ͂���قǖL���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�������B ��������䗦������ƁA�U�D�X���łQ�ʂƂȂ��Ă���B��������䗦�Ƃ́A�W���I�ȍ����K�͂̒��ɐ�߂����̊��������A ���č�̓��X�p�C���X�w���i���ƌ������̋��^���P�O�O�Ƃ����Ƃ��́A�s�����̌��������^�̎w���j���P�R�T�܂ōs���A���{�ꍂ���������Ƃ�����B���̎��͂ǂ�ǂ����s���A�����j�]�������B �����j�]�����o���܂��A�s�v��i�߂Ă��Ă���B �S�|�R�D����܂ł̍s�������v�̎�g ����܂ōs�������v�𑱂��Ă��Ă���A�����P�S�N�x����Q�P�N�x�ŁA�P�N�x���ʊz�ł͂W�P�Q���~�A�ݐό��ʊz�ł͂P�X�O�R���~�ɂ��̂ڂ��Ă���B�܂��A�E���������Ă��A�W�����v�v�����ł͕����P�V�N���畽���Q�Q�N�܂łłP�O���̍팸�ڕW���������A���ʂƂ��ĂP�Q�D�X���̍팸�ɐ��������B �S�|�S�D�V���ȁu�s�������v�v���O�����v�̍���Ɍ����� ����ׂ��s�v�����Ȃ���A�ǂ�ǂʂ����܂��Ă����B���������������Ă������߂ɁA���N�x���ɕ����Q�T�N�x�܂ł̉��v�v���O���������肵�A�������Ǝ�g��@�����������Ǝv���B �s�������v�Ƃ��ẮA�l����̑��_�����s���A���Ԋ�ƂƋύt�̂���l����ɂ������Ǝv���B���ߎs�̐l����͐l���@�Ƃ������̋@�ւƎs�̐l���ψ�������ŋ��^���Ԓ������s���A���߂��Ă��邪�A���̒����͂T�O�l�ȏ�̎��Ə��Ɍ����邽�߁A��̎��Ԃ��l����ƁA�R�O�l�ȏ�Ō��Ă͂ǂ����Ƃ������Ƃ��Ă��Ă���B �����Q�P�N�x����̂P�O�N�ԂŁA����ɂQ���̐l����팸���������Ǝv���Ă���B�E���͏��Ȃ���Ώ��Ȃ��قǐ��s�ɂȂ�Ǝv���Ă���B���̂��߂ɁA��Ŏ��Ǝd�������s���Ă���A����ׂ� ���̌��ʂ�����̗\�Z�ŁA�����~���̍팸���ʂƂ��ďo��Ǝv���B �����\�����v�Ƃ��ẮA�Ō����{�{��̏[����A���Ƃ̑I���ƏW����O�ꂷ��B �O�s�c�̉��v�Ƃ��ẮA�O�s�c�͎̂s�̖{�̂ł͏o���Ȃ��悤�Ȏd��������̂��{���̎p�����A�i�X�Ƃ��Ȃ��Ă��ǂ��悤�Ȏd���܂ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������Q���������B���̂��߁A�������I�����O�s�c�̂p�����邽�߂̃v���������肵�Ă���B �s���̌����鉻�i�����j�ł́A�ӎv����ߒ���O��I�Ɍ��J���Ă���B���c�ł̔����͂��ׂĎs���Ɍ��J���Ă���B�\�Z�Ґ��ߒ������ׂČ��J���Ă���A���̂��߂ɗ\�Z�������̂��Ƃ������Ƃ����J���Ă���B�s��������C���^�[�l�b�g�Ń��C�u�������A�s���̍l�������A���^�C���œ`����悤�ɂ��Ă���B ���N�Q������͋c����C���^�[�l�b�g�Ō��\����悤�ɂȂ�B �S�|�T�D���҂���� �i�P�j�������Ƃ��Ă̍����u�������Ă��邱�� ���͑��{�łP�X�N�l��������Ă���A�����̗̍p�����̖ʐڂɂ��ւ�����B���܂ł́A�u���肵�Ă���v�A�u�����������v�Ƃ������R�Ō��������ɗ��āA�ʐڂł����X�Ƃ��̂悤�Ȃ��Ƃ������l���������A���̂悤�Ȑl�͑S�����f�肵���B���̌������́u�n������v�A�u���v����������v�A�u�n��̋��y�������v���Ƃ��K�v���Ǝv���B �ʘg�ŁA�T�W�܂ł̎Љ�l�̗p���s���Ă��邪�A�����ɂ͖��Ԃ̐l�������������ɗ��āA�V�����Q�� �i�Q�j�s���̒ɂ݂����L�ł��� �s�ɂ͎s�����炢�낢��ȑ��k���オ���Ă���B���͂Ȃ��Ȃ�����ɍs���Ȃ����A���k����Ɍ���Ɏw�����o���A�ꍇ�ɂ���Ă͎������ڌ��ɍs���悤�ɂ��Ă���B ����l�́A�u���e���]���o���œ|��A�x����̑��k����̕��������ɂ��ɍs������A�v���x�̔F��̂ݍs���A�d�x��Q�҂̔F��̐��x���������Ă��Ȃ������B�v�Ƃ����i���������B�d�x��Q�҂ɔF�肳���ƁA�m�g�j�̎�f���������Ȃ�Ȃǂ̓��T�����邽�߁A���̃f�����b�g���ߋ��ɑk���Ďx�����Ă��炦�Ȃ����Ƃ������Ƃ�����ꂽ�B�m���ɋ�̑����ł������苳�����Ă���Ζh������������Ȃ����A��͂�\����`�ł��邽�߁A���܂Ő\�����Ă��Ȃ������l�Ƃ̌��������l����ƁA�ߋ��ɑk���Ďx�������Ƃ͓���Ɠ`�����B �Ȃ��Ȃ��[�����Ă��������Ȃ������Ǝv�����A�����Ή��������Ƃ�������o���Ă���Ηǂ������A�Ƃ������Ƃ����̎��Ɋ������B�s���̑i���ɋ����������Ƃ��厖���Ǝv���B�����X�g�b�v�T�[�r�X�őΉ��ł���悤�ȑ̐��ɂ��Ă��������B ����ŁA�����X�^�[�s�������邱�Ƃ͊m���ŁA������Ƃ������𑨂��āA�������ꌾ��悵�ɗ���l������B�������Ǝv������B�R�Ƃ����Ή����Ƃ�悤�E���Ɏw�����Ă���B �i�R�j�������Ĕ\�͂Ɛ����ӔC���������� �l���팸��i�߂�ƁA�R���T���^���g�Ȃǂ̋Ǝ҂ɔC���Ďd����i�߂Ă������Ƃ����邪�A�厖�ȕ����͐E�������𗬂��čl����ׂ����Ǝv���Ă���B�s���ɑ��Đ����ӔC����������ʂ�����E�����]�܂��Ǝv���B �i�S�j�L������������Ă��� ��ɂ͌Â����炢�낢��Ȑl�����Ă���B�Ⴆ�A�s��͓n���n�̐l�ŁA��Ő��܂�A�������Ƃ��s���A�V���ו��̂��߂ɑS���s�r���ꂽ�B�܂��A�痘�x��A��x�Ȃǂ��낢��Ȑl�����O���痈���č�肠�����B���̂悤�ɁA�O���[�o���Ȑl�ނ������߂Ă���B �܂��A�X�g���X�ϐ��Ƃ��āA�E�ꕗ�y�̌��������łǂ̂悤�Ɏd�����ł��邩�Ƃ������Ƃ��l�����Ȃ��ƂȂ�Ȃ��B���Ȃ��Ƃ�Y��A���t���b�V������p�������Ă��邩�ǂ����Ƃ������Ƃ��d�v�ł���B �i�T�j��ւ̔M���v���������Ă��� ��ւ̔M���v���������Ă��炤���߂ɁA���w�Z�����̗��j�������Ă���B�܂��A�n���̍Ղ�ɕK���Q��������ȂǁA�n������q�ǂ��ւ̓����������K�v���Ǝv���B�M���v���������ĊO�ɏo�čs���āA�܂���ɖ߂��ė��Ă��炢�����B��́A��ؖf�Ղ̊X�ł���悤�ɁA�䂩��O�ɔ�яo���A�܂���ɖ߂��Ă���Ƃ����l�ނ����߂Ă���B
�T�|�P�D�n��匠���v�̈Ӌ` �u�n��匠���v�v�Ƃ������t�������{�̍��̒��ő傫�Șb��ƂȂ��Ă���B�������̈꒚�ڈ�Ԓn�ƌ����邪�A�܂����߂ɁA���E�{���E�s�����̖������S�m�ɂ��邱�Ƃ��K�v���Ǝv���B������n���ւ̌����A�����̈ڏ����K�v�ŁA���̏o��@�ւ̌����ƍ�����{����s�����ɓn���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ⴆ�A�n���[���[�N�͌��X�͕{�̋@�ւ��������A���̊Ԃɂ����̏o��@�ւɂȂ��Ă����B�n���ɂ������������A���ɍs���Ă��܂��Ƃ������悤�ɁA�������v�ɋt�s����悤�Ȃ��Ƃ��������B���̂��߁A�n���[���[�N��s���{���ֈڊǂ���悤�咣���Ă���B ���A���̏o��@�ւ���t���邪�A���̂قƂ�ǂ̎��Ƃ��A�{����s�����ŏo���邱�Ƃł���B�Ⴆ�A�ߋE�o�ώY�Ƌǂ̂���Ă��鎖�Ƃ́A�{����s�����łł��鎖�Ƃ���������B���X�X�U���̕⏕����������o�Ă��邪�A�n���̏��X�X�U���̎��Ƃɉ��̍����⏕�����o���Ȃ��ƂȂ�Ȃ��̂��B�s�����Ɍ����������āA�s���������ꂼ��̏��X�X��U�����ׂ����Ǝv���Ă���B ���̍��̏o��@�ւ̎��Ƃ́A�n���������v�ɋt�s����悤�Ȃ��̂���������B�������ƃ`�F�b�N���Ă����Ȃ��ƂȂ�Ȃ��B �n���������v�A�n��匠���v�̗v�_�́A��b�����̒��S��`�A��b�����̗D��̌����ł���B���̒��g�͓����A�⊮���̌����Ƌߐڐ��̌����ł���B�������Ƃ�n��ɔC����Ηǂ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ���ɍl���A�n��ɂł��Ȃ����Ƃ͎s���������A�s�������ł��Ȃ����Ƃ͕{�������A�{���łł��Ȃ����h�Ȃǂ͍������Ƃ����悤�ɁA�⊮���̌����ɏ]���A���ꂼ��̎������ēx�����Ȃ����ׂ��ł���B �����A�����A�����Ƃ����l�������A�ЊQ�̎��ɂ͑�ɂȂ�B �ߐڐ��̌����́A�悭�hnear
is better�h�ƌ����A�g�߂ȃT�[�r�X�͐g�߂Ȏ����̂ł���������A�Z���ɂ��悭������A�ŋ��̎g��������������`�F�b�N�ł���Ƃ������e�ł���B �T�|�Q�@���S���ߎw��s�s�̘A�g ���̂S���ߎw��s�s�͘A�g���Ă���A�����Q�P�N�P���Q�U���ɓ����ɏW�܂�A�����錾���s�����B���ߎs���A�g���邱�ƂŁA����̎������߁A���ꂼ��̒n��ɍ������n��́E�����́E�l�ԗ͂ɖ����������A��������Ƃ������e�ł���B���B���̓������܂߁A��s�s�̖����̔��{�I�Ȍ�����������{���ɋ��߂Ă������Ƃ��Ă���A���ӂ̎����̂Ɛ����A�g���A���͂��Ȃ���n��̔��W��ڎw���Ă��������B �T�|�R�@�����m���́u���s�\�z�v ���͋����m���ƈꏏ�ɑ��{�Ő����敔�������Ă����B�����m���̎��s�́A���z�́A�J���X�}���A���{��������@�����]���č������������Ƃ͖{���ɑf���炵���Ǝv���B �@�s�����v��O��I�ɂ���Ă������߂ɁA�����m���́u���s�\�z�v��ł��o���Ă���B���̗v�_�́u�����L�掩���̂ƗD������b�����́v�ł���B�����L�掩���̂Ƃ́A�Y�Ɗ�Ղ�s�s��ՂȂǑ�K�͂ōL��ł��ׂ����͕̂{�����s���A�����A����A�q���Ȃǒn�������̂��̂͊�b�����̂����Ƃ������̂ł���B���̂��߂ɁA���݂̑��{�� �Ⴆ�A�`�p�s���ł́A���`�ƍ��k�`�͊Ǘ��҂��Ⴄ�B�p�݂ň�̂ɑ����Ă���̂ɁA���̓�̎s�ƕ{�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ����^�₪����A�Ǘ��҂͈�ŗǂ��Ƃ������ƂŁA �܂��A�����A�p���������Ƃ́A���{������Ă��� ��K�͎{�݂ł���d�s��������A�Ⴆ�A�Ȃ݂͂�h�[���� �T�|�S�D���L��A���̔��� ��苭���L��A�g�����邽�߂ɁA���L��A���������悤�Ƃ��Ă���B �T�|�T����S�̂̔��W�Ɍ������L��A�g����s�s�B�܂� ���S�̂̊������̂��߂ɁA�S���ߎs�̘A�g�Ŋ��S�̂��������A������ɏW����Ŕj�������B�܂��A����ɂ͍����C���Ȃ��A��̃����b�g������ł��Ă��Ȃ��B����͊���Ƃ��ɑ����̌������������Č����{�݂������߁A�ꂵ���ɂ���B�t���Z�b�g�̌����{�݂���n�[�t�Z�b�g�̌����{�݂ւƐ������A���̒��������� ��͓���n��S�̂̊������A�A���A�����@�\��S���Ă��������Ǝv���B
<��>�@�d�_����́u�q�ǂ��Ɍ��C���v�Ƃ������Ƃł́A��̓I�ɂǂ̂悤�Ȏ��g�݂����Ă������Ǝv���Ă���̂��B <��>�@�q�ǂ������C�ɂ��邽�߂ɁA���܂ŗc�t���܂ł��Ώۂ�������Ô�̕⏕���A���w�R�N�܂ŁA�T�O�O�~�̎��ȕ��S�ł��ׂďo����悤�ɂ����B���̂��ƂŁA�q�ǂ����a�C�ɂȂ����ȂǕs���̎��Ԃɔ����Ă���B�܂��A�m�ɍs�������Ă��s���Ȃ��q�ǂ��̂��߂ɁA���w�Z�R�N���璆�w�Z�R�N�܂ŁA�����̕��ی�w�K�����Ă���B��̋���͖��͂�����Ǝv���ĖႢ�A����D���ɂȂ��悤�ȋ�����������Ǝv���Ă���B���̈Ӗ��ŁA������C�ɂ��邽�߂ɂ́A�܂��q�ǂ������C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���Ă���B <��>�@�s���̉����Ɋւ��āA�c��̔����͂Ȃ������̂��B <��>�@�m���ɁA���ʉ��ł͔����͂������Ǝv���B�������A�S�����J���Ă��܂��Ɗy�ɂȂ�̂͊m���������B���J���邱�ƂŁA�s������s�����悭������悤�ɂȂ����Ƃ����ӌ������������Ă���̂ŁA�����炭�����Ƒn�ł�������Ƃ��s���ɂƂ��Ă͗ǂ������Ǝv���B <��>�@��ɂ���ό��������A�ǂ̂悤�Ɋό��Y�Ƃ֎����Ă����̂��B <��>�@���͊ό��̃��f�����[�g���l���Ă���B�Ⴆ�A�؍��̐l�ɑ��ẮA�s��͑嗤�n�̕��ŁA���̈�Ղ��������邽�߂��������Ă��炢�A�܂��A�m���V�c�˂ւ��s���Ă��炤�B�����Ă��̌�ޗǂ̔֍s���Ă��炤�Ƃ����悤�ȃR�[�X���l������B�����̐l�ւ͂܂��K�����R�[�X������B���̂悤�ɁA�ʂɍl���Ă���B �Y�Ɗό��ł́A�V���[�v����ǂ̂悤�ɍH��֍s���Ă����炩�ȂǁA���[�g����i�߂Ă���B��ɗ���K�R���̐헪�����Ȃ��ƂȂ�Ȃ����߁A���낢�딭�M�����Ă���B�Ⴆ�A�P�P���Q�V���Ɂu���ԍ�v�Ƃ�������o���B���܂ł͐���������Ȃ��������A�䂪�������낢�Ƃ������ƂŁA�i�s�a�����Ă���A��̒��������Љ���B <��>�@�E���Ƃǂ̂悤�Ɋւ���Ă���̂��B�܂��A�E���ɂǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����҂��Ă��邩�B <��>�@�����̓��ōl���āA�����Ŋ����o���ē����Ăق����Ǝv���Ă���B�܂��A�E�������[�e�B���Ȏd�����������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���B�m�b�̕�����E�����S���A���Ƃ͖��ԂɔC���Ă��ǂ��B�E�������s�ɂȂ�悤�ɁA��菭���ɂ��āA�������Ĕ\�͂����߂����Ǝv���Ă���B���̂��߁A�E���ɂ͂��Ȃ茵�������Ƃ������Ă���B <��>�@���ꂩ��l���Ƃ��W�߂ĐŎ����グ�A <��>�@���̗͂���邱�Ƃ��K�v���Ǝv���B�������Ȃ���P�O�O�N�����Ă���`���`���d�Ԃ�ׂ��Ƃ������Ƃ����d�C�O���������Ă������A <��>�@�ό��ɂ���ē����鎑�����ǂ̂悤�Ɏs���ɊҌ����Ă����̂��B <��>�@���̊ό��q�̂X�O���ȏオ���A��ό��ŁA���A��ό��ł͍�ŏ���邨������T��~���x�ɂ����Ȃ�Ȃ����A������h���ό��ɂ���ƕ��ςQ���~�ƂȂ�B���̂��߁A��̌l�⎖�Ə��ɑ��āA�ό��q�ɂ��̂��炢�̂������g���Ă��炦��悤�ɂ��邱�Ƃ��A�s����L���ɂ��邱�Ƃł���Ɠ`���Ă���B�������邱�ƂŁA�Ŏ����オ��A <��>�@���Ԍo���̐l���̗p�������ƂŁA��̓I�ȃ����b�g���������狳���Ăق����B <��>�@��s�o���̂�����������������Ă���B�܂��A�o�ʼn�Џo�g�̐l���}���ق̎����E�������ȂǁA�������ƈႤ����ł��̎d�������Ă����l���A�������ɂȂ邱�ƂŁA�E�������ɂ܂������V�����l���������܂��B�l�ނ������邱�ƂŊ��������N���Ă���B |
|||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. ���̃y�[�W�Ɋւ��邨�₢���킹�́A�����ّ�w�@���ʋ��琄�i�@�\�i�����ǁF���ʋ���ہj�@�܂� TEL(075)465-8472 |