 |
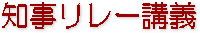  |
|
| 2010年 12月 14日 日本銀行京都支店長 渋谷康一郎 氏 |
||
「 日本経済の現状・中長期的課題と処方箋 」
日本銀行は、中央銀行と言われる日本で唯一の存在で、大きく分けて3つの仕事を行っている。 1つ目は、印刷されたお札の発行である。全国各地、それこそ山奥から離島に至るまで、日本銀行券を広く流通させ、かつ偽造が防止できるように偽札をチェックし、古くなったお金は流通を止めて未だ使用できるものは 2つ目は、国庫とよく言われるもので、国のお金を預かっている。例えば、交通違反をして罰金を払う際、それは日本銀行でも払うことが可能である。多くは金融機関を通すが、日本銀行代理店とよく金融機関の看板には書かれているが、日本銀行代理店が日本銀行が本来行う国のお財布の出入りを管理する仕事を行っている。だから銀行や郵便局が代わりに行っているという事が代理店としてステータスの基になる。 3つ目は、銀行の銀行という役割である。民間の金融機関とは異なり、日本銀行は皆さんの預金を預かることは出来ないし、企業にお金を貸すことも出来ない。基本的には、金融機関のための銀行である。日本銀行は金融機関が持っている当座預金によるお金の決済を日々行っている。例えばA銀行によるB銀行へどのくらいのお金を残高として移すのかという決済を日本銀行が当座で行っている。その意味では銀行券による決済というのと日本銀行の当座による決済、この2つが、通常ファイナリティと呼ばれるが、最終的に決済が可能な方法である。 これら3つの仕事に加えて、支店長の仕事として大事な事を言えば、例えば京都と滋賀県が私のテリトリ―である。そこで景気の現状をマクロの分析だけではなくて企業や消費者のミクロな動きについてしっかり情報収集をし、金融政策を誤りなく行うために常に情報を本部につないでいくのが仕事である。同時に、今の日本の景気の状態や金融政策に関する情報を国民に提供していくという作業も行っている。その意味では私は日本銀行の京都・滋賀地区での広告塔の役割を担っているとも言える。 今回の講義の中心は、目先の景気対策だけでは日本の経済はデフレから脱却できないという構造上の問題があるということである。そしてそこにメスを入れることをしなければ、中長期的にみればなかなか解決しないことを理解してもらいたい。 そういう中で、日本銀行の最近の金融政策に関して言えば、かなり掟破りな事をやっていると言える。歴史的に振り返ってみても、今までにやったことのないような政策を次々と打ち出していて、今そういう政策が何故必要になっているのか、という話にも触れていきたい。
まず、日本経済のここ30年~40年間を振り返った時にどんな風な流れになっているのか確認する。日本はバブル崩壊後「失われた10年」という総括をされている。1970年代あるいは80年代は4%代の経済成長率で推移しており、ある種春を満喫していた時代であった。ところが、90年代はバブル崩壊後1.5%成長というところまで下がり、それが2000年代に入ってもあまり変わらない状況が続いていた。その後08、09年でさらに大きく下がっている。原因はリーマン・ブラザーズという証券会社の破綻による全世界での金融危機で、そのあおりを大きく受ける形で日本の成長率も大きなマイナスを受けた。08年はマイナス4.1%という成長率で、09年はマイナス2.4%の成長率という、それまで経験したことのない経済の状況にある。
日本銀行は4月と10月の年に2回に、足元の景気だけではなくてこれからの先行き1年、2年の経済がどういう風になるのか説明をする展望レポートというものを出している。今回の資料は10月29日に対外的に発表したもの。予想の範囲は2010年度後半、2011年度、2012年度である。ここでは整理の仕方として、今外部的な環境がどうなっているのかについて整理した上で、特に日本の金融環境について述べ、メインの経済物価情勢のシナリオとしてどのように描いているのかについて言及している。そして最後にはメインのシナリオに対しての上振れのリスクと下振れのリスクについて言及している。
まずは世界経済の状況についてである。資料はIMFと呼ばれる国際機関が発行している世界経済見通しであり、95年から世界経済はどのような状況できたのかについてグラフで示している。08年の秋にリーマンショックが起きてから、世界経済はずっと落ちている。しかしIMFの今後2010年から2012年では世界の実質GDP成長率は、グローバル金融危機前の10年(98~07年)の世界経済の成長率の平均を上回っている。例えば11年は4.2%、12年は4.5%となっている。足元で見ると世界経済は若干スローダウン、成長率鈍化しているが、ここから先の11年、12年は全く悲観的に見ていない、という見通しを立てている事が確認できる。 「最近の円の為替レート」では、足元では円高がニュースで話題になっているが、たとえば現在対ドル83円半ばというように、為替相場ですぐドル円を連想するが、実は通貨によって全然事情が違うという事を示したグラフである。例えば韓国ウオンと円のレートを見てみた場合、春先に円高がウオンに対して進んだが、その後は殆ど横ばいの状況である。 円の名目実行為替レートは全ての通貨の平均を表わすが、例えば韓国のウオンに対して言えば全く状況が違う状況になっている。あるいは中国の元という通貨は殆ど同じ状況になっている。このような事が見てとれるので、ニュースを見る時にその辺りについて意識する必要がある。 あるいは韓国のウオンとの闘いというのは、例えば、電化製品など輸出商品を競争する相手として、相手の商品がより安くなるというのが非常に日本の輸出企業にとっては、ダメージになるので、韓国のウオンに対して日本の円が高くなるかどうかというのは輸出企業にとってかなり生命線になる。特に、関西は大阪を中心にデジタル家電のメーカーが非常に多いので、ウオンと相場の関係というのはドル円よりも最近では非常に重要になっている。 あるいは、京都・滋賀の企業は一般機械のウエートが高いが、ユーロの相場を気にしている。ヨーロッパでもドイツの企業との闘いが激しく、ユーロに対して円が高くなりすぎると非常に困る、という声が多く聞かれる。 このように、実際にマスコミが対ドルだけで円高と言うような単純な話で整理されるようなものではない。
海外経済の先行きに関して言えば心配はしていないが、2010年度下半期には少し成長ペースが鈍化する。 この背景について言えば、一つには、世界経済が落ち込んでV字反転をしている間は例えば在庫もどんどん積み増していて非常に経済活動が活発になるが、前の水準に近づいてくると当然前期比・前月比で見てくると回復のテンポがスローダウンするからである。 二つ目は、エコカー補助金やエコポイントという景気対策である。景気対策は日本だけではなくいろんな国で実はやっていた。リーマンショックで起きた金融危機を人間の病気に例えた場合、これは急性症状の非常に強い肺炎である。それを治療するためには抗生物質を多用しなければならない。ともかくカンフル剤を使って何とか体調を元に戻さないといけない状況である。このような何でもありの状態で経済政策を打っていた。それが資料にある「需要刺激策」の説明である。その急性症状がおさまり、V字反転に戻り始めたのでもうそろそろその役目を終えるという段階で、カンフル剤を打ち終えたというのが二つ目の理由である。 三つ目は、新興国あるいは資源国と言われる国がV字反転の景気回復の局面でものすごく強くなりすぎてきた事である。そこで、少し過熱感を抑えるために金利を引き上げ始めているのでスローダウンが始まったといえる。 先行きを楽観的に見ているもう一つの理由として、例えば中国の場合、国民の所得が急に増えたので、①耐久消費財を中心にものすごい消費ブームが起こっている。②二つ目は道路、鉄道のような社会インフラが未整備の状況なのでそのためのニーズが強いのである。 ③三つ目はこれを支えるお金が、先進国の経済が良くないので新興国へ大量に流れ込んでいる。そのような需要を支えるための資金がきちんとついていっている状況である。そのため、新興国では引き続き経済の成長・拡大が見込めるのである。 では、先進国はどうかと言えば、米国を中心に少し重たい状況が続くと予想され、日本の失われた10年と言われた時代に起こっていた事に近い状況である。 つまり、お金を借りて購入や資金運用をするような通常での家計の経済活動が、リーマンショックを契機に家計の資産の価値がものすごい勢いで落ちた事で、借金は残ったまま資産と負債のバランスシートが崩れてしまった。結果、お金が多少入ってきても支出には充てずに借金の返済や貯金に回すようになる。このため、経済活動は支出が起こらないので勢いよく回復する状態が起こらない。実際に米国の貯蓄率が6%を超えるような状況で過去と比べると非常に高い。 このように、バランスシート調整問題というのは経済に非常に深く長く影響を与えるので、マスコミが言うような簡単に経済が立ち直る状況にならないというのを覚悟した方がいいというのが日本銀行の見方である。
日本の経済について言えば、現在輸出が不調ではあるが、今後は新興国の経済の調子の良さに支えられて輸出を中心に再び徐々に回復するだろう。そして2012年度にはそれが所得や雇用につながって、よりその勢いがはっきりしてくるというのが現在の日銀が描いているメインシナリオになる。 実際には、2010年度は実質GDPでプラス2.1%という成長、2011年度はプラス1.8%、2012年度はプラス2.1%の成長見通しである。
2010年度7~9月期の実質GDPは現在1.1に上方修正されて、前期比年率4.5%になっている。日本の経済の成長率が年率2.2%前後という高い数値だが、背景には政策効果による一時的な伸びがある。具体的には民間最終消費支出の項目を見た場合、2010年7~9月期は0.7で、4~6月期の0.0に比べると非常に高くなっている。 要は、消費が9月にものすごく伸びたというのがこのグラフから見てとれる。きっかけはエコカー補助金打ち切りのために生じた駆け込み需要である。あとはエコポイントで家電がものすごく売れた事である。12月1日からエコポイントが半分になるという報道が10月になされたので10月、11月に家電がさらに売れたのが大きな影響だった。もうひとつは、煙草税が10月1日から引き上げられる事による駆け込み需要で9月に売れた事である。 一方で、2010年度7~9月期の純輸出は0.0で、4~6月期や1~3月期と比べるとかなり小さくなっている。これは、世界経済が若干スローダウンしてくる中で 輸出が伸びを欠いてきたためである。 だから、現在は調子の良い数字が出ているが、これは政策効果が押し上げたところによるので一時的な現象と見るべきである。
実質GDPの中身について、項目別に今どのレベルまで戻ってきているのかについて説明したグラフである。(1)海外成長の実質GDPは、リーマンショックで落ち込んだ分を既に回復してさらに突き抜けている状態である。 ところが、(4)輸出(SNA)を見てみると、08年度を100と見た場合、足元では世界経済が調子が良いのに未だ91.1までしか回復していない。これは円高の影響によるものである。 その一方で(6)個人消費(SNA)は、08年度を100と見た場合、99まで戻っていて、ほとんどリーマンショックの前まで戻ったという状況である。背景には既に述べた政策効果によるものがある。ただし、ここから先は自動車の補助金が打ち切られ、エコポイントも半減するので、押し上げる力が弱ってくると予測される。 (5)設備投資(SNA)は、08年度を100と見た場合、78までしか戻っていない。要は政策効果で消費を支えている間にそれが内需拡大に繋がらなければ景気回復は起こらないが、今回は一連の措置が企業の設備投資に結びつかなかった。だから、これからの先行きが心配な状態である。
消費者物価指数は未だ前年比マイナスであるが、少しずつマイナス幅が縮小しつつある状況である。 基調的な物価変動は、高校授業料は無償化が行われて物価にはマイナスで効くのでこの分を除いた数値で見ると、大分マイナス幅は小さくなってきているが、なかなか前年比プラスになってデフレを脱却する勢いにはつながらないのがわかる。 消費者物価指数が正になって前年比1%を上回るようになるには、だいぶまだ時間がかかりそうである。言い換えれば、デフレを脱却するのは困難な状況である。
四半期に一度開く支店長会議で意見交換をする際に用いられる資料である。 前回との比較としての矢印が右下がりになっている地域は足元の調子が悪くなった事を示している。実際には関東甲信越、東海、中国がそうである。これらの地域の特徴は、関東甲信越なら日産、東海なら豊田、広島なら松田、という日本を代表する自動車会社がある地域で、非常に大きなダメージを受けており、特に東海は非常に大きな影響が出ている。 一方で、関西の景気は横ばいである。大阪はデジタル家電のウエートが高く、京都・滋賀でも同じ傾向として自動車のウエートは低い。京都は食料品や電気機械のウエートが高い。 いわゆるクリーンルーム経済的なのが関西の特徴である。工場はあるが人があまりいないタイプの業種が強い傾向が、特に京都、滋賀は顕著である。 足元の関西では、所得・雇用が悪くなる傾向が見られるので、対顧客サービスや消費者関連回りなどの数値が項目として重要視される。
京都・滋賀は製造業のウエートが非常に高い。 特に、滋賀県は県内総生産で見た時に4割近くを占めており、全国でトップである。また、一般機械のウエートも非常に高い。 製造品出荷額の業種別構成比で見ると、京都は飲食料品のウエートが圧倒的に高い。例えば煙草や大手の飲料メーカー、清酒の工場が多いことが特徴である。一方で、輸送用機械は全国の半分くらいしかない。 また、京都・滋賀は、西陣や長浜、丹後など繊維で有名な地域があるように、繊維は全国と比べると倍以上のシェアを持っているが、1975年と比べると低くなっている。
興味深いのは、滋賀県の人口がまだ伸びていることであり、大手の工場の増加によるものである。 一方、京都の人口は横ばいで、年齢構成比で見ると60歳以上のウエートが全国に比べると高く、そのうち60台と80台の人口が高い。
京都の景気は全国比では少し重たく、「持ち直しを続けているが、そのペースは鈍化している」としている。理由は個人消費鈍化と百貨店の売上が全国と比べると低いからである。 製造業では自動車が少ない分だけ痛み方は少なかったのだが、足元では電気機械、電気部品、デバイス等の受注に少し陰りが見られる。 以上で、景気の話について述べたが、目先10年は鈍い動きがあって、それから来年、再来年というのはテンポはゆったりであるが、少しづつ回復過程に戻っていくだろう、というのが日銀の予測である。だが、将来バラ色の道にどんどん戻っていくのかと問われれば、デフレの状況、物価がプラスに安定していかないという状況からは、脱せられない可能性が予測される。
需給ギャップについてわかりやすく説明すれば、経済全体の需要に比べて、供給(企業の提供する財やサービス)が超過してしまっている状態のことである。 (1)需給ギャップを見ると、09年を底に供給超過幅は少しずつ縮小してきているが、相変わらず大きい供給超過の状態である。 そして、日本経済の実力である(2)潜在成長率を見てみると、日本の潜在力は供給する側からの尺度として見ると非常に厳しい状況にあると言える。結果、物価がなかなかプラスにならない。なぜなら物価は需給で決まるので、供給超過では物価は下がったままであるという状況から経済は脱せられない。よって、大きな供給超過が有る中で、エコカー補助金やエコポイントという景気対策をただ続けているだけでは安定した成長は見込めない。
日本が生産性を見込めない理由の一つとして、少子高齢が進行する中で一番懸念されている労働力人口の低下である。長期人口推移が、05年をピークに既に減少に転じている。 年齢3区分別人口比率の推移を見ると生産年齢人口比率は1992年をピークに減少し続け、働き手がいなくなってきている事を示している。
就業者一人あたりGDPの成長率である。これは働き手一人当たりの生産性とも言いかえることができるが、80年代の日本はG7の中でトップだった。ところが、90年代に入ってバブル崩壊後の失われた10年の間に、その中で最下位になった。つまり、ITが劇的に進化し、グローバル化が劇的に進行していく中で、先進国が攻めの戦術を行っていた最中に、日本経済は不良債権処理に追われてしまい、守りの戦術をとらざるを得なかったのが、結果的に生産性を落とす事に繋がった理由である。
なぜ、潜在成長率が下がると実質成長率も下がってデフレから脱却できないのか。 キャッシュ・フローとは、企業の手元にある余裕資金の事である。足元では製造業・非製造業ともに余裕資金を手元に持っている。ところが、①製造業②非製造業のグラフを見ると設備投資が出ていない。つまり、金がないから設備投資をしないのではない。 その理由を示すのが (2)設備投資対キャッシュ・フロー比率と予想成長率である。各業界で見ている5年先の経済成長率のグラフを見ると、企業は日本経済の先行きが良くなるとは思えないなら設備投資をしない事を示している。 つまり、なかなか将来に対して期待を持てない状況になっていると、企業は設備投資を抑えるという傾向がはっきりとここで確認できる。
グラフを見るとエコカー補助金やエコポイントという景気対策の時期を除いて趨勢的に右下がりの傾向である。これも、先ほどの設備投資対キャッシュ・フロー比率と予想成長率と同様に、家計の先行きの所得に対する不安が強いなら、お金を今使わないで貯蓄に回すようになる。 期待成長率が高まってこないと企業も家計も支出しなくなる。結局需要が高まらなくなるから需給ギャップが簡単に埋まらない。つまり、デフレが続くのである。このような悪い状態に陥っているのが中長期的に捉えた場合の予測である。 では今後どのような改善策が考えられるのか。一つは労働人口の低下という課題に取り組むことである。つまり、高齢者、女性の労働参加率をどう引き上げるかという課題である。就職に関して言えば物凄く厳しい印象を受けるかもしれないが、有効求人倍率を業種別にみると、需要超過の業種が世の中には多数ある。例えば医療・介護や3Kと言われる分野である。あるいは、大企業には就職が殺到しているが、中小企業で未だ募集をしているところはある。ここである種の需給のミスマッチが起こっていると言える。 女性の労働参加率を上げるために行政・企業が取り組む課題についてはさまざまな議論があるだろう。高齢者の場合では、年金受給開始年齢が65歳である中で多くの企業では退職年齢がそれよりも若いところがある。今後高齢社会が進んでいく中で、年金制度そのものが維持できるかわからない状況で、高齢者も元気なうちにどうやって働いてもらうかという課題が出てくるだろう。ただ、これらの課題解決には時間がかかる。 上記の課題よりも早めに取り組みやすいもうひとつの切り口は、新たな見込みのある需要である。これは、リーディングインダストリーであるかもしれないし、あるいは新しい売れる商品や技術そのものかもしれない。日本の場合、産業分類でいえばサービス業のウエートが圧倒的に高いので、サービス業のやり口そのものの国際化を考えるのも一つである。 要は新しい産業を考える場合、人を雇っていけるような供給体制を考えて商品を売り出していくという流れにどうやってつなげていくかが非常に重要な事である。 明治維新以降を振り返ってみると、日本の企業というのはずっと一つの産業が強かったわけではない。リーディングインダストリーというのは繊維や鉄道、自動車、電気機械などと、その時々で変遷を遂げている。 例えば現在商売相手として闘っている韓国、中国の企業は労働力の安さを勝負にして、技術レベル的には相対的に低い製品で強みがある。一方、日本の場合、人権費は高いが技術力は非常に高い。そのような状況の中で、何を次の日本の産業の目玉にしていくのかは非常に大きな課題であり、目玉としてのイノベーションを企業が見出していくための努力は非常に必要である。例えば金融機関はこれを一貫して支え続けてきた。まだ芽が出るかどうかわからない産業に対してメインバンクが取り組んできた歴史がある。 もうひとつ、行政の役割である。それは、民間のイノベーションの発掘を絶対に邪魔しないことである。つまり、規制をどのくらい外せるかを考えないといけないし、成長性のある分野に対して、そういう動きを上手に支援していくための流れを作っていくのが行政の役割だと思っている。
明治時代から振り返ってみると、日本のリーディングインダストリーをつくり上げていく過程で金融機関が果たした役割というのはものすごく大きなものがある。 ここをより円滑に回していくためにある種呼び水となるような政策を日本銀行が打てないかという趣旨で導入したのが、成長基盤強化を支援するための資金供給制度である。 内容は、予算3兆円を上限に、日本銀行が貸しつけるものである。レートは、貸付時の無担保コールレイト(オーバーナイト物)の誘導目標水準としており、これは今日本銀行が金融政策を行っていく上で、誘導目標としている金利である。0.1%という金利で最長4年の資金を成長産業強化を実行するべく出てくる資金需要であれば、日本銀行が市場全体で3兆円までを貸すという制度である。

G7諸国のGDP成長率で (3)就業者一人当たりGDPの成長率について、90年代に入って日本が最下位になった事について述べたが、00年以降を見ると、日本はアメリカに次いで2位に回復している。もちろん80年代と比べると、半分くらいの水準になるのだが、先進国中第2位まで再び引き上げたのである。これは日本企業の半端ではない底力、粘り強さがあるからで、この事は明確に認識すべきである。 世界の中でも日本は相変わらず技術立国であるところがあり、国際特許も米国に次いで2位を未だ維持している。あるいは技術者の数も先進国の中でトップであり、その意味では潜在的な技術力が強い。問題は、せっかく培った人材・技術をみすみす海外に流出させてしまっている事もきちんと考えるべきである。 金融システムの安定性で言えば、日本は先進国中一番である。失われた10年の間に日本は金融システムをもう一度構築し直す事にエネルギーを割いたため、他の先進国がリーマンショックの打撃を受ける原因となった金融に手を出す余裕が無かったからである。 世界経済を牽引している中国・東南アジア諸国と歴史的、地理的に非常に近いのも日本である。 以上から、日本が新しいイノベーションにチャレンジする優位性はあると言える。それにも拘わらず、悲観的に受け止め過ぎる傾向が日本国内にはあるのではないか。夢を持って、次の世代の日本の産業・技術を自分たちが担うというモチベーションを持って、社会に出ていく事が望まれる。そのモチベーションが潜在成長率を高めて需給ギャップを埋め経済成長率を確保するための大きな武器になる。
<問> 資料7ページの説明は、今後は駆け込み需要がなくなるので、より厳しい実質GDPになるという意味か。 <答> その通りである。2010年7~9月期の実質GDPの伸びは政策効果によるところが大きいので2010年度下半期には少し成長ペースが鈍化すると言える。ただ、どんどん割れていくかというと必ずしもそうなるとは限らない様子である。 例えば、現在京都・滋賀で車のディーラーにヒアリングすると、補助金制度の期限が切れて販売が伸びなくなっても先行きずっとこれが続くと見ている業者はあまりいない。エコカー補助金の期間が過ぎた後もトヨタ、ホンダなど新車で出ているものは食いつきが悪くはない。底はそんなに遠くなくて、皆悲観的ではない。 世界経済が持ち直している中で、パソコンや薄型テレビなど情報関連機器の輸出は厳しいが、中国は国慶節の時に消費がものすごく伸びて、たまっていた在庫が一気にはけた事から、新興国の需要のすごさがうかがえる。 <問> ①京都はドイツのユーロを気にしているのはなぜか。 ②資料4ページで高校授業料の影響を除いたのはなぜか。 ③2008年秋のリーマンショックの意味がメディアの説明では分からない。 <答> ① 一般の精密機械の企業にとっての競争相手はドイツの企業である。元々価格が同じだとすると、相手の製品の方が売る時に安くなるので、円対ユーロを気にする。また、中国や東南アジアで生産したものをヨーロッパに輸出する時もユーロ安が影響してくる。ドル対ユーロで見てもユーロ安化が進んでいるのでその影響が効いている。 ② 要は0.5%物価に影響を与えるマグニチュードが高校授業料の無償化にはあるという意味である。 ③ 金融危機を分かりやすく言えば、事の発端はアメリカのサブプライムローン問題である。アメリカも日本と同様に不動産マーケットというのは常に右上がりだという神話があったのが、ある日突然崩壊したので、これは日本のバブルがはじけたのとすごく似ている。金融機関は所得階層の低い有色人種に対して商品を売りこんだ。これらの人は所得が低いので、リスクプレミアが高く金利が高くなるが、すごく金利を安く設定して、例えば3年目からは金利がステップアップするような商品をどんどん売り込んでいった。これを裏付けていたのが右上がり神話だった。その際、ローン債権を細かくして証券化商品にして分散した経緯があり、どこにリスクがあるのか分からなくなった。そこに不動産マーケットが崩壊し、いろんな方向で返済が起き、皆が金融機関同士で疑心暗鬼になってしまった結果、お金が貸せなくなったというのが始まりである。 |
||||||||||||||||||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |
 流通させて、お金の流れを日々コントロールしている。
流通させて、お金の流れを日々コントロールしている。