 |
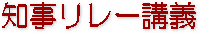  |
|
| 2011年 1月 18日 長野県飯田市 牧野光朗 市長 |
||
「 南信州定住自立圏の構築に向けた地域経営戦略 〜人口10万人の地方都市から「ニッポンの日本」を考える〜 」

私は飯田市長になるまで、日本政策投資銀行(入行時は日本開発銀行)に約20年間勤務していた。大分事務所長を平成16年3月に辞して、ふるさとに戻り半年間選挙活動をして10月の市長選挙で市長に就任した。大分事務所にいたときには、立命館アジア太平洋大学でも講座を持っており、その頃から立命館大学の学生や教員と縁があった。 日本政策投資銀行では、主に地域開発の仕事をしており、フランクフルトで駐在している頃は、ドイツやヨーロッパ全般の様々な地域の地域づくりプロジェクトのレポートを書いていた。大分では、大分の地域づくりに約2年間携わった。私の家族は飯田に住み、私自身は大分へ単身赴任していたため、月に一度ほど飯田に帰っていた。あるとき、私自身も帰ってきて市長選に出ないかと言われた。迷ったが、他の地域の地域づくりには貢献して、自分の地域の地域づくりには貢献しないかと言われたことが決め手だった。 今日は飯田市長として7年間飯田市でどのような地域づくりを進めてきたかを紹介し、今後の日本の地域づくりをどう進めていくかということを皆さんと考えていきたい。
飯田市はアルプスに囲まれた山の都で、日本で最も広い伊那谷の南に位置しており、山が屏風状に見えるのが特徴で、人口約10万人の非常に景観が良い都市である。環境が豊かな所で、平成21年の1月には全国で13箇所しかない環境モデル都市に選ばれた。エコと観光を結びつけ、体験観光旅行やワーキングホリデーのようにエコツーリズム、グリーンツーリズムの先駆けにもなっており、年間約2万人を迎えている。 フィールドスタディを本格的に始めて3年ほど経つが、今後はいろいろな大学を巻き込んだ飯田版インター大学の構築を目指している。これは、飯田を拠点にしながら地域づくりを学ぼうという大学が集まるもので、今年度の夏には21大学約300人の学生が飯田に集まってフィールドスタディに参加した。 飯田市は10万都市だが、飯田市の周りには13の町村があり、14市町村で南信州地域を形成している。飯田市だけでも面積が658平方キロメートルあり、合併の影響もあってかなり大きくなっている。 南信州全体では14市町村で約1900平方キロメートルある。これは大阪府や香川県よりも大きな面積だが、そのうちの約85%は森林で、地域全体では約17万人が暮らしている。これら14市町村が経済圏・生活圏を共にする南信州地域ということになる。 飯田市は山の都で、里やまちなかも独自のライフスタイルを築いており、多様な生活のあるまちとなっている。山は山で生活が非常に豊かで、里は里で人々が田園地帯の中でゆったりと生活しており、豊かな山村に支えられ、まちなかが発展してきた。住民参加が非常に盛んな地域で、そのシンボルとなっているのがりんご並木である。 飯田市は「りんご並木と人形劇のまち」と言われるが、りんご並木は昭和22年の4月に飯田の大火の後に造られたまちの真ん中にある防火帯に、地元の中学生がりんごを植えて育てたいという提案をしたことから始まった。 この提案は大人たちには非常にありがたいもので将来に希望が持てるものだったが、一方で本当にこのようなことができるのかという心配もあった。その頃は飢えの時代で、農村部に十分な労働力がなかったため、みんなお腹を空かせている中でまちの真ん中にりんごがあれば取られてしまうのではないかという心配をしていた。それならやめようという話にならないのが飯田市民らしいところで、とにかくやってみようということになった。 実際にりんごの実がつくと、心配が的中してほとんど全て取られてしまった。みんながっかりしたが、マスコミを通じて全国から励ましが届き、もう一度しようということになった。そのとき、りんごを柵で囲うかどうかということ議論となった。最終的には、飯田市民はこのりんごを子どもたちが育てているということを知っているはずで、その子どもたちを悲しませるようなのは飯田市民ではないと考えて、囲っていない。りんご並木は飯田市民の心のシンボルで、本当に大事にされている。 産業では、水引では全国70%、半生菓子でも40%のシェアを持っている。市田柿なども含め、豊かな食材を生み出している。また、かつてはシルクの地としても栄えた。産業の中心は水引からシルクに移り、大恐慌の後は精密機械に移り、今は環境産業に変遷している。多様なものづくりの集積地になっている。
今では地方圏だけでなく、三大都市圏でも人口減少が進んでいる。これまでの30年間と今後の30年間では大きく状況が違う。 これまでは三大都市圏で1000万人以上の人口増があり、地方圏でも全体で500万人増えたが、今後は三大都市圏も含めて減少となり、地方圏は1200万人以上の大幅減となる。 年少人口が約4割減り、高齢者人口が45%増えることになる。南信州地域でも、平成12年くらいまでは安定的に推移していたが、平成17年以降は減り続けている。地方においてどのような地域経営をしていかないといけないかを考えるようになり、その中で定住自立圏構想が出てきた。全国の自治体の長としてただひとり総務省の審議会に加えてもらい、地方の現状として飯田市の状況を説明した。 3年前の市議会で、飯田市立病院の産科体勢について大議論となったのを覚えている。全国的に医師不足が進み、地域にとってのセーフティーネットである地域医療が崩壊していくという状況の下で、飯田下伊那地域でも、行政と医師会が一緒になって地域医療の崩壊を防いできたが、特に産科医の不足が顕著となっていた。 そうすると里帰り出産の制限をせざるを得ないという状況になってきたが、少子化の中で子育て世代が安心して子どもを産み育てられる地域を確保しておかなければ、今後人口の自然減を食い止めることはできない。そのため、子どもを産む環境は地域で何としても維持したいと思いずっと頑張ってきたが、できなくなった。 議会は、飯田市立病院は飯田市民の税金によって成り立っているため、制限するなら飯田市民以外の利用から制限すべきだと主張した。地域経営はこのような究極の選択をしなければならない場面がある。右肩下がりの状況で、あれもこれもとはいかないため、どれを取ってどれを捨てるのかの決断をしないとならない。 そのときに、なぜこうしたかという考えがないとならない。飯田市立病院は周辺の町村も含めた中核病院として位置づけられている。市民の税金で運営されてはいるが、利用者の6割が飯田市、3割は周辺町村、1割はその他となっている。したがって、飯田下伊那地域の中核病院としての機能を持っており、自分は南信州広域連合の連合長で しかし、議会の議論も一理あり、飯田市と周辺町村でどう役割を分担するかのルールがないため、このような究極の選択をするときに、迷ってしまう。その時に定住自立圏の委員会への参加の話があり、地域医療などでは周辺町村ときっちりと役割分担をせねばならず、そのための協定を結ばねばならないという主張をした。 飯田市では四年制大学がないこともあり、若者の8割方が一度外へ出てしまい、そのうち4割ほどしか地域に戻って来ず、社会限でマイナスとなっている。IターンやUターンで地域に人が来る仕組みを創らなければ、新しい地域づくりにダイナミズムを生み出す活力が生まれてこないため、人材のサイクルということを訴えている。 南信州地域は全国に先駆けて周辺の13町村と協定を結んだが、これには南信州広域連合の取り組みがベースにある。総務省は平成の大合併の前に、広域連合という仕組みを全国に打ち出していた時期があっが、うまくいかず、平成の大合併となったという経緯がある。 長野県と北海道は広域連合がうまくいった地域と言われている。南信州地域は広域連合の取り組みが進み、ゴミ処理や消防といった広域事業だけではなく、14市町村の首長が月一度全員揃い、地域の課題を話し合っている。地域の課題を全市町村で話し合い、広域連合で実行するというのが当たり前の仕組みとなっていた。飯田下伊那の特徴として、国から示された制度をそのまま受け入れるのではなく、それを自分たちに合うように付加価値をつけるということを考える。他と同じ名称を使っていても中身は全然違うということがこの地域ではよくある。総務省の担当者からは「日本最強の広域連合」と評価された。 このようなベースの上に、定住自立圏構想が乗ったため、広域連合でやっていたことを定住自立圏に載せたらできてしまったという形である。 今の地域の状況を見ると、高度成長からバブル時期のように、国の制度をそのまま取り入れていれば地域としてやっていけるという時代ではなくなっており、総合的な地域経営が求められ、そのようなマネジメントができるかどうかで地域が良くなるか悪くなるかがかかっていると言える。 飯田市の市政経営の方向は、人材のサイクルを構築するために住み続けたいと感じる地域づくり、帰ってきたいと考える人づくり、帰ってこられる産業づくりを一体として進めていかなければならないというものである。 これらの取り組みは、行政区画にとらわれていてはできず、行政の区画を超えてやっていかないと成果が期待できない。生活圏・経済圏が行政区画と一致していれば良いが、だいたい一致していない。長野県全体で見ると生活圏は異なり過ぎているし、飯田市単体では小さすぎる。生活圏・経済圏に合わせた定住自立圏を構築しないと効果を引き出すことは難しい。このことが今までの市町村の地域づくりの中では認識されていなかった。
これからは、生活が成り立つような産業を地域の中に創っていかないとならない。飯田市では、経済自立度でこれを考えている。経済自立度とは、地域全体で生活していくのに必要となる「必要所得額」を分母に持ってきて、そのうち地域産業がどれだけ貢献しているかという値を表している。 100%であれば地域は経済的に自立していると言えるが、地域を一つの家計に置き換えると、ほとんど自立していないと言っても過言ではない。飯田市の自立度は45%で、あとは昔の貯金の取り崩しか、国からの公共事業で占められている。昨年9月末で国の借金は900兆円を超えたが、今年度公共工事は16%削減され、地域経済に大きな影響を与えている。 私は市長になる前から、このまま放っておくと地域は大変なことになるため、地域産業の振興を地域全体で考えていく必要があるということをずっと訴えている。選挙の時から地域全体の人口である17万人を念頭に置いていた。 今までの産業振興は、だいたい企業や工場を誘致するというものだったが、そうしたやり方だけでこのグローバル化した状況の中ではやっていくことができず、地域の中から産業のダイナミズムを興していかないとならない。 企業は環境が変わると簡単に他の地域に出て行ってしまい、地域が悲しい思いをすることになるため、この地域から自分の産業を興そうと考える人材をどれだけ育てられるかが重要だと思う。この考えがなかったことが今までダイナミズムを興せなかったことの一つの原因だと思う。 外で学んだ専門的な知識や技術を地域に持ってくる仕組みがないとならず、外部の人が単発的に関わるだけではならない。中心市街地活性化などは典型例で、東京のコンサルが年に数回地域を訪れて、三回目くらいに報告を出すが、本当にやるとうまくいかなかったということがよくある。地域のことをよく分かっていないのが原因で、地域のことを深く理解していれば地域に合った処方箋が書けるかもしれない。 飯田下伊那地域は、ものづくりは得意だが、つくるだけつくって自分たちで消費し、マーケティングをして外に売り出していなかった。この地域を愛して、全国に訴えたいと思った東京生まれ東京育ちの若者が飯田を選び、「かぶちゃん農園」という市田柿の通信販売の会社を立ち上げた。 地域の農業関係者が考えつかなかったようなマーケティングをこの地域にもたらし、1個50円ほどだった市田柿を20倍もの付加価値がつくような産業にまで成長させた。専門家がこの地域が素晴らしいと思い長期的に入り込むことで、ダイナミズムが生まれた例である。 この市田柿の例に限らず、全産業でこのような取り組みを行っていこうというで、飯伊地域地 航空宇宙にも進出しようとして、20社以上が集まってプロジェクトを立ち上げ、航空機メーカーには必ず必要なJISQ9100という資格を7社が取得している。 飯田市が発注した防犯灯では、わずか3ヶ月ほどで安くて質の良いものを開発した。それだけ技術の蓄積があったということを意味する。 小泉改革以来、政策金融機能が非常に弱体化し、地域で産業ダイナミズムを興していく力が弱くなってきた。これを補うために、飯田市では金融政策室を設置した。ここまでやらなければ産業ダイナミズムは創れない状況になっている。オリジナリティを持った日本の地域を目指している。
これからの地域政策の立案の主体は、基礎自治体である市町村が担わざるを得ないと思っている。国が地域政策を考え、都道府県が取り次ぎ、市町村が実施するという枠ではならず、住民に最も身近な市町村が担わなければならない。これをパッケージで支援する仕組みを国が作ってほしい。 南信州地域の地域経営戦略について皆さんと是非考えていきたい。現地でまた会えることを楽しみにしている。
<問> 三遠南信道やリニア新幹線が飯田に来て交通の便が良くなるが、飯田が今後どのように発展していけば良いと考えているか。 <答> 大規模なプロジェクトが来ることを目標としていた地域がその後どうなったかという調査をした。新幹線や高速道路を誘致することを公約として掲げた地域が、本当に実現して発展したかということを見ないとならない。 調査の結果、目標を失った時点で衰退したり、地域づくりとして何をしたら分からなかったりという状況に陥っているということがよく分かった。そのような地域が全国的には多く、大規模な交通インフラで大都市圏と結ばれるのは便利なことだが、プラスだけではなくマイナスの効果もある。 便利になったときに、大都市圏かふるさとかどちらに住むかという問題で、若い人材がどんどん流出していったのが地方圏の実情である。 それを防ぐためには、若い人たちが帰ってきて、地域の中でしっかりと子育てができる環境をつくっていかなくてはならない。そうしないと、子どもたちはふるさとの意識を持たなくなってしまう。だからこそ人材のサイクルを考えられる地域づくりをしていかないとならない。 昨年5月から、南信州広域連合で、「リニアを考える将来検討会議」を設け、有識者に集まってもらい、この地域の将来をみんなで考えていこうということを半年間やってきた。大規模な交通インフラを活かすためには、戦 <問> 行政が産業の種を植えて育てるということは分かるが、産業が大きくなると東京へ出て行ったり海外へ出て行ったりするということがあると思う。地域から逃げていく企業が出てきたときに、どうするのか。 <答> 企業も人の集まりで、ドイツでは大概の企業が社長のふるさとに本社があり、そこから離れることが考えられないという発想がある。 地域が気に入っていればその地域に住み続けるはずなので、そのような人が集まるような地域を創っていったほうが良いと思う。企業とともに地域が成長していくという考えの市政経営が必要だと思う。 |
|||||||
|
Copyright(c) Ritsumeikan Univ. All Right reserved. このページに関するお問い合わせは、立命館大学 共通教育推進機構(事務局:共通教育課) まで TEL(075)465-8472 |

 あることを考えても議会の議論には賛成できず、飯田市民かどうかを問わず一律の制限をするという決断をした。
あることを考えても議会の議論には賛成できず、飯田市民かどうかを問わず一律の制限をするという決断をした。 場産業振興センターをものづくりの拠点として置いている。ここで新しいクラスターを創ろうとして、専門家を集めている。多くは企業の社長で、退職して飯田が好きな人を連れてきたため、飯田の外の人も含まれている。
場産業振興センターをものづくりの拠点として置いている。ここで新しいクラスターを創ろうとして、専門家を集めている。多くは企業の社長で、退職して飯田が好きな人を連れてきたため、飯田の外の人も含まれている。