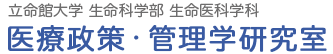本研究室の目標と主な研究内容
1.「安心と納得の医療」を実現するシステムの確立
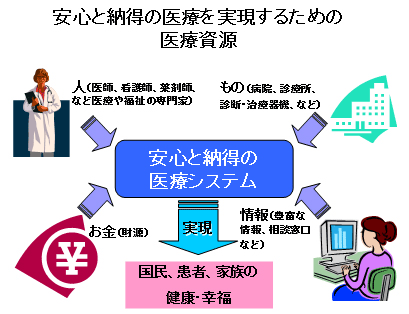 本研究室の大目標は、人々が安心でき、かつ、納得して医療を受けることができるような医療システムを構築することです。
本研究室の大目標は、人々が安心でき、かつ、納得して医療を受けることができるような医療システムを構築することです。
社会における医療資源は有限です。どの医療資源を、どこで、どのくらい、どのように使うか、によって、結果(アウトカム)は異なってきます。
本研究室では、一つ一つの医療技術について、あるいは、様々な医療技術を横断的に、適切に評価するシステムを開発し、評価結果を次の時代の医療の質の改善にどのように応用していくかを追究しています。
2. 医療の質の評価と評価結果の医療システム改善への応用
医療システムは常に適切な評価システムによって分析・評価され、多角的に厳しく吟味され、その結果、医療の質の改善につながっていかなければなりません。
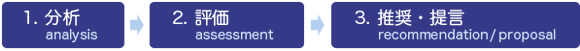
の過程が、常時、適切に行われていることが大事です。
本研究室では、上記のすべての過程について、多角的かつ詳細な研究を行っています。
3. 医療の2大目標
医療の目標には、
- 疾病の予防と健康の増進および維持
- 病気による苦痛の緩和
- 病気を持つ人の治療とケア、および治療が不可能な人のケア
- 若年期の死の回避と穏やかな死の追求
(米国の生命倫理研究所の一つであるHastings Centerが14カ国の有識者の意見をまとめて作成したコンセンサスレポート(1996)より)
が大切であるとされますが、それらをさらに要約すると、
- 生存期間(寿命)の保持・延長
- 健康度や生活・生命の質(quality-of-life: QOL)の維持・向上
(Brulde B, Health Care Analysis 9: 1–13, 2001.)
という医療の二大目標が浮かび上がってきます。
「生存期間」については、現在のわが国においては、比較的容易に信頼性の高いデータを把握することが可能です。一方、「健康度やQOL」については、人々の主観に関わる部分も多く、信頼性の高いデータを得るには、専門的な知識と技術が必要です。
本研究室では、特に後者の、QOLなどの患者の主観的なアウトカム(patient-reported outcomes: PROs)(「患者報告アウトカム」と通常訳される)の定量的な測定・評価に必要なツール(尺度)の開発や、測定方法、データの解析方法、そして、評価結果の応用方法について、永年多くのノウハウを蓄積し、国際的にも高い研究レベルを保っています。
4. QOL/PROの定量的評価の基礎と応用
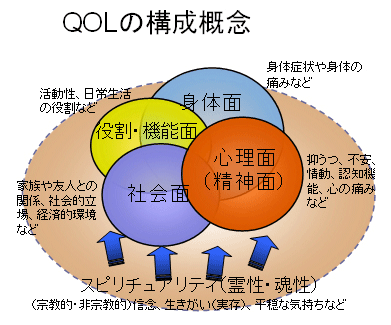 医薬品や医療機器、医療手技(手術など)などの医療技術が患者のQOL/PROに及ぼす影響について定量的に測定・評価を行う研究を行っています。
医薬品や医療機器、医療手技(手術など)などの医療技術が患者のQOL/PROに及ぼす影響について定量的に測定・評価を行う研究を行っています。
基礎的研究としては、主観的測定と客観的測定の哲学的意義の勉強に始まり、実際に患者と医療者の評価結果の相違を明らかにし、さらに、主観を測定・評価する際に留意すべき課題の解決に取り組んでいます。
課題の中でも、特に、臨床試験における効果の有無の判断に直結する、「臨床的に意味のある最小の効果量(minimally important difference: MID)」の問題と、解析におけるバイアスを最小限にするために、「レスポンスシフト(価値基準の変化)」が測定結果に与える影響の検出と、それに基づくデータ補正の可能性追求の課題に取り組んでいます。
また、QOL/PROの評価結果は、診療現場におけるshared-decision makingを通して患者‐医師間のコミュニケーションの向上に役立ったり、質の高いエビデンスとして診療ガイドラインに盛り込まれることなどによって、証拠に基づく医療(evidence-based medicine: EBM)の確立に役立ったりしています。
5. 効率的かつ公平性の高い医療資源配分方法の確立
最近、特に力を入れているのが、本研究です。
わが国を含め、主要先進国は経済の低迷に喘いでいます。一方、医療費は増加する一方です。医療費増加の原因は、第一に医療技術の急速な進歩、第二に少子高齢化があげられています。
従って、より効率的な医療資源の配分が求められています。
わが国では数十年間、世界保健機関(WHO)も世界一と認定してきたような、健康寿命が長く、かつ、医療を受ける機会の平等性に優れた「国民皆保険制度」を維持してきました。しかし、今、その国民皆保険制度は崩壊の危機を迎えています。
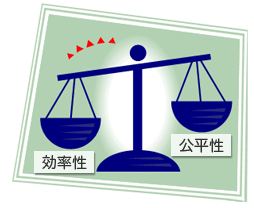 一方、海外に目を向ければ、すでに英国など複数の欧州各国では10数年来医療制度が危機に陥り、医療の公平性(衡平性)を保ちつつ効率性をいかに向上するか、また、同時に医療のイノベーションを阻害しないための様々な工夫が行われてきています。
一方、海外に目を向ければ、すでに英国など複数の欧州各国では10数年来医療制度が危機に陥り、医療の公平性(衡平性)を保ちつつ効率性をいかに向上するか、また、同時に医療のイノベーションを阻害しないための様々な工夫が行われてきています。
今、わが国では、これらの海外の工夫に学び、かつ、日本の国民皆保険制度のいい点を保った新たなシステムの構築が求められています。
そこで、本研究室では、医療の「効率性」を追求するために、医療経済評価、特に費用対効果を医療技術の評価(health technology assessment: HTA)に応用するための基礎的、応用的研究と、医療の「公平性(衡平性)」を保つためにはどのような工夫が必要か、に関する基礎的、応用的研究を、医療経済学者、倫理学者、などの協力を得て推進しています。
6. 在宅緩和医療システムの開発
がん患者や高齢者が増えていますが、病院の数は減っています。しかし、在宅や地域の受け皿が整っておらず、いわゆる、がん難民、介護難民が増えつつあります。
在宅医療を行う場は、病院と違い地域そのもので広範囲です。また、医師や看護師、薬剤師だけでなく、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、さらにケアマネジャーなどの介護の専門家、社会福祉士、その他、行政、ITC関連企業、など多職種が関わるチーム医療が必要です。
これらを解決するための、新たなシステム構築を目標として、質的・定量的研究を行っています。
7. 上記の研究を支える公的資金助成
本研究室は、その研究的価値を認められ、多くの学外公的資金助成を得てまいりました。
最近(2008年度以降)、支援を受けている主な公的資金助成は下記です。
文部科学省科学研究費
| 研究種目 | 研究課題名 | 研究代表者 | 開始(採択)年度 | 終了(予定)年度 |
| 基盤研究C | 効率的かつ公平な医療資源配分方法の確立に関する基礎的研究 | 下妻 晃二郎 | 2016 | 2018 |
| 基盤研究C | 地域における客観的な評価による日常の身体活動量と医療費に関する研究 | 村澤 秀樹 | 2016 | 2018 |
| 挑戦的 萌芽研究 |
医療におけるラショニングの基礎的検討 | 齋藤 信也 (岡山大学) |
2013 | 2014 |
| 挑戦的 萌芽研究 |
医療経済評価における閾値測定研究:東アジアでの国際比較調査 | 下妻 晃二郎 | 2012 | 2012 |
| 基盤研究B | 緩和ケアの新たな展望へ向けた研究:診療ガイドラインと患者の価値観・QOLの課題 | 宮崎 貴久子 (京都大学) |
2012 | 2015 |
| 基盤研究B | 新医療技術の社会への適切な応用を目指して−公正な医療資源配分方法の確立 | 下妻 晃二郎 | 2011 | 2014 |
| 基盤研究B | 緩和ケアへの移行と実施の円滑化に向けた研究:診療ガイドラインとQOL評価の課題 | 宮崎 貴久子 (京都大学) |
2009 | 2011 |
| 基盤研究C | 多職種関与による適切な在宅緩和ケアシステムの開発 | 下妻 晃二郎 | 2008 | 2010 |
文部科学省以外からの公的研究費
| 資金制度・研究費名 | 研究課題名 | 研究代表者 | 交付年度 | |
| 開始(採択)年度 | 終了(予定)年度 | |||
| 厚労省科研 | 医療給付制度への応用のための医療経済評価における技術的課題に関する研究 | 福田敬 (国立保健医 療科学院) |
2013 | 2013 |
| 厚労省科研 | 医療経済評価を応用した医療給付制度のあり方に関する研究 | 福田 敬 (国立保健医 療科学院) |
2012 | 2012 |
| 厚労省科研 | 医療経済評価の政策応用とガイドライン開発に関する予備的研究 | 福田 敬 (東京大学) |
2011 | 2011 |
| 厚労省科研 | 医療経済評価研究の政策への応用に関する予備的研究 | 伏見 清秀 (東京医科 歯科大学) |
2010 | 2010 |
| 厚労省科研 | がん患者や家族が必要とする社会的サポートやグループカウンセリングの有用性に関する研究 | 保坂 隆 (東海大学) |
2007 | 2009 |
| 厚労省科研 | 第3次対がん総合戦略研究事業、がんの医療経済的な解析を踏まえた患者負担最小化に関する研究 | 濃沼 信夫 (東北大学) |
2007 | 2008 |