Special interviewJST「創発的研究支援事業」採択者懇談会
「創発」研究者と大学が語る
支援の最前線と未来ビジョン
ー第2回 JST「創発的研究支援事業」採択者懇談会ー
2024年度「創発的研究支援事業」に、立命館大学から理工学部の小林 大造教授、薬学部の林 嘉宏教授の2名が採択されました。今次の懇談会では、他大学在籍中の2022年度に同事業に採択された生命科学部の竹俣 直道准教授を含む3名の研究者が仲谷 善雄総長、サトウタツヤ副総長、野口 義文副学長と大学としての支援や今後の展望について意見を交わしました。
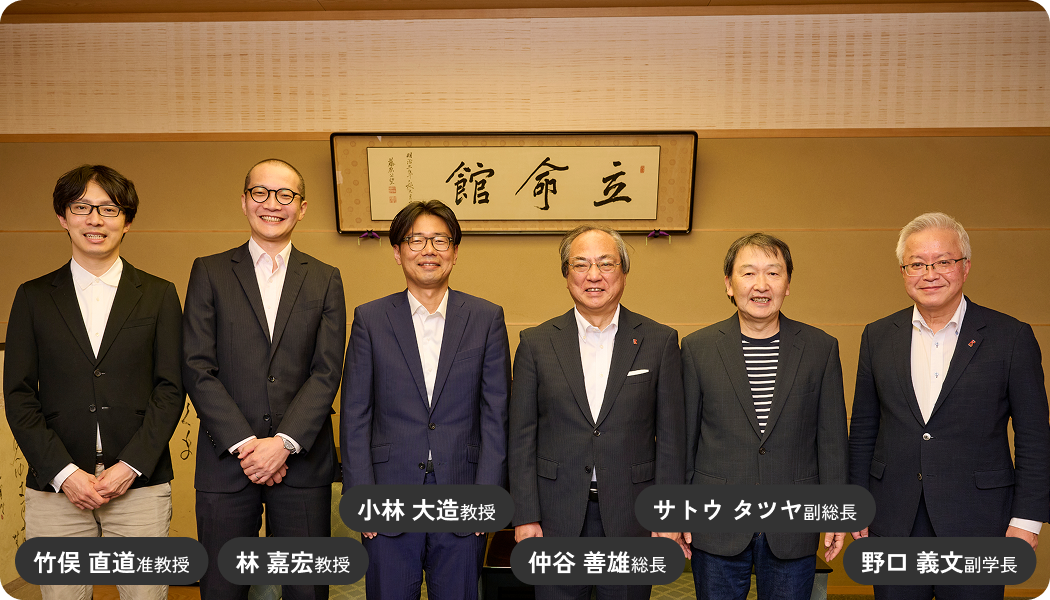
独創的な着想と挑戦で
社会にインパクトを与える研究が生まれる
仲谷
立命館大学は研究環境の充実化を通して、研究成果を社会にインパクトを与えるレベルへ高めていくことを目指しています。今日は、皆さんの研究の内容とそこに込められた思い、そして未来へのビジョンを伺いたいと思います。
小林
ありがとうございます。私は、フィルム型太陽電池の研究をしています。従来の太陽電池は、光をあてると光の強さに応じて一定の電力を出力します。一方で私が研究するフィルム型太陽電池は、光の強弱だけでなく、光が点滅した場合の繰り返し回数、周期や光の強さといった「情報」に反応します。たとえば、光を繰り返し当てると発電能力が上がり、その後ゆっくりと下がるという特性を持つのです。これは人間の網膜がインパクトの強い画像を見た後に残像が残る感覚と似た挙動といえますね。網膜内では「シナプス」という神経の一部が情報を残すかどうかの判断を行っていますが、このデバイスも同様に、非常に少ない電力で高効率に情報を処理して発電量をコントロールしています。この太陽電池をたくさん並べ、新たな情報処理ハードウェアとして実用化することが目標です。
林
私はもともと血液内科医として、白血病などの患者さんを診療していました。しかし約20年前は、治療が難しい患者さんも多く、臨床医としての限界を感じることも少なくない日々。そうした中、病気の仕組みを解明することが将来の治療法につながるのではないかと考え、研究の道へ進みました。
アメリカでのがん研究を経て、最近、がん患者が痩せ細る「悪液質」という状態を引き起こす新しい免疫細胞(CiM)を見つけ、論文で報告しました。そこから発想を広げて、老化によって筋肉が痩せる「サルコペニア」にも、まだ知られていない免疫細胞が関与しているのではないかと考え、今回のテーマを組み立てました。2023年に立命館大学に着任し、リサーチオフィスの方に他学部の先生とつないでいただくなど総合大学の環境があったからこそ、さらに研究が発展し、採択につながったと思っています。

竹俣
私たちヒトを含む真核生物の起源とされるのは「アーキア」という微生物です。私の研究は、その微生物のゲノム構造を解明するというもの。真核生物は「クロマチン」と呼ばれるタンパク質複合体によって遺伝情報の機能が成立していますが、アーキアはクロマチンのプロトタイプともいえるゲノム構造を有しています。この構造と機能を理解することは、まさに真核生物の起源の解明につながるのです。

また、アーキアは高温など極限環境で生育するというユニークな性質や、我々がもっていない代謝経路を持っています。クロマチンの構造を理解し、ゲノムを操作できるようになれば、そうした特性を応用する術につながるのではないかと考えています。
仲谷
改めて皆さんの研究内容を伺うと、着眼点が面白いですね。そして、それが社会の役に立つという点が素晴らしいと思います。それぞれがチャレンジする姿勢から、これなら採択されるな、と納得しました。大学としても、研究費の提供等を通じて挑戦を後押ししていきますので、ぜひ3年目の中間評価(ステージゲート審査)をクリアしてほしいです。また、本学としては、より良い研究環境整備を進めていきたいと考えています。取り入れるべき制度や支援内容について、創発研究者として率直な意見を聞かせてください。

サトウ
小林先生は本学の附属校の出身ですね。我々が重視している初等中等教育から、博士、中核研究者まで一気通貫の創発性人材活躍を支援するシステム構築のために、一貫教育の視点でも知恵を貸してほしいと思います。林先生は「混ざるのが好き」と伺っていますので、ぜひ台風の目のようにエネルギーを吸い上げながら大きくなってほしいですね。竹俣先生は京都大学在籍時に本事業に採択され、立命館でご自身の研究室を開かれました。リサーチオフィスの職員が一丸となって支援していますが、まだ足りないところがあれば遠慮なく申し出てほしいと思います。
野口
創発的研究支援事業は、将来のノーベル賞候補を育てる意気込みで始まった、採択率10%前後の最難関の若手・中堅研究者の支援事業です 。2024年度に、私立大学で採択されたのは慶應義塾大学が3名、順天堂大学が3名、そして本学が2名です 。本学は、医学部を有さない大学でありながら、若手研究者の研究力が非常に高いと認知いただけたのではないでしょうか。また、本学では、論文としての成果だけでなく、研究の社会実装が非常に重要であると考えています。そのための支援も整備していきたいと思います。

無限に広がる研究の可能性
小林
私の開発しているデバイスは、光に反応するだけでなく、力を加えたり変形させたりすることにも応答します。そのため、視覚のシナプス機能だけでなく、触覚を司るような機能も同時に実現できる可能性があります。物を「見て」「触れて」認識するというプロセスは、これまで主にソフトウェア(プログラミング)によって処理されてきましたが、今後はそれをハードウェア(デバイス)側でも実装することを目指して取り組んでいきます。
仲谷
触覚は非常に難しい部分で、ロボット工学の分野でも、ソフトロボティクスなどで「柔らかさをどう測るか」という点で苦労すると聞いています。
小林
そうですね。理工系のモノづくりでは、ハード面の特徴を打ち出すために、まず地盤をしっかり固める必要があり、その準備にどうしても時間がかかります。そうした中で、科研費獲得のためにサポート資金を助成いただける学内制度(科研費獲得推進プログラム)での財政的支援や研究部職員の皆さまからの粘り強いアドバイスを得て、少しずつ形になってきました。

野口
本学では、研究者一人ひとりの多様な挑戦を加速する24の研究高度化推進プログラム(※取材当時)を用意しています。また、リサーチオフィスにURAなど高度専門人材を配置し、研究支援を行う体制を整えてきました。本学の研究環境が小林先生の研究の後押しになったとのこと、大変嬉しく思います。
仲谷
林先生は、本学では珍しく国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の競争的資金に採択されていますね。
林
はい。「次世代がん医療加速化研究事業」として、今回の「サルコペニア」研究の発想元になったCiMの研究が採択されました 。社会実装に向けてしっかりと結果を出さないといけないと頑張っています。私が所属するびわこ・くさつキャンパスには、2025年に「立命館先端クロスバースイノベーションコモンズ」(CVIC)という研究拠点ができました。本拠点を活用して、研究をさらに発展させていけたらと思います。

仲谷
本学では、多重環境化社会におけるウェルビーイング課題を解決すべく、立命館大学の強みであるスポーツ健康科学を核とする「身体圏」という新学術領域の創生に挑戦しようとしています。今、話題に出たCVICは、現実と仮想が融合する「多重環境化社会」に対応した最先端の研究拠点です。仮想世界を含む環境介入と、身体・心理・生体の同時計測を可能にする設備を備えています。ぜひ、分野横断型で研究を進めてほしいと思います。
竹俣先生の研究について、もしアーキアのDNAが真核生物のDNAの起源となっているとすれば、DNAそのものの誕生が、もともと極限環境で起こった可能性も考えられるのでしょうか。
竹俣
生命の起源が極限環境にあった可能性は十分に考えられます。私自身も、高温環境で生きる「好熱菌」を主な研究対象としており、真核生物や初期生命とのつながりを探っています。ただ、私たちが扱う生き物は酸素を嫌う“嫌気性”です 。そのため、嫌気ボックスの中で細胞を植え継ぐ必要があり、少し手間がかかります。それでも、生物を適切に保管・維持する技術を確立できれば、世界をリードするような研究につながるのではないかと考えています。

野口
極限環境と聞くと、宇宙や南極といった場所を思い浮かべます。本学では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が公募する令和6年度「宇宙戦略基金事業」において、「技術開発テーマ・SX研究開発拠点(課題名:月面探査・利用を産業化するための宇宙機器開発・人材育成拠点)」に採択され、宇宙分野への挑戦を続けています。このような分野を超えた連携なども積極的に進めていければと考えています。
サトウ
たとえば、月に存在する膨大な水資源は、将来的に火星探査への活用が期待されています。しかしながら、こうした解析は工学の力だけでは完結しません。もし異分野の先生方との研究がつながれば、宇宙研究にも新たな可能性が生まれますね。

仲谷
宇宙に限らず、16学部・21研究科、6機構・16研究所・34研究センター(※2025年10月現在)の多様な研究者とつながることは、新たな知を築くチャンスでもあります。「立命館」が新たな価値の創出の源泉となれるよう、取り組んでいきたいと思います。
若手研究者への想い-
教育と研究の好循環で未来の研究者を育てる
野口
例えば、日本学術振興会の特別研究員として活躍できるような優秀な博士課程後期課程の学生を育成・輩出していただければ、非常に嬉しく思います。創発的研究支援事業の目的の一つは、まさにその点にあります。国内で博士人材活躍が求められるなか、博士人材の指導体制や安心して研究ができる環境、キャリアパス構築の支援を進める必要があります。博士人材を雇用するための予算が別枠で確保されていますので、ぜひ積極的に活用いただき、次世代の人材育成に力を貸していただけたらと考えています。

サトウ
人材育成の観点は非常に重要です。現在議論を進めている第5期研究高度化中期計画においては、単なる研究高度化ではなく、立命館学園全体の研究・教育(人材育成)の高度化に資する内容を検討しています。
野口副学長から発言のあった博士人材はもちろんのこと、学部学生や修士の大学院生を含めて、研究活動を授業や指導に生かしてもらいたいと考えています。
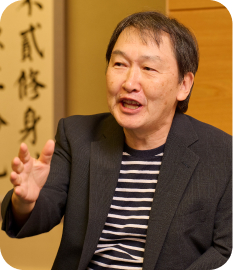
仲谷
立命館学園全体の中期計画にあたる「R2030チャレンジ・デザイン」では、「研究と教育の拡大的再結合」という表現で、研究成果の教育への還元を目指しています。2030年に立命館が目指す「次世代研究大学」の実現に向けて、先生方のような若手研究者の皆さんがより一層活躍し、人材育成の面でも良い循環が生まれるよう、より一層の研究環境の整備と制度の充実に取り組んでまいります。

