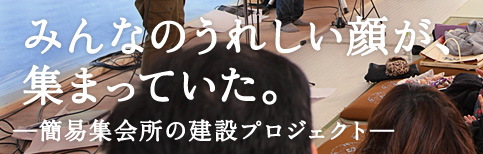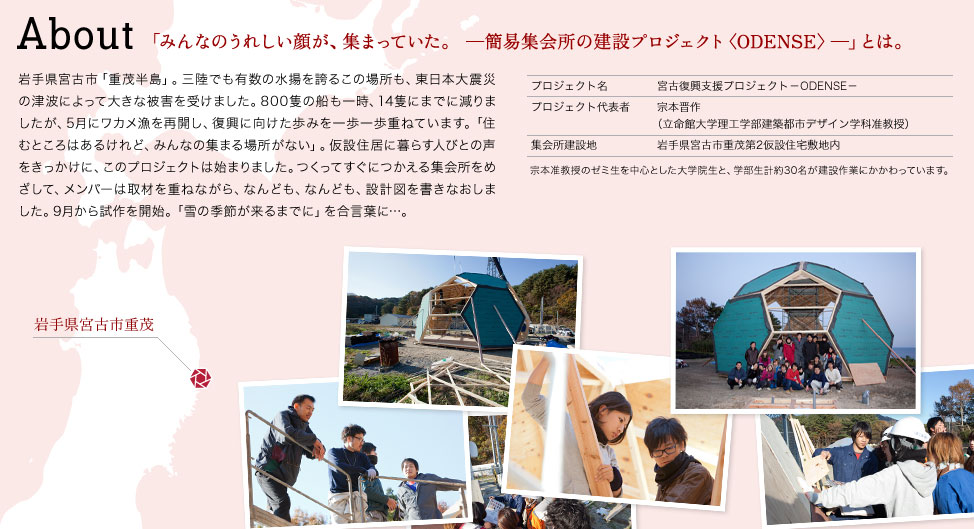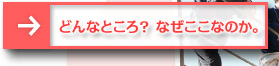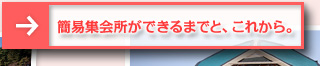![]()
![]()
京都のラジオ局αステーションでオンエア中のRadioB☆B。
2011年9月17日(土)のオンエアに、今回の簡易集会所建設プロジェクトを進める
理工学部建築都市デザイン学科の宗本先生と2名の院生が出演。
このプロジェクトへの意気込みなどを熱く語りました。
進行は、DJのしもぐち★雅充さんです。
「RadioB☆B」毎週土曜日 20:30~21:00
京都αステーションにて放送中!
- しもぐちさん
- 東日本大震災の復興支援活動をおこなう研究者、学生のみなさんにスタジオにきていただいてお話を伺います。本日来ていただいたのは。
- 宗本
- 立命館大学理工学部建築都市デザイン学科教員の宗本です。
- 酒谷
- 理工学部建築都市デザイン学科の大学院1回生の酒谷です。
- 右近
- 理工学部建築都市デザイン学科の大学院1回生の右近です。
- しもぐちさん
- 今日はよろしくお願いします。
- 一同
- よろしくお願いします。
- しもぐちさん
- 理工学部と聞いてちょっと硬いイメージ、何事も机の上でいろいろ考えているイメージですが。
- 宗本
- 建築都市デザイン学科はそんなことないです。絵を描いて、楽しく模型を作って、徹夜してっていう感じです。
- しもぐちさん
- 声だけ聞いていると、学生さんが3人来ているかなという感じです。若いんですよね。
- 宗本
- いやいやもう若くないですよ。気分だけでも学生と一緒で。
- しもぐちさん
- 打ち合わせで話を聞かせてもらったら、僕より先生2つか3つ年下なんですけど、しっかりしてはりますよね。さずが先生というだけのことはあります。
- 宗本
- いやぁ、なんちゃってです。
- しもぐちさん
- 大学院の学生さんとチーム宗本として活躍されているんですよね。どんな活動を。
- 宗本
- もともと建築都市デザイン学科は、設計活動が主体の研究室なのですが、設計するにあたって社会とかかわりをもって設計活動をおこなうということが建築家にとって一番重要だと思うのです。その心を何とか実践の中で学生に見せて、学んでもらうと。たとえば今回のように、震災があった場合にそれに向けてどういった活動をするかということが、僕にとって学生に伝えるべき一番重要ことではないかと思いまして。それを復興支援活動の内容にこめて、仮設の集会所を仮設の住居の隣につくると提案しました。
- しもぐちさん
- 僕は今40歳で、16年前に阪神・淡路大震災が起こりました。僕はそのときにはすでに働いていたのですが、そのとき先生はまだ学生さんだったんですね?
- 宗本
- 僕は大学3回生でした。
- しもぐちさん
- そのときに、自分の無力感を感じられて、何もできなかったと。大人になって大学の教壇に立たれる立場になって、今度は何かできるのではないかと思って、立ち上がられたんですね。
- 宗本
- そうですね。大学生のときは現場を、自分のバイクで見に行って被災状況はわかるんですけど、自分では何もできないですし、今回もそういう場面を反省して、震災を受けて5月に現地に改めていった時に、現地の状況を伺って、仮設住居が実際に孤独死など、コミュニティがないことでそういった問題を抱えていると。小さい仮設住居や民間企業が支援できない小さな仮設住居には、特にそのような問題が発生しがちだと。
- しもぐちさん
- 学生のみなさんはどういった役割を?
- 酒谷
- 東北にいるときに、現地でのコーディネータの方にプレゼンするための資料を作ったり、今回集会所を作るにあたって、模型をつくったり鉛筆スケッチを描いたりしてデザインの探求等をしています。
- 右近
- 僕も酒谷くんと一緒に。僕は主に模型作りをしています。
- しもぐちさん
- 模型は、サッカーボールを半分にきったようなカタチですね。
- 右近
- そうですね。
- しもぐちさん
- バルセロナのユニフォームも着ているし、サッカー大好き?
- 右近
- 僕は、ずっと野球をやってましたね。
- 酒谷
- 僕は、サッカーをしていました。
- しもぐちさん
- 逆やん!
- 右近
- 一応、このTシャツすごい意味があるんですよ。これ現地の震災に対する復興の思いを込めて、災害に対して×を入れているんです。
- しもぐちさん
- 学生たちも一生懸命何かしなければという思いが強いと思うんですが、今プロジェクトは始動しはじめた感じですか?
- 宗本
- 今、始動し始めて、佳境ですね。先ほどお見せした模型をベースにあれをどうやって作るかを原寸大の木のフレームを使ったりして検証しているところです。
- しもぐちさん
- 現地調査を含めて、現場に行かないと見えてこないものがありますよね。
- 宗本
- 現地の要望がわからなくなる可能性はありますので。
- しもぐちさん
- コミュニティスペースといった場所は重要なのですか。
- 宗本
- 人が集まって、どういう風にコミュニケーションをとっていくかというときに、集まる場所があってはじめてコミュニケーションをとって、グループができていくと思うんですけど、単に住まいだけがあっても多分集まる場所がなければ近所づきあいもおきないですし、近所づきあいを作り出すための大きな輪を作るというか、コミュニティスペースがないと。
- しもぐちさん
- 今ほぼ仮設住宅は完成しているような状況ですか。
- 宗本
- 僕らが行っている場所自身は仮設住居はほぼ完成していて、ただ、集まる場所はない。
- しもぐちさん
- プライベートな空間は確保できているけれども、昔の集会所のようなみんなが集まってわいわいできるよう場所はまだないと。
- 宗本
- そうですね。街中とか大きい被害があって、支援が行き届いているところには集会所はできてきています。ただ、小さいコミュニティの場所にはまだないです。
- しもぐちさん
- 今回、岩手県の宮古市に行かれたんですけれども。どんなところですか。
- 宗本
- 場所は湾岸沿いの漁師さんが住まれているエリアです。仮設住居としては15世帯が入っていて、そこに漁業組合の簡易作業場はあるのですが、本当に作業場だけで、広い場所にぽつんとあるだけなんです。
- しもぐちさん
- 何月に入られたのですか。
- 宗本
- ここに見に行ったのは7月です。
- しもぐちさん
- 震災から4ヵ月後。瓦礫も撤去されず、仮設住居もまだしっかりできていない感じですか。
- 宗本
- 宮古の仮設住宅はできていました。瓦礫のあったエリアとは別に、被害のあったところから海沿いの高いところに設計されているので、完全更地の場所にぽつんと仮設住宅があるんです。ただ、見晴らしは抜群で、海を見下ろせるいい場所です。
- しもぐちさん
- 京都の学生が震災支援だときたところで、なかなか受け入れてもらえないのは?
- 酒谷
- 最初どうやって声をかけたらいいかがわからなくて。仮設の人が飼っている犬がほえているのをなだめて、そこからおばあちゃんと話かけるきっかけになりました。動物がつないでくれました。
- しもぐちさん
- 岩手というとなまりもあって、コミュニケーションをとるのが難しいのでは。
- 酒谷
- 僕は、名古屋の出身で、関西でも抵抗があったのに、岩手では本当に何を話しているのかさらにわからない方言はありました。
- しもぐちさん
- どんな調査をまずされたのですか。
- 宗本
- 実際に住まれている方の年齢、必要とされているものを中心にヒアリングですね。
- しもぐちさん
- いらないものを作ってもしょうがないですもんね。
- 宗本
- それが一番重要なので。望まれているものをつくらなければならないので。
- しもぐちさん
- それが「笑いだ」といわれたらどうされるつもりだったんですか。
- 宗本
- それはもう、芸を磨いて練習して、それから東北に入るとか。
- しもぐちさん
- そこにはいったからには最後まで支援しないとね。調査した結果、何が必要とされていましたか。
- 宗本
- 高齢者のコミュニティだったので、高齢者を元気づけるためにもちろん笑いが一番必要でした。それプラス、水周り、トイレ、キッチンとお風呂ですね。特に、お風呂に対する思いが強くって、みんなでお風呂に入れるといいなという要望はありました。
- しもぐちさん
- 日本人ですから、温泉とかゆっくり使ってみんなと一緒に裸の付き合いとかね。
- 宗本
- 裸の付き合いが大事だと思うんですよね。
- しもぐちさん
- 酒谷君は、裸のつきあいは?
- 酒谷
- つぎいったときに挑戦します。
- 右近
- 現地の人とは一緒にお風呂は入っていないですね。9/18~19にまた現地にいきますので。
- しもぐちさん
- まずは、お風呂に入ろう。そのときに面白ネタを。
- しもぐちさん
- 実際に調査をされて、発見したことはなんですか。
- 酒谷
- 現地に行く前に想定していた案があったんですけど、実際要望と規模が違ったりということがあって。
- しもぐちさん
- 想定していたものより高いレベルのものを求められるんだね。
- 右近
- 最初集会所を作ってくれということで、ドーム型の模型を作ったのですが、やたらとお風呂を勧められてなんでなんかなと。
お風呂には意味があって、仮設住居に引きこもらず、お風呂に入るようになることで、裸になることで健康状態がわかるんですよね。
- しもぐちさん
- お風呂は重要なんですよね。
行ってみないとわからないものがたくさん出てきたということですね。
- 宗本
- 想定していることと現地が本当に困っていること、必要としていること、要望していることをちゃんと聞くことによって、イメージして必要なものをちゃんとつくるということが仕事として大事だなと。
- しもぐちさん
- 先生が一番びっくりされたことは。
- 宗本
- 人の強さに一番びっくりしました。しょげている感じがまったくなくて、生きていることがラッキーで、お互いが助け合ってボランティアセンターと協力しながら地域を元気にしていこうという人がかなり多いんです。
- しもぐちさん
- コミュニティの平均年齢はどれくらいですか。
- 宗本
- この仮設住宅に住まれている方は、60歳以上です。宮古のボランティアセンターで活動されている人は僕たちと同世代。30代半ばくらいです。すごく前向きでこちらが元気になります。
- しもぐちさん
- 被災地に行くことで、まずボーダーを超えた。
実際に現地に行って想定していなかった課題がたくさん出てきた。こんどはそのボーダーを超えていくと。
- 右近
- 11月ごろから学生のチームと東北に行って、実際の施工にかかります。現地のサポートもあり、みなさんと一緒に力を合わせてつくっていいきたいと思います。
- しもぐちさん
- 模型ではかなり大きいですよね。
- 宗本
- 半径5メートル、高さ5メートルの完全なドームです。
今どうやって作ろうかと学生と一緒にめちゃくちゃ悩んでいます。
- しもぐちさん
- あれができれば後世に残っていくようなコミュニティスペースになるかもしれませんからね。
- 宗本
- つくったものが現地のすぐに役に立つ、建築は結果がでるまでにかかるんです。急務でつくって、すぐに貢献できるということがぼくらにとってもいい経験になります。
- しもぐちさん
- チーム宗本だけでは難しいところ、できないところもあると思います。
- 右近
- つくる規模が大きくなり、資材もたくさん必要になりました。大学だけの活動では、入手経路がなくて不足していますので、パイプ1本、ねじ1個でもください。
- 宗本
- 仮設住居に中にスキルをもった大工さんを見つけたんです。学生に指導していただきながら、ひとつの課題であったスキルの問題はクリアしました。資材が必要なんです。人出も、できれば多くの人に関わってもらいたいです。関西から一緒にいって盛り上げていければと。
- しもぐちさん
- みなさんもぜひ力を貸してください。
- 宗本
- 実際に被災地での活動に参加して、今回ラジオにも出演して、みんなで一緒にやっていくモチベーションが生まれたのではないかと思います。9月にもう1回現地に入って、10月の頭から中旬に現地と調整しながら施工に向けて準備をすすめ、11月中には完成できるように、雪が降る前にできるように。
- しもぐちさん
- 素敵なコミュニティスペースができるといいですね。
- 宗本
- 現地の人にも感動してもらって、自分たちも感動したいと思います。
- 酒谷
- がんばります。ぜひ応援よろしくお願いします。
- しもぐちさん
- コミュニティスペースを見に行く、元気になれることもかんがえていきたいです。
- 宗本
- 魚もおいしい場所ですので、ぜひ行きましょう!