|
2006年12月23日(土)
「教員養成GP公開研究会・立命館学校教育研究会設立総会および第1回研究会(分科会)」を開催しました。
教員養成GP公開研究会は、「学校教育臨床研修プログラム受講生によるポスター発表」と「教員養成GPの概要と2年間の成果報告」の2部構成で行いました。
ポスター発表では、17組の学生が、「特別支援教育は学校現場に浸透しているのか」、「総合的な学習の時間の実
態とそのあり方」、「特色ある教育は何故必要なのか」など、ポスターと配付資料による学習成果発表を行い、参加者との質疑応答やアドバイスを受けました。
 
また、教員養成GPの採択期間終了を前に、教員養成GP推進プロジェクト事務局長の湯川笑子文学部教授より、プロジェクトの概要と2年間の成果報告を行いました。
その後、受講生2名が、プロジェクト科目と教職関係科目との関連、課外に実施した様々な活動、プログラム
を通じて身につけた力や今後の課題、等について発表しました。
あわせて、これまでに作成した報告集や授業案集、4回にわたる合宿のしおり等、こ
の2年
間の成果物の展示や模擬授業ビデオの上映を行い、実践的力量向上にむけた取組の紹介を行いました。
  
引き続き開催した立命館学校教育研究会設立総会には、近畿地方を中心に約80名の教育関係者が参加しました。この立命館学校教育研究会は、立命館の校友教員や附属校
教員を含めた教職員をはじめとして、教育に関わろうとする者が学校教育における教育実践交流や研究活動などを行い、広く日本教育界に貢献することを目的と
した研究会です。
総会
では、立命館学校教育研究会の設立および会の運営にかかわる申し合わせ、運営委員15名(会長1名・副会長2名含む)が承認され、代表して、会長に就任した﨑野隆教授が挨拶を行いました。続いて、
上田高弘教授(運営委員)より、2007年度研究会活動計画について説明があり、承認されました。
その
後、第1回研究会として、3つの分科会<第1分科会:立命館小学校における学力向上への取り組み 深谷圭介氏(立命館小学校教頭)、第2分科会:学校教育
における「家庭との連携」の重要性~公立中学校の現状から 宗像玲氏(長岡京市立長岡第二中学校教頭)、第3分科会:不登校・ひきこもりと支援ネットワー
ク 春日井敏之(立命館大学文学部教授)>を開催しました。各分科会とも、学生・院生を含む約40名が出席し、報告者の内容を受けた質疑応答や各学校現場での実践例・今後の課題などにつ
いて熱心な意見交換を行いました。参加者からは、今後も都道府県、校種を越えたこのような研究会の開催要請や、学校現場は日々厳しい状況であるが、この会
に参加して元気をもらったなどの感想が寄せられました。最後は、諒友館地下食堂において懇親会が開催され、盛会のうちに終了しました。
2006 年7月29日(土)
講演会「こ
れからの国語教育」を開催しました。
京都橘大学文学部教授で独立行政法人国立国語研
究所前所長の甲斐睦朗氏を講師にお招きし、これからの国語教育について講演していただきました。
講演の中で、甲斐氏は、国語教育と国語科教
育の違いや国語科における2種の異なる目標、文化審議会答申(平成16年2月)に盛り込まれている提案等について、大
変穏やかな口調で語られました。
講演のあとには、参加者との質疑応答を行
い、講演内容をより深めることができました。
 
2006年5
月13日
(土)
シンポジウム「今、求められる教師の力量と学校改革」を開
催しました。
当日は雨にもかかわらず、会場は約300名の教員校友、学生、市民などの参加で熱気
あふれる、内容豊かな研究会となりました。
第1部は、東京大学大学院教育学研究科教授 佐藤学氏から「今、
求められる教師の力量と教師教育―教える専門家から学びの専門家へ―」と題する基調講演が行われました。
佐藤氏は、教育における規制緩和や格差社会と「受難の時代の教師」「教職の危機」について触れながら、教師の力量形成にとって、理論と実践を統合するケー
ス・メソッド(事例研究)の重要性を指摘されました。そのための課題として、①教師の同僚性の構築、②校内研修の充実、③公共性、民主主義、卓越性の尊
重、④実践者と研究者の協同が強調されました。
第2部の実践交流シンポジウムでは、春日井敏之文学部副部長の司会のもとで、神戸市
立板宿小学校 大川昌利氏より授業・学級づくりの実践、京都市立弥栄中学校 澤田清人氏より人権・同和学習、大阪府立千里高等学校 南太一郎氏より新学科
設置の学校改革に関する報告が行われました。3名の先生から報告を受け、参加者を交えた活発な質疑応答、意見交流が行われました。
コメンティターの佐藤氏からは、学校改革に際して、①内側からしか改革は進まない、②教師だけで改革をしない、③改革のビジョンと哲学を持つ(学びの協同
体)、④子どもに対する責任を取る校長、⑤改革をあせらないこと、などが提案されました。同時に、3名の先生の報告から、子ども、保護者、教職員からの
フィードバックを求め、改革の検証と修正の姿勢を持つことの重要性が共通点として確認されました。
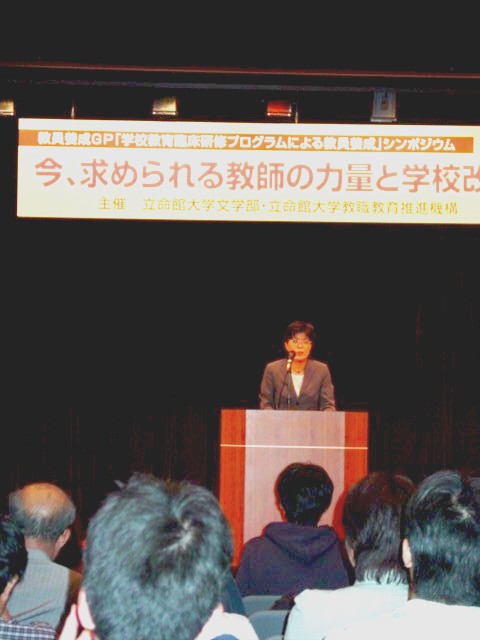  
その後、会場を移して、立命館大学教員校友を中心に
懇親会が持たれ、「立命館大学教員校友・学校教育研究会(仮称)」の設立に向けた準備委員会を立ち上げることが了承されました。
2005 年 12月3日(土)
講演会「生き方を学ぶ高校生~サラワク・スタディーツアーを通して~」を開催しました。
1998年より研修旅行「サラワク・スタ
ディーツアー」を実施している広島工業大学附属広島高校
教諭 野中春樹氏を講師にお招きし、研修旅行の構想を思い立った背景、実施の経緯や苦労、
研修旅行を通じた生徒の成長等を中心に講演していただきました。
 
2005 年 11月 5日(土)
講演会「イマージョン教育とは何か」を開催しました。

講師にはイマージョン研究の専門家である Roy Lyster
氏(マックギル大学助教授)をお招きし、
イマージョンがイマージョン教育と言われるために最低必要な内容やどのように工夫すればより充実
させることができるのか、といった点について講演していただきました。

|