この授業では、主に『映像制作実習Ⅰ』で学んだことや、『映像制作実習Ⅱ』で新たに身につけた映像制作スキルを活かして、実写におけるショートムービーの制作を行います。学生が数グループに分かれて、それぞれ個性的な作品の制作を行っています。グループワークを行いながら監督や照明、カメラ、音響などの様々なパートの映像表現と向き合い、最終回で行われる上映会に向けてひとりひとりが真剣に取り組んでいます。
特色ある教育
1.仲間と作り上げる ~ピア・ラーニング~
映像学部では、少人数だからこそできる演習・実習科目を数多く設置しています。それらの授業ではグループワークが多く、1回生の時点から、仲間と一緒に課題に取り組み、1つのモノを作り上げるという経験をしていきます。時には意見のぶつかり合いが起こりつつも、より良いモノにするために議論を重ね、試行錯誤していく。同じ道を志す仲間であり、またライバルでもある存在との共同作業を通して、コミュニケーション能力が磨かれます。 また、映像基礎演習をはじめとして、先輩学生が授業のサポートに入っている科目も多く、学生同士の学びあいの機会となっています。
2.現場の知に学ぶ ~産学連携~
実際の現場を経験してきた教員が多いことに加え、映画界やゲーム業界、テレビの制作の現場等で多大な功績を残してきた実力者、また各界の第一線で活躍する方々からも協力を得て、「プロの声」「現場の知」に触れる授業を実施しています。
3.関西から世界へ ~成果発信~
映像学部では、「卒業研究」を学びの集大成として位置づけており、その成果を「卒業論文集」や「卒業制作 展示・上映会」という形で発信しています。 学生の活動は大学内に留まらず関西圏が生み出してきたクリエイティブの歴史を肌で感じながら地域や一般社会に発信を行い、さらには世界を視野に入れた学生の成果発信を積極的に進めています。
- Stage1 映像制作実習
-

仲間と力を合わせ、映像作品をつくる。
監督や照明、カメラなど、各々の学生がやりたい仕事を担当。

学期末に上映会を実施。第一位をめざす。
ショートムービーの制作を通して、映像表現に関わる感性や技術を自ら養います。また集団で一つの作品を完成させる運営能力や、社会との接し方の基本も身につけます。学期の最後には全グループによる作品の上映会が開催され、狙うのはもちろん第一位。 様々な議論や制作に関わる作業の結果、生み出される作品を公開する瞬間は、学生生活の中でも特別な時間となることでしょう。
- Stage.2 クリエイティブ・リーダーシップ・セミナー
-

クリエイティブ・リーダーシップ・セミナー
業界第一線で活躍するベテランから人事担当者まで幅広い講師層
この科目は、映画監督、演出家、脚本家、ゲームデザイナー、グラフィックデザイナー、コピーライター、あるいは、美術分野や放送分野などリニア、インタラクティブを含む映像関連分野で活躍しているクリエイター、並びに同産業で活躍しているプロデューサーや経営者などを招聘したゲストによるレクチャーと、キャリア・マネジメント関連の講義で構成しています。 ゲストレクチャーについては、映像業界の第一線で活躍するベテラン(客員教員、訪問教員およびそれに準ずる講師)を講師としたリーダーシップ・セミナーと、映像業界でキャリアを積み始めて5年~10年程度の若手社会人または人事担当者によるキャリア創生・セミナーという二階層の講義構造となります。
過年度登壇企業などの例(順不同)
(株)電通、Unity Technologies Japan、(株)KADOKAWA、チームラボ(株)、松竹(株)、(株)博展、(株)セガ、UUUM(株)、(株)スクウェア・エニックス、(株)カラー、(株)バンダイナムコホールディングス
- Stage.3 社会的ネットワーク型授業
-
「社会連携プログラム」「学外映像研修」
社会的ネットワーク型授業とは?
「社会的ネットワーク型授業」は映像学部キャリア形成科目の一つであり、企業や学外機関と連携して、具体的な目標、目的を持ったコンテンツの共同開発、共同研究を実施する科目です。「社会連携プログラム」と「学外映像研修」の2つのタイプがあり、いずれも学生は実務経験に近い学習を行い、実践的な知識と技術を獲得することができます。
※授業内容や連携先は毎年変動する場合があります。「社会連携プログラム」
企業人を講師に招き、グループごとに与えられた課題に取り組むプロジェクト型の授業。ゲーム開発や劇場映画のプロモーションの企画・運営など、実務経験に極めて近い学習を行うことで、発想力や表現力を養成します。
過年度連携先
キヤノン(株)(キヤノングループ)、京都国際マンガアニメフェア(京都国際マンガアニメフェア実行委員会)、京都ヒストリカ国際映画際(京都映画企画市)、京都伝統産業ミュージアム、京都市交通局、(株)松竹撮影所、BitSummit、京福電気鉄道(株)、医療法人社団小室整形外科医院
学外映像研修
映像関連会社、映像制作会社、ゲーム関連会社など、多彩な企業・団体の現場に赴き、業務の一端を体験。実際に仕事を体感し、現場の厳しさや楽しさを感じながら、知識やスキルを吸収するとともに将来の方向性を見極めます。
過年度研修先
(株)IMAGICA.Lab、(株)AOI Pro.、一般社団法人DPCA(ドローン撮影クリエイターズ協会)、(株)松竹撮影所、(株)デジタル・メディア・ラボ
- Stage.4 映像文化演習(ゼミナール)・卒業研究
-

映像文化演習(ゼミナール)・卒業研究
3回生からスタートするゼミナールでは講義科目と実習科目の学びを統合し、各自のキャリアデザインを十分にふまえ、映像に関わる知識と技術を高めます。それを活かし、4回生では全員が「卒業研究」として、卒業制作あるいは卒業論文執筆を行い、自身の学びの総仕上げに取り組みます。下記では卒業研究の一例を紹介します。
実写映画

「神さまの心臓」 松本 理沙
右腕が動かないトランペット吹きの青年、心臓移植を受けた少女、過去を隠して暮らすシングルマザー、そして終活するオネエ。4人の運命の物語。
CG

「THE FAST FOX」 森本 真由
バイクに乗った主人公の狐が、パトカーに追われるショートアニメーション。デザインやフェイシャルアニメーションにこだわりました。
VR(ヴァーチャルリアリティ)

「MR Book:ミクストリアリティを利用したバーチャル書籍の体系化と活用に関する研究」 舘脇 望
ミクストリアリティ技術を用いた魚図鑑。図鑑下部に設置されているマーカを操作することで、魚のCGモデルがさまざまに動く。
ゲーム

「Gaze Eater」 脇阪 颯太
視線で進化する生物によって、無意識を可視化するコンテンツ。
メディアアート

「ピアノと映像による二重奏」 稲田 優太
「ピアノ×映像」によるパフォーマンス映像。ピアノの演奏をリアルタイムに解析し、そこから得た情報によってグラフィックを生成する。
ドキュメンタリー

「がらんどう」 壷内 里奈
最後に誰もが入る箱。その箱(棺)は、本当に焼くだけのものなのか。棺に関わる人々を通して、棺を調査した。
その他の作品は、こちらからもご覧いただけます。
- Extra Stage 世界へ
-
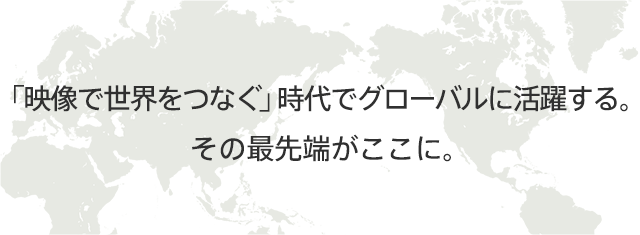
映画、ゲーム、アニメなど、日本発ポップカルチャーがグローバル規模で広がる時代。学生時代から世界の最先端に触れ、世界に発信する機会がここにはあります。自分たちが制作した作品を国際展示会に出展する、世界の学生と創造力を競い合う。世界の才能との出会いが、自らの内なる才能を開花させていきます。
コンテンツを世界へ"発信"
アジア最大級の映画・映像の見本市「香港FILMART」で世界の関心を引く
アジア最大級の映画・映像の見本市「香港FILMART」。世界各国から映画・映像コンテンツを持ち寄り、映画関係者が様々な交渉をおこないます。映像学部もここに出展し、商談の結果「映画制作論」で制作した映画をデルタ航空・KLMオランダ航空などの機内上映作品とする契約を結びました。

最新のデジタル映像やインタラクション技術に関する国際学会「SIGGRAPH Asia」にて展示・発表
最先端の映像テクノロジーの発表、デバイスやソフトウェアの企業展示、テクノロジー・アートの展示、国際会議や特別講義などが開催されるアジア最大の国際的な学会である「SIGGRAPH Asia」において、映像学部も学生作品の展示やトークセッションをおこなっています。自らの研究内容を国際的なスケールで発信し、交流していくことの意識を高めることができました。

欧州のバーチャルリアリティ展「Laval Virtual」で最先端に挑む
最新かつ選りすぐりのVR技術や研究、作品が発表される国際イベントLaval Virtualに、2012 年から継続的に映像学部生が参加しています。小中学生の理科離れ対策を課題として、シャーレなどの実験器具をVRデバイス化した「バーチャル生態系シミュレータ」など、様々な作品を発表してきています。

"授業"で世界を体感する
アメリカでハリウッド映画のCG制作現場に触れる“北米CG研修”
近代ハリウッド映画においてCGがたどってきた発展の歴史や、ハリウッドのCG制作会社の歴史とその活動について学ぶ特殊講義。実際にアメリカを訪問し、最新のCG映画制作の現場に足を踏み入れ、また優れた人材を数多く輩出する教育機関で学びます。

韓国でのフィールドワーク、映像記録を行う“グローバル映像社会実習”
「韓国社会におけるグローバル化」を研究テーマとし、社会内部におけるグローバル化と、韓国文化のグローバル発信の両面から学ぶ特殊講義。 韓国で現地調査や、K-Pop カルチャーの国際化に関わってきた専門家からの講義を受けるなどの見学活動を行います。

学内授業でグローバルを体験。「ジャパニーズ・ポップ・カルチャーの現状と展望」(2024年度カリキュラムからは「ファンダメンタルズ・オブ・ジャパニーズポップカルチャー」)
短期留学生の受講が多いこの科目は、外国人留学生に関心の高い日本のポップカルチャーを「学術」と「体感」の両方から修得できる特別科目。講義では、マンガ、アニメ、ゲーム、キャラクタービジネスを中心に、その特異性や世界への影響力について、日本の伝統文化や日本文化と関連付けながら学びます。

"留学"は目的でなく手段
【EIZOから海外へ】自分の「軸」をみつけられた貴重な8ヶ月間!〜カナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)へ留学〜
ジェンダーに関するカナダの研究や取組に興味があり、立命館大学の留学プログラムを利用してUBCへの留学を選択。カナダは予想以上に多様性を「受容」する文化が根付いていて、マジョリティからの無言の圧力が強い日本の課題を感じました。今後はLGBTQの問題を、あるyoutuberを記録映像で追いながら、多様性の認識の欠乏について研究していきます。

写真右 鈴木玲奈さん(4回生) 【海外からEIZOへ】日本でのキャリアも見据え、映像学部で学ぶ
「日本はアジアの文化中心として、映像業界が一番発展していると思い、日本の大学への進学を選びました。将来はチームで映像を制作する仕事に就きたいです」(ZHAOさん)「東京よりも“日本らしさ”を感じる京都が大好き。アニメを通じて国際関係改善を実現するプロデューサーになり、日韓の文化・社会を繋ぐ架け橋になりたい」(CHOさん)

写真左 ZHAO Naさん
(中国出身、3 回生)
写真右 CHO Kyungwonさん
(韓国出身、2回生)


 アクセス・お問合わせ
アクセス・お問合わせ


