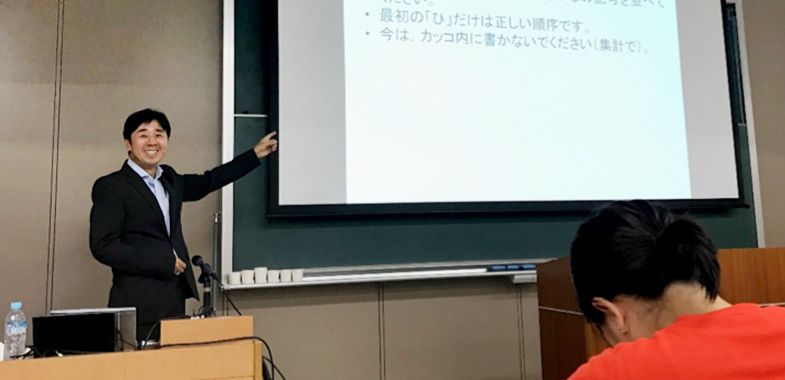教員紹介
YAMAMOTO Hiroki
山本 博樹
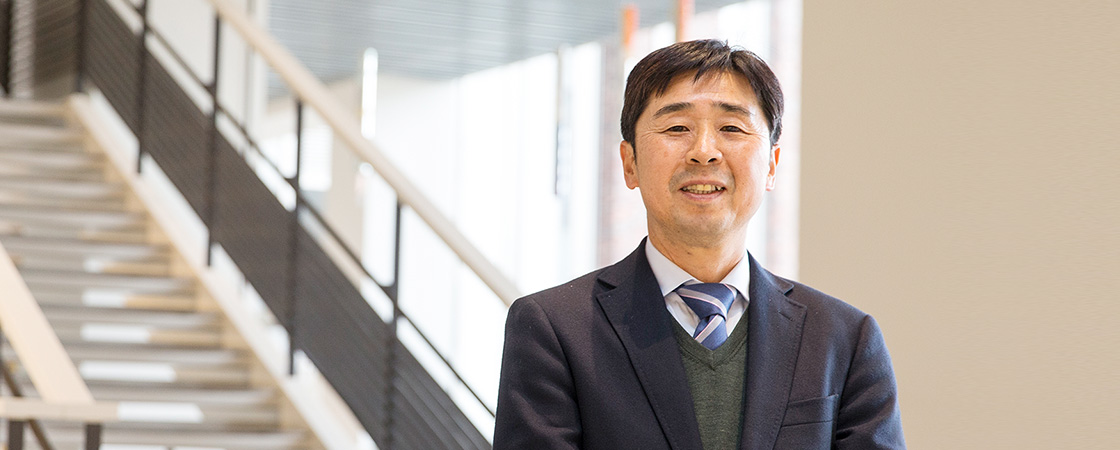
- 所属領域
- 心理学領域(博士前期・後期担当)
- 職位
- 教授
- 専門
- 教育心理学、発達心理学
- 主な担当科目
- 教育心理学特論 、教授・学習学研究、演習、人間科学プロジェクト演習
- おすすめの書籍
- Handbook of Research on Learning and InstructionRichard E. Mayer Routledge2011年
現在の研究テーマ(または専門分野)について教えてください。
研究テ-マは、「理解を支援する説明表現に関する教育・発達心理学」です。学習者が抱える理解不振を改善するために、理解方略を支援する説明表現(説き方)を発達に応じて検討しています。特に理論面・実践面から以下に取り組んでいます。
① 児童生徒の理解不振と理解方略の研究
② 児童生徒の理解方略を支援する説明表現の研究
③ 説明に基づく個別指導・学習相談の研究
なお、こうした研究は自らの「理解のつまずき」が研究を始発させる視点になるのだ、と深く諒解できた時に始まったように思います。研究を重ねるうちに、これを問うことが教育心理学の中心テ-マなのだと気づかされていきました。
現在、説明に関する問題は説明責任の名のもとに広く人々の関心を集めています。ここでは「理解のつまずき」を改善する支援行為としての成否が問われるべきと考えています。説明観を改め、支援モデルによる説明研究の構築を目指しています。
研究の社会的意義について、教えてください。
もとより、現代社会は説明によって成り立つ説明社会です。この社会ではだれもが説き手の役割を果たさなければならず、説明が悪いと社会的な責任を問われかねません。それでは、良い説明の要件とは何でしょうか。朗々と発声することでしょうか。いや、説明とは説いて明らかにすることだったはずです。受け手の理解不振を改善する支援行為としての成否が問われるはずです。それなのに、説けばそれでおしまいになるのでしょうか。説き手は受け手の理解不振を把握し改善しなくてもよいのでしょうか。それではどのような説き方を用いれば、理解不振を改善できるのでしょうか。子どもと高齢者に同じ説き方でよいのでしょうか。教育心理学や発達心理学に基づいて受け手の理解不振のメカニズムをおさえた上でこれらの問いに答え、理解を支援する説き方を考えていくことで説明社会に貢献したいと考えています。
この研究科でめざしたいこと、院生へメッセージをお願いします。
Friedrich Bollnowは、教育は出会いであると言いました。ただ「出会い」というより、「出遇い」と訳した方が良いと私は考えています。なぜなら「会」は鍋にふたにする意であり、予定調和が含意されます。一方で「遇」には偶発性が含意される。それだけでなく「禺」は「愚かな亀のような形をした生きもの」という意味ですから、それらが道の途上でたまたま遭遇するという意味を持つからです。これは教育現象を非常によく表現していると考えています。教える者も学ぶ者もともにどこか不十分なところがあるのかも知れませんが、両者は出遇う。そして互いに成長する。このドラマを本研究科で味わうことができるかも知れません。もちろん、このドラマを研究する分野が教育心理学であることは言うまでもありませんが。