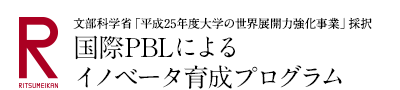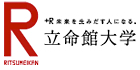参加学生によるプログラム・レポート
2018年01月のレポート一覧
2018.01.31
アクティビティレポート⑤(2017年派遣:バンドン工科大学)
政策科学部 織田 陸矢さん(3回生)
政策科学部3回生の織田陸矢です。バンドン工科大学ビジネスマネジメント学部アントレプレナーコースに留学しました。今回はインドネシア留学中に感じたカルチャーショックについて書いていきます!私は日本にも何人かインドネシア人の友人がいまして、少しはインドネシアについて知ったつもりでいました。ですから、現地に着いてから、インドネシア人(ムスリム)なのに〇〇なの!?と驚いたことが多く、よくイメージしがちなムスリムの姿とのギャップを感じる場面が多くあったことを覚えています。それでは、参りましょう。
1. 意外と「お酒」を飲む
ムスリムのご法度といえば、「お酒」と「豚」。ほとんどのムスリムの方はお酒を飲まず、豚も食べないのでしょう。しかし、私が留学生だったからかはわかりませんが、ちらほらとお酒を飲む学生がいました。日本でお酒を飲む(ムスリムの)インドネシア人に会ったことがなかったので、そのユルさに驚きました。
2.「アンコット」は想像以上にしんどい
みなさん、アンコットはご存知でしょうか?アンコールワットではないですよ!アンコットというのは、乗り合い用のバスのことで、一回あたり大体20円から40円ほどで乗ることができます。最近はゴジェックやグラブ、ウーバーの登場で必要とされてない感が出始めていますが、まだまだ市民の足として活躍しそうです。そんなアンコットを「カワプティ」という観光地まで行くために利用しました。そして、背中、腰、お尻が崩壊しました(泣)。アンコットには横向きに縮こまるようにして座るのですが、これがしんどい。写経を3時間通しでするほうが楽なんじゃないかと思いました。くれぐれも長距離移動にはお気をつけください。
バンドン近くの観光地カワプティにて撮影
3. 意外と「ヒジャブ」を着ていない
最初に書いたお酒の話と似ているのですが、ムスリムの女性の方はヒジャブと呼ばれる布を頭に巻いていることが一般的です。留学前の講義で来日していたインドネシアの学生はもれなくヒジャブを身に着けていました。現地のモールを歩いていると、ヒジャブを巻いていない女性を多く見かけます。イスラム教の方もいるのですが、比率としてはそれほど多くないはず。同じ講義を受けていたムスリムの現地学生も何人かはヒジャブをみにつけていませんでした。同じ宗教であっても多様性を感じるインドネシアは奥が深いな~と感心したのでした。
4. 母校(学部)愛が強い
留学生活を通じて一番印象に残っている出来事の一つかもしれません。卒業式や何かの大会といったイベントがあるたびに、学部の応援歌を歌いみんなで盛り上がります。日本ではそういったことが一切なかったため、非常に新鮮でした。また、学部ごとに異なるオフィシャルカラーがあることにも驚かされ、母校にたいする思いの強さを感じました。
バレーボール大会優勝後に撮影
留学生活を通じて、インドネシアではいろいろなトラブルに見舞われました。到着初日から帰国寸前までアパートのオーナーとずっとトラブルを抱えていましたし、着いてから1ヶ月経ってから右側上下の親知らずの抜歯もしました。1ヶ月に一回は必ずお腹を下したりなど、人間として成長できたかはわかりませんが、打たれ強くはなったのかなと思います。常になんらかのストレスを持ちながら日々の生活を送っていたので、やり過ごす力がついたのかなとも。留学生活全体では、非常にいい経験と楽しい時間を過ごせたので、興味のある方は是非チャレンジしていただきたいです。
2018.01.31
アクティビティレポート④(2017年派遣:インドネシア大学)
国際関係学部 北川 蒼太さん (2回生)
こんにちは! インドネシア大学に留学している、国際関係学部2回生北川蒼太です。12月だというのにこちらは真夏、毎日エアコン生活です。インドネシアって皆さんは何を思い浮かべますか?バリ…だけ?いえいえ、まだまだ奥が深いです!今回は、そんなインドネシアで感じたカルチャーショックについて、紹介していきたいと思います。
カルチャーショック1つ目は、時間の使い方。多くの人がムスリムのため、朝4時にはお祈りを始めます。また渋滞がすごいため、活動開始時間がとってもはやい!友達との待ち合わせ時間も、朝7時!と思ったら、8時からの授業が30分や1時間遅れで始まることもあったり、深夜でも街に出歩いている人もいたりと、日本人の感覚だった私も驚きました。
2つ目は、文化の多様性です。日本にいる時から、多くの民族、言語があることは学んでいましたが、住んでいるジャカルタ都市圏を離れると、違う言語を話す人がいたり、インドネシア人ではあるけれど、スンダやジャワなどそれぞれの生まれの民族に対するアイデンティティを強くもっている人とたくさん出会いました。民族だけでなく、宗教や文化、料理まで、違う島や街にいってみると異なるものにたくさん出会うことができます。
3つ目は、人。インドネシアの人はとにかく話すのが大好き!知らない人同士でも、すぐに友達になれるフレンドリーさと明るさ、笑顔が素敵で、道で困った時などもすぐ助けてくれる優しい人とたくさん出会えました。しかし一方で、日本人と比べて他人との距離感が近い人が多いようにも感じたりといろんな人がいます。最後は格差。よく言われる新興国の格差問題ですが、実際に目の当たりにすると衝撃的でした。首都ジャカルタとカリマンタンなど地方との格差はもちろんですが、ジャカルタ圏内にも様々な格差が広がっています。例えば、超高層ビルの下に広がるスラム街、線路脇のトタン屋根の家に住んでいる人々、赤ちゃんを抱えながら、毎日転々と移動する家族、道路で物乞いをする子供。
北ジャカルタ、コタ駅周辺に広がるスラム街の様子
一方でモールや高級住宅街には、日本とほぼ変わらない物価や風景が広がっていて、一般的な日本人よりも所得が高そうな人もたくさんいます。所得格差だけでなくそれに派生する、水やゴミ問題などの生活環境の格差や教育格差など、5ヶ月ほどの日常生活の中で身をもって感じ、学ぶことができたのは本当に貴重な体験でした。
中央ジャカルタの目ぬき通りには高層ビルが乱立してます、さっきの写真と全然違う!
今回あげたカルチャーショックはほんの一部!毎日いろいろなところにアンテナを張っているとたくさんの発見と学びがあり、本当に新鮮な日々でした。英語など語学だけでなく、日本や先進国では中々知ることができない新興国のリアルについて、自分の目で知り、学ぶことができるのも、アジアや新興国留学の魅力かもしれません。今回のレポートが少しでも、皆さんのお役に立てれば幸いです!
2018.01.31
アクティビティレポート⑤(2017年派遣:タマサート大学)
国際関係学部 中西 朋美さん (2回生)
こんにちは、国際関係学部2回生の中西朋美です。8月から12月までタイのタマサート大学教養学部東南アジア研究(SEAS)に留学していました。12月半ばに全ての授業とテストが終了し、無事日本に帰国しました。今回はPBL科目以外の授業について、私が実際に受講していたものを2つ紹介したいと思います。
1つ目は、これから留学する皆さんも受講する可能性が高い「Elementary Thai as a Foreign Language 1」、タイ語の授業について紹介します。この授業は所属していたSEASで開講されており、東南アジア研究に留学していた学生の多くが受講していました。他学部には中級者向けのタイ語の授業もありますが、授業についていくのがとても難しいと思います。初級のこの授業はタイ人の先生1人に対し、30人ほどの学生で開講される少人数授業です。週に1回、3時間授業で、簡単な日常会話やタイ文字、タイの文化についても授業を通して学ぶことができました。授業の雰囲気は少人数教室ならではの、生徒と先生の距離が近いため和気あいあいと楽しく学ぶことができます。基本的な授業の構成は、前半に会話練習、休憩をはさんで後半にタイ文字や単語等の文法を勉強しました。全授業を終えタイ語ばかりの生活でもところどころ理解できるようになり、現地の人とも少しコミュニケーションがとれるようになりました。また文法に関しては、書いたり読んだりできるようになるためにはこの授業以外にもタイ語を学ぶ場を作る必要があると思います。
2つ目は、教養学部International Studies (ASEAN-China)で開講されている「The Historical Background of Modern Southeast Asia」について紹介します。所属していたSEASとは違う学科で開講されている授業で、主に植民地時代以降の東南アジアの歴史について勉強しました。タイ語の授業とは違い70人ほどの大人数で受ける座学が中心の授業で、最初のほうは3時間のリスニング練習をしているようでした。時には実際の歴史を題材とした映画を観たり、植民地時代やナショナリズムを専門とする先生の小話が挟まれたりと、普通の座学よりリアリティのある歴史を学ぶことができて面白かったです。最終課題のグループワークでは、日本人4人、中国人3人、タイ人2人のグループでベトナムのナショナリズムについてレポートとプレゼンテーションに取り組みました。SEASで英語開講されている授業はほとんど留学生しかいないため、私にとってこの歴史の授業は多くのタイ人と一緒に受ける唯一の授業でした。SEASに留学する人でタイ人の友達をたくさん作りたい人やタイの大学の雰囲気を味わいたい人は、SEAS以外の授業を受けるのもいいと思います。
タマサート大学は他学部、他学科の授業も受講することができるため、自分の興味がある授業を選ぶことができます。PBL科目以外も、PBLとは少し雰囲気が違っていて面白いので、ぜひ自分に合った授業を探してみてください。
タイ語の授業で使用していた教科書 タイ語の先生
2018.01.31
アクティビティレポート⑤(2017年派遣:チュラロンコン大学)
政策科学部 張 暁玲さん(3回生)
ついに留学が終了しました。最後のアクティビティレポートでは約5ヶ月間の留学を振り返り、全体を通じて主に何を感じたか、学んだかについて書きたいと思います。
5ヶ月間の留学の中で、一番印象に残ったのはやはり大学のPBL授業です。チュラロンコン大学で受講したPBL科目は、経済学部の「Culture and Traditions in Thai Lifestyles」で、グループワークやフィールドワークが多い授業です。教室で行う講義形式の授業では、先生が一つ大きなテーマに基づいていくつかの課題をあげ、グループごとに一つの課題を与えます。グループで事前にそれぞれの課題について調べ、調べた内容をまとめてクラスの前で発表します。学生からの発表が終わってから先生からの説明が入るという授業のスタイルです。このように、先生が一方的に講義を行うのではなく、学生に自主的に学び、考え、表現する時間を提供するというスタイルは、日本ではあまり経験したことがなく、新しいと思いました。
また、授業を通してグループワークの難しさを痛感しました。最後の回までに、各自でグループプロジェクトのテーマを決め、役割を分担し、プロジェクトを実行します。そして、最後にそのプロジェクトの内容と成果をクラスで発表します。このプロセスの中で難しいと感じたことは、グループメンバーの中どのようにしてお互いの意見を組み合わせ、納得し合い、グループメンバー全員に役割を果たしてもらうことができるかということです。私のグループではボランティア活動はコミュニティにどのような貢献ができるかということをプロジェクトのテーマにしました。まずはどこで、どのようなボランティア活動をするかということをグループの中で決めなければなりません。それぞれやりたいことや興味のある分野が異なるため、合意形成をするのに何回も話し合いをしました。また、学部や時間割が異なるため、グループメンバーが集まるのも大変でした。このような難しさと大変さがあったからこそ、最後に目標が達成できた瞬間の喜びが大きいのではないかと思います。
グループワークは大変で難しいと感じる一方、その重要さも実感しました。授業のフィールドワークやプロジェクトで、ほとんどの場合はタイ語で説明されることが多かったです。その際タイ人の学生が英語で説明したり、私の質問をタイ語に通訳して代わりに聞いたりしてくれました。一人でできることの範囲が狭いかもしれませんが、グループメンバーそれぞれのできることや得意な分野を組み合わせることができれば、できる範囲が広くなり、大きな力になると思います。
留学生活がもう終わろうとしています。寂しいですが、この留学で新しいものを見たり、たくさんの人と出会ったりすることができて、本当に嬉しく思います。しっかりと今までの留学生活を振り返り、次の新しいステップのスタートになるよう、この経験で学んだことや感じたことを日本に持ち帰り、今後に活かしていきたいと思います。
古紙を再利用して、簡単な道具で山間部の子どもたちに送るノートを作ります。
作成したノート。山間部の子どもたちへのメッセージを込めて、表紙をデザインします。