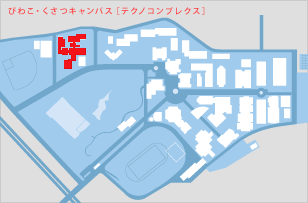|
テクノコンプレクスの一角、ハイテクリサーチセンター内に、エコ・テクノロジー研究センターがあります。この
施設・研究センターは持続可能社会を目指したエネルギーの利用と資源循環、それに付随する環境システムの研究・開発を行い、その成果をもって広く社会に貢
献することを目的とし、国内外にわたっての産学官連携によって研究を推進する、という目的のもと設立されました。
ここではエコ・テクノロジーに関する研究を行っています。その中で見せていただいたのが、炭の多様性。1グラムの炭で100平方メートルもの表面積を持
ち、結果的に悪臭を吸収することが出来るのだそうです。また、ここでは炭から作る「キャパシタ」と呼ばれる電池の研究も行っています。これは何度充電・放
電を繰り返しても電池の容量が全く減らないという充放電に優れた電池です。しかし、電池の大きさがものすごく大きくなってしまうという欠点も併せ持ってい
ます。現在は電池とキャパシタのハイブリッド化などの研究も行っています。
また、ディーゼルエンジンの燃費の良さに注目し、排気ガスに含まれるススを限りなく減らすという研究も行って
います。従来はプラチナ触媒を使っていたのですが、このセンターでは安価な銀でも代用可能だという研究成果が得られました。まさにエコ・テクノロジーの将
来を担う研究が目白押しのセンターでした。
[リンク] エコ・テクノロジー研究センターホームページ
|