
vol.9&10
メタバースがもたらす移動体験の変革 ―乗り物に乗る新たな価値の創造
物理的な距離に関係なく、一瞬のうちに行きたい場所に行き、会いたい人に会える。バーチャル空間上の仮想社会「メタバース」によって、そんな世界が実現しつつある。誰もがメタバースでつながる社会が実現したとき、「移動すること」の意味はどう変化するのだろうか。未来を知るために、まずメタバースの世界に飛び込んでみよう。
立命館大学と株式会社アイシンは、「人とモビリティの未来を拓く」というテーマを掲げて共同研究に取り組んでいる。その一環として、心理学から航空宇宙工学の専門家まで、多様なバックグラウンドを有する立命館大学デザイン科学研究所の研究者が、同社社員の皆さんにデザインサイエンスに関する考え方やノウハウを共有するのが「デザインサイエンスワークショップ」である。
今回のメタバースを学ぶワークショップには、株式会社ゆずプラス 代表、立命館大学 社会共創推進本部 社会共創アドバイザーの水瀬ゆずが登壇。アイシンPT技術センターでメタバース社会について学ぶ前編と、メタバース空間上でデザインサイエンスを学ぶ後編の2回に分けて開催された。

講師プロフィール
水瀬ゆず一般社団法人プレプラ 代表、株式会社ゆずプラス 代表、立命館大学 社会共創推進本部 社会共創アドバイザー
立命館大学在学中にメタバースと出会い、その可能性に惹かれて「水瀬ゆず」名義でメタバース内外をつなぐ活動を開始。なかでも、メタバース上での不登校支援プログラムはメディアに多数取り上げられるなど高い評価を得る。2022年にメタバース上で出会った仲間たちと株式会社ゆずプラスを設立し、メタバースを活用した教育ソリューションや新規事業提案などに取り組んでいる。(本名:岡村謙一)
なりたい自分になれる場所、メタバースの「今」を知る
「みなさんは、20年後の生活をイメージすることができますか?」
アイシンPT技術センターで行われたレクチャーの最初に、水瀬はこう切り出した。2045年にはAIが人間の知能を越えるシンギュラリティが訪れるとも言われている。さまざまな先端技術が有機的に絡み合った先に、一体どんな未来社会が生まれるのだろうか。なかでも、今回取り上げるメタバースは単なる技術やツールではない。そのなかではすでに独自の「社会」が生まれているのだという。水瀬はそんなメタバースでこれまで5000時間以上を過ごし、不登校の生徒のための居場所づくりをはじめさまざまなプロジェクトを手掛けてきたスペシャリストだ。

未来を想像するには、まずメタバースの「今」を知らなければならない。水瀬は自身が出演したテレビのドキュメンタリー番組の一部を引用して、メタバースユーザーの生活やメタバース内の文化の一端を紹介した。
仕事や学校から帰宅し、VRゴーグルを装着すればそこは仲間たちの待つメタバース空間だ。思い思いのアバターの姿になって、飲み物を持って「現実おつかれ~」と乾杯するユーザーたち。自宅にいながらロックスターとしてメタバースのステージに立つユーザー。メタバース上の仲間に祝ってもらう誕生会。現実の自分を脱ぎ捨て、アバター(VR空間での自分の分身)の姿で他のユーザーと交流したり、さまざまなワールド(個別のVR空間)に瞬時に移動したり……メタバースではそんなことが誰でも実現できる。メタバース上で出会ったユーザー同士が恋愛し、カップルになる例も珍しくない(しかも、同性同士や現実の性別にとらわれないカップルも多い)というから、その交流が表面的なものにとどまらないことがわかる。
単に余暇の時間を過ごすだけではなく、人によってはメタバースが日々の生活のさらに大きなウェイトを占めているようだ。水瀬の場合は、朝からメタバース上でミーティング、昼は食事のためにゴーグルを一旦外し、午後からまたゴーグルをかけて仕事。就業後はもちろんメタバース上の友人たちと遊び、そのまま一緒に眠る「VR睡眠」で一日が終わる……という日もあるという。
もはや現実と遜色のない生活空間となっているメタバース。人々を惹きつけるバーチャル空間上の「社会」はどのようにできているのだろうか。
豊かな情報量で構築された「もうひとつの現実世界」
そもそもメタバースという言葉は、ニール・スティーヴンスンが1992年に発表したSF小説「スノウ・クラッシュ」にはじめて登場した。「Meta(超越した)」と「Universe(宇宙)」を組み合わせた造語だ。以来、「サマーウォーズ」「レディ・プレイヤー・ワン」などのフィクション作品でメタバースに類する世界が描かれてきたことはご存じのとおりだ。
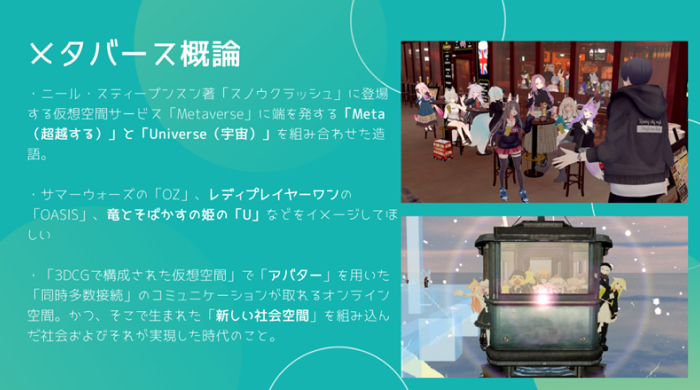
メタバースの詳細な定義は、「3DCGで構成された仮想空間で、アバターを用いて、同時多接続のコミュニケーションが取れるオンライン空間。かつ、そこで生まれた『新しい社会空間』を組み込んだ社会、及びそれが実現した時代のこと」などと表現される。もう少し詳しく見ていくと、メタバースは単なるオンラインプラットフォームではなく、以下の7つの要件があるという。
空間性…3次元的な空間の広がりがあること
自己同一性…ユーザー自身のアイデンティティを投影した唯一無二の自由なアバターで存在できる世界であること
大規模同時接続性…複数のユーザーが同時にアクセスできること
創造性…メタバース内のコンテンツをユーザー自身が作り、シェアできること
経済性…ユーザー同士でコンテンツやサービスを交換したり、売買したりできること
アクセス性…スマートフォン、PC、VRゴーグルなど多数の手段でアクセスでき、物理現実と仮想現実とが垣根なくつながること
没入性…VRゴーグルなどによって実際にバーチャル世界に入り込んだような感覚を得ることができること
これが厳密な定義というわけではないものの、メタバースはこれまでのオンラインでのコミュニケーションとは全く違う指向性をもっているようだ。「たとえばメッセージアプリや、XやFacebookなどのSNSは、扱う情報量を少なくすることで拡散性を高める性質をもっていました。メタバースはその逆で、現実世界での体験情報量を仮想空間で再現するアプローチをとっています。さらに言えば、身振り手振りや表情といったノンバーバルなコミュニケーションや場所の雰囲気など、ウェットな要素をオンライン上に持ち込みつつ、現実の距離などの制約を受けずに交流しようとするものです。私はこれをもうひとつの現実世界だと捉えています」

そんな「もうひとつの現実」が普及しつつある背景には何があるのだろうか。技術的には、通信できる情報量や処理速度が向上したことが最も大きな要因だろう。特にZ世代の若者たちは“常時接続世代”とも呼ばれ、常にスマートフォンを手放さず、生活におけるリアルとバーチャルの比重がほとんど変わらない人も多い。内面的には、3.11やコロナ禍を経験したことで、他者とのつながりを重視する傾向が育まれたのではないかと水瀬は分析する。
メタバースに関する基礎的な知識を学んだ後、グループワークではレクチャーを受けて考えたメタバースのメリット・デメリット、そして「移動体験」はどう変わるのかについてグループで話し合った。帰りにはVRゴーグルが配布され、いよいよ次回はメタバースを本格的に体験することに。

メタバースで学ぶデザイン思考
ワークショップ後編は、参加者がそれぞれの自宅からVRゴーグルをつけて参加する完全メタバース開催だ。実は事前にアクセス方法の確認と簡単なイントロダクションを兼ねた講習を受講したのだが、慣れないVR空間で初めての「VR酔い」を体験することになってしまった。今日は大丈夫だろうかと思いつつ、メタバースの代表的プラットフォームであるVR Chatで立命館VRキャンパスというワールドにアクセスする。

3度目となると感覚が馴染んできたらしく、意外と平気だ。続々集まってきたいろいろなアバターの参加者たちとともに講義室に着席する。講師の水瀬ももちろんアバターの姿だ。
さて今回は、デザイン思考の手法で「メタバースにおける移動体験」を深堀りし、アイデアを見つける。まずは水瀬がVR上の教壇に立ち、デザイン思考とは何ぞや、というレクチャーを行った。
ロジカル思考とデザイン思考を比較してみると、前者が客観的な根拠を積み上げて対象を分析するアプローチであるのに対して、後者は共感を軸にロジックを再構成して問題解決をはかる人間中心のアプローチだという。デザイン思考では、人々が共感できるロジックを探し出す、あるいは創り出すことがより重要になる。ここで注意すべきは、何をロジックと考えるのかはそれぞれのコミュニティによって異なるということだ。
「メタバースにはメタバースのロジックがあります。ゴーグルを付けたまま眠る『VR睡眠』なんて、睡眠の質という一般的なロジックで考えると決して効率的ではありませんが、メタバースユーザーにとっては別の意味があるはずです。例えば、実生活で一人でいる時間が長い人にとって、VR上で仲のいい友達と一緒に寝るという体験は何物にも替えがたい自分を癒す時間なのかもしれません。さまざまなメタバース上の習慣やサービスの裏で、メタバースユーザーが本質的に何を求めているのか。そうしたロジック、つまりインサイトを探っていただきたいのです」
あなたはどうしてメタバースに? ユーザーのインサイトに迫る
特定のコミュニティのインサイトを探る方法として、エスノグラフィー(文化人類学的観察手法)がある。今回はその簡略版として、グループに分かれて株式会社ゆずプラスのスタッフでもあるメタバースユーザーの方々に簡単なインタビューを行うことになった。
筆者が参加したグループでインタビューに答えてくれたのは、犬耳のアバターがかわいらしい「ポリゴン」さん。ご本人は島根在住の男性で、大きめの体格をしているというからイメージに少しギャップがある。メタバースを始めたのは、まだ学生だった2021年のこと。もともと人と話すのが大好きだったが、コロナ禍で学校が休みになってしまい、「誰かと交流したい!」と思っていたときにこの世界を知ったそうだ。「昔からテーマパークのスタッフさんやマスコットに憧れていて、話しかけても怖がられない、親しみやすいアバターを選びました」と話すポリゴンさんは、はじめたばかりの初心者にメタバースを案内するガイド役として活躍中とのこと。明るい声のトーンや感情豊かな身振り手振りは、たしかに初心者にはとても心強い。

根っからの人好きがにじみ出ているポリゴンさんだが、現在は地方で一人暮らしをしているため、実際に人に会いに行こうと思うと時間も移動費もばかにならない。人との交流という意味ではテキストSNSや音声チャットもあるけれど、誰かとその場に一緒にいるかのように、細やかで親密なやり取りができるのはメタバースだけだという。
お話を聞いてみると、ポリゴンさんにとってメタバースは、現実では満たすことの難しい人との交流を可能とする大切な居場所であることが伝わってきた。バーチャル空間やアバターを介した仕組みがあるからこそ、人と人との距離が縮まり、人間らしい心の動きが生まれるのだ。
銀河鉄道に乗って、メタバースでの「移動体験」を知る
メタバースユーザーのインサイトを垣間見ることができたところで、今度はメタバースにおける「移動体験」を覗いてみよう。
案内されたのは「Starlight lane」という列車の中を模したワールド。ウッド調の落ち着いた内装で、窓の外を覗くと一面の星空が後方へと流れてゆく。まさに銀河鉄道だ。何をしなければならないということもなく、備え付けのバーカウンターで乾杯したり、座敷にゆったり腰掛けたりと、皆思い思いに過ごしている。時おり車内放送のような音声も流れるから芸が細かい。先程の講義室ほど広々していない空間だからか、他のユーザーとの距離が近いように感じた。
「メタバースにも旅行企画というのがあって、こうやって乗り物に乗って修学旅行みたいに皆で移動するんです」と水瀬。修学旅行という表現は言いえて妙だ。

束の間の旅気分を味わったのち、先ほどの講義室に戻って「メタバースの移動体験にはどんなインサイトがあるか」をグループで話し合った。実際の旅行でも、早く移動するだけが目的ではなく、みんなでわいわい移動する時間そのものが楽しかったりする。メタバースでは旅行の面倒くさいところをなくして、楽しいところだけを切り取ったような体験ができそうだという意見が出ると、皆がうなずいた。世界観の作り込みに関しては、星の中を走る幻想的な世界にワクワクしたという意見もあれば、反対に、トイレや電話や車内放送など現実味のある要素がプラスされることで世界観に没入できた、という意見も。
筆者なりにもう少し振り返ってみよう。VRの銀河鉄道は実際にどこかに到着するわけではない。むしろ列車に乗らなくても、どこへでも瞬時に行けてしまうのがメタバースだ。いわば乗り物の本来の目的とは関係ない空間なのだが、逆に言えば、とても贅沢な「無目的な時間」を人と共有することができるように感じた。説明が難しいが、「どこへも着かないけれどどこかへ向かって移動している」という状態にはなんとも言えない安心感がある。すれ違うのもやっとな車内で座席に腰掛けると、自然と隣の人との会話が弾みそうだ。そんな心の動きが生まれるのは、窓の外を流れる星や車内放送など、作り込まれたさまざまな要素のおかげでもあるのだろう。
ワークショップの最後は、各グループで話し合ったことを全体に発表する時間だ。
多かった意見は、現実世界での移動というと速さや快適さが求められるものだが、一緒に風景を楽しんだり話したり、体験を共有することの楽しさに改めて気づかされたというもの。これはまさしくメタバースにおける「移動体験のインサイト」だろう。そんなインサイトを満たすために欠かせないのが、メタバースならではの没入感だ。嗅覚や触覚も再現できるような仕組みがあればより没入できるのでは、という意見や、やはり現実に体験することにも価値はあるので、メタバースと現実をうまく組み合わせるのがいいという意見が出て盛り上がった。
水瀬によると、現実とバーチャルを融合させる「インターバース」という取り組みも実際に活発になってきているそうだ。メタバースを通じて、リアルな体験の価値も考えるきっかけにもなったワークショップだった。

conclusion
ワークショップを終えて
参加者の声

第2EV先行開発部
谷山善大さん
メタバースという世界にはあまり馴染みがなかったので、飛び込んでみたら新しい価値観に出会えるのではないかと期待して参加しました。レクチャーや体験を通して、アバターを通して見ず知らずの人と時間を共にするという自分にはなかった価値観に触れられたように思います。モビリティの観点では、瞬時にどこへでも移動できるという環境は率直に優れていると感じましたが、視覚・聴覚以外の感覚を補完するような仕組みと組み合わせることでさらに可能性が広がりそうです。新しいサービスや製品を提案する良いヒントをもらえました。

DXプラットフォーム部
奥本宗一郎さん
私はIT領域における新技術の検証、全社展開、新規事業創出に貢献する部署に所属しています。今回はメタバースというテーマに惹かれて参加しました。メタバースユーザーの価値観に触れ、デザイン思考も学ぶことができ、大きな収穫となりました。メタバース内でのレクチャーやワークショップは、対面やオンライン会議とは異なり新鮮な環境でした。年齢や部署を伏せてアバター同士で交流することで、普段よりも会話が弾み、アイデアも出しやすくなりました。VR酔いなどへの配慮は必要ですが、対面とのハイブリッドで活用できると感じました。
講師の声

一般社団法人プレプラ 代表、株式会社ゆずプラス 代表、立命館大学 社会共創推進本部 社会共創アドバイザー
水瀬ゆず
今回のワークショップは、メタバースという新しい社会の領域に触れ、未来社会を考えていただくきっかけを提供できればと思い企画しました。仮想世界と物理的な移動を伴うモビリティは一見正反対の概念のように思えますが、今回体験していただいたように、メタバース内にも移動の時間を楽しむ文化は存在します。このように、メタバースを通じて既存のモノやコトの新しい価値を発見することもできるのです。
普段の活動では、不登校の生徒をはじめ比較的若い世代の方にメタバースを体験していただくことが多いのですが、今回は参加者の年齢層が幅広く、とくに後半のワークショップでは、管理職など今後組織の意思決定に関わっていかれるような方に重点的に参加していただきました。普段の顧客層とは異なるメタバースのユーザーとの交流を通して、新しい世界に飛び込んで視野を広げる体験を提供できていれば幸いです。
もちろん、新しい技術はメタバースだけではありません。積極的に触れる機会をつくり、事業にどう落とし込むのかを考えていっていただきたいです。一見、既存の事業とは関係なさそうに見える領域こそ、大きなチャンスにつながっているかもしれません。

