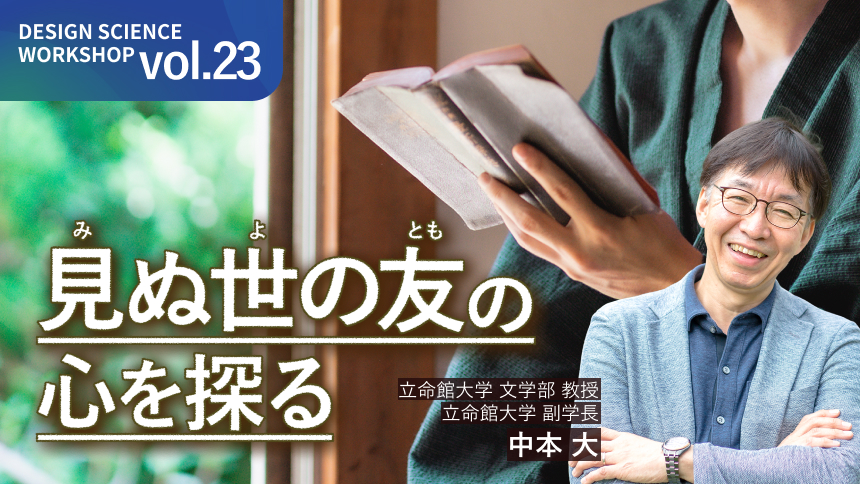
vol.23
日本文学研究:見えないもの・見落としたものを可視化する学問
未来社会の「あるべき姿」を描こうとするとき、その未来にはどんな人がいるだろう。その人は何を喜びとし、どんなことに怒りを感じるだろうか? まだ見ぬ新しい価値を探究するうえで忘れてはならないのが、そこにいつも心を持った人間がいるということだ。時を超えて読みつがれる文学作品は、そんな人間への理解を深める手がかりを示してくれる。自分の中の常識を一旦捨てて、書かれたテキストに虚心坦懐に向き合ってみよう。
立命館大学と株式会社アイシンは、「人とモビリティの未来を拓く」というテーマを掲げて共同研究に取り組んでいる。その一環として、心理学から航空宇宙工学の専門家まで、多様なバックグラウンドを有する立命館大学デザイン科学研究所の研究者が、同社社員の皆さんにデザインサイエンスに関する考え方やノウハウを共有するのが「デザインサイエンスワークショップ」である。
今回は、立命館大学 文学部 教授の中本大が登壇。日本三大随筆に数えられる『徒然草』を題材に、実証的な読解を通して日本文学研究の世界を体験するワークショップを行った。

講師プロフィール
中本大立命館大学 文学部 教授、立命館大学 副学長
大阪大学大学院 文学研究科 博士課程修了。同大学 文部教官助手を経て、1998年に立命館大学 文学部に着任。2008年より教授、2025年4月より立命館大学 副学長(教学担当)を務める。専門は日本文学・日本美術史で、室町時代に漢文で書かれた五山文学を、同時代の美術など他領域との関係のもとで総合的に研究している。
文学研究を通して、多様な人間の姿に触れる
デザインサイエンスワークショップでは、これまで経営学や心理学、システム工学などさまざまな分野の知見から、新しい価値を実現する方法について学んできた。改めて復習しておくと、自然や社会に「あるもの」を探究する従来の科学(コグニティブ・サイエンス)に対して、デザインサイエンスは「あるべき姿」を探究し、まだ存在しない価値を実現しようとするものといえる。
一方で、そもそも人間にとって「あるべき姿」とはどんなものなのかという根本的な問いは、古くから人文学や芸術の領域で探究されてきたものだ。とりわけ文学は、書き手や語り手の言葉を通して、多様な人間の姿を読者に示してくれる。今回はそんな文学研究の世界に触れるワークショップである。

ワークショップはアイシンPT技術センターで行われた。講師を務める中本は、室町時代の五山文学の研究者として研究・教育に携わる傍ら、大学組織では教育に関する業務をとりまとめる教学部長を経験し、現在は教学担当副学長を務めている。
「学生の単位取得や進級・卒業修了にかかわるミスを絶対に起こさないような全学的な制度設計をすることは大学の重要な役割です。他方で、システム化を進めれば進めるほど、どうしても『人』が見えなくなってくる。一人ひとりの学生にとって学びやすい環境になっているのか、学生が成長を実感できているのかという一番大事なことが後回しになってしまいがちなんです。だから私は、教学部長としての仕事をしながら、学部の授業も必ず担当し、学生一人ひとりと向き合う時間をもつようにしていました。現在は副学長という立場ですが、個別の要求や希望をしっかり汲み取れるようなシステムをどうつくるのか、そんなことを考えています」
そんな中本が今回扱う題材は、兼好法師が著し、日本三大随筆のひとつにも数えられる『徒然草』だ。「つれづれなるままに」から始まる序段はとくに有名で、中学の国語の時間に習った人も多いだろう。しかし近年、その解釈が大きく揺れ動いているのだという。誰もが知っている、当たり前だと思っているものの前であえて立ち止まってみることで、兼好法師という人間のどんな顔が見えてくるのだろうか。「アンコンシャス・バイアス」をキーワードに、文学研究の世界に足を踏み入れてゆこう。
書かれていないことから見えてくる、兼好の「自己愛」
徒然草の解釈が揺らいでいるとはどういうことだろうか。なんと、作者として知られる「吉田兼好(卜部兼好)」という人物像自体が捏造だったというのだ。近年の研究で、吉田兼倶という室町時代の人物が、自身の家系を粉飾するために兼好の名を家系図に書き入れてしまったことが明らかになったという。この吉田氏(卜部氏)は京都の吉田神社の神職を務める家系であるが、実際の兼好は、伊勢出身で鎌倉幕府に仕え、京都に派遣されたいわばスパイのような身分の人物だった。徒然草の主な舞台は京都だが、兼好の出自が京都ではなかったとなれば、いろいろな意味が変わってくる。
「たとえば、徒然草には関東出身の人を見下したように書いている箇所があります。これを生粋の京都人が書いていたとすると単なる嫌な奴ですが、兼好自身が東海出身だったとなると、(当時の感覚で)地方出身者が地方出身者を見下している、という面白みにつながるわけです。このように全面的に読み方を変えていかなければならないということで、徒然草の研究は第2フェーズを迎えつつあるんです」
象徴的なフレーズとして、中本は徒然草の第13段から「見ぬ世の友」という言葉を引用した。この段で兼好は、「白氏文集、老子のことば」など「見ぬ世の友」、つまり遥か先達の遺した文章にひとり向き合う時間こそ、この上ない慰めなのだと書いている。書かれた当時の感性・感覚に即して作品を読解する文学研究もまた、「見ぬ世の友」と対話する営みといえる。
そんな文学研究のめざすところは、作品の価値を高める読解、つまり、作品のおもしろさを新たに見出し、多くの人と共有できるような読み方を示すことだと中本は言う。その例題として、第32段を読んでいこう。
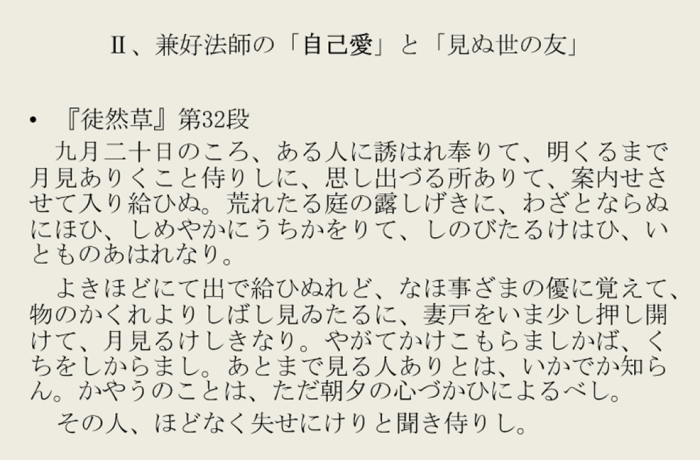
この段では、兼好はある人に誘われて、月見がてら夜の都の散策に出かける。道すがら、誘ってくれた人がふと思い出したというある家に立ち寄ったところ、その趣深い暮らしぶりはとても心を動かされるものであった。しばらくして辞去するが、名残り惜しいものを感じて物陰に隠れて見ていると、先ほど歓待してくれた人が妻戸を押し開けて出てきて、月を見ているようだった。兼好はその自然体の様子を〈日々の心がけから生じるものだろう〉と称賛する。最後は〈その人はしばらくして亡くなったらしい〉とあっけなく結んでいる。
「では、ここで問題です」と中本。「兼好らが訪ねた家で出迎えてくれた人は、男性でしょうか? それとも女性でしょうか?」
参加者にとっては意外な角度からの質問だったが、たしかにどちらか聞かれると困ってしまう。男性が夜中に女性を訪ねるという源氏物語などでよくあるシチュエーションに当てはめて読みたくなるが、実はこの問い、研究者の間でもいまだに論争が続いているのだそうだ。そのうえで、中本は次のような解釈を示す。
「この段のどこにも、この人物の男女を特定する要素は書かれていません。それどころか、容姿にも一切言及していないんですね。もちろん、あえて書かないことで読者に想像させるという戦略もありうるのですが、徒然草ではこの段に限らず人の外見に関する記述が極端に少ないんです。これはなぜか。……実はこの人(兼好)は、自分以外の人のことを見ていないんじゃないでしょうか」
なんとも大胆な推論だ。しかし、先述の13段にも出てきた「ひとり」という言葉などに注目して他の段を見ていくと、友愛や恋愛について語りはするものの、その成就は必ずしも望んでいない、自己愛の人としての兼好がおぼろげに浮かび上がってくるのだという。こうしてテキストの向こうに書き手の顔が見えてくると、遠い昔に書かれた随筆がぐっと身近に感じられる。
問いに戻ると、源氏物語をはじめとする王朝文学のある種の「常識」を当てはめて、この人を女性だと読むことはできるだろう。しかしそれはアンコンシャス・バイアスにすぎないのではないかと中本は指摘する。思い込みを一旦捨ててテキストそのものに向き合い、「なぜ性別を特定する要素すら書かれていないのか?」と穿ってみることで、作品の見えていなかった側面が見えてくるというわけだ。
序段のさりげない言葉に隠された、重厚な背景と感情
続いては、グループワークで「つれづれなるままに」から始まる有名な序文の解釈に挑戦することになった。よく知られた文章を細かく吟味するために、グループごとに①漢字表記にできる箇所は書き直し、②他言語に翻訳したりする場合に気になる点・気をつける点をできる限り書き出す、という手順で取り組む。

漢字表記にするなら、たとえばこうだろう。「徒然なる侭に、日暮らし、硯(すずり)に向かひて、心に移り行く由無し事を、そこはかとなく書き付くれば怪しうこそ物狂ほしけれ」。事前課題として出されていたこともあり、ここまでは比較的スムーズにまとまったのだが、「うつりゆく」を「移り行く」とするか「映り行く」とするかではグループ内で意見が分かれた。どちらにしても、次々と浮かんでは消えてゆく(あれこれの思考を書き留める)というニュアンスになるだろうか。また、一連の文章を翻訳しようとすると、「あやしうこそものぐるほしけれ」のニュアンスでどうしてもつまずいてしまう。一体どんな心の動きがあって「物狂ほし」い気持ちになっているのだろうか……?
答え合わせとしては、「移る/映る」はどちらでもOKだと中本。古語の世界では「影が映る」ことは、影の主がその場所に「移動している」と考える。だから意味は同じになるというのだ(ただし、「映」を「うつる」と読むようになるのは明治以降とのこと)。現代語では聞き慣れない「つれづれなり」は、一般的には、退屈でやることがないなどと訳される。「よしなしごと」は由がない、つまり根拠のない空想、妄想という意味。こうして単語レベルで現代語に置き換えてゆくと翻訳できてしまいそうだが、実は一番厄介なのは、現代でもそのまま通じる「硯に向かひて」という言葉なのだという。ここでは、徒然草が細部にわたるまで源氏物語を意識して書かれたものである、という前提知識を踏まえて見ていく必要がある。

「源氏物語には書き物をするシーンがたくさん登場しますが、ほとんどが『硯を取りて』と書かれています。『硯に向かひて』という表現は一箇所だけ、光源氏の子孫の世代を描いた宇治十帖とよばれる物語の『手習』の項に登場します。宇治十帖は、薫と匂宮という二人の青年の恋の鞘当てを中心とした物語ですが、二人の間で引き裂かれた浮舟という女性が終盤で自殺未遂をしてしまいます。『手習い』で描かれるのは、助けられて命をとりとめた浮舟が、どうにかなってしまいそうな心情を整理するために、自分の人生を振り返りながらあらゆることを書き出そうと苦心する場面です。決意をもって硯に向かって、苦しみ抜きながら人には言えないような心情を書きつけてゆくのです。
徒然草の序段は、実はこの『手習』を下敷きにしているんです。兼好はあえて『硯に向かいて』という言葉を選ぶことで、自身に浮舟を憑依させたのでしょう。この表現は研究者にはほぼ無視されていたのですが、源氏物語のデータベース化が進んだことで、全編にわたって一度しか登場しない表現であるという特異性が明らかになり、再注目されるようになったんです」
これを踏まえると、「つれづれなるままに、日ぐらし、硯にむかひて」は、〈書きたいことはあるけれどどう書いていいかわからず、机に向かって一日中苦悶している〉といったニュアンスになる。学校では文字通り「一日中、退屈に任せて書き綴った」というふうに習った記憶があるが、どうやらイメージが随分かけ離れているようだ。「兼好法師といえば、肩ひじをついてどこか達観した姿で描かれた肖像がよく知られていますが、このイメージにみんな騙されていたんです」と中本。それにしても、見過ごしてしまいそうなほんの短い語句の中にこれだけ重厚な背景と感情が込められていたとは、心底驚かされる。
では、兼好にとって「心にうつりゆくよしなしごと」を書きつけるとはどんなことだったのだろうか。徒然草の第137段では、兼好は、花や月の一番綺麗なときだけを愛でるのはいかがなものか、と疑問を呈し、男女の恋愛のさまざまな側面も引き合いに出して「万の事も、始め終わりこそをかしけれ」と述べている。
「つまり、始めから終わりまで全部の過程が大事だと言っているんですよ。これが清少納言だったら、一番良い瞬間を切り取ることができるんですが、兼好は『うつりゆく』ものを全部書かないと気がすまない。面倒くさい人なんです。
これを踏まえると、序段で兼好は〈机に向かって悶々と自分の人生を振り返っても、次々と浮かんでくるのは根拠のない妄想ばかり。それらを全部書きつけていると、頭がどうにかなってしまいますよね〉と言っているわけです。こんな文章を中学の教科書に載せていいものかとも思いますが(笑)、そういう深みがあるからこそ、国語の教材として長く読み継がれているとも言えるでしょう」
先入観を捨てて、「見ぬ世の友」と対話すること
「硯にむかひて」は、兼好から後世の私たちへの謎掛けなのだと中本は言う。読み飛ばすこともできるが、読み取れた人は兼好に少し近づくことができるという仕掛けだ。さらに言えば、徒然草の向こうには源氏物語を書いた紫式部の存在もある。序段の読解を通して、冒頭に触れられた「見ぬ世の友」という言葉が一層実感を持って胸に迫ってきた。
「私たちが普段、テキストを読むことは、ミルフィーユのように多層な世界の一番上の層を見ているようなものです。もちろん、現代の目線で読んで楽しむのも構わないのですが、その下にさまざまな地層が折り重なっていることを知ると、書いた人物の背景や人間性が浮かび上がってくるようで、作品をさらに楽しめるようになるでしょう。文学研究では、語の用例というエビデンスを丁寧に積み重ねることで解釈を深めてゆきます。そのようにして、表面的に読んで抱いた第一印象を疑い、覆してゆくことが大切なのです」
文学作品は、人間がどこまでも多様で割り切れない存在であることとともに、何百年も前の作者と作品を通して対話できることも教えてくれる。ものづくりの「あるべき姿」を描くうえで、次世代の「見ぬ世の友」への想像力をもつことの大切さを考えるひとときとなった。
conclusion
ワークショップを終えて
参加者の声

PTシステム製品企画部
山口量古さん
先入観にとらわれないものの見方を知りたいと思って参加しました。徒然草は本当にいろいろな方向から解釈することができる題材だったので、先生のお話を聞いていてとてもおもしろかったです。一方で、グループワークでは同じ文章や単語でも人によって解釈が変わるんだということも体験して、文章だけで考えを共有・共感することの難しさを感じました。業務上では、たとえば上位方針はある程度曖昧さが含まれるものなので、そうした文章に出くわしたときに第一印象だけで受け取らないように意識できればと改めて思いました。

E-VC先行開発部
中村匡宏さん
文学はものづくりとは対極にありそうなテーマなので、そこがどうつながるのか、興味を惹かれて参加しました。私自身は国語は苦手な方だったのですが、作者のバックグラウンドを知れば知るほど解釈の幅が広がってゆくのがとてもおもしろかったです。グループワークでは意見が分かれる場面もありましたが、それぞれの解釈の違いも含めて楽しめました。先生が「面白い読解とは、新しい見方を示すこと」とおっしゃっていて、なるほどと思いましたね。ものづくりでも、新しいことをやっているときが一番楽しいです。あとは、日頃からもう少し文字に触れたほうがいいなと感じたので、久しぶりに小説を読んでみようと思います。
講師の声

立命館大学 文学部 教授、立命館大学 副学長
中本大
文学は、最終的には人間はどう生き、何をめざせるのかという可能性を追求する学問だと思っています。今回はそんな大きなテーマまではたどり着けませんでしたが、ものづくりも突き詰めれば人間に届けるものですので、アイシンのみなさんと問題意識を共有できればと思いながらお話しさせていただきました。データからこぼれ落ちてしまうような人間の側面に目を向けることで、ものづくりにおいてもより良いものが生み出せるのではないでしょうか。もちろん文学作品だけでなく、会社の人間関係や家族、あるいは初対面の人との出会いを新鮮に見つめ直していただくと、新しい発見があるかもしれません。
みなさんとご一緒させていただいたことは、私にとっても貴重な経験になりました。文学研究の成果を、いわゆる教養としてお伝えするのではなく、より実践的に体験していただき、一緒に読みを深めていく。人文学の本来の目的に近いことが実現できたのではないかと思います。グループワークで披露していただいたみなさんの読解も非常におもしろかったです。正誤にかかわらず、ああした多様な読解が、次の作品を生み出す種になってゆくのだと思います。それがグループでの議論のなかからでてきたことも大切だと思います。兼好はひとりで硯に向かいましたが、私たちは他人と言葉を交わすことで、新しいものをつくり出すことができるのです。
これからも、人間について考えるということを通して、みなさんと手に手を携えていろいろなことに挑戦させていただけると嬉しく思います。

