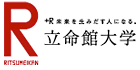ニュース
2014年05月のニュース
2014.05.29
第4回定例研究会 秋田県一の目潟年縞堆積物を用いた東北日本の環境史復元
2012年、福井県三方五湖のひとつである水月湖から採取される堆積物「年縞」が地質学的な時間をはかるための世界基準時計として認定され、今最も世界から注目をあつめる研究のひとつである「年縞」について、秋田県一の目潟の年縞分析を専門にされている篠塚良嗣氏に発表していただきました。
文系の研究者が多くを占める研究会ですが、年縞分析によって解明される可能性に関心度は高く、多くの参加者が、年代測定や自身の研究分析をする際に年縞分析データを応用させられる、という期待を持ったようでした。

多様なデータを駆使し年縞分析について解説する篠塚良嗣氏(立命館大学専門研究員)

考古学を専攻する学生や研究者が多数集まった会場
参加者からのコメント:
年縞について今回初めて知りましたが、考古学を専攻している者としては年代測定の一つとして重要になると思い、とても興味がわきました。(立命館大学文学部考古学・文化遺産専攻)
明らかになっていること、展望としていること、がよくわかりました。その成果を考古学に対比していくには様々な要素を抽出していく努力が不可欠で容易ではないことを実感しました。
(立命館大学文学部)
専門外の者でもとっつきやすく話していただけて良かったです。(立命館大学専門研究員)
発表後の質疑応答での意見交換は非常に興味深く、意義深いものでした。
(立命館大学文学部考古学・文化遺産専攻)
年縞が地域の環境変化、災害の解明に大きく影響することを知ることができて、大変興味深かったです。(立命館大学文学部地理学専攻)
チラシはこちら
文系の研究者が多くを占める研究会ですが、年縞分析によって解明される可能性に関心度は高く、多くの参加者が、年代測定や自身の研究分析をする際に年縞分析データを応用させられる、という期待を持ったようでした。
多様なデータを駆使し年縞分析について解説する篠塚良嗣氏(立命館大学専門研究員)
考古学を専攻する学生や研究者が多数集まった会場
参加者からのコメント:
年縞について今回初めて知りましたが、考古学を専攻している者としては年代測定の一つとして重要になると思い、とても興味がわきました。(立命館大学文学部考古学・文化遺産専攻)
明らかになっていること、展望としていること、がよくわかりました。その成果を考古学に対比していくには様々な要素を抽出していく努力が不可欠で容易ではないことを実感しました。
(立命館大学文学部)
専門外の者でもとっつきやすく話していただけて良かったです。(立命館大学専門研究員)
発表後の質疑応答での意見交換は非常に興味深く、意義深いものでした。
(立命館大学文学部考古学・文化遺産専攻)
年縞が地域の環境変化、災害の解明に大きく影響することを知ることができて、大変興味深かったです。(立命館大学文学部地理学専攻)
チラシはこちら
2014.05.21
国際ワークショップ 「How Forests Think 森はいかに思考するのか」
エクアドル・アマゾン上流地方において、人間を含めた多様な生命体が棲む熱帯林という環境のあいだに生じる複数の交感を捉える先住民の様式を「翻訳」しようと試みるEduardo Kohn氏の最先端の研究に触れるため、国籍問わず学内外から多くの学生や研究者たちが集まりました。
これまでのアニミズム論をさらに拡張するKohn氏の講演、コメンテーターや参加者とのディスカッションなど、多彩なワークショップ形式に、時間の延長を希望する方も現れるほどの盛会となりました。
参加者からのコメント:
「~でないもの」、「~の間にあるもの」に注目する不在論理に大きな興味を持ちました。モノとモノの間にあるマテリアルに関心を寄せる芸術作家を思い起こし、感覚の共通性に気づき驚きを覚えました。(立命館大学グローバル・イノベーション研究機構)
Thanks for the oppotunity to hear this thought-provoking and great talk. (Osaka University)
【意訳】刺激を与えてくれる素晴しい講演でした。(大阪大学)

Eduardo Kohn, PhD (McGill University, Canada)

満席の会場

聴講風景

ディスカッションの様子
左はコメンテーターの大村敬一氏(大阪大学)

質問する参加者

ワークショップ後も絶えない好奇心
これまでのアニミズム論をさらに拡張するKohn氏の講演、コメンテーターや参加者とのディスカッションなど、多彩なワークショップ形式に、時間の延長を希望する方も現れるほどの盛会となりました。
参加者からのコメント:
「~でないもの」、「~の間にあるもの」に注目する不在論理に大きな興味を持ちました。モノとモノの間にあるマテリアルに関心を寄せる芸術作家を思い起こし、感覚の共通性に気づき驚きを覚えました。(立命館大学グローバル・イノベーション研究機構)
Thanks for the oppotunity to hear this thought-provoking and great talk. (Osaka University)
【意訳】刺激を与えてくれる素晴しい講演でした。(大阪大学)
Eduardo Kohn, PhD (McGill University, Canada)
満席の会場
聴講風景
ディスカッションの様子
左はコメンテーターの大村敬一氏(大阪大学)
質問する参加者
ワークショップ後も絶えない好奇心