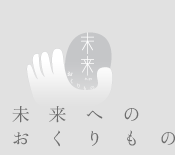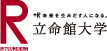2010年5月28日更新
- 田中 弘美
- 総合理工学院 情報理工学部・知能情報学科 教授

- 工学博士。1975年お茶の水女子大学理学部物理学科を卒業後、富士通に入社。1981年ロチェスター大学大学院コンピューターサイエンス学科修士課程修了。1988年ATR通信システム研究所客員研究員。「臨場感通信会議」の研究に従事。1994年から現職。趣味は2人の息子たちとの格闘と「ン十年ぶりに始めたピアノ」という。


ディスプレイの中に、肉の塊のような立体が浮かんでいる。ペンに似た外部装置を動かすと、その肉塊をつついたり引っ張ったり出来る。形が変わるのはもちろんだが、そのペンからは触った感覚や肉塊からの反動が返ってくる。それだけではなく、別のコンピューターで同じ画面を見ている人が、やはりペンを動かして肉塊を引っ張ると、自分のペンもそれにつれて引っ張られていく。この時に指に伝わってくる触覚の共有は、驚きというより感動といっても過言ではない。
「臨場感通信とも言いますが、1980年代末から複数の地点で同じ仮想空間を共有する研究が始まりました。例えば、ある人が画面の中のクルマを裏返しにすれば、別の人はそれを横向きにしてデザインを検討するといった感じですね。でも、これまでの立体は表面だけのハリボテで、色や向きを変えられるだけ。そこで私たちが目指したのは、中身が全部詰まった状態でのインタラクティブ(双方向)なのです」
近年は内視鏡手術が普及しつつあるが、直近の目標は「その訓練への応用」と田中弘美は語る。
「手術は、経験的な感覚が大切なので、今は一対一で教えるしかありません。シミュレーションで同時に複数を訓練するためには、骨や肉などの触感の共有や手術器具の改善なども必要。ところが人間の触覚は1秒に約1000回の情報を伝達しないと感じません。双方向で触感を共有するには大変な計算が必要になります」
そこで田中は、触覚の再現に必要なデータと計算方法などを予め相手のコンピューターに送る分散処理と、モデリングによる徹底的な効率化手法を開発。つまり、変化する部分で重要な情報だけを絞り込み、これをやり取りするわけだ。
「私の専門はソフトウェアなので、スーパーコンピューターに頼ることなく、普通のパソコンで普通に出来るようにしたかった。このシミュレーションは5年以内に完成と宣言してしまったので、これからが大変ですけどね(笑)」
AERA 2009年4月13日号掲載 (朝日新聞出版)
このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学広報課 Tel (075)813-8146 Fax (075) 813-8147 Mail koho-a@st.ritsumei.ac.jp