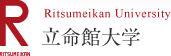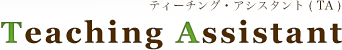演習補助
No.01
- 氏名
- 竹村 朋子 さん
- 所属研究科
- 社会学研究科
- 担当科目名
- 専門演習
TAになったきっかけはなんですか?
ゼミの先生から声をかけていただき、TAになりました。学生との接し方や学生の様子、先生の教え方なども勉強できると思ったこともTAになったきっかけです。
どのような業務をされていますか?
2010年度の授業では「京都三条ラジオカフェ」というコミュニティFMの番組を作成したり、アメフトの応援を盛り上げるPRを行ったり、映像の撮影・編集などを行いました。グループワークでの話し合いに助言したり、発表に対してコメントしたりするのがTAの主な業務です。
TAをする中で工夫していることはありますか?
TAが意見を言い過ぎるとそちらに話が流れてしまうため、助言する際にはアドバイス程度にとどめるようにして、話を導かないように気をつけています。また、先生には話せないこともTAには話せるよう、学生と同じ目線に立ち、学生に近い立場にいられるように心がけています。
どのようなときにやりがいを感じますか?
授業が進むにつれて学生との距離が近くなり、どんどん気軽に話しかけてくれるようになりました。普段は学生とふれあう機会がないので、こうして人間関係を築けるのがとてもうれしかったです。
ゼミを担当してみて、先生が学生1人1人と向き合い、時間をかけて対応しているのがよく分かり、とても勉強になりました。信頼関係を築かないとゼミはうまくいかないと感じました。私も教員になったときには、ゼミだけでなく学生のために時間を取って応対したいと思うようになりました。
ゼミを担当してみて、先生が学生1人1人と向き合い、時間をかけて対応しているのがよく分かり、とても勉強になりました。信頼関係を築かないとゼミはうまくいかないと感じました。私も教員になったときには、ゼミだけでなく学生のために時間を取って応対したいと思うようになりました。
後輩へのアドバイスをお願いします。
ゼミのTAでは、学生とのコミュニケーションが一番大切だと思います。名前と顔を早く覚えたり、1人1人特性が違うのでその違いを理解したりすることも重要です。
アドバイスをする上では、学生に考え直すきっかけを与えたり、正しい方向に導けるように、相手の話を聞いたうえで最後に言うのがよいと思います。
最初のうちは、学生のグループになかなか入れなかったり、あまり話を聞いてくれなかったりするかもしれません。切り口となる学生を見つけて、ちょっとずつ入っていくのがよいかと思いますが、何年かTAをしていくうちに学生との接し方も分かってきます。1年だけでは足りないこともあるので、ゼミのTAはぜひ数年続けて取り組むことをお勧めいたします。
アドバイスをする上では、学生に考え直すきっかけを与えたり、正しい方向に導けるように、相手の話を聞いたうえで最後に言うのがよいと思います。
最初のうちは、学生のグループになかなか入れなかったり、あまり話を聞いてくれなかったりするかもしれません。切り口となる学生を見つけて、ちょっとずつ入っていくのがよいかと思いますが、何年かTAをしていくうちに学生との接し方も分かってきます。1年だけでは足りないこともあるので、ゼミのTAはぜひ数年続けて取り組むことをお勧めいたします。