野生動物と人が共生するために今できることって?
2024.08.09
なぜこの研究をしているの? どんなところが面白いの? 研究の源である「探究心」について先生に聞きました。
-
 桜井 良 准教授
桜井 良 准教授
立命館大学 政策科学部
-
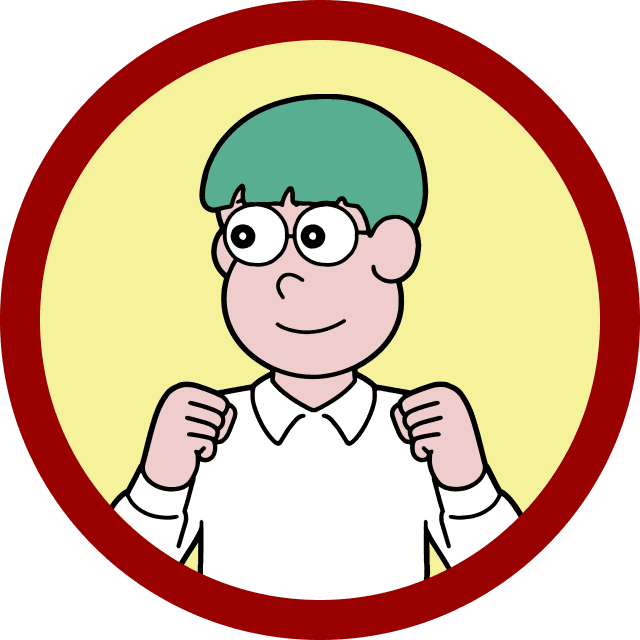
- 先生が研究している「学際的生態学」って初めて聞きました。何を対象にどんな研究をするんですか?
-

- 地球上にいる野生動物と人間が、共存して生きていく方法を考えています。たとえば絶滅危惧種という言葉を聞いたことがありませんか? 絶滅危惧種、つまり放っておいたら地球からいなくなってしまう野生の生き物たちを何とかして救ってあげる。これも大切な研究テーマのひとつです。
-
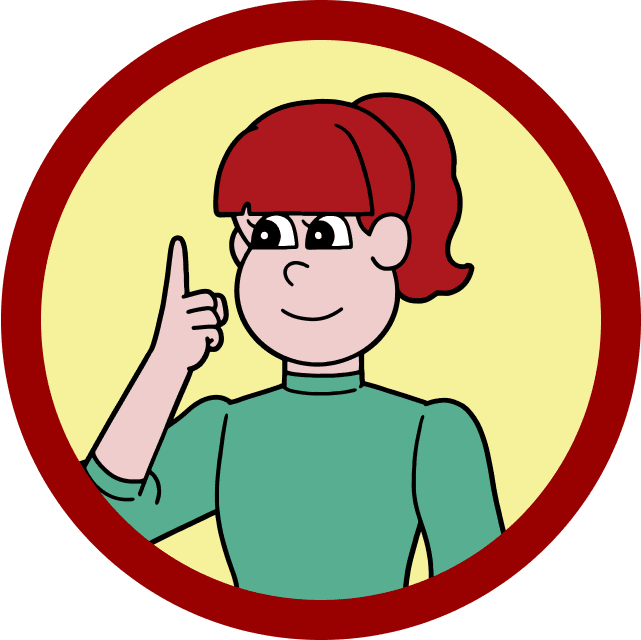
- 日本の絶滅危惧種にはどんな動物がいるんですか?
-

- 日本では、イリオモテヤマネコやシマフクロウが絶滅危惧種ですね。絶滅しそうな動物を守って、数を増やしていくことは大事なことです。絶滅してしまったら元に戻すことはできませんから。昔は日本にオオカミもいたんだけど、知ってますか?
-
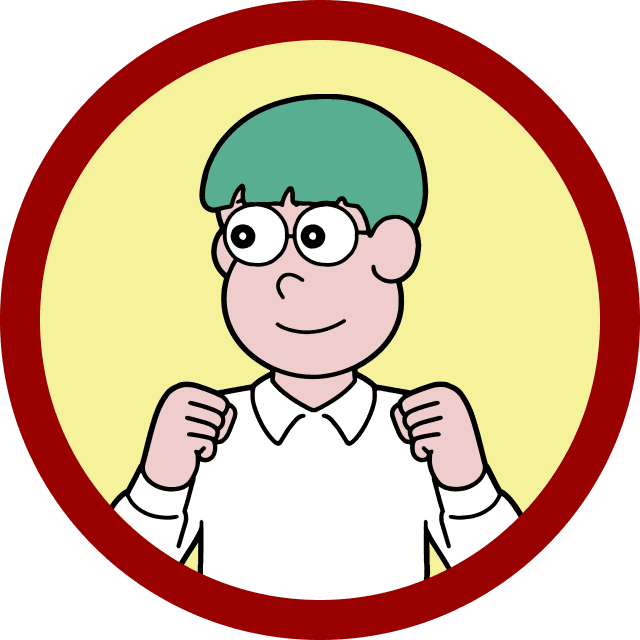
- はい、日本では絶滅しちゃったんですよね。
-
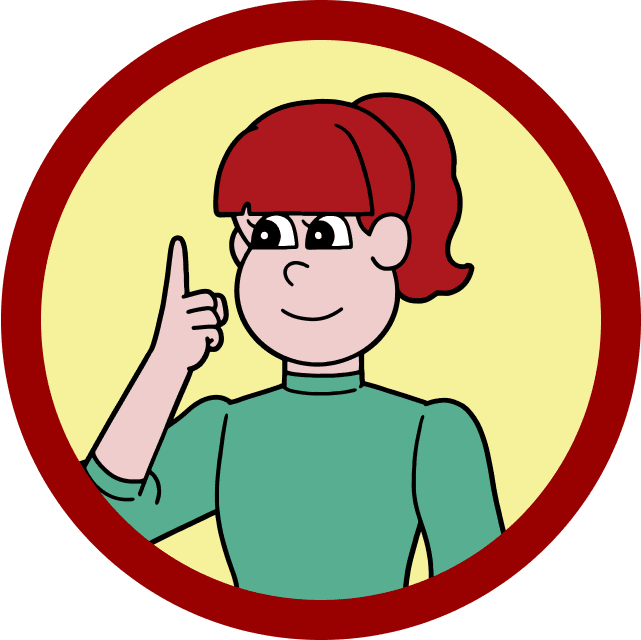
- 外国ではオオカミはまだ絶滅してないの?
-

- アメリカでは絶滅寸前だったことがあります。けれどアメリカのいくつかの地域で、「オオカミの再導入」と言って、他の地域からオオカミを連れてきてオオカミの群れを復活させたんです。だから今では人間とオオカミが共生しています。
-
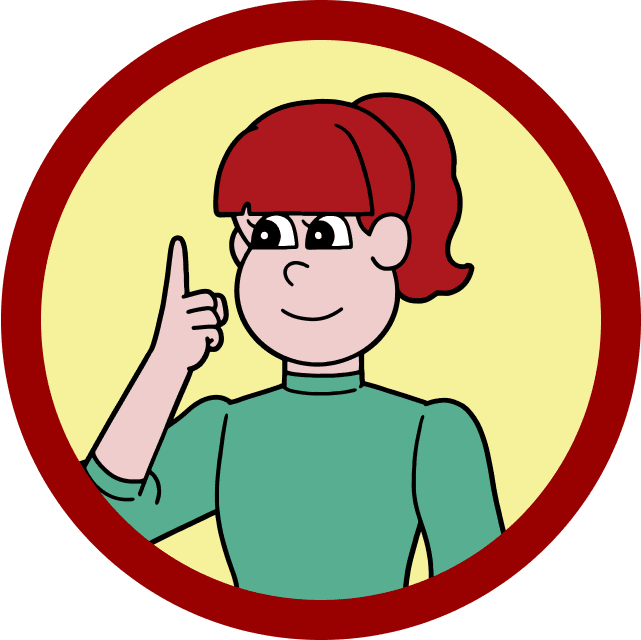
- 復活させるなんてすごい!でも、オオカミと共生ってちょっと怖いなあ……。
-

- 実際のオオカミは、臆病で人目を避ける習性があると言われています。私は子どもの頃から野生動物が大好きで、大学生の時にはわざわざアメリカまで野生のオオカミに会いに行きました。間近で見た野生のオオカミは、とても落ち着いていて穏やかで、人間と共存が可能な野生動物なのだと思いました。
-
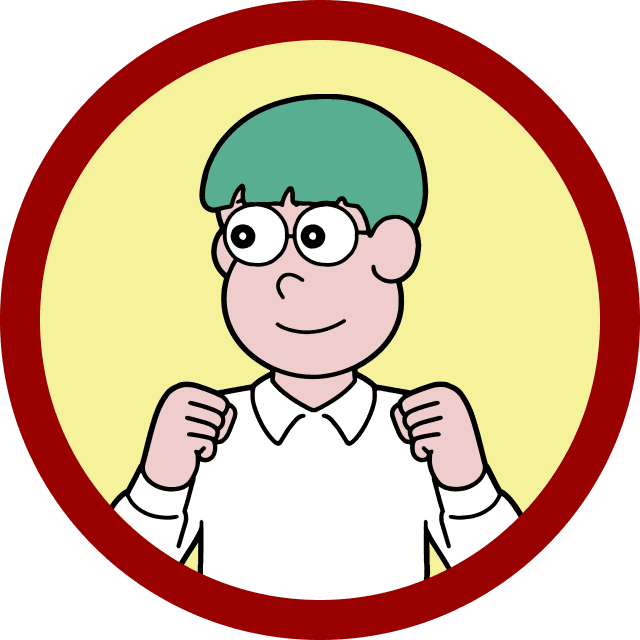
- それなら日本でも、もう一度オオカミと一緒に暮らせたりするのかなあ?
-

- オオカミを復活させることに反対する人もいますし、実際に何らかの被害が出る可能性もゼロではないので、そう簡単にはいかないでしょう。そこがこの研究の難しさでもあります。でも、日本には一度絶滅してしまったコウノトリやトキなどを復活させた実績がありますよね。
-
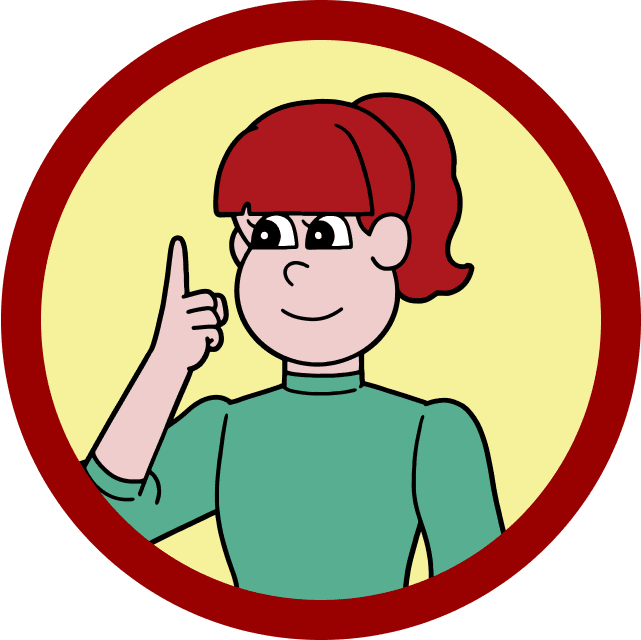
- そっか!そうですね。
-

- それにオオカミは、自然全体を守るためにとても大切な役割を果たしています。だからアメリカはオオカミを復活させたんです。
-
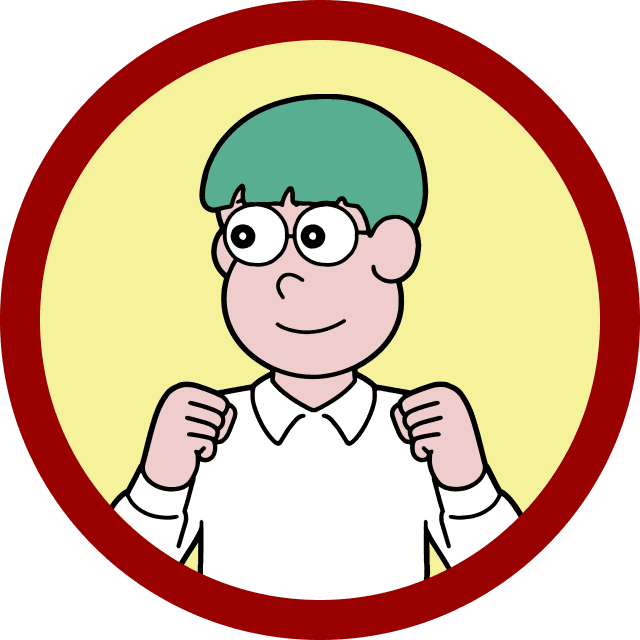
- オオカミが自然を守るってどういうことだろ? オオカミは肉食だから怖がる人もいるのに。
-
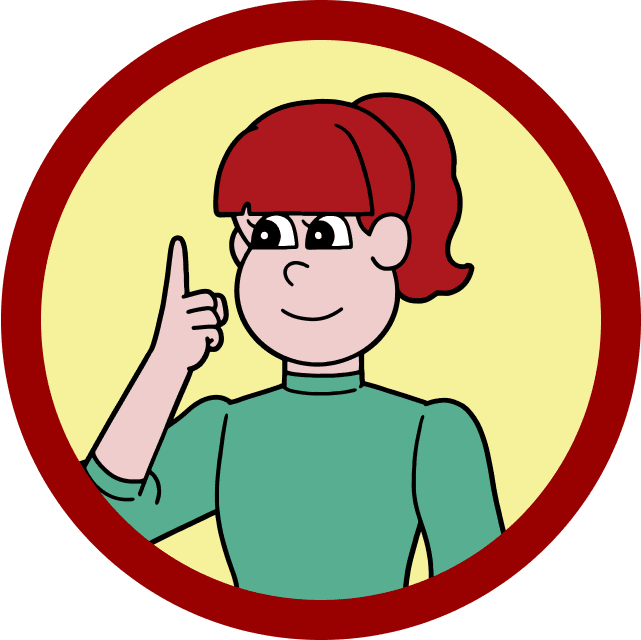
- 逆にオオカミが他の動物を食べるから、自然のバランスを保てるとも考えられそう。
-

- よく気がつきましたね。オオカミは野生動物の中でも、生態系の頂点にいる生き物の一種です。そのオオカミが他の動物を食べてくれるから、たとえばシカの数が増えすぎたりしない。いま日本の山林で問題になっているのは、増えすぎたシカが農作物や草木を食べ荒らす被害です。木の皮をシカが食べるので、木が枯れてしまうんですね。自然を守るためには、全体的なバランスがとても大切なのです。
-
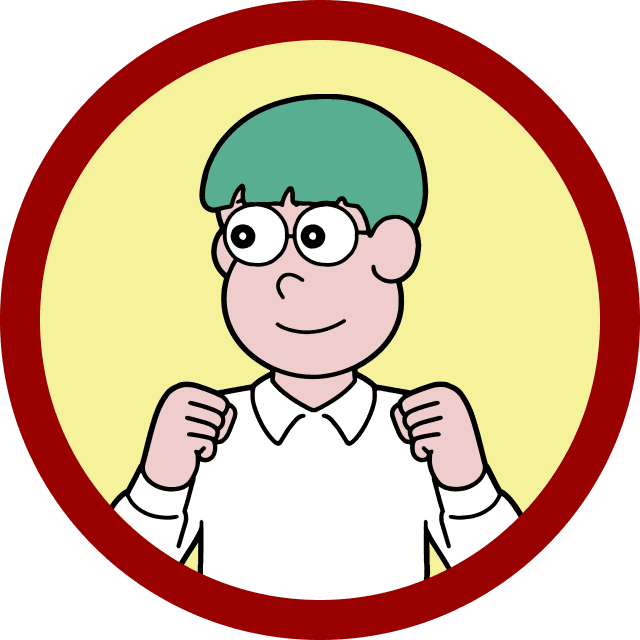
- それでもオオカミを復活させる研究って、とても難しそう。だって復活に賛成する人もいるけど、絶対にイヤだって人もいそうだもん。
-

- だから私たちのような研究者の出番なんです。問題は単純にオオカミを復活させるかどうかだけにとどまらず、地球の持続可能性にもつながります。そもそも人間が、自然をすべて管理できたりするでしょうか?
-
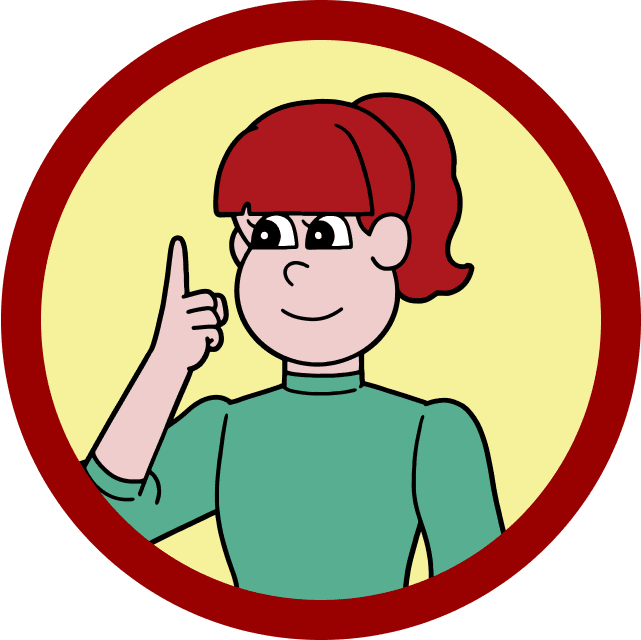
- 人間が自然を管理しようとしても、限界があるんじゃないかなあ。
-

- そうですね。私は、人間は自然と共存しながら生きていくべきだと思います。たとえばコロナの時のように、人間が外出できないことが起きたら誰が自然の管理をするのでしょうか。人間がすべて管理するのではなく、自然の力に任せて再生していく、元の姿に戻していくことが大切なのです。
-
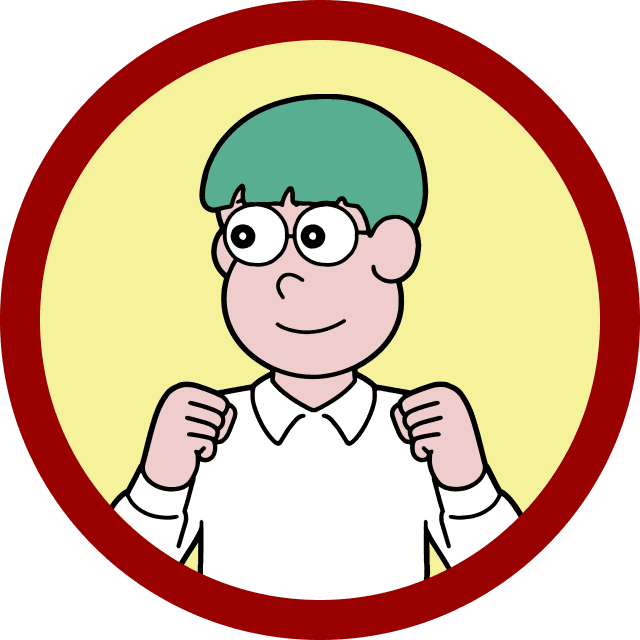
- オオカミの再導入もそういうことですよね。
-

- 北海道の斜里町では、生態系の復元のために、絶滅した生き物を復活させることを目指しています。まずはカワウソを復活させて、いずれはオオカミもと考えているようです。
-
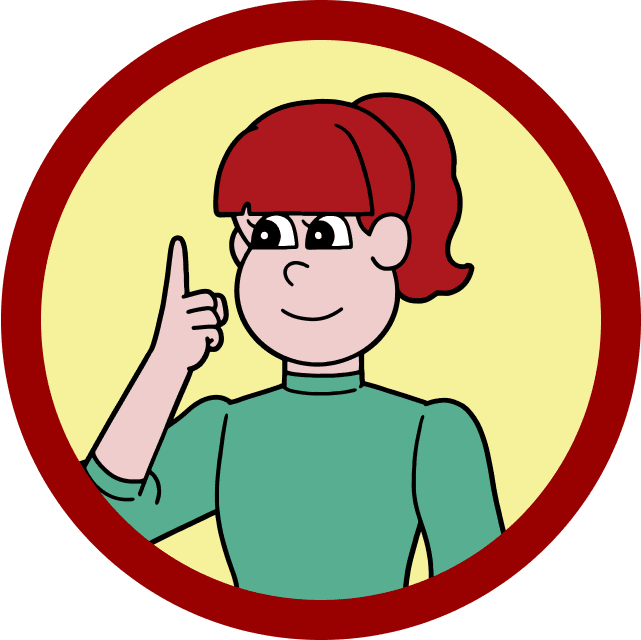
- 日本でもそういう取り組みがスタートしてるんですね。
-
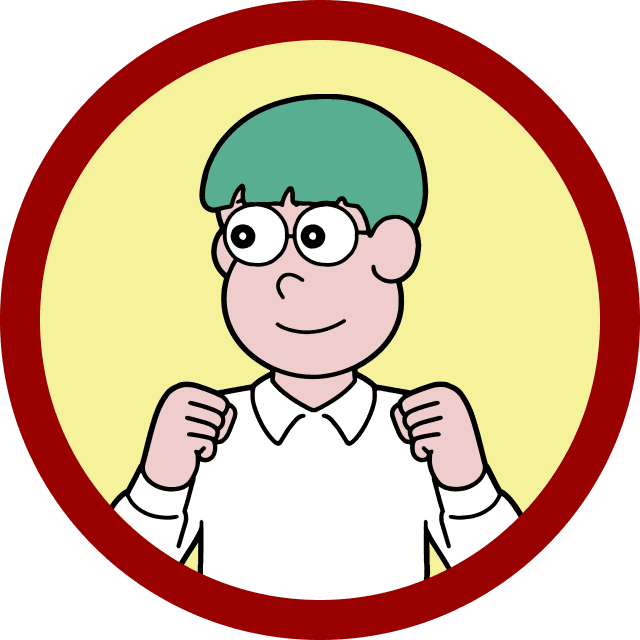
- 最後に、先生がこの難しいテーマの“探究”を続ける理由って何でしょうか?
-

- この研究は、いま世の中で起きていることと関連しています。現在進行形なんですよね。それが自分の原動力になっています。もうひとつ言うと、そもそも動物が大好きなので、好きなものはやめられない。難しいテーマではありますが、動物と一緒に暮らせるようにと考えていけば、世界をもっとよくできると思っています。
