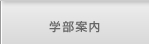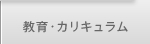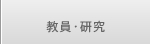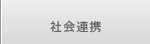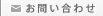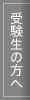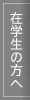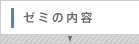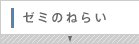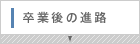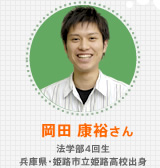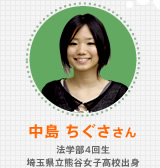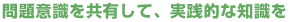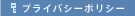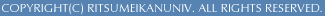- 現在表示しているページの位置
-
- HOME
- 教育・カリキュラムindex
- 授業・ゼミ紹介
- 税法ゼミ
「税」というと経済や会計の勉強と思われがちですが、税に関する基本的なルールは法律で定められています。したがって、税法の学習は、法律の解釈や適用に関する学習が中心となります。近年、税に関する様々な法律問題が多発し、裁判で争われることも少なくありません。税法ゼミでは、主にそのような税金裁判を素材に法的な思考力やコミュニケーション能力を養成するために、ディベート形式で学習を進めています。
前期は税法の基礎知識の習得に力点を置いています。各回事前にテーマと担当を決めて、報告と質疑応答、講義を織り交ぜながら進めていきます。後期はテーマを設定し、班編成をしてディベート形式の演習を行います。実際の判例や裁判例などをもとに、肯定・否定の両サイドから議論してもらいます。法律には絶対的な正義はありません。様々な立場に立つことで、多角的な視点を養います。さらに、相手の意見を聞き、自らの主張を論理的に説得していく力を徹底的に身に付けていきます。
また、後期の11月と12月に他大学とのディベート大会が行われます。真剣勝負の対抗戦を経験することで、自分の現在の学びの到達点を実感できます。立命館大学税法ゼミの学生は、各大会において毎年優秀な成績をおさめています。

税法は我々の生活に密接に関係している法律分野です。例えばアルバイトをすればバイト代から所得税が天引き(源泉徴収)されますし、買い物をすれば5%の消費税を負担しなければなりません。つまり、税法を学ぶことは、日常の身近な生活や我々をとりまく社会のあり方について考えることでもあるのです。まずは税法を身近に感じることが税法を学ぶための第一歩といえます。また、税法というと、他の法律分野との関連性は薄いように一般的に考えられがちです。しかし、税法も憲法秩序の中にある法律分野の一つである以上、憲法や民法をはじめ他の法律分野との整合性を考えなければなりません。ゼミを通じて、税法が多くの法律分野と密接な関係をもっていることを理解してもらいます。
税法を学ぶためには、常に社会の動きに敏感でなければなりません。新聞やテレビ、インターネットの情報はもちろん、法律書に限らず様々な書物を通して豊かな感性を養わなければなりません。何事につけ日頃から関心や問題意識を持ち、視野を広げておくことが必要です。

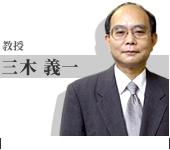
- 東京生まれ。73年中央大学法学部法律学科卒業。75年一橋大学法学研究科修士課程修了。博士(法学、一橋大学)。静岡大学教授等を経て、94年より現職。専攻は税法。学生時代に憲法ゼミに所属していた関係もあり、税法を憲法の人権論との関係で研究を進める。98年前期にドイツ・ミュンスター財政裁判所に留学してから、税務訴訟の国際比較に関心をもつ。そのほか、租税制度の法的研究を中心に多くの著書や論文がある。主な著書として『よくわかる税法入門』(有斐閣)や『日本の税法』(岩波新書)など多数。

- 静岡県生まれ。89年慶応義塾大学法学部法律学科卒業。監査法人朝日新和会計社(現・あずさ監査法人)にビジネスコンサルタントとして勤務した後、97年静岡大学法学研究科修士課程修了。静岡産業大学経営学部講師を経て、2004年より現職。専攻は税法。納税者の権利保障の視点から、アメリカの納税者保護法制を中心に研究を進める。主な論文に「アメリカにおける納税者の権利保護」(『世界の納税者権利憲章』中小商工業研究所、2002年所収)がある。
税法ゼミには法科大学院や大学院に進学して弁護士・税理士・公認会計士等の資格取得をめざす人が多く、実際にこれまで多くの専門家を輩出しています。また、国家Ⅰ種・Ⅱ種や国税専門官など公務員志望者も多く、国家Ⅰ種に採用された人も連続して出ています。もちろん、金融関係を中心に民間企業への就職者も多くいます。そして、それぞれ自分が身に付けたことを活かせる環境へ進んでいます。また、交流会やネット上のフォーラム、メーリングリストによる情報交換など、OB・OGとの交流も盛んです。
 |
||
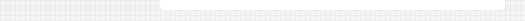 |
||
|
 |
||
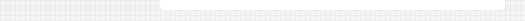 |
||
|