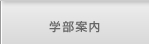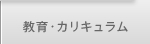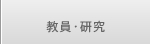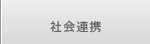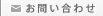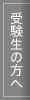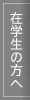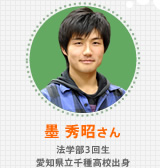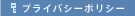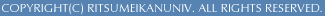- 現在表示しているページの位置
-
- HOME
- 教育・カリキュラムindex
- 授業・ゼミ紹介
- 国際法ゼミ
国際社会の緊密化に伴い、法の分野でも国際化が進んでいます。これまでは国内的な問題として処理できていたものが、国際社会を無視しては解決できない諸問題が生じ始めました。そういった様々な事例・判決を公法的な側面から観察し、国家間で日々繰り広げられる法的調整がどのような意義を持っているかを考えていきます。それを通じて、国境を越える諸問題について的確な法的判断を行えるような能力を身に付けることが、このゼミのねらいです。

「国際社会における法的諸問題」というテーマに即し、実際に起こった事件を対象にして原告・被告・裁判官役に分かれて模擬裁判形式でゼミを進めます。立論して展開、質疑応答、最終弁論という流れで法的な論争をし、判決を提出します。学生が興味のある事件をテーマに選ぶため、各自が主体的に関われるゼミです。過去には、「在テヘラン米国大使館員人質事件」や日本が当事者として関わった「みなみまぐろ事件」など、国際裁判所・機関で争われた様々な国際的事件を中心に扱ってきています。
模擬裁判形式なのでグループワークが中心。学生には参加する姿勢や旺盛な知的好奇心、議論の中で意識を高く持ち、何かを得ようという積極性が求められます。もちろん国際法の知識は必要ですが、それは議論の中でその都度学んでいくことで身に付いていくことになります。それ以上に、異なる立場で物事をとらえることが重要で、多角的な物の見方や、論理的な思考を養うことが大きな目的です。結局はゼミを通じて知識だけでなく、何を身につけるかが大切になってきます。
また3回生後期には他大学との合同ゼミを開催します。ここでも模擬裁判形式で大学間の論争が繰り広げられます。ゼミとして一つの立場に立ち、協力して論破を目指します。その論理構成能力などを学生審査員や教員が採点します。テーマから進行まで全て学生の手で考えるのですが、徳川ゼミの学生は毎年非常に力を発揮してくれています。他大学の学生との交流は自分の成長を実感できるよい機会です。また、新たな視野を獲得する刺激的な場所でもあります。
4回生では卒論作成に大半の時間を当てています。就職活動もありますので、模擬裁判では裁判官役として3回生の議論に加わり、上回生の目線で指摘をしています。

- 90年立命館大学法学部卒業。95年同大学院法学研究科公法博士課程修了。(財)世界人権問題研究センター研究員を経て、1996年に本学へ。国際社会における統合と排除に関わる考え方が、人権・民主主義・市場原理の概念を機軸に再編されようとしている。その現状について国際人権法の視点から研究を進めている。その研究を中心に国際刑事法や国際人道法との関係、さらにEU統合過程と人権・民主主義の関係についても研究している。

国際法は国家と国家の利害関係を調整する法です。例えば捕鯨問題、北方領土、核兵器問題などの事例もそうです。国際法においてはドメスティックな感覚は通用しません。日本社会の法基盤は通用しないのです。まずは自分の持っている常識・基盤を疑うこと。自分の立場が絶対的でないことを認識する必要があります。感情や思いだけでは相手は動きません。確実な論拠を提示し説得力のある論理を展開することが必要なのです。徳川ゼミでは数多くのディベートを通じて論理的な構成、プレゼンテーション能力を養ってもらっています。これは社会においてはどんな分野でも必要なスキルです。
卒業生は外交官・公務員から商社・金融・メーカーといった民間企業まで多岐にわたります。基本的にそれぞれの希望で幅広く就職しています。法律の専門性が求められる現場だけでなく、様々な分野においてこのゼミを通じて培ったコミュニケーション能力や知識が活かされています。
|
|