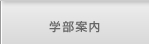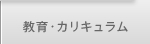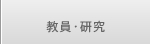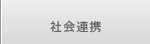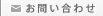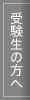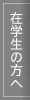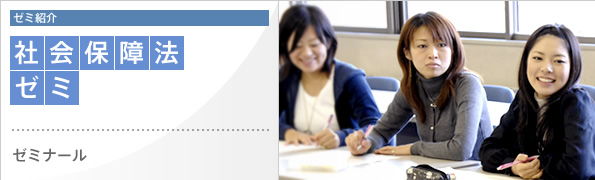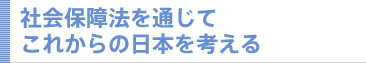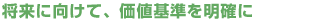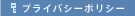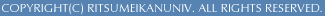- 現在表示しているページの位置
-
- HOME
- 教育・カリキュラムindex
- 授業・ゼミ紹介
- 社会保障法ゼミ
私たちは生活の様々な場面で社会保障法制度を利用しています。年金や医療保険、福祉サービスなどの制度は国民の生活保障において必要不可欠な存在です。近年の社会福祉ニーズの普遍化や財政問題を背景に、日本の社会保障・社会福祉制度は大きな見直し・改革が進められています。この諸改革が国民生活にどのような影響を及ぼし、さらに日本をどのような国にしていこうとしているのか。法律学の視点から論理的かつ実体的に考察していきます。
一年間を通じて、「これからの社会保障を考える」という大テーマの下で、学生各自の関心に応じた具体的な領域・論点について研究を進めてもらいます。市民生活の身近な問題に関心を持ち、指示された課題をこなすのではなく自ら問題解決する姿勢が必要です。3回生時にはレポート提出が義務づけられていますので、それに向けて研究し、前期と後期に1回ずつ、その成果を個別報告するスタイルでゼミを進めます。個人単位の勉強が多いため自由度も高い分、主体的に研究に取り組む姿勢が必要です。研究発表を通じて、ゼミ生の間で問題意識を共有すると共に、プレゼンテーション能力を養います。
またグループワークとして関心内容により班に分かれ、施設見学なども行っています。今年度は企業を訪れ福利厚生の実態を調査したり、社会保険事務所や視覚障害者施設などを訪れる班もありました。
年に1度は他大学と共同開催の合同ゼミも行われます。そこでは一つのテーマに則し、各大学の班ごとに研究結果を発表し討論会を行います。各大学が様々な視点でテーマに取り組んでいるので、毎年ゼミ生にとって良い刺激となり、有意義な学びの時間になっています。

- 1961年富山生まれ。85年金沢大学法学部法学科卒業。92年大阪市立大学法学研究科民刑事法博士課程、単位取得満期退学。94年から立命館大学法学部に赴任。社会保障法を専攻。高齢者から障害者まで様々な生活問題についての実践的な研究とあわせて、人権保障の観点からの立法政策研究も進めている。主な著書・論文として「社会保障の権利と社会福祉の公的責任」「社会保障法と年金問題」などがある。

社会保障法は時代の最先端の課題が多い領域です。狭い意味での法学にとどまらず、政治学、経済学、社会学、教育学など学際的な視点が求められる学問です。私たちは生活の様々な場面で社会保障制度を利用しています。年金や医療保険、老人や障害者への福祉サービスなどもそうです。生活の中に深く根ざしていますので、普段から問題意識を持つことが必要になります。大学での勉強は人に言われてするものではありません。主体的に問題に取り組むゼミを通じて、勉強することの面白さに気づいてもらいたいと願っています。社会に出れば、ますます社会保障は生活に直結してきます。選挙においても毎回争点になっています。そうした場面において、きちんと自分の意見を持って未来を選択していく力を養ってもらいたいと考えています。
社会保障法というテーマのゼミだけあって、公務員志望が多いです。ただ一般企業へ就職する学生も多くいますが、金融系に就職する人が多いようです。基本的には本人の希望次第です。どの学生も自らが関心のある問題に関わることができる環境を求め、就職先を決めています。
|
|