「グローバル化する福祉 ―アジアと欧州の進展する対話」を考える国際シンポジウムが開催
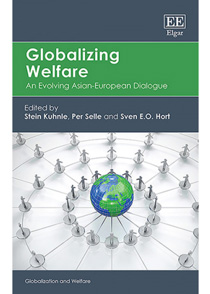
福祉先進国として知られる北欧ですが、実は紆余曲折を経験しながら福祉国家としての持続性を保ってきています。東アジアは北欧とはシステムが根本的に異なるととらえられてきましたが、今や社会経済のグローバル化と高齢化という共通課題において、北欧と東アジアは福祉国家の持続性に関して情報共有し、対話することが求められる時代となっています。
政策科学研究科では2019年10月31日(木)にOIC総合研究機構地域情報研究所との共催で比較福祉国家研究の第一人者であるノルウェー国立ベルゲン大学比較政治学部名誉教授のスタイン・クーンレ(Stein Kuhnle)氏、デンマーク国立南デンマーク大学福祉国家研究センター長・政治行政学部教授であるクラウス・ペーターセン(Klaus Petersen)氏をお招きして、国際シンポジウムを開催しました。本企画は、両氏および本研究科教員3名も執筆したStein Kuhnle, Per Selle and Sven E. O. Hort (eds), Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European Dialogue, Edward Elgar, 2019の出版記念も兼ねておこなわれました。なお、クーンレ氏は2016年度OIC総合研究機構地域情報研究所客員研究員として本学に滞在されています。

講演では、まずクーンレ氏(編著者)が社会政策のグローバル化に関する欧州での事例をあげ、一国レベルでの福祉供給のゆきづまりと国際的な共同体による国境を越えた社会問題の解決について提起しました。続いてペーターセン氏(第12章担当)が、デンマーク福祉国家の最盛期(1960-1970年代)における保育をめぐるさまざまなレベルでの政治的議論について紹介しました。日本では同年代には男性稼ぎ手モデルが定着して経済発展しましたが、デンマークでは逆に女性を納税者とするために全日制保育が徐々に進められ、現在でも3-5才児の95%が入所したうえで福祉国家の質が維持されているのは興味深い点です。
両氏の講演の後は、3名のコメンテーターとのディスカッションがおこなわれました。林相憲(Sang Hun Lim)氏(Kyung Hee University准教授、2019年度OIC総合研究機構地域情報研究所客員研究員)からは福祉はどれくらいグローバル化できるのかという問いかけがありました。また、上久保誠人氏(本学部教授、第6章担当)からは、福祉のグローバル化の一方で台頭するポピュリズムや福祉国家と増税についての疑問が投げかけられました。さらに、桜井政成氏(本学部教授、第8章担当)からは、日本とデンマークの保育運営主体の相違に関しての質問がありました。フロアからも学部生・院生が自身の出身地や研究テーマに絡めた活発な質問が相次ぎました。クーンレ氏・ペーセン氏はそれらの質問に丁寧に回答され、従来の福祉国家論の枠組みを超えたグローバル化時代における東西問わない知識共有の必要性を参加者全員が認識したところで、モデレーターの大塚陽子氏(本学部教授、第7章担当)から閉会の辞があり、国際シンポジウムは盛況のうちに終了しました。


