|
大久保 いろいろあるにせよ、みなさんは「これだ」と思って、期待してきたわけですね。それで、どうでした。実際に入ってみて。
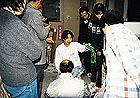 |
| 自然エネルギー学校・京都...雨水利用の実験風景 |
|
田嶋 いくら環境問題は幅広いといっても、最初は、やっぱり主役は理系かなっていう思いもありました。1回生の終わりごろから、理工学部の笹谷先生がやっておられた「気候ネットワーク」の活動に深く関わるようになったのですが、その中で、環境問題には文系的というか、理論を現場に下ろす時点での問題も非常に大きいというのがわかりました。経営学部で企業の視点とか市民の視点について勉強をしつつ、理系の環境問題に関する知識も付ける、ということが非常に重要だと思うようになりました。
木村 私としては、経済と経営が一緒になっていて、経営戦略系のこともやれるし、経済の基本のミクロ・マクロ系もやれるので、とても満足しています。今は就職活動前ですから現実的になっていて、サービス系だけではなく、メーカーや流通、金融とか、いろんな方面も知った上で、何をやりたいか考えようと思ってます。とはいえ、サービス系の顧客満足とかコミュニケーションとかいった分野は、何をするにも重要だし、社会に出る上での基本について学ぶことが多い。サービスのインスに入ってよかったと思っています。
大久保 もう将来の話も出ましたけど、今、どういうことをやっていて、それを今後どうつなげていきたいかということでは、いかがですか、杉崎さん。
 |
 |
| すぎさき・ゆきえ...経済学部経済学科3回生、佐藤ゼミ。環境・デザインインスティテュート。3回生で立命館大学へ編入、今年の夏に電通へインターンシップ。私立桐蔭学園高校出身。
|
|
杉崎 BKCに行くとき「かがやき通り」を通るんですが、輝いてない気がして、ゼミで「かがやき通りをその名のとおりにしたい」って言ったんです。夏休み明けにかがやき通りのごみを集めて、市役所に持っていって、それを何回か重ねた上で、何か自分なりの提案をしようと考えています。日本は町づくりに統一性や計画性がないような気がします。ヨーロッパなんか、古い建築をきれいに保存して、調和を乱さない中で新しいものをつくる。町づくりに注意が払われていて、歩いていても気持ちがいい。そういうふうに日本をきれいにできればなと。ゼミではあと「京都駅で四季の演出をする」という課題が出まして、うちの班が「なんちゃってウエディング」というプランを出したところ、9月か10月に企業の方にプレゼンできることになりまして、今、その準備をしています。
田嶋 私は近々、ISO14001の外部監査に必要な「環境審査員」の資格を取得するための研修と試験を受ける予定です。あと、京都府下にある市の環境基本条例策定の支援もやっていて、一般に環境基本条例は、「できた、終わり」というパターンが多くて、実効性に疑問があるのですが、その市は最初の作成の段階から市民を巻き込むことで実効性を上げようとしていて、そのお手伝いをしています。環境問題で理論的な部分というのは、だいたいわかっているのですが、わかっていながら改善ができていない。それは理系か文系かという問題じゃなくて、国と国の関係だとか、国と企業、産業界の関係が複雑にからんでいる。最終的にはそういう問題を解決したいと思っています。
福田 私はゼミでカードマネーや電子マネーについて学んでいまして、卒業後はシステムエンジニアになりたいと思っています。ユーザーとつくる側の方の間に立って、どっちの要求もちゃんと把握できる人間になりたい。そこが把握できていないのが、今大きな問題だと思うのです。私がやりたいのは銀行のシステムで、金融のことと、システムを構築する側のこと、両面を理解したいと考えています。
大久保 SEっていう職業があるでしょう。一口で言えば、お客さんの話を聞きながらシステムをつくるわけだけど、理系の勉強だけだと難しいのです。経営的な視点、経済的な視点もいる。「スーパーSE」というキーワードがあって、一人の人間が、簿記も経済も、システムもハードも、もうあらゆることを知っていて、お客さんの要求を分析しながら、機器はこうだ、ソフトウエアはこうだって、実際のシステムにまとめていく。そういう能力が今非常に求められていて、まさに福田君が言ったようなことが重要になるのです。
山下 私は、インスならやりたいことがやれると思いながらも、なかなか何をテーマにすればいいのかわからなくて、インターンシップをそのきっかけにしたいと思いました。京都パープルサンガの普及部に行って、子どもたちに教えていますが、幼稚園児と触れ合う中で、子どもとスポーツについて、少しずつ勉強を始めています。
|