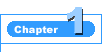|
最初に向かった場所は、末川記念会館。立命館の歴史のすべてが集まっている「立命館百年史編纂室」(以下、編纂室)がここにあります。1980年代には立命館史編纂室とよんでいましたが、1991年に現組織に変更。現在はその名のとおりに立命館の百年の歴史に関する資料を収集・分析・編集し、『立命館百年史紀要』(年1回発行)や『立命館百年史』にまとめる編集局の役割を果たしています。
「あっ、これが『立命館百年史』ですね」。
佐野隊員が発見した分厚い書籍こそは、昨年3月に発行された『立命館百年史 通史編第1巻』。立命館の創始(1869年)から終戦(1945年)までの戦前・戦中史がこと細かにまとめられています。『通史編』はこの後に戦後前半編(1945年〜1980年)の『第2巻』、戦後後半編(1980年〜2000年)の『第3巻』へと続けて編纂されます。また、『通史編』には各分冊に対応した『資料編』も併せて発行され、『立命館百年史』は合計6冊の大作になる予定です。
「佐野隊員、『立命館』の名前の由来は知ってる?」
疑問の答えは…「立命」は中国の古典『孟子』の盡心章にある、『殀壽不貳 修身以俟之 所以立命也』(ようじゅたがわず、みをおさめてもってこれをまつは、めいをたつるゆえんなり)の一節から採られたものだそう。
「これは『若死にする人も、長生きする人も、すべて天命で決められているから、人は生きている間は勉強に努めて天命を待つのが、人間の本分をまっとうすることになる』(大意)という意味で、『立命館』は人が本分をまっとうするための場所ということらしいですよ」。
|