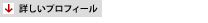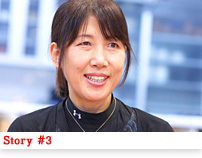「遠い土地に行き見知らぬ人びとから生き方を学ぶ。それは人類学が創りだした、謙虚さの作法だった」。自著の中でこう記したように、見知らぬ土地に赴き、「人の生き方の幅」を確かめることは、現代人類学の重要な一側面です。
私が人類学研究をスタートさせたのは、アフリカでした。コンゴ民主共和国(旧ザイール)に残る王制社会について、1984年から90年にかけて都合1年半ほどのフィールドワークを中心とした研究に取り組みました。そして現在は、現代人類学の基礎を作ったと言われるマルセル・モース(1872~1950)の業績を21世紀の視点から再評価し、その人類学的探求をつまびらかにしようとしています。
 モースは、フランス社会学の創立者エミール・デュルケーム(1858~1917)の甥であり、この偉大な叔父から直接薫陶を受けました。さらにその思想は、現代人類学の頂点とも称されるレヴィ=ストロース(1908~2009)へと引き継がれていきました。モースの業績は、生前はもちろん、没後から現代にいたるまで何度か再評価されています。私は、モースの業績の今日的な意義と射程を解明することはもちろん、同時代的な文脈においても再読したいと考えています。そのために、彼の著作を日本語に翻訳する取り組みを進めています。何人かの研究者そして出版社と協力して彼の仕事をまとめ、他の分野からの評価も受けられるよう著作集を刊行する予定です。
モースは、フランス社会学の創立者エミール・デュルケーム(1858~1917)の甥であり、この偉大な叔父から直接薫陶を受けました。さらにその思想は、現代人類学の頂点とも称されるレヴィ=ストロース(1908~2009)へと引き継がれていきました。モースの業績は、生前はもちろん、没後から現代にいたるまで何度か再評価されています。私は、モースの業績の今日的な意義と射程を解明することはもちろん、同時代的な文脈においても再読したいと考えています。そのために、彼の著作を日本語に翻訳する取り組みを進めています。何人かの研究者そして出版社と協力して彼の仕事をまとめ、他の分野からの評価も受けられるよう著作集を刊行する予定です。
モースの業績の全容を解き明かすことは、狭義の人類学の発展に寄与するだけに留まりません。モースを同時代の人文社会科学の動向の広い文脈に置き直すことが、現代の文脈における人類学の可能性を再検討すること、さらには人類学という学問領域を超えて、人文社会科学全体を問い直すことにもつながります。その成果はきっと、私たちが生きる「今」というこの困難な時代を活性化する道を模索するための手がかりとなるはずです。
モースが「未開社会」へ目を向けたのは、19世紀後半から20世紀前半にかけて、ヨーロッパの列強がアフリカやアジアを次々と植民地化した時代でした。そうした中でモースは、植民地支配下にある人々の暮らしや文化に対しても、謙虚で知的な姿勢を貫きました。モース自身はフィールドワークをほとんど行いませんでしたが、かわりに膨大な民族誌の記録を精読し、それぞれの土地の人々が「生きるために見出した価値」を汲み取ろうとしました。未知の世界の人々の文化や習慣、生きるための技術や創造力に優れているところを見出し、感動し、尊敬する。そうした温かくも謙虚なまなざしを通して、世界に対する彼にしかできない見方を培ったのです。重要なのは、そうした視線が、遠い土地のみならず、彼が生きるフランスの都市へ、具体的には協同組合活動へも向けられたことです。多様な人間の生き方の幅を確かめ、それを糧に自分が生きている世界を変えていく。それこそが、モースにとっての人類学でした。
晩年もモースは、彼自身がフィールドへと旅立つ代わりに、彼の後に続く若い研究者たちに「民族誌学」の講義を行うことで、世界を既存の視点とは違った目で見るための視座を鍛える努力を続けました。彼にとってはそれが、より良い生を求める世界の人々のさまざまな生き方の中に「記録されるに値するものがまだ山のように残っている」ことを確かめ、「この世で飛びぬけているものを知る」人類学の新たなフィールドだったのです。最晩年の直弟子の一人があの岡本太郎でした。

現代において真の意味での「未開社会」はもう存在しないともいわれます。しかしフィールドワークの重要性は、その長さや場所ではありません。重要なのは、自分とはまるで異なっているかもしれない世界を生きている人と出会い、限られた時間であれ深く接し、その短い時間の経験を増幅し、豊かなものにするための方法や着眼点を探求することです。人類学は、既存のあらゆる物事の意味を問い直す機会と経験を与えてくれる実に豊かな学問なのです。
人間の生き方の幅・可能性を知ること、それを踏まえて、今生きている場所をより良い方向に変えていくこと。人類学の研鑽が、世界の行く末に少なからず意義をもたらすと信じています。
-
若手研究者のみなさまへ
フィールドワークという短い時間の経験を増幅し、豊かな時間にするための方法を一人ひとりが模索することが大切です。
渡辺公三
Kozo Watanabe
先端総合学術研究科 教授
1981年 東京大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士(文学)。1981年 国立音楽大学講師着任、同助教授、1994年 立命館大学文学部教授、2003年 同大学院先端総合学術研究科教授、現在に至る。民族芸術学会、日本アフリカ学会、日本科学史学会生物学史分科会、日本文化人類学会、精神医学史学会に所属。