![]()
バーチャルとリアルが融合した打撃練習システムを開発
樋口貴俊さん 立命館大学総合科学技術研究機構プロジェクト研究員
/日本学術振興会特別研究員(PD):写真右
髙木将樹さん (2014年度情報理工学部卒業):写真左
スポーツ健康科学部の樋口さんと情報理工学部の髙木さんが中心となって開発しているこのシステム。ゴーグル型のディスプレイに野球場や投手が立体的に表示され、投球モーションに合わせてセンサーを取り付けたバットをスイングすることで野球の打撃練習ができるというものだ。スイングに応じてボールがバットの芯に当たった、根元に当たった、などを表す4種類の音が出るようになっている。
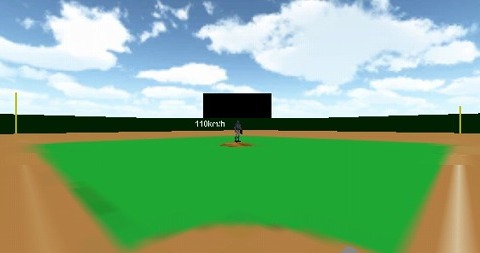
樋口さんのこれまでの研究から、打者のパフォーマンスの向上には素振りやティーバッティングで正確かつ高速度でスイングすることではなく、ボールの到達位置を正確に予想し、それに合わせてスイングできる能力をあげる練習が必要であるとわかっていた。しかし、毎日何十回何百回と実際の投球を打つことは、専属の打撃投手でも雇わない限り難しいのが現実だ。
このシステムを使うことで、投手の人数や疲労、スペースに制約なく打撃練習に取り組むことができる。開発にあたり、立命館大学硬式野球部の選手5名に実際に3ヶ月間装置を利用してもらった。週3回、1日30球以上スイングしてもらった結果、スイングの速度が向上し、タイミングのばらつきが減少したことが確認された。

写真提供:読売新聞社
利用した選手からは、「通常の素振りでは球種やコースを頭でイメージしてスイングするが、このシステムでは球種やコースがランダムなので、より実戦的な感覚で練習できる」という意見が聞かれた。一方で、試合や遠征が多い選手たちにより快適に使ってもらうためには、コンパクト化やワイヤレス化が必要であることがわかった。
実用化に向けた更なる改善点として、髙木さんはスイングの軌跡を画像で表示し、打者が自分のスイングを視覚でも確認できるようにすることと、現実とバーチャルでわずかに差があるボールのスピード感を現実に近付けることを挙げた。

樋口さんは、将来的にこのシステムをインターネットでつなぎ、コーチが離れた場所にいる選手の打撃動作を仮想空間内でチェックしたり、コーチの身振りでの指導を選手が見たりといった双方向での活用も実現させたいという。また、実際の投球の軌道データを取得して練習することで、特定の投手の攻略にもつなげたいと思っている。
一般向けには、プロの投球を打者目線で体験できたり、時間やスペースが限られている学校教育現場での活用などが考えられるという。立命館大学ならではの、スポーツの科学的分析とIT技術の融合で生まれたこのシステム。実用化される日が待ち遠しい。
樋口さんのこれまでの研究から、打者のパフォーマンスの向上には素振りやティーバッティングで正確かつ高速度でスイングすることではなく、ボールの到達位置を正確に予想し、それに合わせてスイングできる能力をあげる練習が必要であるとわかっていた。しかし、毎日何十回何百回と実際の投球を打つことは、専属の打撃投手でも雇わない限り難しいのが現実だ。
このシステムを使うことで、投手の人数や疲労、スペースに制約なく打撃練習に取り組むことができる。開発にあたり、立命館大学硬式野球部の選手5名に実際に3ヶ月間装置を利用してもらった。週3回、1日30球以上スイングしてもらった結果、スイングの速度が向上し、タイミングのばらつきが減少したことが確認された。
写真提供:読売新聞社
利用した選手からは、「通常の素振りでは球種やコースを頭でイメージしてスイングするが、このシステムでは球種やコースがランダムなので、より実戦的な感覚で練習できる」という意見が聞かれた。一方で、試合や遠征が多い選手たちにより快適に使ってもらうためには、コンパクト化やワイヤレス化が必要であることがわかった。
実用化に向けた更なる改善点として、髙木さんはスイングの軌跡を画像で表示し、打者が自分のスイングを視覚でも確認できるようにすることと、現実とバーチャルでわずかに差があるボールのスピード感を現実に近付けることを挙げた。
樋口さんは、将来的にこのシステムをインターネットでつなぎ、コーチが離れた場所にいる選手の打撃動作を仮想空間内でチェックしたり、コーチの身振りでの指導を選手が見たりといった双方向での活用も実現させたいという。また、実際の投球の軌道データを取得して練習することで、特定の投手の攻略にもつなげたいと思っている。
一般向けには、プロの投球を打者目線で体験できたり、時間やスペースが限られている学校教育現場での活用などが考えられるという。立命館大学ならではの、スポーツの科学的分析とIT技術の融合で生まれたこのシステム。実用化される日が待ち遠しい。






