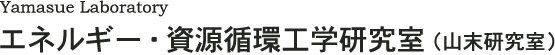
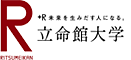 English
English
大学において教員は学生を指導する立場ではありますが,研究を行う上では,教員と学生は全く対等な共同研究関係にあると考えています.自分が与えられた研究テーマについては「自分が世界で一番知っている」という自覚を持ち,教員と対等な議論ができるようになってもらうことを強く望みます.
研究を行うときだけでなく,就職して社会の一員として活躍するため,そして私生活においても論理的な思考力を持つことは強力な武器となります.当研究室では,常に「なぜそうなのか?」「論理的にどういう意味があるのか?」という問い繰り返し投げかけ,論理的な思考力の理解と育成を促進します.それにより,自分で考えて行動できるような能動力につなげるとともに思考の瞬発力を身につけてもらいます.
当研究室の特徴の一つは学際的な研究を行っていることです.これは,教員・研究員・学生が単に別々の研究をしているというわけではありません.全てのメンバーが個々の得意分野は持ちつつ,自分の興味対象に対してできるだけ広い研究領域からのアプローチを行いながら議論できるようにします.より具体的には,自然科学的な視点と社会科学的な視点から考えることのできる学生の育成・研究の遂行を目指します.
研究には基礎研究から応用研究まであります.基礎研究であれば,それがその研究領域の発展においてどのような位置づけにあるのか,そして応用研究であれば,それが社会のどのような問題に対して貢献するのかを意識しながら研究を進める必要があります.当研究室では,積極的に研究成果を活かすための現場(工場見学,フィールド調査,研究会,学会)へ足を運び,地に足のついた研究を行うことを心がけます.
研究は生き物ですから,得られた結果を基によりよい方向に軌道修正が必要です.そのため研究の最初の段階では,完成度が100%のものを十日かけて作るより,まずは80%のものを1日で作り,研究の全体像を掴むことが大事です.そのために自然科学系の研究でも社会科学系研究でも,研究の「プロトタイプ」を作ることを心がけてもらいます.
研究は集中力を持って行うことが重要です.計画的な研究計画を立て,研究に集中するときは集中し,プライベートはプライベートで思いっきり楽しむというメリハリが重要です.充実したプライベートがあってこその(学業)研究活動ですし,逆も然りです.もちろん論文執筆時,学会直前等,研究側のウェイトがかなり重くなる時期があることは否定しませんが...そのため,自分の研究に対するタスクとtodoを常に意識しながら研究を進めてもらいます.
「楽するための苦労は厭わない.ただし手は決して抜かない」が合い言葉です.ここで言う「楽」は「効率化」と考えてください.単純なルーチンワークや自分がいなくてもできるような作業は安全を考慮した上で可能な限り自動化したり,リモートでコントロールできるようなシステムを自ら構築してもらいます.また当研究室では,種々のwebサービス等を有効活用し,自分がいないときでも情報を自動収集し,どこにいても情報共有を行えるような方法を教授します.それにより時間や人間資源の有効活用,ひいてはQOL (Quality of Life)の向上につながります.
研究成果は社会に伝えて初めて意味をなします.どんなに素晴らしい成果を出しても,それを伝える能力が無ければ意味がありません.当研究室では,研究自体に注力することは当然として,さらにその成果を伝えるためのコミュニケーション力(プレゼン力)の育成も常に意識ながら研究を進めます.その集大成として,卒研生,大学院生ともに,他大学との合同研究会や国内・国際学会での発表を行うことを大きな目標としてもらいます.