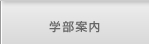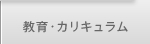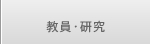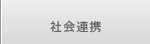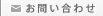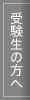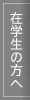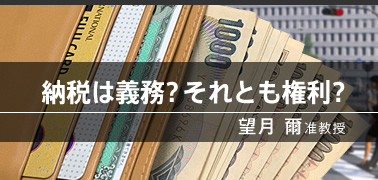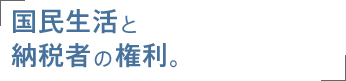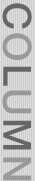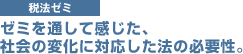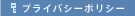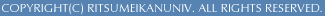- 現在表示しているページの位置
-
- HOME
- 教員・研究index
- 法律で社会を変える研究者たち
- 納税は義務? それとも権利? (望月 爾准教授)

国民の三大義務に教育・勤労・納税があります。そして、すべての国民は教育を受ける権利と勤労の権利 を有しています。なぜ、納税だけが義務であって権利ではないのでしょうか。欧米では、「代表なければ課税 なし」のスローガンの下、納税は権利として考えられてきました。英語で納税者は“Tax Payer”と表現されるように、日本ではお上に「納める」べき税金が、社会保障やインフラに対する“pay”、つまり対等な立場での 「支払い」と認識されているのが通常です。日本の租税制度は徴収する側の財政の論理から語られることが多く、国民の生活や財産権※1などの権利を守るという 納税者の側から十分な議論がなされていません。ここ数年、消費税率の引上げ論議が活発ですが、国民生活を 圧迫し逆進性※2が問題となる消費税を本当に増税する 必要があるのでしょうか。それよりも、もっと税金の使途を 明らかにしてもらわなければ、私たち国民は増税に対する 費用対効果や税金の使われ方が正しいものであるかを チェックすることができません。生活と密接に結びつく税法の正しいあり方を考えることは、国民生活と納税者の権利を守るための非常に意義のある学びといえます。
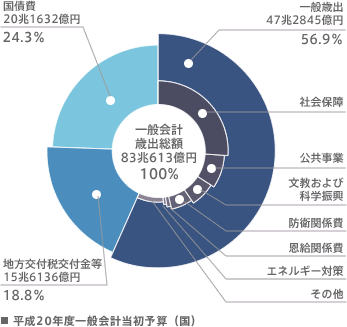
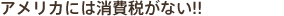
- EU各国の付加価値税と比べて議論されることの 多い日本の消費税ですが、実はアメリカには連 邦政府(国)が賦課する消費税は存在しません。 消費税と誤解されている税金は、州や郡、市に よって課されている小売売上税という地方税で、 税率は4~8%程度、原則的に食料品などは課税 されず、オレゴン州などなかには売上税がない 州もあります。。
- 【財産権※1】
- 憲法第29条1項は、「財産権はこれを侵してはならない」と定める。国民・納税者の権利を考慮に入れない租税制度は、財産権を侵害し憲法に違反する。
- 【逆進性※2】
- 目的のための行為が、実質として逆の効果をもたらすこと。消費税の場合、国民生活を豊かにするための税金が、低所得者層の生活を圧迫することが問題となっている。
|
||