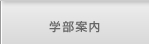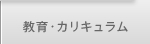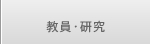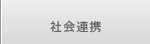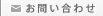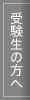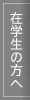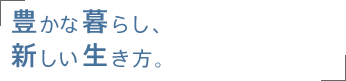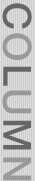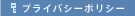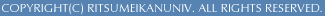- 現在表示しているページの位置
-
- HOME
- 教員・研究index
- 法律で社会を変える研究者たち
- 信託法が、社会の未来を変える (山田 希准教授)

2006年、信託法が84年ぶりに改正され、これまで一般にはほとんど使われていなかった信託制度 の実用化が期待されています。信託法が見直された主な理由は、社会情勢の変化・経済の活発化 に伴い、信託※1を用いた金融資産運用が増えたほか、福祉・扶養など多様な形態での信託活用のニーズが高まってきたからです。たとえば、ある老人が信託制度を用いて息子を受託者として財産を 譲渡し、自身を受益者に設定すれば、財産は受益者である老人の利益のためにしか使われないので、安心して余生を過ごすことができます。また、自分の財産を奨学金給付などの公益活動に使いた いと考えた時、財団法人をつくるしか方法がありませんでしたが、信託制度を利用すれば同様のこと がより簡単に行うことができます。このように信託制度は、今までできなかったこと、困難であったこと が簡便化できる制度といえます。 これからの高齢化社会・福祉社会を考える上でも、大きな注目を 集める分野だと思います。
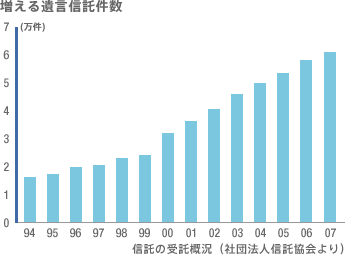
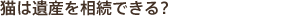
- 法律上、猫は物と同じため遺産を相続させることはできません。しかし、信託制度を利用して遺産を使う目的を猫の利益に限定することで、猫に財産を残すのと同じような効果をもたせることができます。これまでの法は人間中心の設 計になっていましたが、信託制度は、法に新しい視点を持ち込むきっかけとなっています。
- 【信託※1】
- Aが自分の財産をB に譲渡するとともに、その財産を運用管理することで得られる利益をCに与えることをBと取り決める枠組みのこと。Aを委託者、Bを受託者、Cを受益者と呼ぶ。
- 【信託財産】
- 委託者が定めた特定の目的にしか使われない財産のこと。受託者が財産の所有者となるが、その財産を自由に使用・収益・処分することができず、その収益を受ける権利は、受益者にある。
|
||