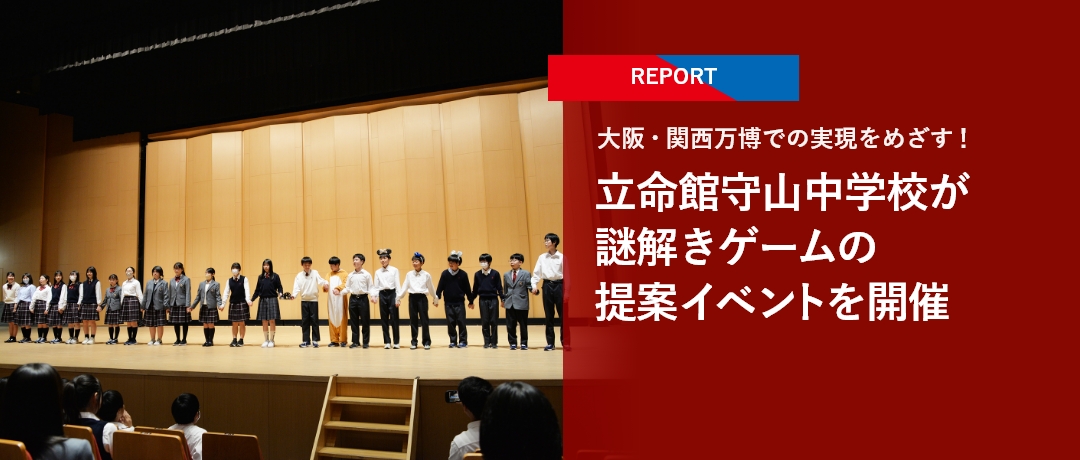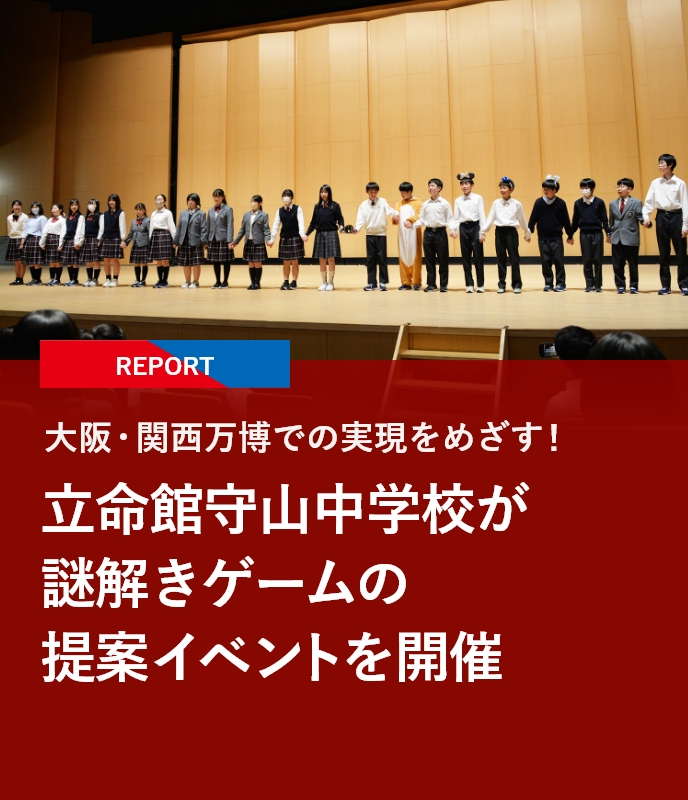立命館守山中学校では大阪・関西万博での実施に向けて、会場と世界をフィールドとした謎解きゲームの企画・提案を進めています。これは、来場者が専用冊子を見ながら万博会場の各場所や建物、イベント、体験などをヒントに謎解きをするゲームで、楽しみながら会場を探索できることを想定しています。
その準備の一環として、4月26日(金)に大阪・関西万博のテーマ事業「シグネチャープロジェクト」のプロデューサーである中島さち子さんを迎え、生徒たちが創作した謎解きゲーム「OICクエスト」を実施。中島さんに体験してもらうとともに、大阪・関西万博での実現に向けたアドバイスを伺いました。
大阪いばらきキャンパスが魔法学校に! 謎を解いて魔王を倒す
今回、大阪いばらきキャンパス(OIC)で謎解きゲーム「OICクエスト」を行ったのは、立命館守山中学校の2年生全生徒、約170名です。「OICクエスト」の設定は、「立命館守山中学校にいたはずの2年生170名が、大魔王に支配された魔法学校OICに転生してしまった」というもの。参加者は魔王の手下が出す謎を解いて鍵を手に入れ、元の世界に戻らなくてはいけません。ゲームに登場した謎は、生徒たちは事前にOICを訪れて考えたもの。大阪・関西万博で実施の際は、事前に会場やパビリオンを視察した上で、オリジナルの謎解きゲームを創作します。
この日、生徒たちは出題チームと謎解きを体験するチームに分かれてゲームをスタートしました。中島さんは体験チームでの参加です。今回のゲームのルールは、グループごとに異なる地点からスタートし、謎解きに挑戦。謎を解くと番号を手に入れることができるので、その番号と事前に渡された「OICクエストマップ(キャンパス全体図)」を頼りに次のスポットに向かいます。スポットには魔王の手下に扮した出題チームがいて、さらなる謎を出題してくるので、それに答え、さらに次のステップに向かう、というのを繰り返していきます。

中島さんのチームは謎を解きながら移動し、待ち受ける魔王の手下役の生徒から謎を聞き出します。「大学のキャンパス模型に隠された数字を探して足せ」「里山エリアを歩くと遭遇するものに共通する数字はなんだ」など、中学生の柔軟な発想から生み出された謎について答えを探ります。いざ答えを口にしても、間違えると手下になりきった生徒たちが「愚か者め! それでは簡単すぎる!」などと物々しい口調で叱られることに。その後、ヒントが提示されるのですが、出題する生徒もゲームの進行のミスリードにならないようにヒントを出すことに苦戦しており、「あ、そっちは行き過ぎ!」など、素の口調が飛び出す一幕も見られました。
チームでの謎を解き終え、キャンパス内にある立命館いばらきフューチャープラザのグランドホールに全員が集合すると、ステージでは実行委員の生徒たちによる寸劇が披露され、現れた大魔王が最後の謎を出題。この謎を解いて、無事に元の世界に帰ったところでゲームは終了しました。

ブラッシュアップに向け、生徒と中島さんらがセッション
ゲーム終了後には中島さんと生徒のセッションが行われました。「みなさん無事に魔王から逃れての帰還、おつかれさまでした。私も謎を解きながらたくさん歩きました」と生徒を労った中島さんは、「謎解きの内容に加えて、演劇感がたっぷりの仕草など、クスッと笑える要素があっておもしろかったです」とコメント。そして、生徒に今日の体験を通じた気づきを問いかけたところ、数名の生徒がステージに上がり意見を述べました。
中ボス役で謎を出題した女子生徒は「謎を出すときの表現を、あえて中二病のようにしたところ、みんなが驚いてくれたのがおもしろかったです。でも、惜しい答えが出た時に、感情が顔に出ないようにすることに苦労しました」と発表。このほか、「第三者の立場になってゲームを体験しても、ストーリーがおもしろかった」と自信をのぞかせる男子生徒や、わかりづらかった謎に対する生徒からの質問に、謎を考えたメンバーが出題の意図を説明するなどの場面もありました。
謎解きゲームには、中島さんとともにSTEAM教育の推進に取り組む中楯浩太さんもゲストとして参加。中島さんとともに謎解きゲームでキャンパスを巡った中楯さんは、「万博で実施することができれば、今日ここにいるみんなが、万博での謎解きゲームも考えるんだよね、こういう取り組みをしている学校は、あまりありません」と生徒を称賛。さらに「今日、目の前の人の表情を見ながら出題したことで、相手への伝わり具合がよくわかったと思います」と振り返ったうえで、改善点をみんなで話し合うことをアドバイスされました。

最後に「皆さんには2つの観点を持ってほしい」と中島さん。1つは大阪・関西万博に参加する約160の国々を絡めたグローバルな視点でストーリーや問いを考えること。もう1つは、車椅子の人や目の不自由な人などハンディキャップがある人も一緒に楽しめるような問いを出題するなど、インクルーシブな発想でゲームを設計することです。
「万博は、いろいろな国、特性のある人といった、今はまだ知らない誰かとつながれる機会です。そして、大阪・関西万博のコンセプトは『未来社会の実験場』。謎解きゲームも、皆さんで深く考えて実験をしながら、笑いが起こるゲームを作っていってください。今日は楽しい1日でした」との中島さんからのエールに、生徒たちは感謝の拍手を送りました。
グローバルとインクルーシブを意識したゲームへ
「OICクエスト」を終えた先生と生徒に話を聞きました。
立命館守山中学校の犬飼先生、稲田先生は、この取り組みが学校の探究学習の一環であることを紹介。他の学校ではできない課外活動であるという自負を持ち、試行錯誤を続けていると話します。

「本校では教員が作成した謎解きゲームを、入学後のオリエンテーションに取り入れています。それをおもしろいと中島さんが興味を持たれたことから、生徒が企画した謎解きゲームを万博で開催できないかという話が生まれました」(犬飼先生)
今回の取り組みに際して、先生たちはあらためてプロが作成した謎解きゲームを体験してゲームの構成などを分析し、生徒に説明するための謎解きゲームを作成。生徒たちがそのゲームを体験した後、今回の「OICクエスト」を作成しました。
「生徒たちが作った謎には、私たちが示したお手本にはない形式のものがあり、そのオリジナリティある発想に感心しました。ただ、難易度の設定やヒントの出し過ぎなど、運営面を含めて未完成なところがあり、今後の課題です」(稲田先生)
生徒とのセッションで中島さんが伝えた「グローバルとインクルーシブの要素」は、万博に向けて取り入れていきたいとも。今日、ゲームに携わった生徒たちは、中学1年次の授業で車椅子の方とのボールゲーム体験でルールについて考える機会があり、「これまで学んできた多様性への理解や、さまざまな国の人とつながるという部分を、今後は謎解きゲームに取り入れていきたい」と語りました。
続いて、「OICクエスト」のベースとなるストーリーを考えた実行委員会約20名を代表して、4名の生徒に話を聞きました。実行委員長の奥田さんは、「練習や台本作りで、仲間と話し合いながらゲームを作るのがとても楽しかったです。ただ、取り組みへの意識の温度差があったので、みんなが一丸となれたかというと悔いが残ります。次回のゲームでは、謎を作る時からイベント当日まで、みんなが楽しいと思えるようにしていきたいです」と今後への意気込みを語ります。

他のメンバーからも「謎の難易度と、出題者がわかりやすく伝えられるかを分けて考えないといけないことが反省点です」(松本さん)、「世界観をおもしろく作れたのは良かったです。次は参加してくれた方がもう少し世界観に入り込めるよう工夫したいです」(村田さん)、「謎のレベルの設定や、ヒントを出す加減が難しく感じました」(上野さん)と感想を語りました。
大きな視座で謎解きゲームを仕掛けてほしい
最後に謎解きゲームと大阪・関西万博について、中島さんにお話を伺いました。中島さんによると、今回の「OICクエスト」のように、体験型の謎解きゲームは国内外で人気があるのだそう。また、万博も従来のように最新技術を見るだけでなく、来場者が一緒になってなにかを作り上げるといった体験の場へと変化しているといいます。それをふまえて、中島さんは大阪・関西万博で謎解きゲームのような体験イベント開催を検討していたことから、立命館守山中学校の取り組みには期待を寄せていると話します。

「ゲームの楽しさは大事なことなので、どうしてもそちらに目が向きがちですが、ゲームを通して参加者に何かに気づいてもらったり、出会いを生み出すといったことが、本当の目的かもしれません。大阪・関西万博で実現するには『いのち輝く未来社会って、どんなもの?』と開催テーマを来場者みんなで考える仕掛けになるような大きな視座で、ゲームを仕掛けていってほしいと思います」
そして、中島さんからはエールの言葉も寄せられました。
「万博まであと1年あります。生徒さんたちが各国の万博担当者に会って謎解きの種を探したいということになったら、事前ヒアリングできる機会を設けるなどサポートをできれば。来年の実現に向けての土壌を育んでほしいですね」
立命館守山中学校の謎解きゲームは、今後、同中学校のオープンキャンパスなどでの実施を重ねながらブラッシュアップしていく計画です。大阪・関西万博での謎解きゲーム実現にご期待ください。