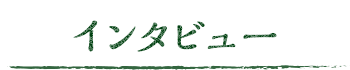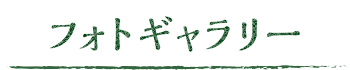日本を伝える
Jan 17, 2017

「雅楽を実際に演奏して楽しみ、その楽しさをより多くの人に知ってもらおう!」という趣旨のもとに1999年に発足した雅楽会。2017年1月現在、衣笠キャンパスに10人、びわこ・くさつキャンパスに6人が在席し、週2回、衣笠キャンパスで活動している。また、京都市内にある市比賣神社の雅楽会にも所属し、大学での定期演奏会のみならず神社で行う演奏にも参加している。
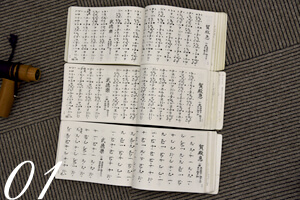
譜面
雅楽の譜面(ふめん)は、通称「カナ譜」と呼ばれ、旋律を歌にした「唱歌 (しょうが、あるいは、しょうか)」と、指使いを表す記号とでできている。各楽器によって譜面の表記の仕方が違う。

鳳笙(ほうしょう)
その音色から「天から差し込む光」を表しているとされる。吹きこんだ息で水滴が出来るのを防ぐため、吹く前に必ず笙あぶり(写真左)を使い温めなければならない珍しい楽器。

篳篥(ひちりき)
雅楽を代表する楽器で、「地上の人の声」「大地の音」として力強くダイナミックな音色で演奏全体を牽引する。表側に7つ、裏側に2つの孔(あな)を持つ縦笛。主旋律を担当し、「塩梅(えんばい)」という独特の奏法で演奏に彩を加える。

龍笛(りゅうてき)
表側に「歌口(うたぐち)」と7つの「指孔(ゆびあな)」を持つ横笛。現在では入門用にプラスチックでできた物も存在する。雅楽の楽器の中では広い、2オクターブの音域(E5~D7)をもつ。「舞い立ち昇る龍の鳴き声」と例えられる。牛若丸が吹いていたことで有名。

高麗笛(こまぶえ)
表側に6つの孔(あな)を持つ横笛、音の高さは龍笛より一音高い。曲によって、龍笛と使いわける。
部活動の特徴や魅力について、お二人にインタビューを行いました。
-

高原怜央さん
理工学部2回生 -

石原康惠さん
法学部2回生
- Q1「雅楽会」の特徴は?
-
初めの頃は、管楽器である鳳笙・篳篥・龍笛のうち一つ選び練習します。希望があれば、打楽器である羯鼓(かっこ)・鉦鼓(しょうこ)・太鼓や絃楽器の楽琵琶(がくびわ)・楽箏(がくそう)も神社で練習でき、また、舞の稽古を受けることもできます!
 石原さん
石原さん
- Q2雅楽の魅力は?
-
世界最古のオーケストラといわれている雅楽は、指揮者がおらず全員でリズムをとることが難しいので、練習を重ね、全員のリズムが合った瞬間に楽しさを感じます。雅楽は中世を主とした日本の文化と密接な関係を持っているため、美術品や寺社仏閣などでも雅楽を題材としたものが多くみられ、日本の文化についてもより深く知ることができます。
 高原さん
高原さん
- Q3トリビアを教えてください!
-
雅楽を由来とする言葉が実は沢山あります!
・相撲で使われる「千秋楽」は雅楽の楽曲名が由来となっています。
・「打ち合わせ」、これも雅楽から生まれた言葉です!
雅楽では、曲中に太鼓などに合わせて吹き始めたりして拍子を合わせる箇所があります。これが転じて事前に協議や相談するという意味になりました。 石原さん
石原さん
- Q4今後の目標を教えてください。
-
先日学内で行なった第17回定期演奏会では、前会長が舞楽である「落蹲」を舞いました。会長はもちろん、私たちもその舞に相応しい演奏に仕上げるために、練習を積み、納得いく成果を得ることができました。その経験を踏まえ、今後は管絃で基本の曲となる越殿楽(えてんらく)などの曲と舞楽を中心に、お客さんに魅せることはもちろん、何よりも雅楽会のみんなで楽しく演奏することを大切にしていきたいです!また、少しでもみなさんに親しんでもらえるように、雅楽の魅力をSNSで発信し続け、活動の幅を広げていきたいと思っています。
 高原さん
高原さん