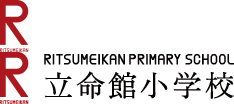「Uカーブ理論」を参考に
ゴールデンウィークが開けたら、学校玄関前にあるアンネの薔薇が咲き誇っていました。
4月から新学期が始まり、子どもたちは新しいクラスで、新しい仲間と出あいながら過ごしてきました。当たり前のことですが、新しい環境に慣れるまでは無意識のうちにいろいろと気を使うものです。去年とは違う、一年成長した自分を発揮するために、少し背伸びしてみては、ちょっと疲れたなと感じたり、ということの連続かもしれません。
異文化適応に関する古典的な理論で、「Uカーブ理論」というのがあります。これは私が大学の授業で、これから1年以上の海外留学をしようとする大学生に教えてきた内容の一つです。これを海外留学の前に教えておくと、現地での異文化適応の荒波を前向きに捉え、うまく乗り越え、自分の成長に結びつけられるようです。新しい環境に入ると、以下の3つの時期を経験する、という理論です。
①ハネムーン期:新しい環境に入ってすぐは、お互いに気をつかって親切に振る舞うし、新鮮味があって毎日が楽しい。
②カルチャーショック期:2ヶ月から3ヶ月ぐらいの間で疲れが溜まり、本当はこうありたい自分と実際のギャップに自信を失い始めたり、いつもなら受け止められたり、軽く流せるような出来事が一大事となって自分の心を占領したり、といったことが起こる。
③回復・適応期:カルチャーショック期を抜け出すと、新しい環境の中での自分の役割や居場所の調整が落ち着いてきて、より適切なコミュニケーションの仕方もわかるようになり、少しずつ成長していく等身大の自分を受け入れられるようになる。
異文化適応においてはこの心身の状態の上下動はより明確に経験されることが多いですが、ちょっとした環境変化においても同じような作用があるということは、おさえておいた方が良いと思っています。
学校生活にこの理論を当てはめるなら、これから一番気を付けたいのは6月、その次は2学期の11月、ということになります。
ところで、この理論の素敵なところは、「焦らずに日々のことにしっかり取り組んでいれば、いつか必ず抜け去ることができる」としているところ、そして、「カルチャーショック期の経験こそが成長の種だ」としているところです。異文化環境でもまれて人が成長するのは、このカルチャーショック期に自分の強みと弱みをいやというほど自覚するからという分析もあります。
カルチャーショック期に大切なことは、これは誰もが経験しうることで成長の種であると認識すること、自分と周りにいつもより思いやりをもって過ごすこと、睡眠・食事をしっかりとること、と言われています。子どもたちには、こんなことを気にかけながら穏やかに5月を過ごし、学びの多い夏を迎えてほしいと思います。
校長 堀江未来