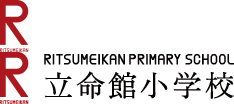1年生と6年生
子どもの成長過程、特に思春期に差し掛かる年代では、自分のいろいろな面を引き出してもらえる相手や、そういう場に身を置くことが、とても大事だと思います。この1年生と6年生の合同の取り組みも、そんなことを感じられる場でした。
少し前になりますが、1年生と6年生のペアで、音楽科&体育科の合同授業をしばらく行ないました。そして、こちらはその最終発表の時の様子です。
まずはグループに分かれて、6年生の合奏。1年生が鑑賞します。じっと聴いています。
それに続いて、1年生が歌と踊りを披露します。6年生の眼差しがあたたかい。
しばらく歌や踊りで交流した後は、6年生の宿泊体験学習の報告です。それぞれに作成したスライドを見せながら、別府で見てきたこと・感じたことを1年生にお話しして伝えました。
6年生は、1年生にわかるように、興味をもってもらえるように、工夫して話しています。1年生は興味津々。
最後は、一緒に合同で練習してきたダンスの披露です。この間、6年生が1年生に教えてきたものです。
さて、冒頭に書いたことですが、この取り組みでの6年生、いつもとは違った一面が見えて、とても印象深かったのです。甘えてくっついてくる1年生を膝に乗せて安心させてあげる6年生。先生の話を聞く時間に落ち着かない1年生をなんとか落ち着かせようと声をかける6年生。一度の説明では伝わらないことを何度も言葉を変えて説明しようとする6年生。
それぞれに、優しくて思いやりのある気持ちが全面に出ていました。出ていました、というより、小さい子どもを目の前にして、優しくて思いやりのある態度を出さざるを得ない、恥ずかしがっていられない、そんな状況だったかもしれません。
子どもたちは、幼い自分と成長した自分の両極を自分の中にもちながら、その間を行ったり来たりして日々を過ごしています。その両極の幅が大きくなり、成長した側面をたくさん表に出せるようになると、私たちはその子に対して「成長したなあ」と感じるわけです。
普段、自分が甘えられる相手に対して見せる側面、同年代の仲間見せる側面は、本人の一部にしか過ぎません。そして、誰にでも優しくて思いやりのある側面は隠れていて、今回の1年生と向き合う取り組みは、それが否応なく引っ張り出されるものでした。ハウス活動での異年齢交流でもそんな様子が見られますが、6年生と1年生というペアでの取り組み、思春期に向かう子どもたちにはさらに効果的だったように思います。
校長 堀江未来