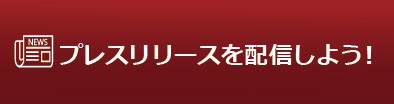特許出願等の相談
1.特許出願の相談先
特許出願したいアイデアが生まれた場合や、特許出願に関する疑問などは、リサーチオフィスのスタッフへ(びわこ・くさつキャンパス所属の場合は、担当TPまたは知財・契約担当まで)ご連絡下さい。 リサーチオフィスのスタッフが伺い、アイデアのヒアリング、特許出願手続き等のご説明、出願手続きのサポートをいたします。
|
知財・契約担当 Mail:ritsip@st.ritsumei.ac.jp Tel:(外線)077-561-2802 (内線)理工系:515-6566/ライフサイエンス系:515-6021 |
2.「まだ、発明かどうかわからない」場合
まずは、リサーチオフィススタッフへご相談ください。
技術の内容を伺い、発明が未完成な場合、発明の完成、特許出願に向け以下の視点を中心にご説明、サポートさせていただきます。
なお、ご相談案件によって、とるべき対応・対策が変わる場合があります。場合によって、特許出願せずに「論文」「その他の発表のみ」が適切とご提案させていただく場合があることを、ご理解ください。
- 今後、特許出願を目指す際にご提出いただく発明に係る資料
- 特許として認められる要件(特許性)
- 先行技術調査のサポート・アドバイス
- 大学が特許を受ける権利を承継する際の手続き
- 教職員がもつ市場情報の整理など
3.職務発明とは
職務発明とは、特許法第35条に基づき、「その性質上、本学の業務範囲に属し、かつ、その発明などをするにいたった行為が本学における当該教職員の現在または過去の職務に属する発明」をいいます。 職務発明であるかどうかは、産学官連携戦略本部長等で構成される審議体にて決定します。
| その性質上、本学の業務範囲に属し、かつ、その発明などをするにいたった行為が本学における当該教職員の現在または過去の職務に属する発明か? | |
YES

|
NO

|
4.共同発明者の要件
(1)共同発明者かどうかの判断共同発明者かどうかは、発明の成立過程で、着想の提供(課題の提供又は課題解決の方向づけ)と着想の具体化との2段階に分け、各段階において実質上の協力関係の有無から次のように判断します。
- 1) 提供した着想が新しい場合、 着想 (提供) 者は発明者である。
ただし、着想者が着想を具体化することなく、そのまま公表した場合、その後に他人がこれを具体化して発明を完成させたとしても、着想者は共同発明者となれません。お互いに協力関係がないからです。 - 2) 新着想を具体化した研究者は、その具体化が自明程度でない限り共同発明者になります。
着想自体に関係しない研究者、たとえば、単なる管理者・補助者又は後援者等は共同発明者に該当しません。
- 単なる管理者 : 部下の研究者に対して一般的管理をした者、例えば、具体的着想を示さずに単に通常のテーマを与えた者、又は発明の過程において単に一般的な助言や指導を与えた者
- 単なる補助者 : 研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者又は実験を行った者
- 単なる後援者・委託者 : 発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は委託した者
5.リサーチオフィススタッフのサポート内容
リサーチオフィスのスタッフは、本学で生じるそれぞれの発明に関し特許出願相談、特許権利化、技術移転等の支援を行っております。
●サポート内容
- (1) 特許出願相談
- (2)先行技術調査
- (3) 弁理士との連絡調整
- (4) 学内手続き
- (5) 特許技術の学外へのライセンス活動・契約締結およびそのための調査、広報活動
6.発明の届け出について
「 発明届 」の提出をお願い致します。リサーチオフィススタッフまでご連絡下さい。
|
ヒアリング リサーチオフィススタッフがヒアリングを行い、発明の内容についてご説明を伺います。 |
|
 |
|
| 職務発明か否かの検討および特許性・市場性に関する調査 | |
 |
|
| 本学が発明に基づく特許を受ける権利を承継するか否かの決定 | |
 |
 |
|
権利譲渡書の提出(承継) 本学が承継すると決定した場合には、 |
非承継の通知 本学が承継しないと決定した場合には、 |
7.「市場性」検討の必要性
そもそも特許とは、特許法第1条に定めるとおり、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的」とした制度です。 従って、大学で生まれた発明を権利化して保護する目的は、大学で生まれた発明を社会実装することです。発明(特許)技術の学問的価値と市場性とは必ずしも一致しません。また、特許技術の活用により適切な対価が大学に還元されれば、更なる研究の高度化と研究成果の創出が期待されます。そのために、「産業界で活用されうる発明技術=市場性のある発明技術」を、権利化していく必要があります。
(承継) |
 大学
大学
|
(技術移転) |
 社会実装
社会実装
|
|
 (対価の還元) (対価の還元) |
 (対価) (対価) |
8.学生・客員研究員の発明の取り扱い
学生・客員研究員の発明は、本学と雇用契約を締結するなどして本学の職務の中で生まれた発明は、職務発明として取り扱われます。また、本学知的財産ポリシーや発明規程に沿った取り扱いを受けることについて本学との間で契約することもできます。研究室配属当初からこのような取り扱いをすることにより、発明などを一元管理することが可能となり、研究室内の統一的な指針のもとで研究・教育を進めることができる利点があります。この場合、学生の教育を受ける権利や選択の自由などを損なわないように配慮しなければなりません。
9.論文発表等について、注意すべきポイント
論文等が「公開」されると、それと同一か類似の技術の出願をしても、「新規性なし」「進歩性なし」として権利化することができません。 したがって、権利化をめざす研究成果については、論文投稿等をする前に、特許出願をしておくことが重要です。新聞、雑誌、Webでの公開も新規性を喪失してしまうので注意してください。 なお、論文発表の救済策として、新規性喪失の例外規定(特許法第30条)がありますが、これはあくまでも「例外規定」であり、安易に頼ることは危険です。公開後、特許出願するまでの間に、第三者が同じ内容で出願した場合、権利化することができなくなるからです(先願主義)。
10.学内での論文公聴会について
本学の場合、博士・修士論文公聴会については、一般的な学会等と同様に、新規性喪失の例外規定を適用することが可能な場合がありますが、基本的には、博士・修士論文公聴会で発表する前に、特許出願してください。
学士論文発表会は、クローズな場で行われますが、慎重な取扱が必要となります。新規性を喪失せず、研究成果を他の研究者に明らかにするためには、その研究者に対して、当該研究成果に関する情報を秘密にすることを了解してもらう必要があります。
詳しい手続きについてはリサーチオフィスにお問い合わせください。 下記の「公聴会における守秘誓約書」もご確認ください。
11.企業等との共同発明の取り扱い
受託研究、共同研究等によって共同発明が生まれた場合は、リサーチオフィススタッフにご相談ください。 特許出願費用・実施料などの条件は、リサーチオフィススタッフが企業等と教職員との間に入って交渉し、特許出願に関する契約を締結します。
(1)発明貢献度を、共同発明者間で協議して決めます。 |
 |
 リサーチオフィス
リサーチオフィス
(2)共同発明をした企業等と共同特許出願契約について協議いたします。 (3)共同特許出願契約において、権利の持分(特許を受ける権利および特許権)の割合を決めます。 (4)出願および権利化に係る費用の交渉をいたします。 (5)不実施の代償、第三者への実施許諾など実施料の収入についても交渉を行います。 |
 |
 企業
企業
|
 |
 |
※出願決定に至る学内手続きは単独発明の場合と同様です。
12.発明の貢献度
発明の貢献度とは、共同発明等の場合に、その発明を完成するまでに貢献した各発明者の寄与度をいいます。これは、学内における共同発明の場合でも、企業等の学外者の間における共同発明の場合でも、同様です。その判断基準は、あくまでも「発明の完成(特許請求の範囲)」に貢献した度合になります。
たとえば、発明者から指示されて行った単なる実験補助者や、装置・器具の提供者などは「発明者」に該当しないため、「発明の貢献」はありません。
 |
寄与した貢献度100% |
 |
||
 |
||||
 |
13.大学の発明補償
「発明者からの特許を受ける権利の譲渡」、「譲渡を受けた権利による特許権の付与」、「大学が取得した権利の譲渡またはライセンス(実施許諾)による収入(ロイヤリティ収入)」について、本学は発明者(教職員)に補償金を支払います。
| 補償の種類 | 補償金額 |
|---|---|
| 1.特許を受ける権利の譲渡を受けて特許出願(出願補償) | 1件につき 5,000円 |
| 2.譲渡を受けた権利による特許権の付与(登録補償) | 1件につき 10,000円 |
| 3.大学が取得した権利の譲渡による収入またはライセンス(実施許諾)による収入(ロイヤリティ収入) | 大学が得た収入から当該特許出願その他に要した費用を差し引いた残額の50% |
Q.学内共同発明者がいる場合は?
A.上記補償金は、共同発明者間で合意した割合に応じて支払われます。
Q.学外者との共同発明の場合は?
A.上記補償金は、本学と共同研究相手の持分割合に応じて支払われます。
Q.退職後、卒業後の支払いは?
A.退職・卒業された後も補償金は支払われます。ただし、転居等をされた場合に連絡先等をご連絡頂けないと支払いができないことになります。連絡先等に変更があった場合には、必ずリサーチオフィスまでご連絡ください。
14.受け取った補償金の、税金面の取り扱い
確定申告が必要となります。 所得税法により「出願補償」と「登録補償」は「譲渡所得」、「ロイヤリティ収入」は「雑所得」として扱われます。何れも、源泉所得税の対象にはなりませんので、個人での確定申告が必要となります。
| 出願補償・登録補償 |  確定申告が必要
確定申告が必要
|
譲渡所得 |
| ロイヤリティ収入 |  確定申告が必要
確定申告が必要
|
雑所得 |
※上記税法上の取扱いについては税務署に確認しておりますが、個々の事情によって異なる場合も考えられます。ご不明な点は、BKCリサーチオフィス知財・契約管理までお問い合わせ下さい。
15.ライセンス(実施許諾)先を探す活動
発明者、リサーチオフィス等が、互いに協力して進めます。 研究成果のライセンスにおいて、発明者の協力は非常に重要です。"研究成果を学会などで発表された際、関心を示された企業等があった。""この企業の研究内容から見て、興味を示すのではないか"といった情報がありましたらリサーチオフィスのスタッフにお知らせください。また、リサーチオフィスは独自のネットワークにより多数の企業情報を蓄積しており、それらのなかから研究成果にマッチした企業を選び出し、発明者と検討しながらライセンス交渉を進めることも可能です。このようにリサーチオフィスでは、発明者との相談を踏まえ様々なルートを通じライセンス先の交渉を進めます。
16.発明者自身が起業したベンチャー企業へのライセンス
本学教員等の発明は、原則的に本学の帰属となります。従って、発明者である教員が自らベンチャーを起業されるような場合、本学からそのベンチャー企業へライセンス(実施許諾)を行うことも可能です。ライセンスの条件などについても柔軟に対応します。 ライセンスの際には、利益相反の観点も踏まえ、手続きを進める必要があります。 詳しくは、リサーチオフィスへご相談ください。
17.ライセンス(実施許諾)の条件
ロイヤリティ(実施料)や契約期間等の条件は、発明者の意向を踏まえ、相手先企業との話し合いで決定していきます。 ロイヤリティや契約期間といったライセンスの条件には、客観的な基準がほとんどありません。 リサーチオフィスでは、研究成果が産業界で有効活用されることを第一に発明者の意向も踏まえながら、企業との交渉にあたるよう努めています。ライセンスの条件について、ご要望があるときは担当のリサーチオフィススタッフにお申出下さい。
| 立命館大学単独出願の場合 | 企業との共同出願の場合 | |
|---|---|---|
| 専用実施権のロイヤリティ | 独占的 | 不実施の対価 (ロイヤリティ、不実施補償と呼ぶ場合もあります。) |
| 通常実施権のロイヤリティ | 独占的 | |
| 非独占的 | ||
18.企業への特許譲渡の取り扱い
状況次第ですが、企業への特許譲渡は可能です。
基本的に本学が承継した発明は、広く産業界での活用を目指す観点より、本学で権利化し、原則として実施許諾契約により技術移転を目指していきます。すなわち、本学の発明が、適切な時期に、適切な企業へ、適切な条件で技術移転され、より多くの場面にできるだけ長期間にわたって活用されるよう、本学が特許権を保有した状態で実施を希望する企業に実施権を認めていきます。
特許権等の譲渡の申し出があった場合、リサーチオフィスまでご連絡ください。